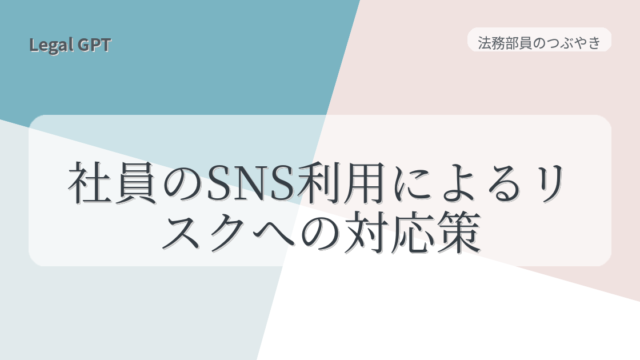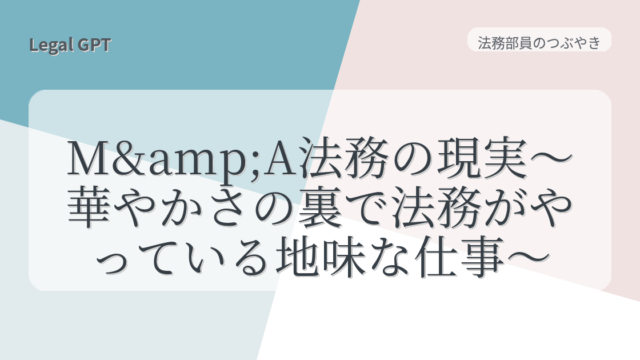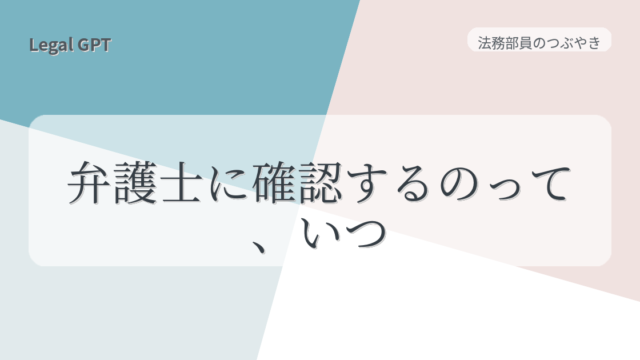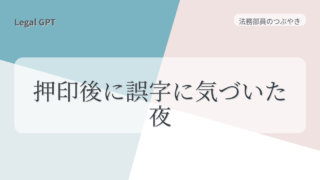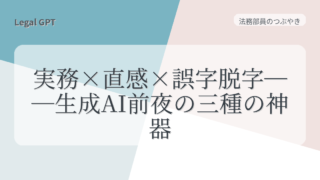逐条解説と睨めっこしてた頃の話
逐条解説と睨めっこしてた頃の話
AIが普及する前、契約書の条文解釈は本と索引と自分の読み込み力に頼る仕事でした。善良なる管理者の注意義務や「努力義務→義務」昇格のハプニングなど、実務で覚えた小さな教訓をまとめます。今の速さの背景にある“遅さ”の価値も振り返ります。
「この条文、どう解釈すればいいんだ?」
ある朝、共同開発契約書の逐条を見て固まりました。表現は丁寧でも、実務でどう使うかは曖昧なことが多い。たとえば:
具体的に何をどの程度までやるべきか分からない場面で役立つのが、実務向けの雛形・チェックリスト類です。業務委託契約での善管注意義務の扱いを確認したい場合は、実務チェックをまとめたテンプレ(業務委託の条項チェック)を参照すると目安が得られます。業務委託の条項チェックリスト(実務テンプレ)。
とりあえず本屋へ行くしかなかった
Googleの解説は用語辞典的で、実務での使い方までは載っていない。だから会社近くの書店で逐条解説や実務書を立ち読みし、必要なら1冊買って持ち帰る。索引を頼りに目的ページを探す根気も求められました。
当時の「本とにらめっこ」作業が、条文の曖昧さに対する肌感覚やリスク把握の基礎を作ってくれた面もあります。
面白エピソード:知らぬ間に「努力義務」が「義務」に昇格していた話
押印直前に発見できて本当に良かった、という実務あるあるでした。
今なら1分で出てくるけど…
今なら ChatGPT 等に「善良なる管理者の注意義務とは」と聞けば、要点・判例・交渉ポイントまで素早く示されます。ただし AI は「視点の補助」であり最終判断は人間が担うべきです。契約レビューの効率化や多段階導入事例は、実務ガイドとしてまとまっているので導入検討時の参考になります(例:契約レビューの多段階導入ガイド)。
とはいえ、当時の“読み込む時間”で培った「どこがフワッとしてるか」を感じ取る力は、AI時代になっても価値を保つと思います。
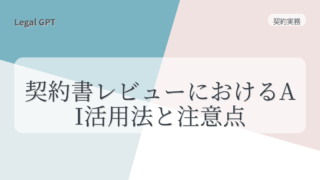
\ChatGPTをこれから使う人におすすめ!/
『はじめての生成AI ChatGPT「超」活用術』(安達恵利子 著)は、ChatGPTの基礎から実務応用までを網羅した初心者向け実践書です。
「そもそもChatGPTってどう使えばいいの?」
「どんなことができるのか、事例を交えて知りたい」
そんな方にぴったり。
・入力の基本
・正しい指示の出し方(プロンプト)
・メール・議事録・資料作成の効率化
など、仕事で今すぐ使えるノウハウが満載です。
初心者でも迷わず活用できる「3部構成」で、文系・非エンジニアでも安心!
👇Amazonで詳細をチェック

📚 さらに学びたい方に:おすすめ書籍
- 『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』(幡野直人 著)
契約書レビューの流れ・コメントの書き方など、現場で役立つ基本がこの一冊に。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。