【保存版】2025年プライバシーポリシー改定テンプレート — 法改正対応から生成AI活用まで
【保存版】2025年プライバシーポリシー改定テンプレート — 法改正対応から生成AI活用まで
2025年、個人情報保護法の見直しと生成AIの普及により、プライバシーポリシーの早急な点検が必要です。本テンプレートは、2024年改正の必須対応から2025年改正案の想定対応、生成AI利用ルールまで法務担当者が今すぐ使える実務チェックリストを含めて提供します。
はじめに:なぜ今、プライバシーポリシーの見直しが必要なのか
「うちのプライバシーポリシー、大丈夫かな?」
2025年、そんな不安を抱える法務担当者が急増しています。その背景には、個人情報保護法の継続的な改正と、生成AI普及による新たなリスクの顕在化があります。
重要な注意点
2025年8月時点では、個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに係る改正は委員会での検討が継続中であり、最終的な法案・施行時期は未確定です(個人情報保護委員会が検討資料や報告を順次公表しています)。改正案の内容は今後の議論で変わる可能性が高いため、本稿は「検討段階の想定案」を前提に記載しています。
| 区分 | 状況 | 対応優先度 | 施行予定 |
|---|---|---|---|
| 2024年改正 | 施行済(2024/4/1) | 最高 | 施行済(2024/4/1) |
| 2025年改正(3年ごと見直し) | 検討中 | 高 | 未確定(委員会で検討中) |
| 課徴金制度 | 検討課題 | 中 | 未決定 |
【緊急対応必須】2024年改正への完全対応
ウェブスキミング対策関連(施行規則第7条第3号改正)
改正背景:近年のECサイト等でのウェブスキミング被害を受け、「個人データ」になる前の「個人情報」段階での漏えい等も報告対象に拡大しています。
プライバシーポリシーへの追記例
【安全管理措置】
当社は、個人データのほか、個人データとして取り扱われることが予定されている
個人情報についても、不正目的をもって行われるおそれがある行為による漏えい等を
防止するため、以下の安全管理措置を講じています:
・ウェブサイトへの不正プログラム設置防止対策
・入力フォームにおけるセキュリティ対策の実施
・定期的なシステム脆弱性点検
・物理的な個人情報の適切な管理
今月中の必須チェック項目
- 現在のプライバシーポリシーに上記の安全管理措置が記載されているか
- 社内の漏洩対応マニュアルが2024年改正に対応しているか
- 委託先との契約書に新たな安全管理措置が盛り込まれているか
【準備推奨】2025年改正案への対応戦略(想定案)
1. 同意規制の柔軟化(検討案)
検討内容:本人同意を要しないデータ利活用の範囲が拡大される可能性があります(統計分析等)。
プライバシーポリシー記載例(検討案ベース)
【現行】
個人データの第三者提供は、原則として本人の同意を得た場合のみ行います
【改正案適用想定】
個人データの第三者提供は、本人の権利利益への直接の影響がない統計分析目的での
利用等、法令で認められた場合を除き、原則として本人の同意を得た場合のみ行います
2. 漏洩等発生時の本人通知義務の緩和(検討案)
検討内容:本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合には、本人通知を要しない方向での検討があります。通知省略の判断基準・証跡保持が重要です。
3. 委託先事業者に対する規律強化(検討案)
検討内容:DX の進展に伴い、委託先の監督義務強化が想定されます。
実務のヒント:委託先監督の実務テンプレ・チェックリストは別途用意しておくと即対応できます(実務テンプレの例は章末関連記事で参照ください)。
2025年版プライバシーポリシー改定テンプレート(本文)
基本構成(項目)
1. 事業者情報
【事業者の名称】
【所在地】
【代表者氏名】
【個人情報保護責任者】
【問い合わせ窓口】
2. 個人情報の取得・利用
【取得する個人情報の種類】
・氏名、住所、電話番号、メールアドレス
・サービス利用履歴、アクセスログ
・その他サービス提供に必要な情報
【利用目的】
・サービス提供
・問い合わせ対応
・マーケティング(同意取得済みの範囲内)
・統計分析(個人を特定できない形式)
・法令遵守
委託先管理(強化版)
当社は、個人データの取扱いを委託する場合、以下の監督を行います:
- 委託先の適格性審査
- 委託契約における安全管理措置の明文化
- 定期的な監査・点検の実施
- 委託先における事故発生時の報告義務
- 再委託時の事前承諾・同等の監督義務
実務リンク(委託先監督のチェックリスト・テンプレ参照):委託先監督・契約チェックの実務テンプレ(実務チェックリスト).
生成AI活用に関する記載(新項目)
当社が業務効率化のために生成AIを利用する場合、以下の措置を講じます:
- 個人情報を生成AIに入力することを原則禁止する。
- 業務上やむを得ず個人情報を用いる場合は、事前に仮名化・匿名化を行い、AI 利用申請書を作成のうえ情報統制担当が承認する。
- AIベンダー契約に(i)学習データの利用可否、(ii)出力物の二次利用、(iii)セキュリティ要件、(iv)事故時の報告義務を明記する。
- 出力結果は必ず人間が検証し、個人情報に係る誤用がないことを確認する。
参考:AI関連の法令・ガイドラインや法務部向けの直近チェックポイントは、AI 新法の実務ガイドが役立ちます(章末関連記事参照)。
業界別対応のポイント
金融機関
- 金融庁ガイドラインとの整合性確保
- 機微な個人情報の特別な保護措置
- システム障害時の対応手順
医療・介護
- 要配慮個人情報の適切な取扱い
- 診療情報の第三者提供基準
- 研究利用時の倫理規定
IT・通信
- 総務省ガイドラインへの準拠
- 通信の秘密との関係整理
- 海外データセンター利用時の留意点
製造業
- 取引先従業員情報の取扱い
- IoT デバイス等からの情報収集
- 国際展開時のデータ移転規制
段階的対応スケジュール(推奨)
Phase 1(2025年8月〜12月):基盤固め
- 2024年改正の完全対応完了
- 2025年改正案の詳細分析
- 現行プライバシーポリシーの全体見直し
Phase 2(2026年1月〜3月):法案成立後の迅速対応
- 確定した改正内容に基づく修正案作成
- パブリックコメント対応(該当する場合)
- 社内承認プロセスの実行
Phase 3(2026年4月〜施行前):運用体制構築
- 新プライバシーポリシーの運用開始
- 全社研修の実施
- 委託先への対応要請
今月中にやるべき具体的アクション(実務チェックリスト)
短期(今月中)
- 既存プライバシーポリシーの2024年改正対応確認(安全管理措置・漏洩時対応)
- 委託先契約書の安全管理措置条項の見直し
- 社内の漏洩対応マニュアルの更新(ランサムウェア等)
- 生成AI利用に関する暫定ルールの制定(社内禁止事項と申請フロー)
- 報告フローの試運転実施
中期(3〜6ヶ月)
- 2025年改正案の最新情報収集体制の構築
- 委託契約テンプレの見直し(再委託・監査・報告義務)
- 業界別ガイドラインの改正状況確認
- AI活用による効率化の本格検討
長期(法案成立後)
- 法案確定内容を反映した改定版の作成
- 全社研修の実施
- 外部監査を含む社内周知
- 委託先への対応要請

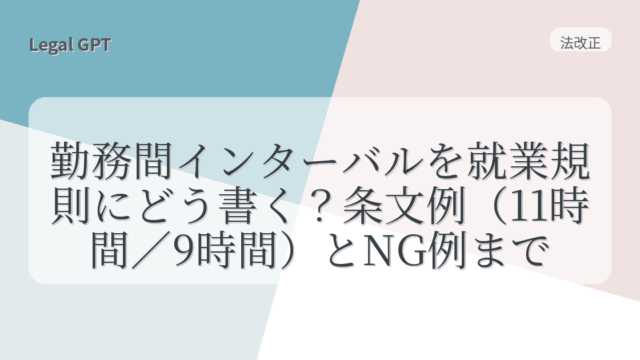
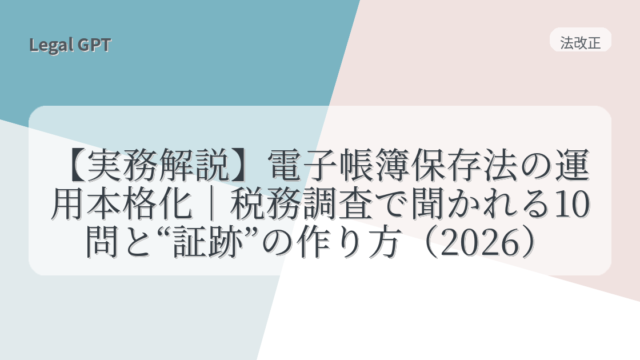
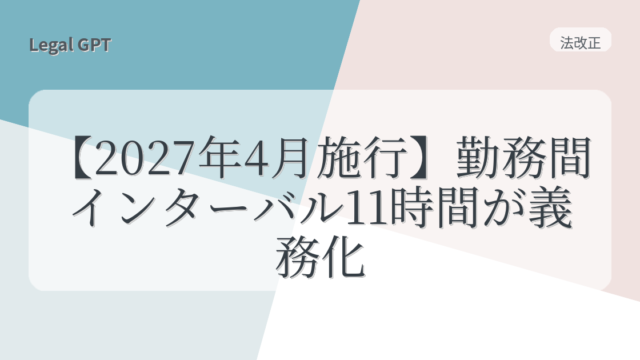

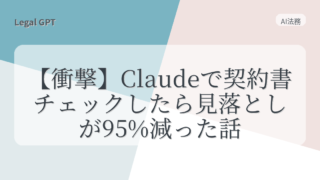



I’m no longer certain where you’re getting your information, however great topic. I must spend some time studying much more or figuring out more. Thank you for fantastic information I was in search of this information for my mission.
Thanks — I appreciate your kind words! The info comes from official sources and research materials I’ve studied, and I’m glad it helped with your mission.
Thank you for that question. You’re right to ask about my sources—that’s an important thing to check.
I wrote this post by drawing from multiple resources, though I admit I could have cited my sources more clearly. I’ve pulled from reliable websites, expert opinions, and personal experience.
[…] → 【保存版】2025年プライバシーポリシー改定テンプレート|法改正対応から… […]