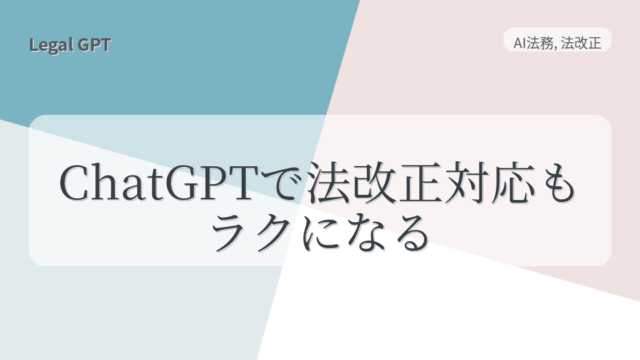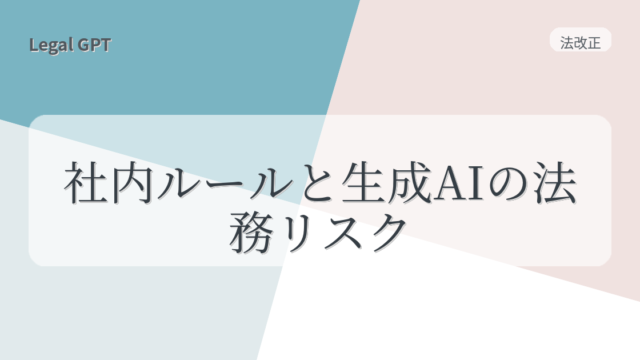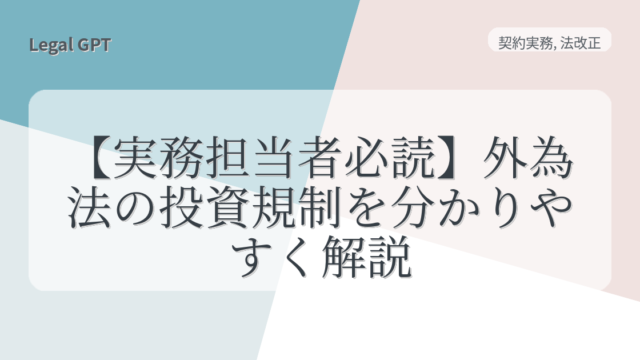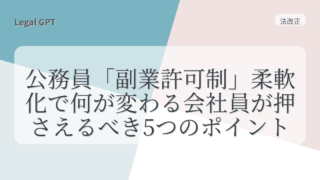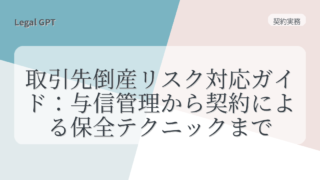独禁法チェックリスト:営業・取引先契約でやりがちなNG行為と条項修正例
独禁法チェックリスト:営業・取引先契約でやりがちなNG行為と条項修正例
法務部門必読!2025年最新法令対応版 — 営業・契約実務で陥りがちな独占禁止法リスクを条項例で示し、即実務で使える修正案とフローを提示します。
🚨 執行強化の現実 — 令和6年度の公正取引委員会による排除措置命令は21件と過去10年間で最多を記録し、延べ61名の事業者に対して法的措置が講じられました。課徴金納付命令は延べ33事業者に対し総額37億604万円に上り、企業の営業・契約実務における独禁法リスクが顕在化しています。
独占禁止法(正式名称:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的として、私的独占、不当な取引制限(カルテル、入札談合等)、不公正な取引方法などの行為を規制しています。
監視強化の具体例:令和6年度は大手損害保険会社らによる企業等向け損害保険の価格カルテル等、給食サービス提供事業者による中学校スクールランチ調理等業務の入札談合、機械式駐車装置メーカーらによる受注調整など、多様な業界で摘発が相次いでいます。
第1章:独禁法の基本構造と企業への影響
1-1. 法的根拠の整理
独占禁止法の体系
- 目的・基本理念:第1条
- 私的独占・不当な取引制限の禁止:第3条
- 不公正な取引方法の禁止:第19条
- 不公正な取引方法の定義:第2条第9項
1-2. 不公正な取引方法の法的構造
独占禁止法第2条第9項第6号に基づき、公正取引委員会が「不公正な取引方法」(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)で具体的な禁止行為を指定しています。
一般指定の主要類型(営業実務関連)
- 12項:再販売価格の拘束(RPM)
- 10項:拘束条件付取引(抱き合わせ販売等)
- 2項:排他条件付取引
- 14項:優越的地位の濫用
1-3. 違反した場合のペナルティ
- 排除措置命令:違法行為の停止・是正措置(独禁法第20条)
- 課徴金納付命令:令和6年度は33事業者に対し総額37億604万円
- 刑事罰:重大な違反には懲役・罰金(独禁法第89条等)
- 損害賠償請求:被害者からの民事訴訟(独禁法第25条)
第2章:リスクレベル別NG行為チェックリスト
🚨 リスクレベル判定表
| リスクレベル | 行為例 | 緊急度 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 🔴 RED | 価格拘束・競合排除強制 | 即座 | 法務相談必須 |
| 🟡 AMBER | 希望価格・推奨条件 | 24時間内 | 表現修正要検討 |
| 🟢 GREEN | 参考価格・協議条項 | 通常 | 定期確認 |
営業部門向け緊急チェック(即座に法務相談が必要)
- 🔴RED:即座に法務相談 — 「○円で販売せよ」「○円を下回って販売禁止」など
- 「A商品購入時はB商品も必須」
- 「当社商品のみ取扱い」「競合商品取扱い禁止」
- 「費用負担を拒否できない」
2-1. 【最重要:★★★】再販売価格維持行為(RPM)
法的根拠:独占禁止法第2条第9項第4号イ、一般指定第12項
❌NG条項例
第○条(販売価格)
甲は、本商品の販売価格を以下のとおり指定する。
・標準小売価格:10,000円
・乙は、上記価格を下回って販売してはならない。
⚠️ 問題点
「再販売価格の拘束」は、不公正な取引方法の一つとして禁止されています。消費者が価格による販売店選択ができなくなり、本来安く購入できた商品を高く購入せざるを得なくなるためです。
✅ 修正案(法的に安全な表現)
第○条(参考価格)
甲は、本商品のメーカー希望小売価格を10,000円と表示することができる。
当該価格はあくまで参考情報であり、乙の販売価格は乙が自主的に決定するものとする。
甲は乙に対し、価格違反を理由とした出荷停止、取引停止、優遇取り消し、
その他一切の不利益取扱いを行わない。
📌 重要な例外規定:書籍、雑誌、新聞、音楽CDなどの著作物に関しては、例外となっています。
(執行事例の概説は後段の「第5章:業界別注意点と最新執行動向」を参照)
2-2. 【重要度:★★★】拘束条件付取引
法的根拠:一般指定第10項
❌NG条項例
第○条(取引条件)
乙は、甲から商品Aを購入する場合、必ず商品Bも併せて購入しなければならない。
⚠️ 問題点
競合他社の商品Bの取扱いを事実上排除し、公正な競争を阻害するおそれがあります。個別事案では競争に与える影響の程度により判断が分かれる場合があります。
✅ 修正案
第○条(推奨・併用説明)
甲は、商品Aと商品Bの併用を推奨するが、乙は自己の裁量により商品を選択・購入するものとする。
甲は乙に対して商品Bの取扱いを強制することはない。
2-3. 【重要度:★★☆】排他条件付取引
法的根拠:一般指定第2項
❌NG条項例
第○条(専売義務)
乙は、本契約期間中、甲の競合他社の製品を取り扱ってはならない。
✅ 修正案(限定的・合理的範囲)
第○条(優先取扱い)
乙は甲製品を優先的に販売する努力を行うものとする。
ただし、以下の場合には制限されない:
(1) 既存契約上の義務がある場合
(2) 地域:○○県内に限定
(3) 期間:契約締結から1年間に限定
(4) 対象製品:△△シリーズに限定
2-4. 【最重要:★★★】優越的地位の濫用
法的根拠:独占禁止法第2条第9項第5号、一般指定第14項
❌NG条項例
第○条(費用負担)
乙は、甲が実施する販売促進活動に要する費用の50%を負担するものとし、
甲の要求があった場合は拒否することができない。
⚠️ 問題点
令和6年度においては、優越的地位濫用事件タスクフォースが中心となって、優越的地位の濫用に当たるおそれがあるとして複数の注意・警告が行われています。
✅ 修正案
第○条(販促費負担)
販促費の負担については、両当事者が事前に協議し合意した範囲内で実施するものとする。
甲は、乙に対して一方的に費用負担を命ずることはできない。
第3章:下請法との重複適用と2026年改正対応
3-1. 下請法改正の正確な施行スケジュール
改正法成立:2025年5月16日「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」成立。公布日:2025年5月23日。施行日:2026年1月1日(令和8年1月1日)。新法律名:「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
主要な改正点
- 従業員数基準の導入(委託先企業の従業員数が300人または100人以下の場合は対象)
- 手形払いの原則禁止(現金払いまたは電子決済への移行が必要)
- 価格交渉義務の強化(協議なき一方的な価格決定の禁止)
3-2. 独禁法×下請法 クロスチェック表
| 条項内容 | 独禁法リスク | 下請法リスク | 対応例 |
|---|---|---|---|
| 代金減額 | 優越的地位の濫用 | 代金減額の禁止 | 協議による変更条項 |
| 返品条項 | 優越的地位の濫用 | 返品の禁止 | 契約不適合時の限定 |
| 購入強制 | 拘束条件付取引 | 購入等強制の禁止 | 推奨表現への変更 |
(参考)下請法の実務チェック術に関する詳細ガイドを用意しています。社内での下請法対応のテンプレ作成や従業員数チェックについては外部記事も参照してください。下請法に違反しないためのリーガルチェック術。
第4章:実務判断フローチャート
📊 契約条項チェックフロー — 以下の手順でまず一次スクリーニングを行い、疑義箇所は速やかに法務にエスカレーションすること。
- START:契約条項の確認
- 価格関連条項はあるか? → 「指定」「定価」「拘束」の語があるか? → YESなら即時法務相談 / 参考価格表現に修正
- 取引相手との力関係は? → 優越ありなら下請法適用確認(従業員数チェック)
- 競合排除・拘束条項はあるか? → YESなら合理性・必要最小限の範囲か検証(期間・地域・製品の限定)
- END(法務最終確認)
契約書のレビュー・改善ワークフローの詳細やドラフト改善例については社内テンプレ集・契約書レビュー手順を参照してください(外部記事「契約書レビューが変わる多段階アプローチ」参照)。
第5章:業界別注意点と最新執行動向
5-1. 製造業
リスク要因:部品調達での拘束条件、技術仕様の囲い込みなど。最近の処分事例として機械式駐車装置メーカーらによる受注調整での排除措置命令が挙げられます。
5-2. 流通・小売業
リスク要因:仕入先への販売価格指示(「正価」「定価」等)の使用、棚割り強制、優越的地位を利用した不当要求。
5-3. デジタル・IT分野(新領域)
デジタル分野での執行は本格化しています。Google等のプラットフォーマーに関する事案でも確約手続を利用した処理が行われており、デジタル取引での取引妨害やプラットフォーム支配に対する監視が強まっています。
第6章:社内体制構築と継続的コンプライアンス
6-1. 予防措置の標準化
必須チェック項目
- 価格関連条項の自由度確保(「参考価格」「メーカー希望小売価格」表記)
- 強制的措置の禁止条項を明記
- 下請法適用確認(2026年対応準備)
6-2. 営業部門向け実践ガイド
✅ 適切な営業表現例 — 「参考価格として○円を提示いたします」「メーカー希望小売価格は○円ですが、販売価格は貴社でご判断ください」など。
❌ 絶対に使ってはいけない表現 — 「この価格で売ってください」「価格を下げたら取引停止」など。
第7章:グレーゾーンと例外規定
7-1. 適法性の境界線(事案別判断が必要) — 再販売価格維持の例外(書籍等)やインセンティブ制度の扱い、推奨表現の言い回しなどは個別事情で判断が分かれます。慎重に事実関係(代替手段の有無、当事者の力関係)を整理してください。
第8章:問題発生時の対応手順
8-1. 緊急対応フロー(48時間以内)
- 事実関係の調査(契約書・メール・議事録の確認)
- 法的リスクの評価(法務・外部弁護士との協議)
- 応急措置の実施(問題のある営業活動の一時停止)
- 是正措置の検討(条項修正・運用変更)
- 再発防止策の策定(社内ルール・研修の見直し)
8-2. 公正取引委員会との関係
相談制度の活用 — 令和6年度における申告件数は多数にのぼっており、事前相談を積極的に活用することは有用です。違反が疑われる場合には、自主的改善措置や公正取引委員会との協議を速やかに検討してください。
まとめ:速攻でやるべき3つのアクション
- 価格条項を見たら法務へ相談(「希望小売価格」「参考価格」への表現変更・価格違反時の不利益措置禁止の明記)
- 優越性ある場合は下請法チェック(2026年改正の従業員数基準対応・手形払い見直し)
- 参照根拠付きテンプレを使う(一般指定に準拠した条項例の整備・業界別ひな型の更新)
底線(Bottom Line):令和6年度の排除措置命令21件は過去10年間で最多という執行強化の現実を踏まえ、「知らなかった」では済まされない時代に突入しています。独禁法遵守は企業存続の基盤です。今すぐ契約書を見直し、健全な取引環境を構築しましょう。
優越的地位濫用リスクの初期診断
取引条件が独禁法違反に該当するリスクを初期段階で診断。2026年1月施行の改正下請法にも対応し、公取委からの警告・課徴金リスクを事前に回避できます。
優越的地位濫用リスク診断プロンプト
下請法・独禁法に精通したAIが、取引条件のリスクレベルを「高・中・低」で判定。改善策を優先順位付きで提案します。
📦 収録内容
- 下請法適用判定:資本金・従業員数基準で適用有無を自動判定(2026年改正法対応)
- 優越的地位の3要件分析:地位の優越性・利用・不当な不利益を法的観点で検討
- リスクレベル判定表:各項目を高/中/低で評価し、該当条項と改善策を明示
- 業種別注意点ガイド:製造業・IT・物流・建設・小売業の特有リスクを網羅
- 公取委の取締動向:2024年度の警告・注意件数と重点分野を反映
- 推奨アクションプラン:1週間/1ヶ月/3ヶ月の対応スケジュールを自動生成
💡 使い方のヒント:PDFに記載の入力情報(当事者情報・取引内容・懸念事項)を埋めてAIに送信するだけ。手形払い・価格据え置き・協賛金要請などのリスクを即座に診断できます。診断結果で「高リスク」と判定された場合は、必ず弁護士に相談してください。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。