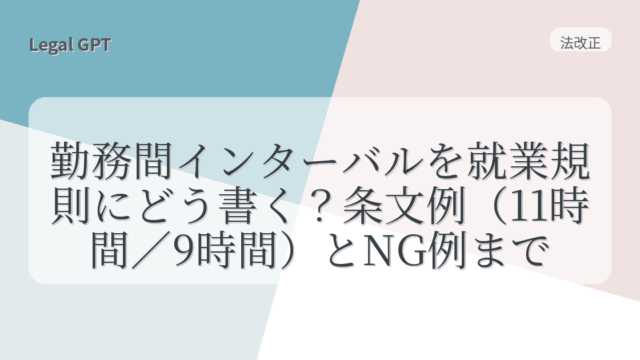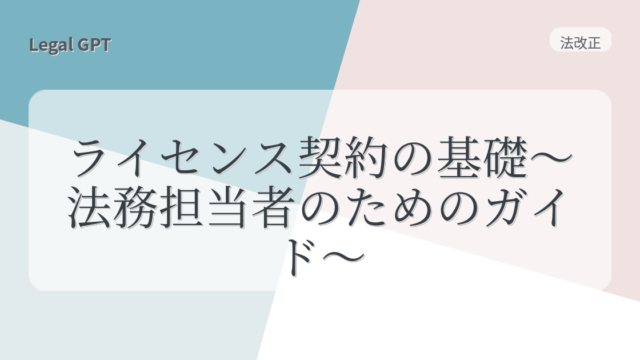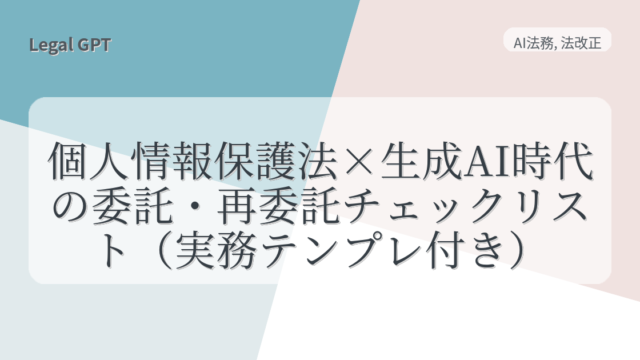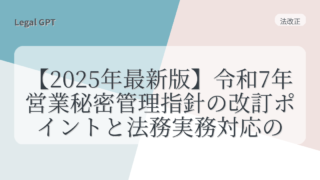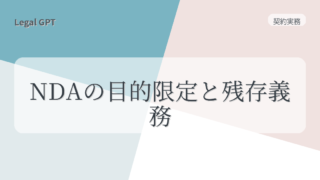改正商法・会社法の実務影響まとめ【取締役・株主総会・社外規程】2025年最新動向
改正商法・会社法の実務影響まとめ
【取締役・株主総会・社外規程】
2025年最新動向
法制審議会で審議中の会社法改正案を徹底整理。バーチャル株主総会、株主提案権の見直し、従業員への株式無償交付制度など、検討中の主要論点と実務対応案を条文ベースで解説します。各セクションで審議状況の出典を明示し、あなたの実務対応の優先順位決定をサポートします。
【結論】2025年会社法改正で企業が対応すべき3大ポイント
2025年2月に法務大臣から法制審議会に諮問され、現在審議が進行中の会社法改正では、以下の3つが主要な論点です。いずれも最終法文は未確定であり、本文中で示した出典(法務省/経産省等)を随時確認してください。(出典例:法務省議事録)
※重要な注意事項:改正法の最終的な内容および施行時期は未確定です。一般に法案成立後の施行までには数か月から数年を要することが多いですが、本件の施行時期は法案の立法過程に依存します。最新の審議状況は法務省議事録等でご確認ください。
特に注目すべきは、産業競争力強化法で上場会社に限定して特例として認められている「場所の定めのない株主総会」を会社法本体に組み込む方向で検討されている点です。これが実現すれば、非上場会社も含めて広く利用可能になる可能性があります。ただし、具体的な要件(定款規定、行政手続の要否等)は審議中であり確定していません。
1. 改正の背景と全体像
1-1. なぜ今、会社法改正なのか
会社法は2019年の改正以来5年が経過し、デジタル化の進展や企業統治の高度化、グローバル競争の激化といった環境変化に対応する必要性が高まっていました。政府の「規制改革実施計画」(2024年6月)および「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」において、具体的な検討課題が示されたことを受け、法制審議会での審議が開始されました。
改正の基本方針は「企業の稼ぐ力の強化」です。経済産業省の「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」では、企業経営者が大胆なリスクテイクを行い、成長投資を実行していくことを後押しする観点から、企業活動の基盤である会社法制の見直しを提言しています。
1-2. 改正スケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2024年9月~2025年2月 | 会社法制研究会で論点整理 |
| 2025年2月10日 | 法務大臣から法制審議会に諮問 |
| 2025年4月~ | 法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会で審議開始 |
| 2026年以降(見込み) | 法案提出・成立・施行の可能性(※審議状況により変動) |
現時点(2025年10月)の状況:法制審議会における審議が開始されたばかりであり、最終的な改正内容や施行時期は未確定です。企業は審議状況を注視しつつ、改正の方向性を踏まえた準備を進めることが推奨されます。
1-3. 諮問事項の全体構造
法制審議会への諮問事項は大きく以下の3分野に分類されます。
- 株式の発行の在り方(従業員等への株式無償交付、株式交付制度の拡充、現物出資規制の見直し)
- 株主総会の在り方(場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー)、株主提案権、書面決議制度、実質株主の把握)
- 企業統治の在り方(指名委員会等設置会社制度の見直し、社債権者集会のバーチャル化)
2. 【最重要】場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー)の会社法本体への位置づけ
2-1. 現行法の運用と特例制度
現行会社法の運用上の要点:会社法上は、株主総会の招集に際して通常「開催場所」を定める運用が通例とされています(会社法298条1項1号参照。なお、この解釈は学説・実務上の通説的説明であり、具体的事案での解釈は事案により異なります)。このため、物理的な場所を設けない「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)は、会社法の原則的な解釈では認められていないとされてきました。
産業競争力強化法による特例:2021年6月の産業競争力強化法改正により、上場会社に限り、以下の要件を満たせば「場所の定めのない株主総会」の開催が可能となりました。
- 経済産業大臣および法務大臣の確認を受ける
- 定款に「株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる」旨を定める
- 一定の省令要件(書面投票の採用、通信手段の確保等)を満たす
実務の現状:産業競争力強化法の特例を活用して場所の定めのない株主総会を開催する企業が増加しています。
2-2. 改正の検討内容
今回の会社法改正では、産業競争力強化法の特例を会社法本体に組み込む方向で検討されています。これにより、非上場会社も含めて広く利用可能とする制度設計が議論されています。
検討されている主な論点:
- 対象会社の拡大:上場会社に限定されていた制度を非上場会社にも適用する方向で検討中
- 手続の在り方:現在産競法で求められる経済産業大臣・法務大臣の確認手続について、その要否や簡素化の可能性が論点となっています。手続の扱いは審議中であり確定していません。
- 株主総会決議取消しの特則:通信障害が生じた場合の責任範囲を明確化する制度(例:故意または重過失による障害の場合に限り決議取消事由とする等)が検討されています。
2-3. 実務への影響と対応
- 会場費用・設営費用の削減
- 遠隔地・海外在住株主の参加促進
- 感染症リスクへの対応
- 複数の株主総会への参加が可能
- 通信障害による決議無効リスク
- デジタル機器に不慣れな株主への配慮
- サイバー攻撃への対応
- 株主の本人確認の困難性
【法改正確定前に準備できる事項】
- 技術インフラの検討
- バーチャル株主総会システムベンダーのリサーチ
- システム要件の整理(配信システム、バックアップ回線、セキュリティ対策)
- 定款変更案の準備
- 改正法施行後に必要となる定款変更の内容を検討
- 株主総会特別決議の準備
- 運営マニュアル案の作成
- 議事進行手順の検討
- 質問・動議の受付方法の検討
- 議決権行使の方法の検討
- リスク管理体制の検討
- 通信障害対応プランの策定
- サイバーセキュリティ対策の強化
- 法的リスクの評価(外部法律事務所との連携)
法改正確定前の準備チェックリスト
- ☐ 取締役会で場所の定めのない株主総会導入検討の方針決定
- ☐ システムベンダーのリサーチ開始
- ☐ 定款変更案の検討
- ☐ 運営マニュアル案の作成
- ☐ サイバーセキュリティ対策の検討
法改正施行後の対応チェックリスト
- ☐ システムベンダーの選定と契約締結
- ☐ 定款変更議案の株主総会上程・承認
- ☐ 必要な行政手続の実施(改正法の内容により確定)
- ☐ 株主への事前説明資料の作成
- ☐ 招集通知記載事項の整理
- ☐ 通信障害対応マニュアルの策定
- ☐ 本番前のシミュレーション実施
- ☐ 株主からの問い合わせ対応体制の構築
- ☐ 議事録作成フローの確認
3. 株式の発行に関する検討事項
3-1. 従業員等への株式無償交付制度(検討中)
現行法の状況:2019年改正で、取締役および執行役に対する株式の無償交付が認められました(会社法202条の2に基づく取扱い)。しかし、従業員や子会社の役職員への無償交付については明文規定がなく、実務では第三者割当増資等の手法を工夫して対応してきました。
改正の検討方向:従業員や子会社の役職員に対する株式の無償交付を制度化する方向で検討されています。
検討中の2つの案:
- A案(包括的方針型):取締役会決議に基づき、一定の方針の下で交付を実施
- B案(個別承認型):株主総会決議を必要とする(既存株主の利益保護を重視)
税務上の重要注意点:従業員への株式無償交付は、原則として給与所得として課税されます。株式の時価が給与所得として認定され、所得税・住民税が課税されます。
- 交付時の課税:株式交付時の時価相当額が給与所得として課税される(源泉徴収義務が発生)
- 譲渡時の課税:将来株式を譲渡した際のキャピタルゲインにも課税される(譲渡所得課税、約20%)
- 従業員の税負担:現金収入がない状態で税金が発生するため、従業員の納税資金の確保が課題
3-2. 株式交付制度の拡充(検討中)
現行制度:2019年改正で創設された株式交付制度は、親会社が自社株式を対価として他社を子会社化する場合に利用できます(会社法774条の2以下)。
改正の検討方向:
- 適用範囲の拡大:子会社株式の追加取得、外国会社の子会社化等にも適用する方向で検討
- 手続の簡素化:反対株主の株式買取請求権の廃止、債権者保護手続の廃止が論点として議論されています
3-3. 現物出資規制の見直し(検討中)
現行規制の課題:現物出資を行う際には、原則として検査役の調査が必要とされ(会社法207条1項)、手続が煩雑で時間がかかります。
改正の検討方向:
- 取締役等による評価説明や外部専門家の証明により検査役調査を不要とする方向で検討
- 不足額填補責任の範囲を合理化する方向で検討
4. 株主総会に関するその他の検討事項
4-1. 株主提案権の見直し(検討中)
現行法の要件:総議決権の1%以上または議決権300個以上を6か月以上継続して保有する株主は株主提案が可能です(会社法303条2項ほか)。
改正の検討方向:株主提案権については、議決権数基準(300個)と保有比率(1%以上)をどう組み合わせるかが議論されています。濫用的な株主提案を防止すべく、議決権数基準要件(300個)を廃止し、1%以上の保有要件に一本化する案などが論点の一つとして検討されています。
※重要:300個要件の廃止の是非が議論されている段階であり、最終的な制度設計は審議結果に依存します。現時点では確定していません。
濫用的提案の具体例:実務上、濫用的提案とされる可能性があるのは、(1)議案数が過度に多数(例:10件以上)、(2)会社の事業運営と無関係な提案、(3)株主総会の混乱を目的とする提案、などが想定されます。
4-2. 書面決議制度の要件緩和(検討中)
現行法の要件:株主総会の書面決議制度(いわゆる「みなし決議」)を利用するには株主全員の同意が必要です(会社法319条1項)。
改正の検討方向:非上場会社において書面決議が活用されている実態を踏まえ、書面決議要件を緩和する方向で検討されています。具体的には、一定割合(例:総議決権の90%以上)の株主の同意で足りるとする案などが議論されています。
4-3. 実質株主の把握制度(検討中)
背景:株主名簿に記載された株主(名義株主)と実際に株式を保有する株主(実質株主)が異なる場合があり、企業が適切にエンゲージメントを行うことが困難な状況があります。
改正の検討方向:企業が実質株主を把握するための制度整備が検討されています。具体的には、証券保管振替機構(ほふり)や信託銀行を通じて実質株主情報を取得できる仕組みを会社法に組み込む方向で議論されています。
5. 企業統治に関する検討事項
5-1. 指名委員会等設置会社制度の見直し(検討中)
現行制度の課題:指名委員会等設置会社において、指名委員会(取締役の一部のみで構成)のみが取締役の選任に関する議案の内容を決定する権限を有することは、特に取締役の過半数が社外取締役である場合には合理性が乏しいとの指摘があります。
改正の検討方向:指名委員会の権限を取締役会に移管する、または取締役会との権限分配を見直すことが検討されています。
よくある質問(FAQ)
場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー)を開催する場合、通信障害で株主が参加できなかった場合、株主総会決議は無効になりますか?
A: 改正案では、通信障害を巡る決議取消しについて、故意または重過失が認められる場合に限定する案が議論されています(現時点は検討中)。企業側は「合理的な備え」を示せるかが重要です。
リスク度:中~高実務対応のポイント:
- バックアップ回線の確保(複数の通信手段を用意)
- サイバーセキュリティ対策の実施(DDoS攻撃等への備え)
- 通信障害時の代替手段(電話会議併用、後日の継続総会開催等)の準備
- 事前の株主への周知(通信障害リスクの説明、対応方針の明示)
- 障害発生時の記録・報告体制の整備
中小企業でも場所の定めのない株主総会を導入すべきですか?
A: 中小企業においても、以下のメリットがある場合は改正法施行後の導入を検討する価値があります。
- 株主が遠隔地に居住している(地方企業で東京在住の投資家がいる等)
- 会場費用を削減したい
- 新型コロナウイルス等の感染症対策を重視したい
一方で、システム導入コスト(初期費用・年間維持費)や運営の複雑さを考慮すると、少人数の株主で全員が近隣に居住している場合は、従来のリアル株主総会で十分な場合もあります。
従業員への株式無償交付制度を導入する場合、どのような税務上の注意点がありますか?
A: 従業員への株式無償交付は、原則として給与所得として課税されます。
主な注意点:
- 交付時の課税:株式交付時の時価相当額が給与所得として課税される(源泉徴収義務が発生)
- 譲渡時の課税:将来株式を譲渡した際のキャピタルゲインにも課税される(譲渡所得課税、約20%)
- ストックオプション税制との違い:ストックオプションの税制優遇(一定要件を満たせば譲渡所得課税、給与所得課税を回避)とは異なる
- 従業員の税負担:現金収入がない状態で税金が発生するため、従業員の納税資金の確保が課題
改正法が施行される前に準備を始めるべきことは何ですか?
A: 改正法の施行時期は未確定ですが、以下の準備は今から始めることができます。
今すぐ始めるべき準備:
- 情報収集体制の構築(法制審議会の議事録や報道をモニタリング)
- 社内関係部署への共有(取締役会、経営会議での情報共有)
- システムベンダーのリサーチ(機能、費用、セキュリティ対策等)
- 外部専門家の確保(法律事務所、税理士との連携体制構築)
- 予算確保(次年度予算にシステム導入費用を計上)
株主提案権の議決権数要件が廃止されると、実務にどのような影響がありますか?
A: 仮に議決権数要件(300個)が廃止され、1%以上の保有要件に一本化された場合、以下の影響が想定されます。
想定されるポジティブな影響:
- 濫用的な株主提案の抑制
- 株主総会運営の効率化
- 真に議決権を有する株主による建設的な提案の促進
想定されるネガティブな影響:
- 一部の少数株主による正当な提案機会の喪失
- 株主との対話の機会が減少する可能性
※注意:最終的な制度設計は審議結果に依存するため、現時点では「検討中」の段階です。
今すぐ始める3つのアクション
参考資料・関連リンク
法令・公的資料
- 法務省「法制審議会第201回会議(令和7年2月10日開催)」
- 企業会計基準委員会「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」
- 経済産業省「場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度」
- BUSINESS LAWYERS「株主提案権とは?要件や行使への対応を会社法に基づき解説」
- アンダーソン・毛利・友常法律事務所「会社法改正に向けた動向と今後の実務への影響」
- ガバナンスクラウド「株主総会の書面決議(みなし決議)とは?-メリットと必要手続き」
- 法務省「法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会第1回会議」
- クリエア株式会社「第298条【株主総会の招集の決定】」
- 法務省「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会制度説明資料」
関連記事(legal-gpt.com内)
まとめ:今から始める会社法改正対応
2025年に始まった会社法改正の審議は、企業法務に大きな影響を与える可能性があります。特に、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー)の会社法本体への位置づけは、上場・非上場を問わず多くの企業にとって検討すべき重要なテーマとなる見込みです。
成功する企業の5つの特徴:
- 早期着手:法改正情報を継続的に収集し、審議段階から準備開始
- 体系的対応:場当たり的ではなく、全社的な対応計画を策定
- 技術活用:場所の定めのない株主総会システム、AI活用による業務効率化
- 専門家活用:複雑な改正内容は外部専門家と連携
- 継続改善:法改正後も継続的に制度を見直し・改善
最後に:会社法改正は、企業にとって「負担」ではなく「チャンス」です。場所の定めのない株主総会の導入によるコスト削減、従業員株式無償交付による人材確保、株式交付制度の拡充によるM&A戦略の多様化など、改正を機に自社のコーポレート・ガバナンスを見直し、競争力を高めるきっかけとしてください。
【免責事項】
本記事は2025年10月時点の法制審議会における審議状況に基づいて作成しており、最終的な改正内容や施行時期を保証するものではありません。記事中の「検討中」「審議中」と明記した事項は、今後の審議により変更される可能性があります。実際の法改正内容については、法務省等の公式発表をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の法的助言を構成するものではありません。個別の事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。
【最終更新日】 2025年10月24日
【次回更新予定】 法制審議会で改正要綱案が確定次第、内容を更新します
【更新履歴】
- 2025年10月24日:初版公開(法制審議会第1回会議の議論を反映)
会社法改正への先手対応が企業の競争優位性を決定づけます。2025年の変化を機会として捉え、より強固で効率的なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指しましょう。
法改正対応タスクリスト作成プロンプト
法改正への対応漏れを防ぎ、施行日までに確実に対応を完了させるタスクリストを自動生成。就業規則改定からシステム改修、従業員周知まで、必要なタスクを網羅的に抽出し、優先順位・担当部門・期限を明確化します。
法改正対応タスクリスト作成
育児介護休業法、個人情報保護法、労働基準法など、あらゆる法改正に対応。タスクの依存関係を整理し、現実的な期限を自動設定。施行日厳守のプロジェクト管理を実現します。
📦 収録内容
- 法改正タスクの網羅的抽出と優先順位付け
規程改定・システム改修・従業員周知など、対応に必要なすべてのタスクを自動抽出 - 実務的な期限設定と依存関係の整理
施行日から逆算し、タスク間の依存関係を考慮した現実的なスケジュールを提案 - 担当部門の明確化とマイルストーン管理
法務・人事・システム部門ごとの役割を明確化し、重要な節目を可視化 - 就業規則改定・システム改修の対応手順
労働基準監督署届出、ベンダー協議、テスト期間まで考慮した詳細手順 - 従業員周知・研修実施の計画策定
管理職研修、全社周知、申請書類改訂など、社内浸透のための具体的プラン - 施行日遵守のリスク管理とチェックリスト
遅延リスクを事前に検出し、確実に施行日までに対応を完了させる仕組み
💡 使い方のヒント: 法改正の名称・施行日・改正内容をプロンプトに入力するだけで、優先順位付きタスクリストが自動生成されます。そのままプロジェクト管理ツールに転記して進捗管理が可能です。

🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。