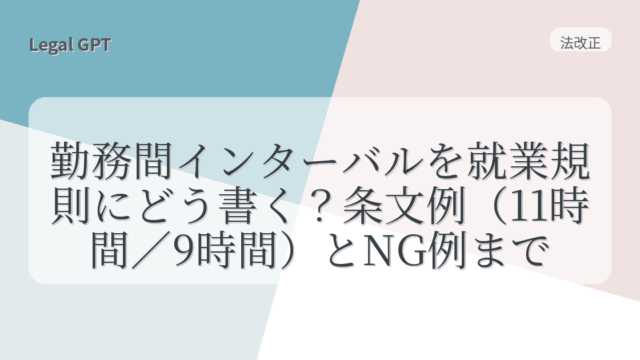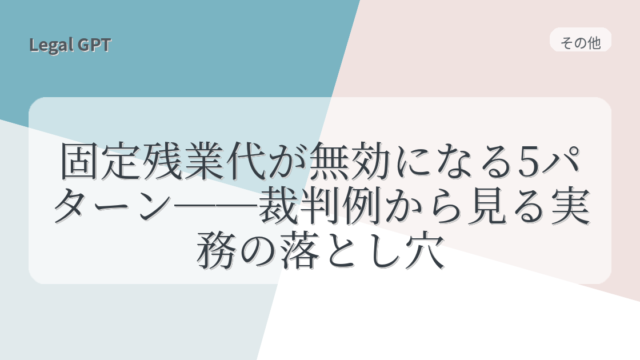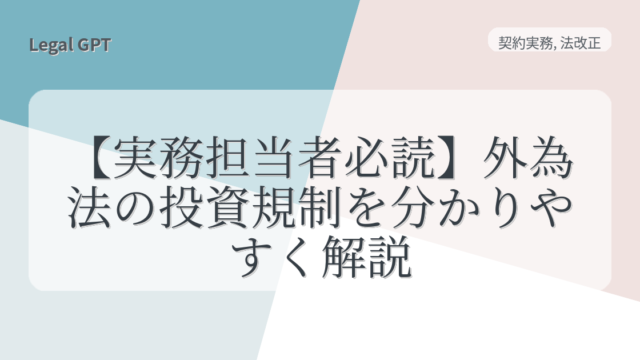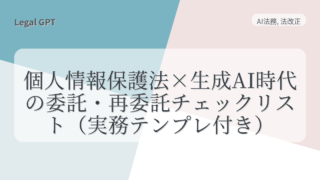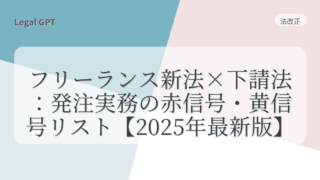【2026年1月施行】価格据え置きで社名公表も!改正下請法”協議義務”の実務対応完全版
取適法(改正下請法)への社内対応を、条文対応×チェック×文面まで一気に整備
改正対応は「理解」よりも、契約条項・運用チェック・通知/是正の文面を揃えられるかで実装が決まります。
- 条文対応(やること一覧・優先順位づけ)
- 取引実態チェック(支払期日・書面/表示・減額等)
- 契約条項の見直し(雛形差し替え)
- 社内通知・是正・取引先対応の文面
※機密情報の入力範囲・マスキングは社内ルールに従ってください。一般的情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。
【2026年1月施行】価格据え置きで社名公表も!改正下請法”協議義務”の実務対応完全版
TL;DR — 本記事の結論
はじめに(背景と施行スケジュール)
近年の物価上昇や人件費の上昇を背景に、公正取引委員会は下請法の運用基準を改正し、さらに2025年に改正下請法(通称「取適法」)が成立、2026年1月1日に施行されます。親事業者は従来の「据え置きでやり過ごす」運用から脱却し、能動的かつ記録性のある対応が求められるようになりました。[公正取引委員会]
1. 長年価格を据え置いたときの下請法上の問題点
(1) 「買いたたき」とは(条文の位置づけ)
下請法第4条第1項第5号は、親事業者が「同種又は類似の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金を不当に定めること」を禁止しています。公正取引委員会の運用基準改正は、公表資料等からコスト上昇が把握できるにもかかわらず説明なく従前単価を据え置く行為が「買いたたき」に該当するおそれがある点を明確化しています。個別事案は「協議の有無」「価格決定手法」「通常支払われる対価との乖離」を総合して判断されます。[公正取引委員会]
【重要な法的解釈】
公正取引委員会の運用基準改正は、労務費・原材料等の実質的な上昇が公表資料等から把握できる場合に、従前の単価を説明なく据え置くことが「買いたたき」(不当に低い下請代金の定め)に該当するおそれがあることを明確化しています。
個々の事案は「協議の実施状況」「価格決定方法」「通常支払われる対価との乖離」等を総合的に勘案して判断されます(ただちに違法と断定されるわけではありません)。
(2) 代表的な問題となるケース(運用基準の指摘)
公正取引委員会の改正運用基準では、次のようなケースに注意するよう示されています:
- 公表資料(賃金統計・物価指数等)からコスト上昇が明らかなのに下請代金を据え置く場合。[厚生労働省]
- 価格交渉の場でコスト上昇の反映について協議することなく据え置く場合。[公正取引委員会]
- 下請事業者が価格引上げを求めたにもかかわらず、理由を文書で示さずに据え置く場合。[公正取引委員会]
【行政執行の強化】
これらの改正により、行政は運用基準改正・転嫁支援施策(情報提供フォーム設置)・法改正により、実効性を高めています。
実際、違反行為が疑われる親事業者に関する情報を匿名で公正取引委員会に提供できる「違反行為情報提供フォーム」も設置されており、下請事業者からの申告がしやすくなっています。
2. 受注者からの価格協議要請に応じないときの改正下請法上の問題点
(1) 協議に応じない一方的な代金決定の禁止(法改正のポイント)
改正法(中小受託取引適正化法)では、中小受託事業者から価格協議の求めがあった場合、協議に応じないこと、又は必要な説明を行わず一方的に代金を決定することが禁止行為として明記されました。条文レベルで義務化されたため、単なる「協議拒否」も行政処分(勧告・社名公表等)の対象となり得ます。[公正取引委員会]
【条文レベルでの義務化】
改正法では、「中小受託事業者から価格協議を求められた場合に協議に応じないこと、又は必要な説明を行わず一方的に代金を決定すること」が禁止行為として明記されました(条文レベルで義務化)。
このため、単に「協議を拒否した」という事実自体が行政上の問題とされ得ます。行政執行(勧告・社名公表等)の根拠が法律に上がったため、従来より事態が重いことを認識する必要があります。
(2) 協議拒否・不誠実協議の具体例(実務の視点)
【協議拒否に該当する例】
- 協議要請に一切返答しない
- 「価格改定はできない」とのみ通告し協議の場を設けない
- 協議の申入れを理由なく何度も先延ばしにする
【不誠実な協議に該当する例】
- 形式的に協議は行うが、下請側資料を検討せず実質的な討議を行わない(不誠実協議)
- 下請事業者が求めた原材料費や労務費の上昇に関するデータの提供を拒否する
- コスト上昇の根拠資料を受け取っても、合理的な理由なくすべて却下する
- 協議の場で一方的に「価格据え置き」を通告するのみで、実質的な協議を行わない
3. 価格協議チェックリスト(実務対応のポイント)
(1) 要請への対応・能動的提案の判断基準
【基本的な考え方】
実務チェック(推奨)
- ☐ 協議要請の受付窓口・手続きを明確化する(メールテンプレ・受領証の発行)
- ☐ 年1回程度の定期価格見直し会等を設定する
- ☐ 公表統計(賃金・CPI等)を定期モニタリングし、閾値超過時は能動提案を検討する [厚労省統計]
- ☐ 協議要請への対応期限を社内で設定する(例:要請受付後2週間以内に初回協議日程を調整)
(2) 協議プロセスでの注意点(準備→実行→フォロー)
【協議前の準備】
- ☐ 下請側のコスト根拠を事前に収集・社内で検討
- ☐ 公表されている賃金統計、物価指数、原材料価格データ等を収集する
- ☐ 自社の予算状況と価格転嫁の可能性について社内で検討する
- ☐ 協議の日時・場所・参加者を明確にし、下請事業者に通知する
【協議の場での対応】
- ☐ 下請事業者の説明を真摯に聴く姿勢を示す
- ☐ コスト上昇の根拠について、不明点があれば質問し、必要に応じて追加資料の提出を依頼する
- ☐ 価格転嫁が困難な場合は、その理由を具体的かつ合理的に説明する(単に「会社の方針だから」「予算がないから」といった抽象的な理由は不十分)[公正取引委員会]
- ☐ 全額の価格転嫁が難しい場合でも、部分的な価格改定や他の支援策(発注量の増加、納期の調整等)を検討・提案する
- ☐ 協議の結果、価格を据え置く場合は、その判断理由を書面(電子メール可)で明確に回答する
【協議後の対応】
- ☐ 協議の内容(日時、参加者、協議事項、結論)を議事録として記録し、保管する
- ☐ 合意した価格改定内容は、速やかに契約書または注文書に反映する
- ☐ 価格据え置きとなった場合でも、次回の定期協議時期を伝える
(3) 対価算定の実務チェックポイント
【適正な対価の考え方】
- 「通常支払われる対価」を参照基準とし、従前対価と現状の経済指標を比較する
- 下請側提示の見積根拠が合理的であれば、適切に反映する
- 同業他社の水準や注文量条件(大量発注に伴う単価)を考慮する [厚労省統計]
実務上のチェックポイント
- ☐ 厚生労働省の「毎月勤労統計」、総務省の「消費者物価指数」等の公表データを確認する
- ☐ 業界団体が公表している原材料価格指数や労務費の動向に関する情報を参照する
- ☐ 従前の単価設定時期と現在の経済状況の変化を比較する
- ☐ 下請事業者が提示した見積もりの根拠を精査し、合理的と認められるコスト上昇分は適切に反映する
- ☐ 同業他社との価格水準を比較し、著しく低い価格設定になっていないか確認する
(4) 記録(立証)の留意点 — 優先順位付き
【記録の重要性】
下請法違反の調査が行われた場合、親事業者が「適切な価格協議を行った」ことを立証する責任を負います。そのため、価格協議の過程を適切に記録・保管することが極めて重要です。
【記録すべき事項(優先順位)】
- 協議要請メール(受領日時・差出人)
- 協議の議事録(日時・出席者・要旨・結論)—可能なら双方確認・署名
- 下請事業者のコスト根拠(見積・領収書・相場資料)
- 親事業者の社内稟議・決裁資料(判断理由)
- 次回協議予定・通知記録等
保管要領:下請法に基づく運用上の留意(立証のための保存)を踏まえ、最低2年間の整備・保存を推奨します。[公正取引委員会]
【記録の方法と保管】
- ☐ 議事録を作成し、可能であれば双方で確認・署名する
- ☐ 電子メールでのやり取りも記録として保管する
- ☐ 価格改定に関する稟議書や決裁書類も関連資料として保管する
- ☐ 公正取引委員会の調査に備え、速やかに提出できる形で整理・管理する
まとめ(親事業者が取るべき初動5点)
これらを怠れば、公正取引委員会による勧告・社名公表等のリスクだけでなく、取引先の信頼を損ないサプライチェーン全体の持続可能性を損なう可能性があります。適正な価格交渉を通じて、発注者・受注者が対等な関係の下で共に成長する取引環境を構築することが求められます。[公正取引委員会]
実務テンプレート集
【テンプレート①:営業向けワンセンテンス(受領確認・初期返答用)】
「御社からの価格改定要請(受領日:YYYY年MM月DD日)を確かに受領しました。提出資料を精査のうえ、○営業日以内に協議日程のご提案を差し上げます。」
【テンプレート②:協議結果の書面(価格据え置き等の説明用)】
「当社は、御社からの提出資料を確認した結果、現時点では(理由:具体的事実)により価格を据え置く判断をしました。判断理由は下記のとおりです。今後の再協議予定はXXXX年XX月です。」
参考資料(一次情報・必読)
- 公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(令和6年5月27日改正)
- 内閣官房/公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日)
- 公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」(改正法成立・施行情報)
- 公正取引委員会「違反行為情報提供フォーム」(情報提供窓口)
- 厚生労働省「毎月勤労統計」
- 総務省「消費者物価指数」
- e-Gov法令検索「下請代金支払遅延等防止法」
関連記事(legal-gpt 内の参考記事)
取適法対応、準備は進んでいますか?
AIプロンプト集で対応工数を大幅削減
契約書作成・発注書改訂・価格交渉・コンプライアンスチェック・社内研修まで、
取適法対応に必要な作業をAIで効率化するプロンプトを収録。
優越的地位濫用リスクの初期診断プロンプト
取引条件の独禁法・下請法リスクを2時間〜半日分の作業を短縮して初期診断。2026年1月施行の改正法にも対応した実務直結のプロンプトです。
優越的地位濫用リスク診断プロンプト
公正取引委員会からの警告・勧告・課徴金リスクを事前に回避するための包括的な初期診断ツール
📦 収録内容
- 下請法適用判定:2026年1月施行の中小受託取引適正化法(従業員数基準・運送委託追加)を含む適用要件を自動判定
- 優越的地位3要件分析:取引上の地位の優越性・地位利用・不当な不利益付与を体系的にチェック
- 濫用類型別リスク評価:独禁法2条9項5号イ〜ハの各類型(購入強制・協賛金・買いたたき等)への該当性を個別検討
- リスクレベル判定:各項目を高・中・低の3段階で評価し、法的根拠を明示
- 公取委取締動向参照:2024年度の警告・注意件数と価格転嫁調査の最新動向を反映
- 優先順位付きアクションプラン:即座(1週間)・短期(1ヶ月)・中長期(3ヶ月)の具体的改善策を提示
💡 使い方:PDFを開き、プロンプト本体をコピーしてお使いのAI(ChatGPT・Claude・Gemini)に貼り付けてください。【入力情報】欄に自社の取引情報を記入することで、即座にリスク診断が実行されます。
⚠️ ご注意:本プロンプトは初期診断用です。リスクが「高」または「中」と判定された場合は、必ず独占禁止法・下請法に精通した弁護士にご相談ください。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。