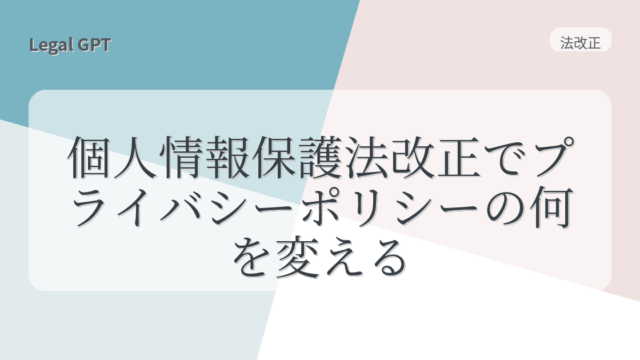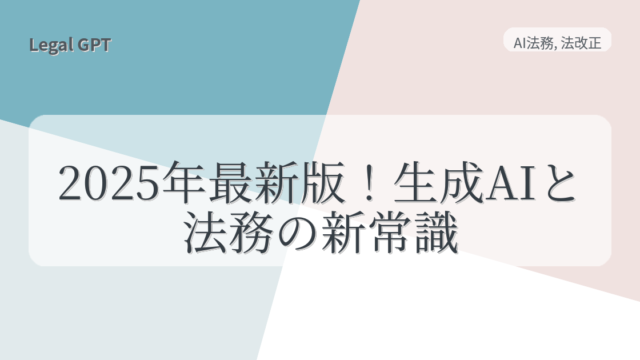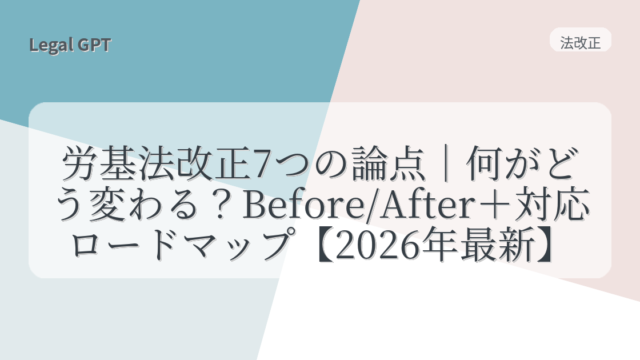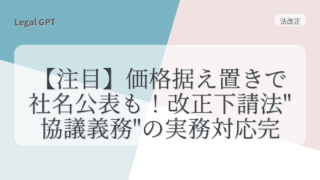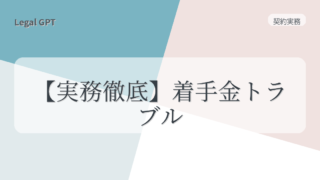フリーランス新法×下請法:発注実務の赤信号・黄信号リスト【2025年最新版】
取適法(改正下請法)への社内対応を、条文対応×チェック×文面まで一気に整備
改正対応は「理解」よりも、契約条項・運用チェック・通知/是正の文面を揃えられるかで実装が決まります。
- 条文対応(やること一覧・優先順位づけ)
- 取引実態チェック(支払期日・書面/表示・減額等)
- 契約条項の見直し(雛形差し替え)
- 社内通知・是正・取引先対応の文面
※機密情報の入力範囲・マスキングは社内ルールに従ってください。一般的情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。
フリーランス新法×下請法:発注実務の赤信号・黄信号リスト【2025年最新版】
本記事をお読みになる前に(重要)
本記事は、フリーランス法と下請法に関する一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法律相談に代わるものではありません。
- 資本金区分や取引類型の最終判断は、個別の事案ごとに異なります
- 法律の適用可否については、必ず社内法務部門または顧問弁護士に確認してください
- 契約書の作成・修正にあたっては、専門家の確認を得ることを強く推奨します
記事内の情報は2025年11月6日時点のものであり、法改正や運用の変更により内容が変わる可能性があります。
本記事の重要ポイント
- 適用判定の基本ルール:発注者・受注者の資本金区分と取引類型で判定(後述のフローチャート参照)。個別事案ごとに総合判断が必要
- 赤信号行為(即違反):法定の9項目を欠く書面交付・給付受領日から60日超の支払期日設定・事前合意なき一方的減額・報復措置
- 黄信号行為(リスク高):口頭での追加作業依頼・振込手数料の事後控除・曖昧な仕様に基づく変更要求
- 2025年の執行強化:公正取引委員会の報告によれば、令和6年度(2024年度)におけるフリーランス関係相談は5,018件、またフリーランス・トラブル110番への相談は12,323件と報告されています(出典:公正取引委員会「令和6年度におけるフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組及びフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」令和7年5月15日)
- 両法重複適用時:受注者保護の観点から、受注者にとってより手厚い(発注者の義務が重い)要件を適用。支払期日は短い方、禁止行為は両方遵守
本稿で使用する重要用語の定義
本記事では、以下の用語を以下の意味で使用します。法律の解釈については、最終的には各法律の条文および公正取引委員会等のガイドラインを参照してください。
| 用語 | 定義 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 給付受領日 | 発注者が成果物を実際に受領した日、または役務の提供を受けた日。検収完了日とは異なる点に注意 | フリーランス法第4条、下請法第2条の2 |
| 受領日 | 「給付受領日」の略称として本稿で使用 | 同上 |
| 給付 | 成果物の納品または役務の提供を指す | フリーランス法・下請法の一般的な用法 |
| 特定受託事業者 | 従業員を使用しない個人または実質的に一人で事業を行う法人 | フリーランス法第2条第1項 |
| 業務委託事業者 | 特定受託事業者に業務委託をする事業者(発注者) | フリーランス法第2条第2項 |
| 親事業者 | 資本金等が一定の金額を超える事業者で、下請事業者に製造委託等をする者 | 下請法第2条第7項 |
| 下請事業者 | 親事業者から製造委託等を受ける事業者 | 下請法第2条第8項 |
| 書面交付 | 法定の記載事項を記載した書面または電磁的記録を交付すること | フリーランス法第3条、下請法第3条 |
| 電磁的記録 | 電子契約、メール(PDF添付)等、受注者が保存・出力できる形式の記録 | フリーランス法第3条第2項、下請法第3条第2項 |
重要な注意事項
1. 給付受領日と検収完了日の違い
- 給付受領日:発注者が成果物を実際に受け取った日(物理的・データ的な受領の日)
- 検収完了日:発注者が検査を終え、合格と判定した日
- 支払期日の起算日は「給付受領日」であり、「検収完了日」ではありません
2. 契約での定義の重要性
- 本稿の定義は一般的な解釈に基づきますが、契約書内で明確に定義することで実務上の混乱を防げます
- 特に「給付受領日」は契約書の冒頭で明確に定義することを強く推奨します
3. 個別事案での判断
- 法律の適用や用語の解釈は、個別の事案や取引の実態により異なる場合があります
- 疑義がある場合は、必ず社内法務部門または顧問弁護士に確認してください
1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)と下請代金支払遅延等防止法(下請法):適用範囲の決定的違い
1-1. 3つの適用パターン
フリーランスへの発注実務では、以下3パターンのいずれかに該当します。
| パターン | フリ新法 | 下請法 | 判定要素 |
|---|---|---|---|
| ① フリ新法のみ適用 | ○ | × | 受注者が実質的に従業員なしの個人・一人法人 + 下請法の資本金要件・取引類型に該当しない |
| ② 下請法のみ適用 | × | ○ | 下請法の資本金要件・取引類型に該当 + 受注者が従業員雇用法人 |
| ③ 両法重複適用 | ○ | ○ | 下請法の資本金要件・取引類型に該当 + 受注者が実質的に従業員なしの個人・一人法人 |
重要注意点
- 「資本金1,000万円以下→フリ新法のみ」という単純な判定は不正確です
- 下請法は親事業者・下請事業者の資本金区分と取引類型(製造・修理・情報成果物・役務提供)の組み合わせで適用が決まります
- 例:親事業者が資本金5,000万円超で情報成果物作成委託を資本金5,000万円以下の下請事業者に発注する場合→下請法適用
- フリーランス新法は発注者側の資本金区分に基づく適用制限がないため、親事業者(発注者)の資本金にかかわらず、特定受託事業者への業務委託には書面交付等の義務が生じ得ます
1-2. 適用判定フローチャート
重要な前提
下請法の適用は単に資本金の大小だけで決まるものではなく、(1)発注側・受注側それぞれの資本金区分、(2)取引類型(製造・修理・情報成果物・役務等)、(3)当該取引が「事業のため」か等の要素を総合して判断します。以下は簡易判定フローですが、最終的には公正取引委員会の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」や各省のガイドラインを参照してください。
注記: 下請法適用の判定は資本金だけでなく、当該委託が「事業のため」に行われているか、受注者の業態(従業員の有無等)等を合わせて判断します。詳細は公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」参照。
1-3. 資本金区分別・取引類型別の適用一覧表
| 親事業者資本金 | 下請事業者資本金 | 取引類型 | フリ新法 | 下請法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 不問 | 全業種 | ○※ | × | ※受注者が実質的に従業員なしの個人・一人法人の場合 |
| 1,000万円超〜3億円以下 | 1,000万円以下 | 製造・修理 | ○※ | ○ | 両法重複適用 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1,000万円以下 | 情報・役務 | ○※ | ○ | 両法重複適用 |
| 3億円超 | 3億円以下 | 製造・修理 | ○※ | ○ | 両法重複適用 |
| 5,000万円超 | 5,000万円以下 | 情報・役務 | ○※ | ○ | 両法重複適用 |
フリーランス新法の適用条件
- 受注者が「従業員を使用しない個人」または「実質的に一人で事業を行う法人」
- 実質判断であり、名目的な従業員の有無だけでは判定しない
- 詳細は公正取引委員会の解釈基準を参照
取引類型の定義
- 製造委託:物品の製造・加工等を委託
- 修理委託:物品の修理を委託
- 情報成果物作成委託:プログラム、映像コンテンツ等の作成を委託
- 役務提供委託:運送、物品の倉庫保管、情報処理等を委託
2. 【赤信号】即座に違反認定される重要行為
違反時の制裁措置について
違反があった場合は、通常は(①指導・助言→②勧告→③命令→④企業名公表)という段階的措置が採られます。
フリーランス法・下請法の罰則規定
両法とも、一定の違反行為に対して罰則規定が設けられています。
- 命令違反・報告拒否等に対する罰金刑:各法律において罰金刑が規定されています
- 法人に対する両罰規定:違反行為を行った従業員個人だけでなく、法人も罰金刑の対象となります
具体的な罰則の内容:
- フリーランス法:第24条(命令違反)、第25条(報告拒否・虚偽報告・検査拒否等)、第26条(両罰規定)
- 下請法:第10条(報告拒否・虚偽報告・検査拒否等)、帳簿の作成・保存義務違反等
重要: 罰則の適用要件や具体的な金額等の詳細は、法律の条文を直接確認してください。
どの違反行為にどの罰則が適用されるかは、法文の趣旨や個別事案の状況により判断されます。疑義がある場合は、専門家(弁護士・社労士等)への相談を推奨します。
2-1. 書面・電磁的記録の交付義務違反
赤信号行為(即アウト)
- 法定の9項目(フリーランス法第3条第1項各号)を記載した書面・電磁的記録を交付しない
- 口頭発注のみで書面・電磁的記録を交付しない
- LINE・Slack・SNSメッセージのみ(受注者側でファイル保存できない形式)
- メール送信後、法定の9項目の一部が未記載
法定の9項目(フリーランス法第3条第1項)
- 給付の内容(第1号)
- 報酬の額(第2号)
- 支払期日(第3号)
- 業務委託事業者・特定受託事業者の名称(第4号)
- 業務委託をした日(第5号)
- 給付を受領する日/役務の提供を受ける日(第6号)
- 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所(第7号)
- 検査をする場合:検査完了日(第8号)
- 現金以外の支払いの場合:報酬の支払方法(第9号)
法的根拠
- フリーランス新法第3条:契約内容や取引条件を書面または電磁的方法で明確に記載する必要
- 電磁的方法の要件:受注者が将来出力・保存できる形で交付すること(PDF保存や電子契約サービスからのDL可能等)が必須条件
- 下請法では受注者の事前承諾が必要で、携帯電話メール・SMS・チャットツールは「受注者が電磁的記録を出力して書面を作成できる方法」でない場合は認められない(公正取引委員会「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」参照)
実務対応策
1. 発注時の必須チェックリスト作成
- 給付の内容(具体的に)
- 報酬額(税込表示)
- 支払期日(給付受領日から起算)
- 業務委託日
- 給付受領日・場所
- 検査完了予定日(検査ある場合)
- 支払方法
- 当事者名称
- 未定事項がある場合:理由と確定予定日
2. 電磁的方法の適合性確認(保存可能性・出力可能性がポイント)
- 📧 メール(PDF添付):○(推奨) – 受注者側でファイル保存・出力が可能
- 💻 電子契約サービス:○(条件付き) – 受注者がいつでもDL・出力できる設定を確認
- 📱 SMS・携帯メール:△〜×(リスク高) – 受注者のファイルに記録されない場合は不可
- 💬 Slack・Chatwork等:△(要確認) – エクスポート機能があり、受注者が出力可能なら可
重要: 電子的方法の可否は、受注者側で「ファイルとして保存」「書面として出力」が可能かどうかで判断します。
2-2. 報酬支払期日設定義務違反(給付受領日から原則60日以内)
赤信号行為
- 「検収完了後、翌々月末払い」(検収日次第で70日超の可能性)
- 「月末締め、翌々月末払い」(最大60日超)
- 再委託で元請入金待ち(元請支払日から30日超)
法的根拠
- フリーランス法第4条第1項:給付受領日から60日以内の「できる限り短い期間」で支払期日を設定
- 起算日は「給付受領日」:成果物を実際に受け取った日(検収完了日ではない点に注意)
- 下請法第2条の2第1項:給付の受領日(役務提供委託の場合は役務が提供された日)から起算して、60日以内において、かつ、できる限り短い期間内
実務対応策
| 従来の支払条件 | 改善後の条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 検収後翌々月末 | 受領日の翌月末 | 検収≠受領に注意 |
| 月末締め翌々月末 | 受領日の属する月の翌月末 | 最大約31日 |
| 元請入金後7営業日 | 元請支払日から30日以内 | 再委託特例適用 |
起算日の実務判定
2-3. 7つの禁止行為違反(1か月以上の継続委託)
フリーランス新法は継続的な業務委託(1ヶ月以上)が対象、下請法は単発の取引も対象
① 受領拒否
赤信号行為
- 「社内事情で不要になった」として納品物を受け取り拒否
- 納期に受け取らず、2週間放置後に「期限切れ」として拒否
- 仕様書に記載ない軽微な理由で受領拒否
グレーゾーン(黄信号)
- 明らかな仕様違反がある場合の受領保留(合理的範囲内なら可)
- ただし「仕様書が曖昧」「口頭で伝えた」は発注者側のリスク
② 報酬の減額
赤信号行為
- 一方的な報酬減額(事前合意なく報酬の減額・振込控除等を行う行為)
- 振込手数料の事後控除(発注時に明示なし)
- 「品質が想定より低い」として一方的に10%減額
- 源泉徴収税を事前合意なく控除
重要注意点
- 契約書に「振込手数料は受注者負担」と明記されていても、発注後の報酬額から事後的に控除すると減額に該当
- 事前合意があれば控除可能だが、「報酬額=手取額」と認識される可能性があるため、発注書面に明記が必須
実務対応策
③ 返品
赤信号行為
- 受領後に「やっぱり不要」として返品
- 「イメージと違う」(仕様書に定めなし)として返品
④ 買いたたき
赤信号行為
- 「一律20%コストカット」の号令で既存契約も減額
- 「競合他社はもっと安い」として不当に低い単価を強要
- 市場相場の50%以下での発注(合理的理由なし)
⑤ 購入・利用強制
赤信号行為
- 自社製品の購入ノルマ
- 会社の忘年会費用の負担要求
- 自社指定ツールの購入強制(業務に直接不要)
⑥ 不当な経済上の利益提供要請
赤信号行為
- 「ついでに資料整理も」(契約範囲外の無償作業)
- 「手が空いてるなら手伝って」(別プロジェクトへの無償参加)
- 交通費実費を支払わず無償で出張要請
⑦ 不当な給付内容変更・やり直し
赤信号行為
- 納品後に「やっぱり別デザインで」(追加費用なし)
- 「仕様変更があった」として大幅修正を無償要求
- 成果物の流用・転用(契約範囲外)
実務対応策:変更管理プロセスの明文化
2-4. 報復措置の禁止
赤信号行為(最重要)
フリーランスが行政機関に申出をしたことを理由に、取引の数量削減、取引停止その他の不利益な取扱いをすることは禁止
- 「公取委に通報したから今後の発注はなし」
- 申出後の単価引き下げ・契約更新拒否
- 社内ブラックリスト化
立証責任の注意点
- 申出と不利益処分の時系列が近い場合、因果関係が推定される可能性
- 「業績不振」等の別理由があっても、疑義を招くため慎重対応必須
3. 【黄信号】グレーゾーンだが高リスクの行為15選
3-1. 書面交付関連のグレーゾーン
① 未定事項の扱い
黄信号行為
- 報酬額を「応相談」「別途協議」として発注
- 納期を「〇月頃」と曖昧に記載
適法な対応
- 未定事項は「確定しない理由」「確定予定日」を記載
- 確定後は直ちに補充書面を交付
② 電子契約サービスの利用
黄信号行為
- クラウドサイン・DocuSign等で締結後、フリーランス側が書面をDLできない設定
- 契約書PDFを送信したが、相手方の受信確認なし
実務対応策
- 電子契約サービスの場合:フリーランスが書面出力可能な設定確認
- メール送信の場合:開封確認・受信確認を取得
3-2. 支払期日関連のグレーゾーン
③ 継続的役務提供の起算日
黄信号ケース
- 毎月のコンサルティング業務:「月末締め」の解釈が曖昧
- 継続的な記事執筆:「納品日」と「掲載日」のどちらを起算日とするか不明確
実務対応策
④ 検査期間の設定
黄信号ケース
- 「検査に最大30日を要する」と規定(給付受領日から60日超のリスク)
- 検査基準が不明確で、恣意的な不合格リスク
改善策
- 検査期間は「給付受領日から14日以内」等、60日ルールに収まる設定
- 検査基準を具体的に明記(受入テスト項目書等)
3-3. 禁止行為関連のグレーゾーン
⑤ 「軽微な修正」の範囲
黄信号ケース
| 修正内容 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 誤字脱字の修正(5箇所以内) | ✅ セーフ | 通常の瑕疵修補範囲 |
| 色調整・レイアウト微調整 | ⚠️ グレー | 契約書で修正回数明記推奨 |
| デザイン全面変更 | ❌ アウト | 不当な変更・やり直し |
契約書での明確化例
⑥ 振込手数料の負担
黄信号ケース
- 契約書に「振込手数料は受注者負担」と記載し、報酬額から控除
- 発注書面では報酬額のみ記載し、実際の振込額は手数料控除後
実務対応(3パターン)
| パターン | 記載例 | 評価 |
|---|---|---|
| ① 発注者負担 | 報酬100,000円(振込手数料は当社負担) | ◎ 最も安全 |
| ② 込み表記 | 報酬100,000円(振込手数料込) | ○ 許容範囲 |
| ③ 控除明記 | 報酬100,000円(振込手数料450円控除後、99,550円支払) | △ リスクあり |
⑦ 知的財産権の帰属
黄信号ケース
- 「成果物の著作権は全て発注者に帰属」と一方的に規定
- 二次利用・改変の権利関係が不明確
実務対応
3-4. 業界特有のグレーゾーン
⑧ IT業界:準委任契約での成果物期待
黄信号ケース
- 「準委任契約」と称しながら、実質は成果物納品を期待
- 成果物の完成度に応じて報酬を変動(請負的要素)
実務対応
- 準委任契約:「善管注意義務を果たせば報酬請求権発生」を明記
- 請負契約:「成果物完成で報酬請求権発生」を明記
- ハイブリッド型は避け、明確に区分
⑨ クリエイティブ業界:「イメージと違う」問題
黄信号ケース
- 主観的な理由で受領拒否・やり直し要求
- 「もっとこう…」という曖昧な指示での修正依頼
実務対応
1. 発注時に具体的な要件定義
- NG:「かっこいい感じで」
- OK:「ターゲット層30代男性、高級感・信頼感を重視、参考サイト3つ添付」
2. 中間確認の義務化
- ラフ案→確認→本制作→納品
- 各段階での承認を書面・メールで記録
⑩ 建設業界:材料費高騰時の価格転嫁
黄信号ケース
- 契約後に材料費が30%高騰したが、価格据え置きを要求
- 「社会情勢の変化」を理由とした一方的な価格変更拒否
実務対応
4. 両法重複適用時の実務対応
両法が同時適用される場合、3条書面と3条通知は同一の書面・電子メール等で一括提示可能
「より厳しい方を適用」の具体的判断基準
両法重複適用時は、受注者保護の観点から双方の規定を比較し、受注者にとってより手厚い(=発注者の義務が重くなる)要件を実務上採用するのが安全です。具体的には以下の項目ごとに比較し、より厳格な要件を採用します:
| 比較項目 | 判断基準 | 実務対応 |
|---|---|---|
| 書面交付義務 | 記載事項の多い方 | 両法の必須事項を網羅した統合書面を作成 |
| 支払期日 | 短い方の期日 | フリ新法60日 vs 下請法の期日→短い方を採用 |
| 禁止行為 | 両法の禁止事項すべて | フリ新法7項目+下請法11項目をすべて遵守 |
| 帳簿保存義務 | 保存期間の長い方 | 下請法の帳簿保存義務を基準とする |
| 検査期間 | 合理的期間内 | 給付受領日から60日以内に収まる検査期間設定 |
重要: 「より厳しい方」とは、受注者(フリーランス・下請事業者)にとって有利な方を意味します。発注者側の義務が重い方、受注者側の権利が手厚く保護される方を採用してください。
4-1. 書面交付義務の統合対応
必要記載事項の比較
| 項目 | フリーランス新法 | 下請法 | 統合記載例 |
|---|---|---|---|
| 給付内容 | ○ 具体的に | ○ 具体的に | 「〇〇システムのUI設計・実装(Python/Django)」 |
| 報酬額 | ○ 税込 | ○ 税込 | 「金500,000円(消費税込550,000円)」 |
| 支払期日 | ○ 60日以内 | ○ 60日以内 | 「成果物受領日の翌月末日」 |
| 下請法特有事項 | – | ○ | 親事業者・下請事業者名、発注日 |
4-2. 支払期日の統合ルール
安全策:最短期日を採用
| 取引類型 | 下請法 | フリ新法 | 採用すべき期日 |
|---|---|---|---|
| 製造委託 | 60日 | 60日 | 60日(同じ) |
| 修理委託 | 60日 | 60日 | 60日(同じ) |
| 情報成果物作成 | 60日 | 60日 | 60日(同じ) |
| 役務提供 | 60日 | 60日 | 60日(同じ) |
重要: 両法重複適用時は、より厳格な(短い)支払期日を採用することでコンプライアンスリスクを回避できます。
4-3. 禁止行為の統合チェックリスト
| 禁止行為 | フリ新法 | 下請法 | 統合チェック |
|---|---|---|---|
| 受領拒否 | ○ | ○ | 両法で禁止 |
| 報酬減額 | ○ | ○ | 両法で禁止 |
| 返品 | ○ | ○ | 両法で禁止 |
| 買いたたき | ○ | ○ | 両法で禁止 |
| 購入強制 | ○ | ○ | 両法で禁止 |
| 利益提供要請 | ○ | ○ | 両法で禁止 |
| 不当な変更 | ○ | ○ | 両法で禁止 |
| 支払遅延 | 別規定 | ○ | 下請法で禁止 |
| 不当な給付内容決定 | × | ○ | 下請法のみ |
| 割引困難な手形交付 | × | ○ | 下請法のみ |
5. 2025年の執行動向と違反事例
5-1. 初の行政指導事例(2025年3月28日)
公正取引委員会による45事業者への指導
2025年3月28日、公正取引委員会はフリーランス新法施行後初となる行政指導を実施しました。45名の事業者に対して、取引条件の明示義務などに違反しているとして是正を求める指導が行われました(出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章に基づく行政指導について」令和7年3月28日公表)。
指導対象業種
- ゲーム関連
- アニメ制作
- リラクゼーション
- その他サービス業
違反内容(推定)
- 取引条件の書面明示義務違反(口頭発注、電子メール等での明示不備)
- 報酬支払期日の設定義務違反
- 必須記載事項(9項目)の一部欠落
企業への影響
- 初回の指導段階のため企業名は非公表
- 今後、勧告に従わない場合は「勧告→命令→企業名公表→罰金」へとエスカレーション
- 業界団体への注意喚起により、同種違反の未然防止を促進
実務への示唆
この初の行政指導は、公正取引委員会が「施行初年度でも違反には厳格に対応する」姿勢を示したものです。特に以下の点に注意が必要です:
- 口頭発注の完全禁止:慣習的な口頭発注は即座に是正対象
- 電子メールの記載不備:9項目の記載が不完全な場合も指導対象
- 業界慣行の見直し:「業界ではこれが普通」は通用しない
5-2. 2024年度の執行状況
公正取引委員会における令和6年度(2024年度)の相談対応状況
公正取引委員会の報告によれば、令和6年度におけるフリーランス関係相談は5,018件でした(出典:公正取引委員会「令和6年度におけるフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組及びフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」令和7年5月15日)。
また、フリーランス・トラブル110番(第二東京弁護士会運営)では、令和6年度に12,323件の相談に対応しました(出典:同上)。
相談内容の内訳(推定)
- 取引条件明示関連:約30%
- 報酬支払関連:約25%
- 禁止行為関連:約20%
- ハラスメント・就業環境:約15%
- その他:約10%
注記: 上記の内訳は公表資料から推定したものです。詳細な内訳については公正取引委員会の運用報告書を参照してください。
5-3. 下請法との比較
| 項目 | フリーランス新法(2024年度) | 下請法(参考:2023年度) |
|---|---|---|
| 相談件数 | 5,018件 | 約23,000件 |
| 行政指導 | 初事例(2025年3月) | 年間約7,000件 |
| 勧告 | 0件 | 年間約10件 |
分析:フリーランス新法は段階的執行の方針
- 施行初年度は啓発・相談対応中心
- 2025年度以降、行政指導・勧告の増加が予想される
6. 実務担当者向けチェックリスト
6-1. 発注前チェック(10項目)
- 1. 受注者は「従業員なしの個人・一人法人」か確認
- 2. 自社資本金を確認(1,000万円超→下請法も検討)
- 3. 取引内容が下請法4類型に該当するか判定
- 4. 適用法令を確定(フリ新法のみ/下請法のみ/両法)
- 5. 発注書面に9項目(または3条書面項目)記載
- 6. 報酬額は税込表示(振込手数料の扱い明記)
- 7. 支払期日は給付受領日から起算して設定
- 8. 電磁的方法の場合、受信確認・保存可能性確認
- 9. 未定事項がある場合、理由と確定予定日を記載
- 10. 社内稟議・承認プロセスを経ること
6-2. 契約履行中チェック(8項目)
- 1. 仕様変更は書面・メールで記録
- 2. 追加作業は追加報酬の合意を取得
- 3. 「ついでに」依頼は厳禁
- 4. 修正依頼は契約書の範囲内か確認
- 5. 振込手数料等の控除は事前合意の範囲内か
- 6. 納品物の受領を遅延させない
- 7. 検査は合理的期間内に完了
- 8. 不当な受領拒否・返品をしない
6-3. 支払時チェック(6項目)
- 1. 支払期日を厳守
- 2. 減額・相殺は契約書の範囲内か
- 3. 振込手数料の扱いは契約通りか
- 4. 源泉徴収は事前合意があるか
- 5. 支払通知書・支払明細を送付
- 6. 支払記録を保存(帳簿記載義務)
6-4. トラブル発生時チェック(5項目)
- 1. フリーランスからの申出・通報の有無確認
- 2. 報復措置の禁止を社内周知
- 3. 弁護士・社労士への相談
- 4. 公正取引委員会・厚労省への事前相談(任意)
- 5. 証拠資料の整理(契約書・メール・議事録等)
7. よくある質問(FAQ)
A: 原則として、親事業者の資本金が1,000万円以下でかつ当該取引が下請法の4類型(製造・修理・情報成果物・役務提供)に該当しない場合は、下請法の適用はないことが多いです。ただし、下請法の適用は(親事業者・下請事業者双方の資本金区分、取引類型、当該業務が「事業のため」の委託かどうか等)を総合的に判断するため、個別事例ごとに判断が分かれる可能性があります。
実務上の判断基準
- 親事業者・下請事業者の資本金区分の確認
- 取引が下請法4類型に該当するかの確認
- 当該取引が「事業のため」に行われているかの確認
最終的な判断については、公正取引委員会の「下請法の運用基準」や「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」を参照してください。
安全策としての対応
資本金1,000万円以下の企業であっても、フリーランスへの発注時はフリーランス法の義務(書面交付・60日ルール等)を確実に履行することで、法令遵守リスクを最小化できます。
A: 3条通知と3条書面の交付をそれぞれ行う必要はなく、受注者に対して同一の書面や電子メール等で両法が定める記載事項を併せて一括で示す形で構いません。ただし、各法律の必須記載事項をすべて網羅する必要があります。
A: 60日の起算点は「給付受領日」です。例えば、1月15日に成果物を受け取り、1月31日に検収完了した場合、起算日は1月15日となり、支払期日は3月15日までとなります。契約書で「給付受領日」の定義を明確化することを推奨します。
A: フリーランス新法の7つの禁止行為は、継続的な業務委託(1ヶ月以上)が対象です。1か月未満の単発契約には禁止行為規定は適用されませんが、書面交付義務・60日ルール・ハラスメント対策は期間に関わらず適用されます。
A: 契約時に「振込手数料込の報酬額」として明記していれば違法ではありません。ただし、発注時に決定した報酬額から事後的に控除すると「報酬の減額」に該当するリスクがあります。安全策として「報酬100,000円(振込手数料込)」または「報酬100,000円+振込手数料は当社負担」と明記することを推奨します。
参考文献・法令リンク
法令
行政機関資料
公正取引委員会
- フリーランス法特設サイト
- フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組
- フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章に基づく行政指導について(令和7年3月28日公表PDF)
- 令和6年度におけるフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組及びフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況(令和7年5月15日)
- 下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項
中小企業庁
厚生労働省
内閣官房
ガイドライン・解釈指針
- フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和6年10月18日改定)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(公正取引委員会・厚生労働省)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(公正取引委員会)
相談窓口
- フリーランス・トラブル110番(無料法律相談・第二東京弁護士会運営)
- 公正取引委員会 相談窓口
まとめ
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)と下請代金支払遅延等防止法(下請法)の「赤信号・黄信号」を理解することで、発注実務のリスクを大幅に低減できます。
今すぐ実施すべきアクション
- 適用法令の判定:自社の資本金区分と取引類型から適用法令を確定(個別事案ごとに総合判断)
- 発注フローの見直し:法定9項目の書面交付・給付受領日から60日以内の支払期日設定を徹底
- 禁止行為の社内周知:営業・調達部門への研修実施
- 契約書の改定:統合発注書のテンプレート整備(ただし個別事情に応じた調整が必要)
- 定期的なコンプライアンスチェック:四半期ごとの自己点検
両法重複適用時の重要原則
受注者保護の観点から、双方の規定を比較し、受注者にとってより手厚い(=発注者の義務が重くなる)要件を実務上採用するのが安全です。
令和6年度は5,018件の相談があり、今後行政指導・勧告の増加が予想されます。早期の対応により、企業名公表・罰金といったレピュテーションリスクを回避し、優秀なフリーランスとの信頼関係を構築することが可能です。
法令遵守は単なるコストではなく、持続可能な発注体制の構築による競争優位の源泉となります。本記事のチェックリストを活用し、安全かつ効率的な発注実務を確立しましょう。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法律相談に代わるものではありません。
特に以下の事項については、必ず専門家(社内法務部門・顧問弁護士)に確認してください:
1. 適用法令の最終判断
- 自社の資本金区分と取引類型の組み合わせによる法律の適用可否
- 「従業員を使用しない」の実質判断
- 「事業のため」の委託に該当するかの判断
2. 契約書の作成・修正
- 統合発注書テンプレートの自社への適用可能性
- 業界特有の条項・リスクの検討
- 知的財産権、秘密保持、損害賠償等の重要条項
3. 個別事案での対応
- 違反の有無の判断
- 行政機関からの問い合わせへの対応
- 訴訟・紛争への対応
法改正・運用変更のリスク
本記事の情報は2025年11月6日時点のものです。法改正やガイドラインの改定により、内容が変更される可能性があります。最新の情報は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の公式サイトで確認してください。
本記事の使用により生じた一切の損害について、当サイトは責任を負いかねます。
フリーランス法への対応、まだ手作業でやりますか?
契約書チェック、発注書作成、禁止行為の判定、トラブル時の対応文書——
これらをAI×専門プロンプトで効率化。コピペで即利用可能です。
📚 収録内容(全7章)
優越的地位濫用リスクの初期診断プロンプト
取引条件の独禁法・下請法リスクを2時間〜半日分の作業を短縮して初期診断。2026年1月施行の改正法にも対応した実務直結のプロンプトです。
優越的地位濫用リスク診断プロンプト
公正取引委員会からの警告・勧告・課徴金リスクを事前に回避するための包括的な初期診断ツール
📦 収録内容
- 下請法適用判定:2026年1月施行の中小受託取引適正化法(従業員数基準・運送委託追加)を含む適用要件を自動判定
- 優越的地位3要件分析:取引上の地位の優越性・地位利用・不当な不利益付与を体系的にチェック
- 濫用類型別リスク評価:独禁法2条9項5号イ〜ハの各類型(購入強制・協賛金・買いたたき等)への該当性を個別検討
- リスクレベル判定:各項目を高・中・低の3段階で評価し、法的根拠を明示
- 公取委取締動向参照:2024年度の警告・注意件数と価格転嫁調査の最新動向を反映
- 優先順位付きアクションプラン:即座(1週間)・短期(1ヶ月)・中長期(3ヶ月)の具体的改善策を提示
💡 使い方:PDFを開き、プロンプト本体をコピーしてお使いのAI(ChatGPT・Claude・Gemini)に貼り付けてください。【入力情報】欄に自社の取引情報を記入することで、即座にリスク診断が実行されます。
⚠️ ご注意:本プロンプトは初期診断用です。リスクが「高」または「中」と判定された場合は、必ず独占禁止法・下請法に精通した弁護士にご相談ください。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。