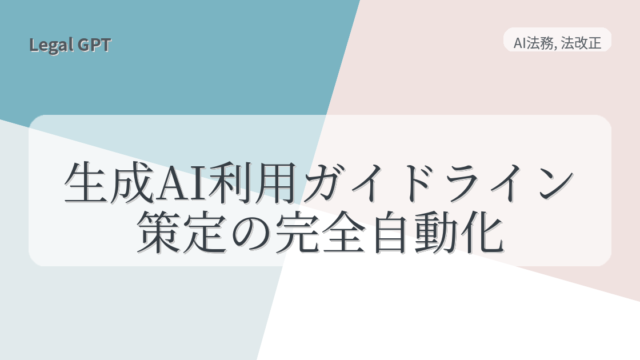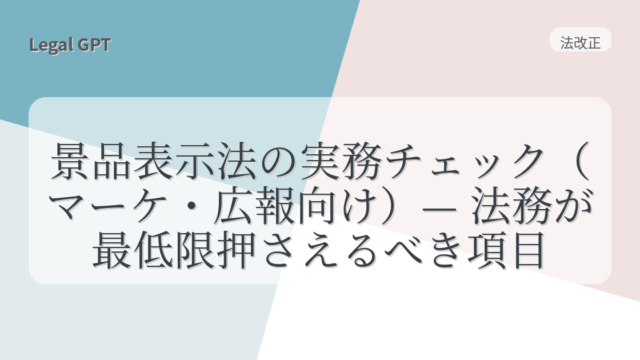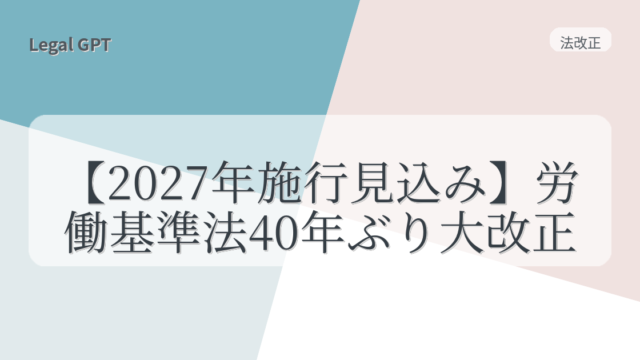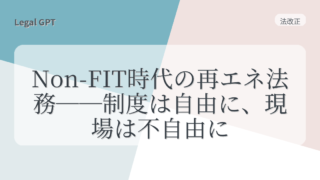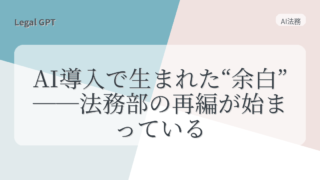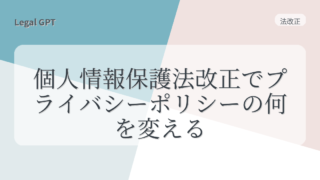社内ルールと生成AIの法務リスク
社内規則に利用制限がある場合は「その範囲内」で
社内で生成AI利用に関する規制がある場合は、定められたルールの範囲内のみで利用する必要があります。単に「便利だから」と使うと、懲戒や事故時の責任追及につながる恐れがあります。
典型的な社内規程の例:
- 外部 AI サービスの業務利用禁止
- 個人情報・機密情報の入力禁止
- 業務利用には情報セキュリティ部門の事前承認を要する
違反した場合、懲戒処分や事故対応時の責任追及が生じる可能性があります。ルールを逸脱した “運用” は重大なリスク行為です。
個人情報の入力は”別格のリスク”
個人情報(氏名・連絡先・顧客固有情報など)を生成AIへ入力する行為は、本人の同意がない第三者提供に該当する可能性があり、個人情報保護法上の問題となり得ます。送信行為自体が問題になるおそれがあるため、絶対に避けるべきです。
■ 個人情報保護法違反の可能性
仮に AI が情報を長期記憶しない仕様であっても、送信によって外部の処理系に渡す行為は第三者提供に当たるケースがあります。安易な入力は法的リスクを伴います。
■ 再識別のリスク
匿名化されていると思われる情報でも、他情報と突合されることで個人が特定される「再識別リスク」があります。これも広義の個人情報の扱いと考えて慎重に扱ってください。
■ 社内処分・行政対応のリスク
個人情報の誤送信が発覚した場合、就業規則に基づく懲戒・個人情報保護委員会への事故報告・レピュテーションリスクが想定されます。
AI出力内容の誤用にも注意
生成AIは「もっともらしい」出力を返すことがありますが、内容が事実や法令に適合しない場合があります。特に契約条文案や法的助言をそのまま転用するのは危険です。
- 契約書案が実務的に不適切である
- 古い法制度や誤訳に基づく誤情報が含まれる
- 条件や背景に合わない汎用的な助言が提示される
出力をそのまま社内文書や対外資料に使うことは避け、必ず人間のレビュー(検証)プロセスを挟むことが必須です。
法務部門に求められる対応
生成AI の社内利用が広がる中、法務は以下を主導することが期待されます。
- AI 利用ガイドラインの策定(利用範囲・禁止事項・承認フロー)
- 研修・周知活動の実施(具体例を交えた啓発)
- 個別業務へのレビューと助言(社内ルール運用の相談窓口)
禁止だけでなく「どう使えば安全か」を示す実践的な運用ルールを作ることが現場で受け入れられるポイントです。
参考(社内運用のテンプレ・実務ガイド): 法務部門向け AI 利用ガイドライン(テンプレ例)
まとめ:法務は”AI活用の交通整理役”
個人情報の入力は例外なく NGという共通認識を徹底するとともに、運用ルールを定期的に見直すことが重要です。法務はブレーキ役であると同時に、安全な活用を促すナビゲーターでもあります。
\ChatGPTをこれから使う人におすすめ!/
『はじめての生成AI ChatGPT「超」活用術』(安達恵利子 著)は、ChatGPTの基礎から実務応用までを網羅した初心者向け実践書です。
「そもそもChatGPTってどう使えばいいの?」
「どんなことができるのか、事例を交えて知りたい」
そんな方にぴったり。
・入力の基本
・正しい指示の出し方(プロンプト)
・メール・議事録・資料作成の効率化
など、仕事で今すぐ使えるノウハウが満載です。
初心者でも迷わず活用できる「3部構成」で、文系・非エンジニアでも安心!
👇Amazonで詳細をチェック

🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。