AI時代の法務部──これからの役割と、新任法務が最初にやるべきこと
AI時代の法務部──これからの役割と、新任法務が最初にやるべきこと
導入:AIが定型業務を代替する今、法務の主戦場は「設計・翻訳・調整」へと移行しています。本稿は新任法務や法務部の実務担当者向けに、最初に押さえるべき観点と実務で使えるAI活用例を整理します。
法務部はこれからどう変わるのか?
1. 「契約書を読む人」から「仕組みを整える人」へ
契約書の一次チェックやリスク抽出はAIが高速化します。代わりに法務は契約プロセス全体の設計やリスク分担のルール作りに時間を割く必要があります。関連して、最新のAI規制や企業の対応事例については当サイトの解説「2025年AI新法施行|法務部が今すぐ対応すべき3つのチェックポイント」を参照してください(社内ガイドライン整備の実例あり)。(AI新法対応ガイド)
従来の法務
- 契約書の条文チェック
- 個別案件のリスク判定
- 定型的な法的問題への対応
これからの法務
- 契約プロセス全体の構築・改善
- リスクの予見・分担をビジネス目線で調整
- 経営判断の土台となる「ルール」と「仕組み」を整備
2. 「調整力」と「翻訳力」が価値になる
単に法律を知っているだけでなく、ビジネスインパクトに翻訳できる能力が重要です。AIツールの種類や法務適用例については当サイトの技術比較記事や「思考型法務」の議論が参考になります。(思考 vs 作業の記事)
新任法務がまず取り組むべき3つのこと
1. AIが使える業務領域を見つける
- 契約書ドラフト作成の補助(機密情報は除く)
- 法改正情報の要約・整理
- 社内研修資料の下書き作成
ポイント:「任せられる作業」と「人がやるべき判断」を明確に線引きすること。
2. 自社の「文脈」を学ぶ
過去のトラブル、意思決定スタイル、重視する会社価値(信用・スピード等)を把握することが重要です。先輩や営業に同行して現場の空気を掴みましょう。
3. 「契約を見る」より「全体を見る」
起案・承認・署名・保管までのプロセス整備や、契約管理システム連携を優先的に改善すると、現場の遅延やリスクが減ります。
AI活用の具体例:法務での実践
📋 契約書レビュー支援
- 入力: 契約ドラフト(個人情報・機密情報は除外)
- 出力: 一般的なリスクポイントの指摘
- 人間の仕事: 自社固有リスク判定と交渉戦略の決定
📝 社内規程の下書き
- 入力:「テレワーク規程を作りたい。従業員50名、IT企業」
- 出力: 規程のたたき台
- 人間の仕事: 実情に合わせた調整と法的精査
📚 法改正情報の整理
- 入力: 官報や省庁の告知文
- 出力: ポイントを整理した要約
- 人間の仕事: 自社影響度判定と対応策立案
採用や評価の観点でもAIスキルの重要性が高まっています(参考:法務採用動向記事)。(採用動向)
おわりに:AI時代の法務部は「翻訳者」から「設計者」へ
AIは単なる効率化ツールではなく、法務の仕事の「質」を変える機会です。若手法務はまず全体を俯瞰し、仕組みづくりとビジネス視点の翻訳力を磨いてください。
\ChatGPTユーザー必読!/
『ChatGPT はじめてのプロンプトエンジニアリング』(本郷喜千 著)は、生成AIの指示出しスキル=プロンプトエンジニアリングをやさしく解説した入門書です。
「AIにどう指示すればうまく動いてくれるのか?」
「仕事を効率化する“言葉の魔法”を身につけたい!」
そんな方にぴったり。初心者でも実践できる豊富なプロンプト例とともに、体験型で学べます。
AI時代の必須スキルを、この一冊から始めてみませんか?
👇Amazonでチェックできます:

📚 さらに学びたい方に:おすすめ書籍
- 『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』(幡野直人 著)
契約書レビューの流れ・コメントの書き方など、現場で役立つ基本がこの一冊に。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

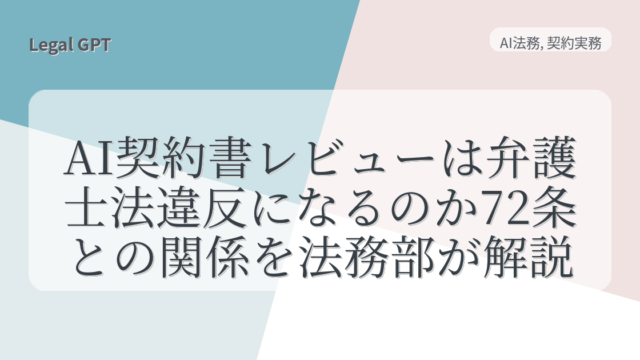
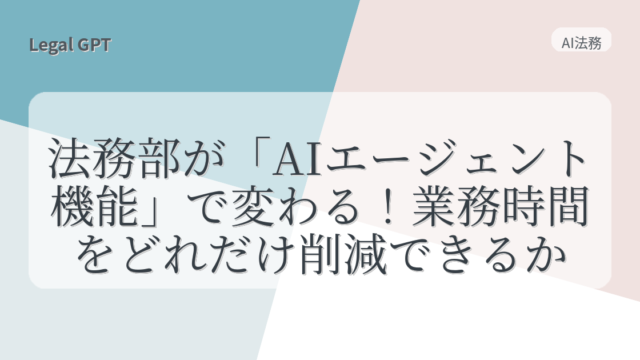
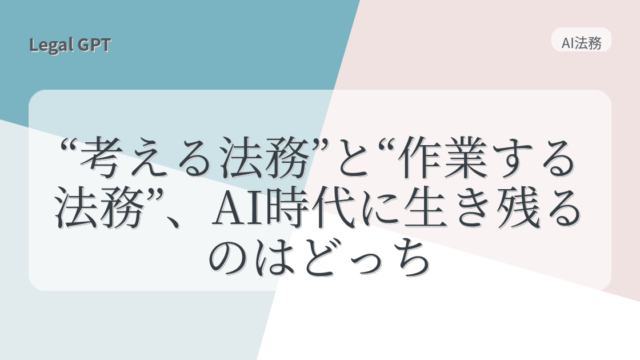
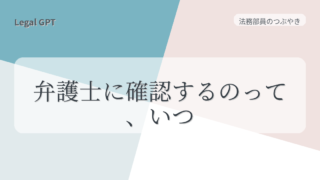
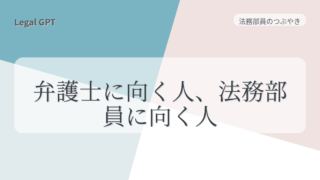



[…] 行政監督が強い業界では、まず所管省庁への照会が先に有効になることが多く、条文解釈だけでなく「運用実態」を踏まえた判断が求められます(参照:「AI時代の法務部」解説記事)。 […]