契約書の「甲乙」の決め方 ~こだわる会社とそうでない会社の違い~
レビュー方針→論点抽出→修正文案→交渉論点まで、“漏れない型”で揃える
契約レビューは、経験者でも「抜け」が起きやすい作業です。STEP化して再現可能にすると、品質が安定します。
- 前提整理(当事者/取引/優先順位)
- 地雷条項の抽出(損害賠償・解除・保証・責任制限など)
- 修正文案・代替案・交渉論点(説明つき)
- レビュー結果の報告書・メール文面まで
※機密情報の入力範囲・マスキングは社内ルールに従ってください。一般的情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。
契約書の「甲乙」の決め方
こんな組織に遭遇したことはありませんか?
営業部:「ちょっと待って。うちが甲で相手が乙だよね?」
法務部:「…はい。では改めて、第3条の責任条項ですが—」
営業部:「甲乙、間違いない?本当に?」
一方で「甲乙なんてどっちでもいいでしょ」という会社もある。
実は、「甲乙」の決め方には、その会社の「取引スタンス」や「組織文化」が如実に現れます。結論から言うと、法的には全く差がないのに、なぜか心理的・慣習的に大きな意味を持ってしまう。これが「甲乙問題」の本質です。
法務部で10年以上契約書を見てきた経験から、このような「本質的でないが無視できない問題」をいかにスマートに処理するかが、信頼される法務部員の条件だと感じています。
今回は、契約実務の現場で見えてくる「甲乙問題」の実態と、法務部としての適切な対応を整理してみました。
📋そもそも「甲乙」に法的な意味はあるのか?
結論:法的効力に差はない
まず大前提として、契約書において「甲」と「乙」のどちらが先に記載されていても、法的な効力や当事者の地位に差はありません。
民法第95条(意思表示の解釈)等をはじめとする法律では、契約当事者の記載順序について特段の定めはなく、契約の有効性や解釈に影響を与えることもありません。つまり、甲乙の順序は法的には完全に「無意味」です。
判例でも同様:最高裁判例では、当事者の記載順序に関わらず契約の有効性が認められており、甲乙の順序が争点となった事例は存在しません※1。
では、なぜこだわるのか?
法的には無意味でも、実務上は以下のような「心理的・慣習的意味」があります:
心理的優位性の表現
- 「甲」が先頭=主導的立場の印象
- 取引における主従関係の暗示
- 「格上感」の演出
社内政治への配慮
- 営業部門からの要望対応
- 経営陣の「面子」への配慮
- 稟議書類での「見栄え」重視
業界慣行・過去の経緯
- 「いつもうちが甲だから」
- 取引先との力関係の慣例化
- 契約金額の大小による慣習
🏢「甲乙」にこだわる会社の特徴
パターン1:伝統的大手(製造・金融)
特徴
- 歴史ある大企業、特に製造業
- 階層的な組織文化と内部統制重視
- 取引先との「格差」を重視
こだわる理由
- 「当社は業界のリーディングカンパニー」意識
- 下請け・協力会社との明確な上下関係
- 社内稟議・コンプライアンス文化での「体裁」重視
- 内部統制上の一貫性確保
実際の声
「株主総会で『乙』の契約書を見せるわけにいかない」
「監査法人からも体裁の統一を求められている」
パターン2:営業主導(BtoB営業・サービス業)
特徴
- 営業部門の発言力が強い
- 顧客との関係性を最重視
- 契約書も「営業ツール」かつ「信頼醸成手段」
こだわる理由
- 顧客に対する「敬意の表現」
- 営業担当の「メンツ」保持
- 次回交渉での心理的優位確保
- クライアントとの信頼関係構築の一環
実際の声
「甲乙で契約が決まることもある」
「長期取引のためには相手の気持ちも大事」
🤝「甲乙」にこだわらない会社の特徴
パターン1:合理主義的企業(IT・コンサル系)
特徴
- IT・コンサル系企業に多い
- 効率性・合理性を重視
- 形式よりも実質を追求
考え方
- 「契約の中身が重要」
- 「甲乙の順序で時間を使うのは無駄」
- 「Win-Winの関係構築が目標」
効率偏重の反面、相手先に「ぞんざい」と思われるリスクもある
実際の声
「相手に合わせて最短で契約締結」
パターン2:協業・共創重視の業界
特徴
- 双方向取引が多い業界
- パートナーシップ重視の業界
- 対等性が重要な取引
- コンソーシアム契約・共創モデル等の複雑な取引形態
考え方
- 「お互い様」の取引関係
- 長期的パートナーシップ重視
- 上下関係よりも協力関係
- 現代的な協業トレンドへの対応
実際の声
「共創プロジェクトで甲乙とか古い」
⚖️法務部としての適切な対応
基本スタンス:「実질重視、形式配慮」
優先順位
- 契約内容の適法性・妥当性 ← 最重要
- スムーズな契約締結 ← 重要
- 社内政治への配慮 ← 必要に応じて
- 甲乙の順序 ← 最後
実践的対応フロー
本質的条項合意 → ドラフト反映 → 最終調整
具体的な対応方法
ケース1:社内から「甲乙」の指定あり
「承知いたしました。ただし、相手方から異論が出た場合は
契約締結を優先させていただく場合があります。
その際は事前にご相談いたします」
理由
- 社内要望への一定の配慮
- 実務優先の姿勢明示
- 交渉決裂リスクの回避
- 再調整の可能性を事前に明示
ケース2:相手方が「甲乙」にこだわる場合
「甲乙の順序については相手方に合わせますが、
契約条項については適切に調整させてください。
なお、社内調整が必要な場合は別途ご相談させていただきます」
理由
- 本質的でない点で交渉を複雑化させない
- 重要な条項交渉に集中
- Win-Winの姿勢を示す
- 社内説明の準備時間確保
ケース3:双方がこだわる場合
1. アルファベット順(会社名の頭文字)
2. 設立年順(老舗企業が先)
3. 契約金額順(支払い側が甲)
4. 業界慣行に従う
5. じゃんけん(最終手段)
やってはいけないNG対応
「甲乙なんてどうでもいいです」
→ 社内関係が悪化、担当部門のモチベーション低下
「甲乙のために契約締結を遅らせます」
→ 本末転倒、事業機会の逸失、契約遅延リスク
「甲乙は当社が決めます」
→ 交渉関係の悪化、不要な対立、信頼関係の毀損
「甲乙逆転」が実務に与える影響
注意すべきポイント
条項の主語確認
- 「甲は乙に対して○○する」の論理的一貫性
- 権利義務関係の整合性チェック
- 損害賠償・違約金条項の確認
社内承認プロセス
- 稟議書での説明責任
- 担当部門への事前説明
- 必要に応じて理由書添付
継続取引への影響
- 次回契約での先例化
- 他部門での混乱防止
- 統一的運用の確保
💼社内稟議・承認での実用例
【ケース1】社内要望対応時の稟議書文例
【ケース2】相手方配慮時の社内説明例
【ケース3】稟議不要の場合の一文
【ケース4】各部長決裁時の例
💡法務部員への実践的アドバイス
「甲乙問題」をスマートに処理する方法
1. 事前の期待値調整
契約書作成開始時に確認:2. 相手方との初期すり合わせ
契約交渉開始時に軽く確認:3. 社内政治への配慮
本質的でないが無視もできない場合:🎯まとめ:法務部の真価は「本質」を見極めること
契約書の「甲乙」問題は、法務部の実力が問われる場面のひとつです。
重要なのは以下のバランス感覚:
- 法的無意味性の理解 – 甲乙に実質的な差がないことを正しく認識
- 実務政治への配慮 – 社内外の人間関係や慣行への適切な対応
- 本質重視の姿勢 – 契約の実効性を最優先にした判断
- 効率的な解決策 – 不要な対立や遅延を避ける調整力
「甲乙なんてどうでもいい」と突っぱねるのも、「甲乙が全て」と思い込むのも、どちらも適切ではありません。
法務部の真価は、こうした「本質的でないが無視できない問題」を、いかにスマートに処理できるかにあります。
契約の中身を詰めることに集中しつつ、関係者の期待にも適切に応える。そのバランス感覚こそが、信頼される法務部員の条件なのかもしれません。
契約書の修正提案を自動生成!
法務交渉を効率化するプロンプト
取引先から届いた契約書ドラフト、不利な条項の発見と修正案作成に45分〜2時間かかっていませんか?このプロンプトで即座に3パターンの修正提案を生成できます。
相手方ドラフトの修正提案生成プロンプト
不利な条項を特定 → 法的根拠付きで3パターンの修正案を自動生成
交渉戦略・説明ポイントまで一括出力
📦 このプロンプトでできること
- リスク条項の自動特定 – 損害賠償・解除条項・知財権など重点項目を漏れなくチェック
- 3パターンの修正案生成 – A案(自社有利)/ B案(バランス型)/ C案(最低限)を一括出力
- 法的根拠の明示 – 民法○条など、修正理由と法的根拠をセットで提示
- 交渉戦略の提案 – 相手方への説明ポイント・落としどころを具体的にアドバイス
- 修正優先順位の明確化 – 「絶対に修正すべき条項」を★評価で可視化
- 業種別カスタマイズガイド – 製造業・IT・金融など業界特有の注意点を解説
💡 使い方のヒント
契約書本文をAIに入力する際は、実名・機密情報を匿名化してください。出力された修正案は必ず法務担当者・弁護士がレビューし、「たたき台」としてご活用ください。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

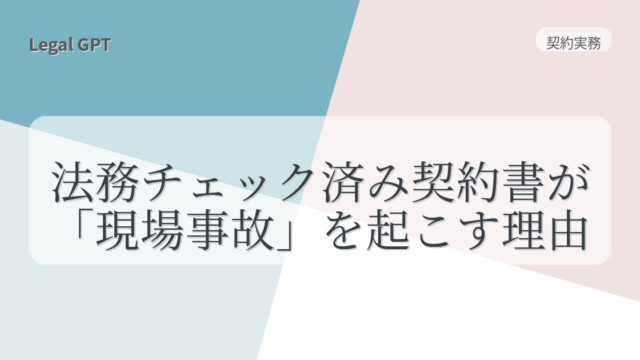
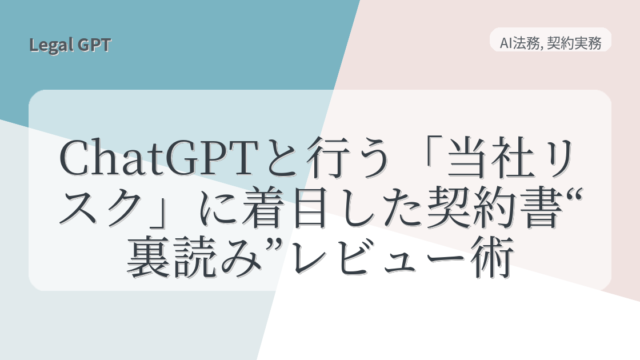
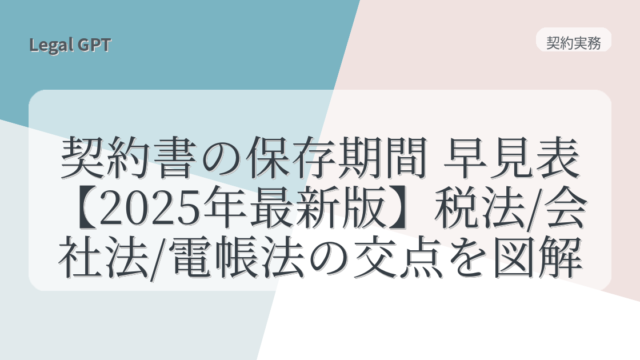
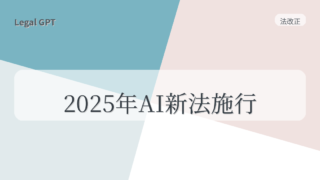
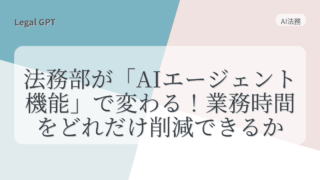



[…] また、「甲乙の取り扱い」に関する運用ルールやよくある設計方針については別記事で具体例を解説しています。内部運用ガイドの参考にしてください: 契約書の「甲乙」の決め方(実務的なハンドブック) […]