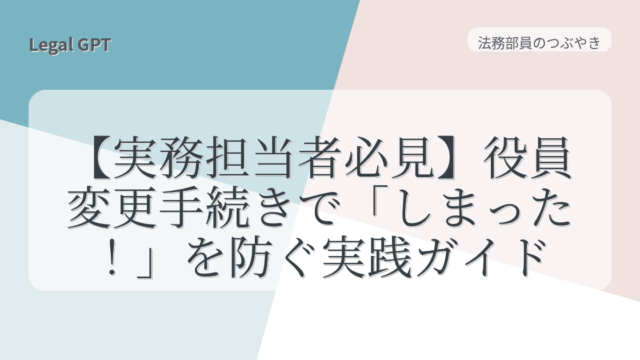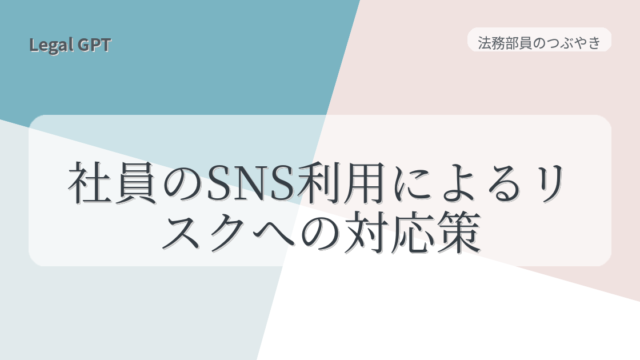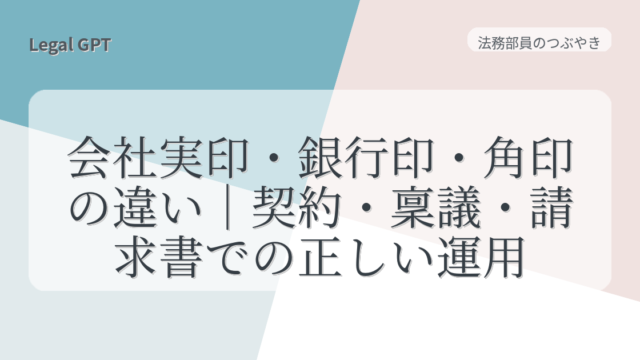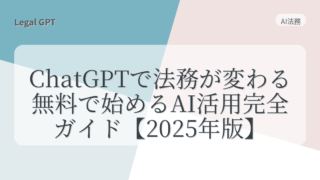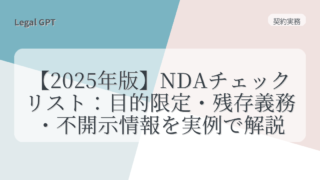英文契約書の基本|これだけは知っておきたい頻出条項15選
英文契約書の基本|これだけは知っておきたい頻出条項15選
はじめに
国際取引の増加に伴い、英文契約書の実務力は法務チームの必須スキルになっています。本稿では、実務で頻出する15の条項について、チェックポイント・交渉のコツ・日本企業が落ち入りやすい罠を具体的に解説します。契約レビューの現場ですぐに使える実践的テンプレ付き。
1 Definitions(定義条項)
基本概念
契約書で使用される重要な用語を明確に定義し、解釈の混乱を防ぐ条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- 大文字の使用:定義語は必ず大文字で始める(”Affiliate”, “Agreement”等)
- 循環定義の回避:定義の中で同じ用語を使用しない
- 数値基準の明記:「control」は50%等の具体的基準を設定
実務担当者からの視点
定義条項は契約解釈の基盤となるため、曖昧さを残すと紛争原因になります。特に「control」「material adverse effect」等の抽象的概念は、可能な範囲で具体的基準(閾値・期間・例外)を明記しましょう。
交渉スタンス
買主側:50%基準で関連会社の範囲を限定し、予期しない債務承継を防ぐ。
売主側:事実上の支配や実質的支配を認める文言で柔軟性を確保したい。
2 Representations and Warranties(表明保証条項)
基本概念
契約締結時点での事実関係について、当事者が相手方に対して行う表明と保証です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- True and correct標準:「true and correct in all material respects」等の限定を付ける
- Knowledge qualifier:「to the best of knowledge」等で責任範囲を限定
- Survival period:表明保証の存続期間を明確化(例:一般表明12ヶ月、重要表明は存続)
実務担当者からの視点
英米法では表明保証違反は契約違反として扱われるため、過度に広範な表明保証は避ける。上場企業の場合は開示規制との整合性も確認する。
日本法上の注意点
- 日本の商慣行では「善管注意義務」が重視され、売主が完全保証を与えることは難しい場合あり。
- 上場会社は情報開示規制に抵触しないかを確認。
交渉スタンス
買主側:重要事項については広く要求(materialityを限定しない文言)
売主側:materiality qualifier と knowledge qualifier を付加して限定
3 Indemnification(補償条項)
基本概念
一方当事者が特定の事由により損害を被った場合に、他方当事者がその損害を補償する義務を定める条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- Mutual vs. One-way:相互補償か一方向補償かの選択は事業リスクに依存
- 知的財産権侵害:第三者クレームは例外や上限の設定が中心争点
- Defense obligation:防御コントロール(defense control)を明確化し、和解の可否・承認手続きを規定する
実務担当者からの視点
補償条項は実質的にリスク配分を決める。因果関係を巡る争いを避けるため、文言(「arising out of」「resulting from」等)と手続き(通知、証拠保全、和解条件)を厳密に設計する。
交渉スタンス
サービス提供者:利用者側の利用法に起因するクレームは除外し、IP侵害に限定する。
サービス利用者:第三者クレーム全般の補償と防御参加権を要求。
4 Limitation of Liability(責任制限条項)
基本概念
契約違反等による損害賠償責任の範囲や金額を制限する条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- 特別損害の除外:間接損害、逸失利益等の除外を明示
- 金額的上限:業界・契約形態に合わせた現実的上限の設定
- 適用除外事由:故意・重過失、機密保持違反、IP侵害などは除外することが一般的
実務担当者からの視点
責任制限は有効性(適用法上の制限)を考慮しつつ、補償条項や保険と整合させるのが鍵。
業界別の責任上限設定例:
- SaaS提供: 月額料金×12ヶ月
- ハードウェア: 契約金額×1–2年分
- コンサルティング: プロジェクト総額または年間報酬額
交渉スタンス
サービス提供者:間接損害の完全除外、上限を低く設定
サービス利用者:重要な責任(故意・重過失・機密・IP)は上限から除外するよう要求
補償・責任制限・保険の統合設計
3層防御システムの基本構造
英文契約では、リスク管理を以下の3層で設計することが重要です:
- 第1層: Insurance(保険) — Contractor shall maintain USD 2,000,000 per occurrence general liability insurance.
- 第2層: Indemnification(補償) — Contractor shall indemnify Company for third-party IP claims up to the available insurance proceeds plus USD 500,000.
- 第3層: Limitation of Liability(責任上限) — Total liability of each party shall not exceed USD 2,500,000, EXCEPT for (i) liabilities excluded from limitation (e.g. willful misconduct), and (ii) liabilities that are the subject of a carve-out specified in the indemnity clause.
統合設計の実務例:保険2,000k + indemnity top-up 500k = 実効上限2,500k。設計上は保険、補償、責任上限の関係が矛盾しないように数値を合わせること。
5 Termination(契約終了条項)
基本概念
契約の終了事由、手続き、終了後の義務等を定める条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- Termination vs. Expiration:期間満了による終了と解除(termination)の違いを明確化
- Cure period:違反是正期間(cure period)の長さは業種により調整
- Post-termination obligations:秘密保持、データ返還、移行サービス等を具体化
交渉スタンス
継続的サービス利用者:移行期間とデータ返還手順の明記を要求
サービス提供者:即時解除権を保持し終了後の義務を限定
6 Force Majeure(不可抗力条項)
基本概念
天災、戦争、政府規制等の不可抗力事由により契約履行が困難となった場合の免責条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- COVID-19対応:パンデミックの扱いと経済的困窮の区別を明確に
- Mitigation obligation:損害軽減義務を規定
- Notice requirement:発生時の通知期限を定める
2025年版追加リスク
- サイバー攻撃(システム停止・データ侵害)
- 気候変動(異常気象による物流停止)
- AI規制(突然の法規制による技術利用停止)
交渉スタンス
義務履行者:幅広い不可抗力事由を認め、長期継続時の解除権を確保
義務受益者:economic hardship を不可抗力から除外し、代替履行の義務を追加
7 Governing Law and Jurisdiction(準拠法・管轄条項)
基本概念
契約の解釈・履行に適用される法律と、紛争解決の管轄裁判所または仲裁地を定める条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- 法抵触規則の排除:「without regard to conflict of law principles」の有無
- Exclusive vs. Non-exclusive:専属管轄にするか否かの影響
- 仲裁条項:ICC、SIAC、JCAA等の選択とseat(仲裁地)・準拠法の区別
実務担当者からの視点
準拠法・管轄は実務上のリスク(執行可能性・コスト)に直結する。第三国法や仲裁を採用する選択肢を検討。
実務で好まれる組み合わせ:
- 英法 + ロンドン仲裁(商事案件で実績)
- ニューヨーク法 + ニューヨーク裁判(金融系)
- シンガポール法 + SIAC(アジア取引の中立選択)
交渉スタンス
日本企業は日本法・日本での執行容易性を優先、又は中立地の仲裁を提案すると合意が得やすい。
8 Intellectual Property(知的財産権条項)
基本概念
契約に関連する知的財産権の帰属、使用許諾、侵害対応等を定める条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- Work for hire:米国の概念と日本法の相違に留意
- Pre-existing IP:既存権利(Background IP)の明確化
- Moral rights waiver:著作者人格権の取扱い(日本では限定的)
実務担当者からの視点
日本法での著作者人格権は譲渡困難なため、実務的には譲渡+著作者の同意(別途同意書)や使用許諾(exclusive license)で解決するケースが多い。
交渉スタンス
発注者:「work for hire」+moral rights waiver(適用法で有効な範囲で)を要求。
受託者:Background IP を保留、改善発明の利用権を明確化。
9 Confidentiality(秘密保持条項)
基本概念
契約に関連して開示される機密情報の保護義務を定める条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- 機密情報の定義:技術情報、営業情報、財務情報等を具体化
- 例外事由:公知情報・独自開発情報等を除外
- 返還・廃棄義務:契約終了後の情報処理を定める
実務担当者からの視点
越境データ移転や個人情報が絡む場合、GDPRや日本の個人情報保護法との整合が必要。SCCや適切なデータ移転手段を検討する。
AI時代の追加論点
- 学習データの取り扱い(機密情報が学習に使用されない保証)
- 生成物の責任(誤情報・権利侵害の帰属)
- ログ保存・監査(説明可能性の確保)
交渉スタンス
情報開示者:AI学習への利用禁止、目的外使用の厳格制限を要求。
情報受領者:通常の事業目的に限定した柔軟利用を主張。
10 Payment Terms(支払条件条項)
基本概念
対価の金額、支払時期、方法、遅延時の取り扱い等を定める条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- 通貨リスク:支払通貨と為替リスクの分担を明確化
- 源泉徴収:クロスボーダー取引の税務処理(gross-up 条項の有無)
- Withholding tax:源泉税の負担者を明記
日本法上の重要注意点
- 印紙税:日本国内で作成・行使される契約書は印紙税対象になる場合あり(契約形態を確認)
- 源泉徴収:ロイヤリティや一部のコンサル料は源泉対象の可能性あり
- 為替変動リスク:円建てか外貨建てかとヘッジ措置の取り決め
- 金利設定の現実性:月利1.5%は年率約18%に相当。各国の利息制限や商慣行との整合を確認し、年率表示で合意することを推奨。
交渉スタンス
支払義務者:円建て・遅延利率は法定利率に合わせる。
支払受益者:外貨建て・gross-up 条項や高い遅延利息を求める。
11 Insurance(保険条項)
基本概念
契約履行に関連して必要な保険の加入義務を定める条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- Additional insured:発注者を被保険者に追加する条項の有無
- Waiver of subrogation:保険会社の代位求償権放棄の適否
- Coverage amount:保険金額は責任上限と整合させる
補償・責任制限との整合性:Insurance → Indemnification → Limitation of Liability の順番で保護される設計が理想。
交渉スタンス
リスク移転を受ける側:十分な保険金額、証明書提出義務、additional insured を要求。
リスク負担側:既存保険で代替、保険料負担の明確化を主張。
12 Assignment(譲渡条項)
基本概念
契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡に関する制限を定める条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- Change of control:支配権変更時の扱い(M&A時の自動譲渡or承諾制)
- Affiliate assignment:関連会社への譲渡例外の範囲を明確化
- Assumption of obligations:譲受人が義務を適切に履行できることの確認条項
交渉スタンス
譲渡する側:柔軟な譲渡条件、change of control の例外を求める。
譲受側:承認権の保持、譲受人に関する承認基準を設定。
13 Compliance(法令遵守条項)
基本概念
適用される法令、規制、業界標準等の遵守義務を定める条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- FCPA/UK Bribery Act:腐敗防止法の遵守
- Export control:輸出管理(EAR、ITAR 等)の遵守
- ESG要件:環境・人権・サプライチェーン対応
2025年重要トピック
- AI Act(EU)の域外適用リスク
- サプライチェーン法(ドイツ等)に基づく人権DD義務
- サイバーセキュリティ強化(重要インフラ保護)
交渉スタンス
規制対象企業は相手方にも高い遵守水準を求める。非対象企業は実行可能性を理由に要求を限定。
14 Dispute Resolution(紛争解決条項)
基本概念
契約に関する紛争の解決方法(交渉→調停→仲裁/訴訟)を定める条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- Multi-tier:段階的解決手続きは費用と時間のバランスを考慮
- 仲裁機関の選択:ICC、SIAC、JCAA などの特徴比較を行う
- Emergency arbitration:暫定救済を確保する条項を検討
交渉スタンス
資金力ある側は仲裁を好む傾向。費用抑制が必要なら調停や段階的手続きを重視。
15 Entire Agreement(完全合意条項)
基本概念
当該契約書が当事者間の完全な合意を構成し、従前の合意や交渉内容を排除する条項です。
典型的な条文例
実務上の注意点
- Parol evidence rule:口約束や外部文書の排除効果を理解する
- Amendment条項:契約変更手続き(書面・署名等)を明示する
- Survival provisions:終了後も存続する条項(秘密保持、補償等)を明確に
交渉スタンス
リスク回避重視なら完全排除・厳格な変更手続を要求。柔軟性が必要なら軽微変更の簡素化手続きを定める。
実務テンプレート:責任制限条項の交渉例
ベンダー側提示案(問題箇所)
❌ IN NO EVENT SHALL VENDOR BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER.
❌ VENDOR’S TOTAL LIABILITY SHALL NOT EXCEED USD 1,000.
修正交渉案(改善箇所)
✅ IN NO EVENT SHALL VENDOR BE LIABLE FOR INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, EXCEPT FOR DAMAGES ARISING FROM GROSS NEGLIGENCE, WILLFUL MISCONDUCT, OR BREACH OF CONFIDENTIALITY.
✅ VENDOR’S TOTAL LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE AMOUNT PAID UNDER THIS AGREEMENT IN THE 12 MONTHS PRECEDING THE CLAIM, OR USD 100,000, WHICHEVER IS GREATER.
最終合意案のポイント
- 段階的除外(全損害→間接損害のみに限定)
- Carve-out(故意・重過失・機密・IP等は除外)
- 契約価値に応じた現実的上限設定
役割別チェックリスト
法務部門の確認事項
財務・経理部門の確認事項
調達・事業部門の確認事項
情報システム部門の確認事項
最新動向とトレンド(2025年)
1. AIと契約条項
ポイント:学習データの権利クリアランス、ログ・説明可能性、学習利用の同意は必須項目に。
2. サイバーセキュリティ
データ侵害対応、SLA、インシデント通知期限、緊急復旧手順を規定。
3. ESG要件
サプライヤーへの人権DD、環境基準、監査権限の契約化が潮流。
4. デジタル署名
国際的有効性と証拠力を踏まえた署名方式の明記を推奨。
5. Supply Chain Act 等
EU・ドイツ等のサプライチェーン規制への対応を契約に組み込むことが増加。
実際の失敗事例と教訓
ケース1:知的財産権条項の不備
状況: 日本企業がソフトウェア開発を米国企業に委託し、「all IP shall vest in Customer」のみ記載。
問題: 米国でwork for hireが成立せず、開発者個人に著作権が残存。日本での著作者人格権も未処理。
改善案:
ケース2:責任制限の抜け穴
状況: SaaS契約で「liability cap = 月額×12ヶ月」設定。ただし、データ消失時の補償除外が不十分。
問題: 重要データ消失により数億円の損害。責任上限を超えた請求。
教訓: データ関連事故は責任制限の例外として明記し、バックアップ・復旧手順を詳細化。
ケース3:準拠法と執行の齟齬
状況: ニューヨーク法準拠、日本での契約履行。相手方の債務不履行で日本で強制執行を試行。
問題: 外国判決の執行が複雑で時間とコストが過大。
教訓: 執行地を考慮した準拠法・管轄の選択、仲裁を利用した国際執行性の検討。
よくある質問(FAQ)
法務部からの最終アドバイス
英文契約は単なる書面ではなく、リスク配分と事業実行をつなぐ設計図です。本稿で示した項目を基礎に、次の3点を実行してください:
- 予防法務の徹底:契約締結前のリスク分析と対策
- 継続的学習:国際法務の最新動向と判例研究
- 専門家との連携:現地法務事務所や国際経験豊富な弁護士との協力体制
契約レビュー時に使えるチェックリストとテンプレートは、ダウンロード可能な別稿として配布すると実務への定着が早まります。
英文契約書の和文要約プロンプト
英文契約の重要条項とリスクを60〜180分で日本語要約。国際取引の初期検討や社内報告に即活用できる、実務特化型プロンプトです。
英文契約書の和文要約
NDA、ライセンス契約、SPA等の英文契約を、重要条項・リスク・準拠法の影響まで日本語で明確化。契約交渉の初期段階で必須のツールです。
📦 このPDFに収録されている内容
- ✅ プロンプト本体 – そのままコピペで使える完成版プロンプト
- ✅ 入力例 – Software License Agreementの実践的サンプル
- ✅ 出力例 – AIによる実際の生成結果(重要条項・リスク評価付き)
- ✅ カスタマイズ方法 – 準拠法・重点項目の指定テクニック
- ✅ FAQ – 準拠法が不明な場合の対処法など
- ✅ 関連プロンプト – 契約書リスク分析・修正提案生成との連携
Claude 4.5
Gemini 2.5
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。