G検定を受けてよかった3つの理由実務でここが本当に役立った
G検定を受けてよかった3つの理由
実務でここが本当に役立った
〜法務部員が語る、AI時代の基礎教養としてのG検定〜
はじめに:正直、最初は迷った
ChatGPTが話題になった2年前、そんな疑問を抱きながらも受験を決めたG検定。結果的に合格はしたものの、当時は「資格商法では?」という冷めた目線もありました。
G検定って結局どんな試験?
念のため簡単に説明すると、G検定は120分のオンライン選択式試験で、数学やプログラミングの専門知識は不要。AIの概念理解が中心です。私は公式テキストと過去問アプリで約1ヶ月勉強しました。
AIエンジニア向けの「E資格」や実装系の「AI実装検定」とは違い、ビジネスパーソンがAI活用に必要な基礎教養を身につけるのがG検定の位置づけです。
でも実際に1年半、AI活用を続けてきた今だからこそ言えます。
G検定で学んだ基礎知識が、想像以上に実務で活きている。
今回は、非エンジニアの法務部員という立場から、「G検定のここが本当に役立った」という実体験をお伝えします。
理由①:生成AIの「限界」が見えるようになった
受験前の自分
- ChatGPTに何でもかんでも聞いていた
- 「AIが言ってるから正しいはず」と盲信気味
- ハルシネーション(幻覚)の仕組みを理解していなかった
G検定で学んだこと
- 深層学習の基本的な仕組み(ニューラルネットワーク、学習データの重要性)
- AIモデルの種類と特性(CNN、RNN、Transformerなど)
- AIが「知らない」ことは「知らない」と言わない理由
実務での変化
契約書のレビューでChatGPTを使う際、以前なら「AIが大丈夫と言ってるから安心」だったのが、今では:
- 「この回答はどの学習データに基づいているんだろう?」
- 「2024年の法改正後の情報は反映されていない可能性が高い」
- 「複雑な解釈が必要な部分は、最終的に人間が判断すべき」
こんな風に、AIとの適切な距離感を保てるようになりました。
理由②:社内でのAI活用ルール策定に自信が持てた
G検定で身についたスキル
- AI倫理・バイアス問題への理解
- データプライバシーとセキュリティの基礎知識
- AI活用における法的・倫理的配慮
実務での応用例
社内の「生成AI利用ガイドライン」策定において、G検定の知識が大活躍:
個人情報の取り扱い
- なぜAIに機密情報を入力してはいけないのか、技術的背景を含めて説明できる
- 「学習データとして使われる可能性」を具体的にイメージして伝えられる
AI生成コンテンツの著作権問題
- 「AIが生成した契約書の著作権は誰のもの?」という質問に、学習データとの関係性を踏まえて回答
品質管理体制
- 「なぜAI出力の最終チェックが人間に必要なのか」を、ハルシネーションの仕組みから説明
G検定の基礎知識があったからこそ、「なんとなく危ないから禁止」ではなく、「技術的にこういうリスクがあるから、こう対策しよう」という建設的なルール作りができました。
理由③:AIツールの使い分けができるようになった
受験前:とりあえずChatGPT一択
- 何でもChatGPTに投げていた
- 他のAIツールの存在すら知らなかった
G検定後:用途に応じた使い分け
- 文書生成・要約:ChatGPT、Claude
- データ分析:Google Bard(当時)、現在はGemini
- 画像生成:DALL-E、Midjourney
- コード生成:GitHub Copilot
実務での具体例
契約書レビュー
- 初期チェック → ChatGPT(汎用性重視)
- 英文契約の翻訳 → DeepL + Claude(精度重視)
- リスク分析レポート → ChatGPT(構造化された出力が得意)
社内説明資料作成
- 骨子作成 → ChatGPT(アイデア出し)
- 図表作成 → 専用ツール + AI支援
- 最終調整 → 人間(法的正確性の担保)
G検定で「AIにも得意・不得意がある」ことを学んだおかげで、適材適所の使い分けができるようになりました。
実際のところ、受験する価値はある?
正直なメリット・デメリット
○ メリット
- AI活用の「地図」が手に入る
- 技術的な背景を踏まえた判断ができる
- 社内でのAI活用議論に説得力を持って参加できる
- 最新技術の動向を理解する基礎力が身につく
△ デメリット
- これだけで転職市場で評価が上がることはない
- 受験料(13,200円)+ 学習時間のコスト
- 技術の進歩が早いため、定期的なアップデートが必要
どんな人におすすめ?
特におすすめ
- 業務でAIを使っているが、なんとなく不安な人
- AI活用ルールの策定に関わる可能性がある人
- 「AIの仕組みを体系的に理解したい」と思っている人
微妙かも
- 「資格を取って年収アップ!」を期待している人
- エンジニアとして実装スキルを身につけたい人
まとめ:「AI時代の基礎教養」として
G検定は、プログラミングスキルを身につけるための資格ではありません。
でも、AI時代に必要な「素養」を効率的に身につけるためのカリキュラムとしては、非常によくできていると思います。
特に法務のような職種では:
- AIに何ができて、何ができないのか
- どこまでAIに任せて、どこから人間が関与すべきか
- AIを活用する際のリスクとその対策
こういった判断を、「なんとなく」ではなく「根拠をもって」行えるようになることの価値は計り知れません。
もしAI活用に関して「基礎から体系的に学びたい」と思っているなら、G検定はその第一歩として悪くない選択だと思います。
ただし、受験は目的ではなく手段。大切なのは、学んだ知識を実務でどう活かすかです。
次のステップとして
この記事を読んで「G検定、受けてみようかな」と思った方へ。まずは公式サイトで試験日程をチェックしてみてください。年3回実施されており、次回の申込期間も確認できます。
実務でのAI活用経験があれば、きっと学習内容が「腑に落ちる」はずです。
📘 生成AIのリスクを扱うなら、技術の基礎理解は不可欠。
非エンジニアでもわかりやすく学べるG検定テキストがおすすめです。

🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

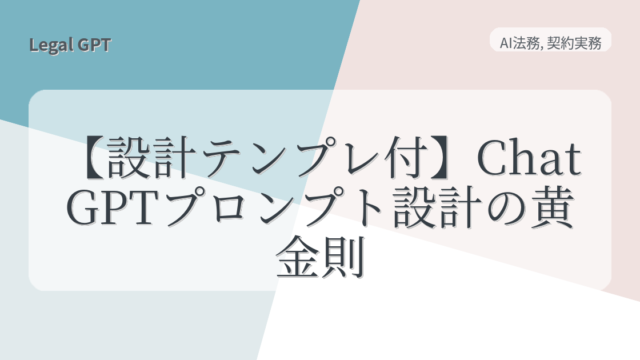
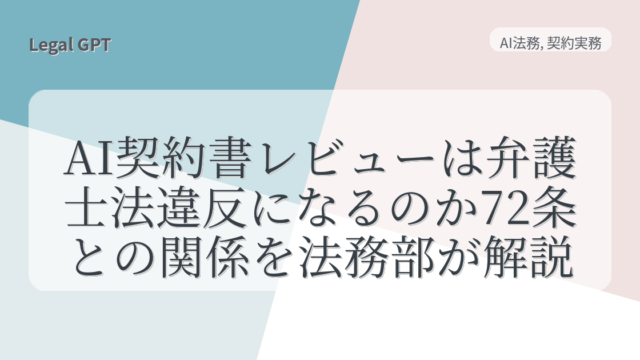
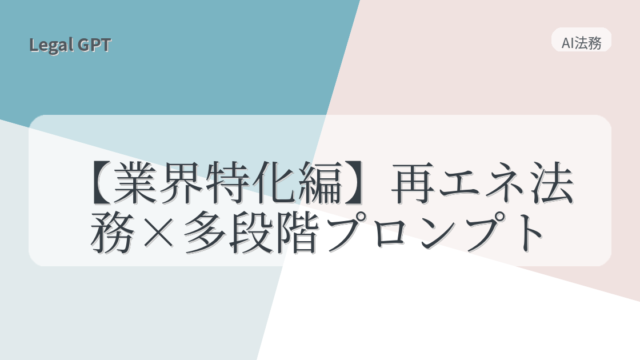
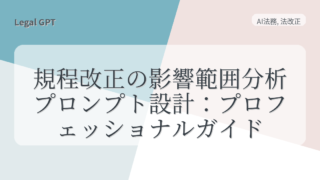
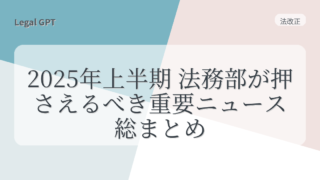



[…] (体験的に有益だった点は別記事でまとめています:G検定を受けてよかった3つの理由(実務で活きるポイント)) […]