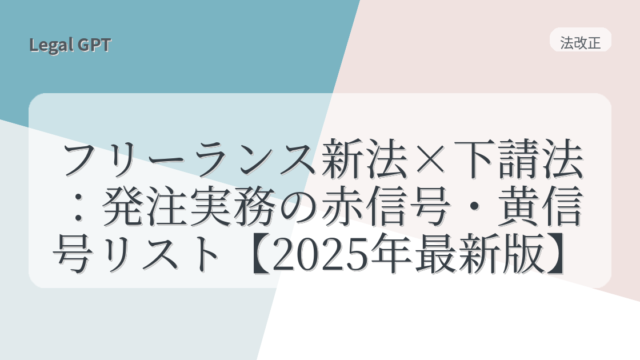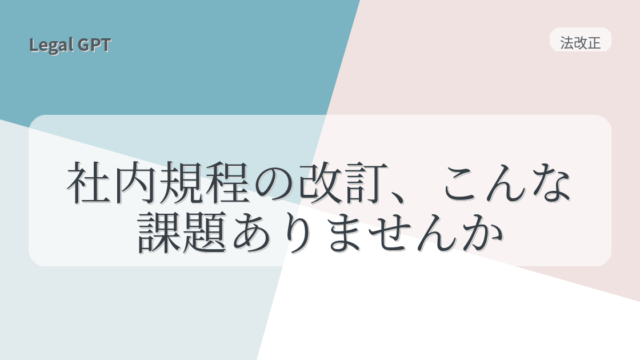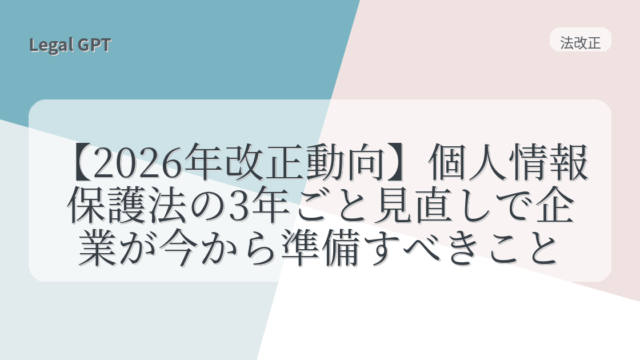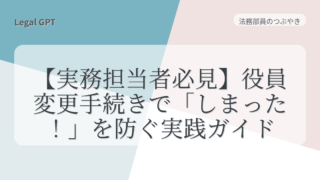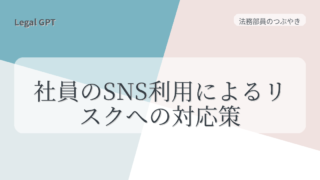譲渡担保・所有権留保契約法(新法)の概要と実務への影響
譲渡担保・所有権留保契約法(新法)の概要と実務への影響
初めて法制化された「生かす担保」—企業法務担当者が今押さえるべき重要ポイント
TL;DR(30秒要約)
- 成立・施行: 2025年5月30日成立、6月6日公布。施行は公布日から2年6か月以内に政令で定める(2027年末~2028年初頭見込)
- 実務インパクト: ①動産・債権譲渡登記制度の抜本改正(競合担保登記目録新設で公示性向上)、②実行手続の明文化(帰属清算・処分清算)、③既存契約にも適用(契約書改訂必須)
- 今すぐやること: 既存契約の棚卸し、基本契約書雛形の改訂着手、登記実務フローの整備開始
はじめに:画期的な新法の成立
2025年5月30日、日本の担保法制史上、歴史的な転換点となる法律が国会で可決・成立しました。「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(令和7年法律第56号)、通称「譲渡担保法」です。同法は6月6日に公布され、公布日から2年6か月以内に政令で定める日に施行される予定です。
この新法の最大の特徴は、これまで明文規定がなく、判例法理のみに依拠してきた譲渡担保・所有権留保という取引を、初めて法律で明確に定めた点にあります。「自社取引にどんな影響があるのか」「基本契約書の見直しは必要か」と疑問を持たれている法務担当者の方も多いのではないでしょうか。
本稿では、新法のポイントを専門的かつ分かりやすく解説し、実務で今すぐ取り組むべき対応策を具体的にご提案します。
なぜ今、法制化が必要だったのか
譲渡担保・所有権留保は、実務で長年活用されてきた担保手法です。在庫商品、機械設備、売掛債権など、事業継続に必要な財産を担保に資金調達できる「生かす担保」として、特に不動産を持たない中小企業やスタートアップにとって重要な選択肢となってきました。
従来の三大課題
しかし、これまで法律上の明文規定がなかったため、実務は判例法理に頼らざるを得ず、大きな課題がありました。
法的不安定性: 権利の効力範囲が不明確で、判例の射程も限定的でした。実行手続のルールが統一されておらず、倒産時の取扱いにも解釈の幅があり、第三者対抗要件の整備も不十分でした。
公示性の欠如: 特に占有改定による動産譲渡担保は外部から把握が困難で、取引安全を損なうリスクがありました。二重譲渡担保などのトラブルも発生していたのです。
事業再生との緊張関係: 担保権実行が迅速すぎて再生の余地が狭まる懸念があり、倒産手続との調整ルールも不明確でした。
こうした課題を解決し、法的安定性と予見可能性を高め、円滑な資金調達と事業継続を両立させることが、新法制定の目的です。
新法の骨格:何が定められたのか
では、新法は具体的に何を定めたのでしょうか。重要なポイントを条文と共に見ていきましょう。
対象となる財産と基本構造(第1条・第2条)
新法が対象とするのは、動産(個別動産・集合動産)、債権(個別債権・集合債権)、その他の譲渡可能な財産です。ただし、不動産は抵当権の対象として既に法整備されているため対象外となります。知的財産権等も原則として対象外です。
新法は、譲渡担保権者が「他の債権者に先立って優先的弁済を受ける権能」を有することを明文化しました(第3条)。この優先弁済の効力の明確化が、実務上最も重要なポイントの一つです。
さらに、以下の重要な権利内容も規定されています。
- 被担保債権の範囲(第4条): 元本、利息、違約金、実行費用、損害賠償を担保
- 物上代位性(第9条): 目的物に関連する保険金等に対する権利
- 不可分性(第7条): 債務の一部弁済があっても担保権は全体に及ぶ
根譲渡担保の導入(第13条~第26条)
特に注目すべきは、根譲渡担保の規定です。民法の根抵当権に倣い、「一定の範囲に属する不特定の債権」を被担保債権とする根譲渡担保権が認められました(第13条)。これにより、継続的取引における柔軟な担保設定が可能になります。
根譲渡担保権の重要規定として、元本確定事由(第24条)、元本確定前の譲渡(第17条)、債権を目的とする根譲渡担保権の特則(第21条~第23条)などが整備されています。
対抗要件の明確化—登記制度の抜本改正
対抗要件についても明確なルールが定められました。
動産譲渡担保
- 引渡し(占有改定を含む)が対抗要件(民法178条)
- 動産譲渡登記による対抗要件具備も可能(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第3条)
債権譲渡担保
- 債務者への通知または承諾(民法467条)
- 債権譲渡登記による対抗要件具備も可能
重要なのは、整備法により「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が改正され、動産・債権譲渡登記制度が抜本的に見直された点です。競合担保登記目録制度が新設され、複数の譲渡担保権の順位関係が可視化されます。これにより、外部から把握が困難だった担保関係が、登記により明確になります。
実行手続の明文化(第27条~第96条)
新法は、譲渡担保権の実行手続についても詳細に規定しています。譲渡担保権者は、原則として新法が定める実行手続によらなければ、譲渡担保財産を譲渡できません(第5条)。
実行方法
- 私的実行
- 帰属清算方式(第33条~第35条、第52条~第54条): 一定の要件下で担保財産を譲渡担保権者に帰属させる
- 処分清算方式(第36条~第47条、第55条~第75条): 担保財産を処分し、その代金から優先弁済を受ける
- 競売による実行(第48条~第51条、第76条~第82条)
設定者保護の仕組み
- 実行通知義務(第33条、第36条等)
- 清算金の交付義務(第35条、第47条等)
- 不当な実行に対する異議申立て
これらの規定により、設定者の権利が適切に保護されつつ、権利行使の透明性が確保されます。
所有権留保の特則(第109条~第111条)
所有権留保についても重要な規定が設けられました。二当事者間の所有権留保だけでなく、三者間所有権留保(信販会社等が立替払いして所有権を留保する形態)も明確に規律の対象とされています(第2条第16号)。
対抗要件の特則(第109条第2項)
目的動産と牽連性のある債権のみを被担保債権とする所有権留保(狭義の所有権留保)は、引渡しがなくても第三者に対抗できるとされました。これは従来の判例法理を明文化したものです。
所有権留保登記制度の新設
法人間の所有権留保契約について、所有権留保登記の申請が可能になりました。登記により、引渡しがあったものとみなされます。これは新たに創設された制度であり、今後の実務に大きな影響を与えるでしょう。
倒産時の取扱い—事業再生への配慮(第97条~第108条)
倒産時の取扱いも重要なポイントです。再建型倒産手続(民事再生・会社更生)において、譲渡担保権の実行手続が裁判所の「中止・禁止命令」(第97条)や「取消命令」(第99条~第104条)の対象となることが明文化されました。
特に重要なのは、所有権留保契約について、再生手続開始や更生手続開始の申立てがあったことを解除事由とする条項は無効とされた点です(第110条)。いわゆる「倒産解除条項」の無効を明文化したもので、債務者が倒産手続を申し立てても、直ちに所有権留保の目的物を引き揚げられることはなくなり、事業再生の余地が生まれます。
実務への影響:現行と新法の比較
新法により実務がどう変わるのか、比較表で整理します。
| 項目 | 従来(現行) | 新法での違い | 対応策 |
|---|---|---|---|
| 対抗要件(動産) | 占有改定で実務的に対抗可が多い | 登記での公示も利用可能、競合担保登記目録新設で可視化 | 占有改定+登記(重要案件)を検討。登記フロー整備 |
| 債権譲渡担保 | 通知・承諾が慣行、集合債権は不明確 | 集合債権・根譲渡担保の規律が明確化(第13条~第26条) | 債権管理台帳の精緻化、取立権限を契約で明示 |
| 実行方法 | 判例実務に依存(帰属/処分) | 帰属清算・処分清算・競売の規定(第27条~第96条で手続明文化) | 実行時の評価基準・通知テンプレ整備 |
| 登記の公示性 | 事実上不十分(外部から把握困難) | 競合担保登記目録等により公示性向上 | 登記実務の社内責任者を定める |
| 倒産時の効力 | 判例上の不確実性 | 再建型手続との調整規定(第97条~第108条、倒産解除条項の制限) | マニュアルの更新、管財人対応フロー整備 |
実務で使える契約条項例
新法に対応した契約条項のサンプルを示します。社内方針・既存条項との整合や判例等を踏まえ、必ず弁護士と最終調整してください。
被担保債権の範囲(極度額設定例)
対抗要件の充足
実行方法と通知
倒産事由に関する特約
注: 上記条文例には「別紙(評価基準・登記フロー・通知書式)」をワンセットで準備すると運用がスムーズです。
実務対応チェックリスト(優先度別)
施行1年前まで(優先度:高)
- 既存契約の棚卸し: 在庫、機械設備、売掛金、リース債権、集合動産/集合債権を対象に洗い出し
- 重要条項の抽出: 対抗要件の方法、実行条項、倒産解除条項を確認
- ステアリング委員会設置: 法務、与信、営業、経理、IT部門横断で
- 新法の基本理解: 社内勉強会の実施(外部講師も検討)
- 基本契約書ドラフト作成開始: 上記条項例をベースに
施行6か月前まで(優先度:中)
- 標準条項案の確定: 新契約用の条項セット完成
- 登記運用フロー整備: 動産・債権譲渡登記の社内申請フォーム作成
- システム要件定義: 被担保財産管理モジュール追加の検討
- 取引先・顧客向け説明資料: 新法の影響と対応方針を説明する資料準備
- 外部弁護士との連携体制: 緊急連絡先、実行時の代理・交渉体制
施行前まで(優先度:低)
- 全社研修実施: 法務(審査基準)、営業(顧客案内)、経理(会計処理)
- 実務テスト: 模擬登記、模擬実行手続のシミュレーション
- マニュアル完成: 運用手順書、チェックリスト、Q&A集
- 既存契約の改訂: 必要に応じて取引先と変更合意
- 最終確認: 政令・省令の確定内容チェック
実務上のリスクと留意点
登記コストと効果のバランス
動産・債権登記を全件で行うとコスト・事務負担が増加します。重要案件(高額、取引リスク高)に限定する戦略が現実的です。登記の要否判断基準を社内で明確にしましょう。
集合動産・集合債権の評価
在庫回転や混合在庫の同定問題が発生しやすく、第三者抗弁(善意第三者)のリスク評価が必要です。評価基準(評価日・評価機関・評価方法)を契約で明確にしておくことが重要です。
実行時の手続違反リスク
法定の通知・清算金取扱いを誤ると、債権者の行為が無効となったり、不当利得返還や民事責任(背任)につながるリスクがあります。実行フローを詳細なチェックリスト化し、複数人でのダブルチェック体制を整えましょう。
倒産手続との調整
再建型手続(民事再生・会社更生)下では裁判所の判断により実行差止め等が出る可能性があります。早期に管財人との情報連携ルートを確保しておくことが重要です。
よくある質問—現場の疑問に答える
施行前に締結された既存契約にも新法が適用されます。ただし、占有改定で対抗要件を備えた動産譲渡担保権の順位計算など、一部では既存の権利関係を保護する経過措置が設けられています。実務対応としては、既存契約の棚卸しと新法適合性チェックが必要です。「既存契約だから大丈夫」と安心せず、積極的な見直しが求められます。
不動産を持たない中小企業やスタートアップでも、在庫・機械設備・売掛債権などを活用した資金調達が法的に安定化します。また、個人保証に過度に依存しない資金調達が促進されることも重要です。新法は「中小企業のための法律」という側面も持っているのです。
担保権の実行手続が明確化され、リスク管理と債権回収の予見可能性が向上します。また、集合動産・集合債権を担保として利用できることで、事業性評価に基づく融資(ABL)の推進が容易になります。不動産担保に頼らない、企業の事業価値や成長性を評価した融資が広がることで、新たなビジネスチャンスが生まれます。
まとめ:「待ち」ではなく「攻め」の対応を
譲渡担保・所有権留保契約法の成立は、日本の担保法制における歴史的転換点です。この新法がもたらすものは、法的安定性と予見可能性の向上、不動産・個人保証に依存しない多様な資金調達の促進、そして事業再生と債権者保護のバランスです。
施行まで2〜3年の猶予がありますが、「様子見」は危険です。新法は既存契約にも適用されるため、準備不足は法的リスクに直結します。また、新法を単なる「規制対応」と捉えるのではなく、資金調達手法の多様化・高度化のチャンスとして積極的に活用する視点が重要です。
今すぐ始めるべきアクション
- 新法の全体像を正確に把握する(法務省公表資料、条文の精読)
- 自社の既存契約を棚卸しする(影響を受ける契約のリストアップ)
- 社内関係部門との連携体制を構築する(横断的プロジェクトチーム)
- 外部専門家との相談体制を整える(弁護士、税理士とのパートナーシップ)
- 施行に向けたロードマップを作成する(具体的なスケジュール策定)
新法の詳細は、今後、政令・省令・ガイドラインで順次明らかになります。法務省の公式サイトや業界団体の情報を継続的にフォローし、最新情報をキャッチアップすることが重要です。この新法への対応が、御社の法務力を高め、より強固な取引基盤を築く機会になることを願っています。
参考資料・出典
新規事業の法的リスク、見落としていませんか?
許認可・契約・知財・個人情報…新規事業に潜む8つの法的論点を体系的に洗い出し。4時間かかる初期検討が30分で完了します。
新規事業の法的論点整理プロンプト
事業化判断前の法的デューデリジェンス、PoC から本格展開への移行判断に最適。経営層への説明資料作成を効率化します。
📦 収録内容
- 法的検討フロー図:8つの観点(許認可・契約・知財・データ等)を体系化
- コピペ用プロンプト本体:事業概要を入力するだけで論点を自動整理
- 具体的な入出力例:AI契約書レビューSaaSを題材にした実践例
- カスタマイズ Tips:業種特化・優先度設定・タイムライン形式への変換方法
- よくある質問(FAQ):非弁行為、海外展開、既存事業変更への対応
- 関連プロンプト一覧:契約書レビュー、利用規約作成、M&A法務DDへの導線
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。