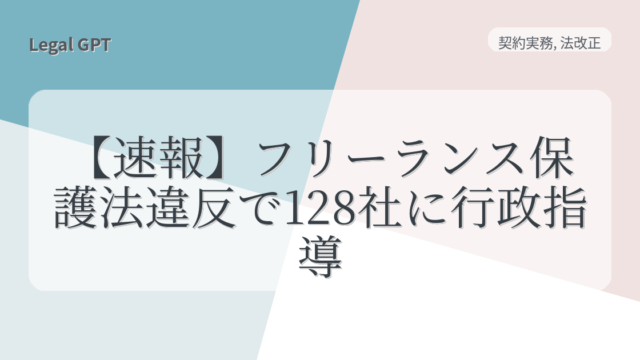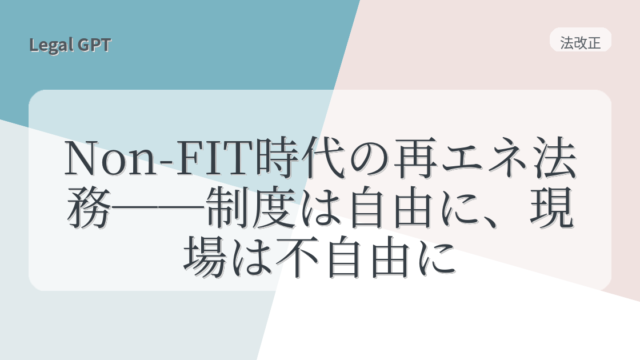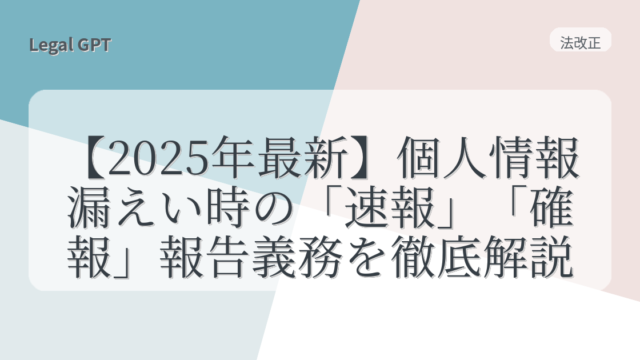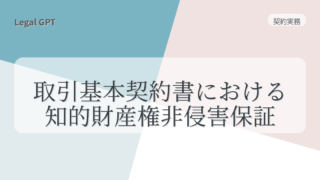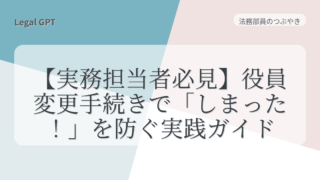地方自治体の契約実務、こんなに変わってる!【実務担当者が知らないとヤバい2025年の大改正と、談合事件から学ぶリスク対策】
地方自治体の契約実務、こんなに変わってる!
実務担当者が知らないとヤバい2025年の大改正と、談合事件から学ぶリスク対策
「えっ、随意契約の基準額がこんなに上がったの?」
「談合事件って、まだそんなに起きてるの?」
もしあなたがそう思ったなら、この記事は必読です。
契約実務が激変した2025年、あなたは対応できていますか?
地方自治体で契約や調達業務に携わっているみなさん、お疲れさまです。毎日の膨大な契約処理、法令解釈の難しさ、業者からの様々な要求への対応…本当に大変ですよね。
そんな中、令和7年(2025年)3月に地方自治法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第94号)が公布され、1974年以来の大幅な少額随意契約基準額の見直しが行われたことを、きちんと把握されていますか?そして、今でも談合事件が相次いで発覚していることを知っていますか?
実は、地方自治体の契約実務を取り巻く環境は、ここ数年で劇的に変化しています。のんびり構えていると、知らないうちに法令違反をしてしまったり、思わぬトラブルに巻き込まれたりする危険性があるんです。
1. まず押さえよう!地方自治体契約の「いろは」
契約方法は4つだけ、でも奥が深い
「入札って難しそう…」と思っている新人さんも多いかもしれませんが、実は地方自治体の契約方法はシンプルに4つしかありません。地方自治法では、より効果的に公益を図るために、契約方法を「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」「せり売り」の4つに限定しているんです(地方自治法第234条第2項、同施行令等)。
- 一般競争入札は、いわば「オープン参加の競争」です。参加資格を満たせば誰でも参加でき、最も公正性と透明性が高い方法として、原則的な契約方法とされています。
- 指名競争入札は、自治体が事前に指名した複数の業者で競争してもらう方法です。一定の品質確保と事務効率のバランスを取った方法ですが、透明性の観点から最近は慎重な運用が求められています。
- 随意契約は、競争を行わずに特定の相手方と契約する方法です。地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から第9号で定められた厳格な9つの要件のいずれかに該当する場合しか適用が可能ではないため、最も注意が必要な契約方法なんです。
- せり売りは、主に動産等の売却に関する方法であり、すべての契約類型に用いるものではありません。
契約担当者のリアルな日常
実際に契約業務を担当していると、理想と現実のギャップに悩むことも多いのではないでしょうか。
「予算執行期限が迫っているのに、一般競争入札をしている時間がない…」
「この案件、本当に随意契約の要件に該当するのかな?」
「業者さんから『他の自治体では』って言われたけど、うちはどうすべき?」
こうした悩みを抱えながら、上司や議会、監査委員への説明責任も果たさなければならない。契約担当者の苦労は、本当に大変だと思います。
2. 2025年の衝撃!約50年ぶりの大改正で何が変わった?
少額随意契約の基準額が引き上げられ、適用範囲が拡大
令和7年(2025年)3月28日に公布された地方自治法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第94号)により、1974年以来の大幅な少額随意契約基準額の見直しが行われました(施行日:令和7年4月1日)。この改正、実はとんでもなくインパクトが大きいんです。
普通地方公共団体(市町村等)の運用例では、以下のような改定が行われています(自治体ごとに財務規則等で適用開始日が異なります):
| 契約種別 | 改正前基準額 | 改正後基準額 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 工事・製造請負 | 130万円以下 | 200万円以下 | +54% |
| 財産買入れ | 80万円以下 | 150万円以下 | +88% |
| 物件借入れ | 40万円以下 | 80万円以下 | +100% |
| 委託・役務 | 50万円以下 | 100万円以下 | +100% |
随意契約の適用範囲拡大は競争性低下のリスクを伴う
今回の基準額引き上げにより、一般競争入札による発注案件が減り、少額随意契約による発注案件が増えることが予測されます。
でも考えてみてください。随意契約の適用範囲拡大は、競争性低下のリスクを伴うため、説明責任や内部統制の強化が不可欠です。
実際、公平性や透明性の観点から、随意契約であっても経済性や提案内容の確認が求められ、見積もり合わせ、オープンカウンター、コンペ、プロポーザル等、各自治体が規則等で定める方法で発注先の選考が行われます。
つまり、「随意契約だから簡単」ではなく、「随意契約だからこそ慎重に」という姿勢が求められているんです。
随意契約の9つの要件を再確認
地方自治法施行令第167条の2第1項各号では、随意契約が認められる9つの要件が定められています。主な例として:
- 第1号:少額随意契約(上記基準額以下の契約)
- 第2号:性質又は目的が競争入札に適しない場合
- 例:特殊な技術・ノウハウを要する業務、既存システムの保守・運用等
- 第6号:競争入札に付することが不利と認められる場合
- 例:緊急を要する災害復旧工事等
- 第7号:時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できる場合
- 例:既存設備を活用できるため有利な条件で契約できる場合
- 第9号:競争入札に付しても入札者がない場合、落札者が契約を締結しない場合
3. まだ続いている!談合事件の衝撃的な実態
2023年、現役職員が逮捕された兵庫県の事件
「談合なんて昔の話でしょ?」と思っている方、大間違いです。2023年10月に兵庫県道路公社が発注した工事を巡り、同公社に派遣されていた県職員らが入札情報を漏えいした疑いで逮捕・送検され、後に贈賄容疑での再逮捕も報じられました(神戸新聞等報道)。
30代の職員です。もしかしたら、この記事を読んでいるあなたと同世代かもしれません。報道によると、播但連絡道路の耐震補強修繕工事の競争入札で、非公表だった最低制限価格の情報を業者側に漏洩したとして、官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の両容疑で逮捕されたとのことです。
なぜ談合は繰り返されるのか?その心理的背景
実は、談合が起きる背景には、職員の「善意」があることが多いんです。
発注者側の「きちんとした業者に施工してもらいたい」「安かろう悪かろうでは困る」という思惑がゆえに、官製談合を引き起こしやすいという課題もありました。
「住民のために良い工事をしてもらいたい」
「実績のある信頼できる業者に頼みたい」
「工期に間に合わせるためには、この業者しかない」
こうした気持ちは、公務員として当然のことです。でも、その善意が法令違反につながってしまうのが、談合事件の恐ろしいところなんです。
法的責任の重さを知っていますか?
5年以下の懲役です。これは相当重い刑罰です。しかも、逮捕されれば社会的な制裁も免れません。家族にも迷惑をかけることになります。
4. 危険な「グレーゾーン」を見極める実践的な方法
こんな場面、あなたならどうする?
シーン1:業者からの「何気ない質問」
ある日、いつもお世話になっている業者の担当者から電話がかかってきました。
業者:「来月の○○工事の入札、どの程度の価格で考えればよいでしょうか?こちらとしても適正な価格で応札したいので…」
さて、あなたならどう答えますか?
→ これ、実は危険な回答です。暗に価格情報を求められているかもしれません。
→ これが安全な対応です。
シーン2:見積合わせで気になる「偶然」
3社から取った見積書を見ると、なんと提案内容や記載方法がとても似ています。価格も僅差です。
見積書の様式や記載内容が極めて類似している場合、談合の可能性を疑われることがあります。形式的には複数の見積が提出されていても、事業者間で内容が打ち合わせ済みであれば、実質的に談合と評価される可能性があります。
こういう場合は、見積書の取り直しや、追加の業者からの見積もり取得を検討しましょう。
身を守る3つの鉄則
鉄則1:すべてを記録に残す
業者との電話内容、面談の記録、判断の経緯…とにかく記録を残しましょう。「言った、言わない」のトラブルを防ぐだけでなく、適正な手続きを踏んでいることの証明にもなります。
鉄則2:一人で判断しない
重要な判断は必ず複数の職員で行いましょう。業者との面談も、できるだけ複数人で対応することをお勧めします。
鉄則3:迷ったら法務に相談
「これって随意契約の要件に該当するのかな?」と迷ったら、法務部門への事前照会を強く推奨します。一人で抱え込まず、組織として適切な判断を行いましょう。
5. デジタル時代の新しいリスクにも要注意
情報セキュリティ対策の強化が急務
令和7年3月28日に総務省が「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」を改訂しました。契約事務においても、情報管理の重要性がますます高まっています。
主な改訂ポイント(契約実務に関連する項目):
- マイナンバー利用事務系の画面転送方式の明確化
- 無線LAN利用時の認証強化(クライアント証明書等)
- インシデント対応体制の整備・強化
- アクセス制御・ログ管理の厳格化
- サイバーレジリエンス(攻撃を受けることを前提とした対策)の導入
契約担当者が確認すべきチェック項目:
電子契約システム運用時は、これらのガイドラインに準拠した運用ルール作成を検討してください。電子契約システムの導入が進む中、情報漏洩のリスクも新たに発生しています。予定価格や仕様書などの機密情報が、思わぬ形で外部に漏れることがないよう、十分な注意が必要です。
まとめ:住民の信頼に応える契約実務を目指して
いかがでしたか?地方自治体の契約実務を取り巻く環境は、想像以上に複雑で、かつ重要な責任を伴うものだということがお分かりいただけたでしょうか。
でも、悲観的になる必要はありません。適切な知識と意識を持って業務に取り組めば、リスクは十分にコントロールできます。
今日からできる5つのアクション
- 2025年改正内容を完全理解する – 基準額の変更を正確に把握し、適用を間違えない
- 記録・文書化を徹底する – すべての判断過程を記録に残す習慣をつける
- 業者との適切な距離感を保つ – 透明性を確保し、適正な関係を維持する
- 「おかしいな」という感覚を大切にする – 違和感を感じたら立ち止まって考える
- 継続的に学習する – 法令改正や事例研究を怠らない
私たち地方自治体職員が扱っているのは、住民の皆さんから預かった大切な税金です。一円たりとも無駄にしてはいけませんし、不正や不適切な使われ方をしてもいけません。
同時に、適正な手続きを経て、質の高い公共サービスを提供することで、住民の皆さんの生活をより良くすることができます。
一人ひとりの実務担当者の意識と行動が、自治体への信頼、ひいては地方自治の発展につながります。ぜひ、この記事を参考に、より良い契約実務の実現に向けて頑張ってください!
📚 【参考】主な法令・資料
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
- 地方自治法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第94号)
- 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)
- 総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」
🔗 【主要出典・参照リンク】
- 総務省「地方自治法施行令の一部を改正する政令の概要」
- 総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」
- 公正取引委員会「入札談合等関与行為防止法について」
- 兵庫県道路公社談合事件関連報道(神戸新聞等)
※この記事は2025年9月時点の情報に基づいています。最新の法令改正等については、必ず公式情報をご確認ください。

🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。