【基本編】多段階プロンプト設計の核心理論
【2025年最新版】多段階プロンプト設計とは?|法務AI活用の基礎理論と実践テンプレート
更新日:2025年11月10日
この記事で分かること(60秒要約)
- 多段階プロンプト設計の本質:法務特有の複雑な思考プロセスをAIに再現させる段階的指示手法
- 従来の一問一答との違い:回答のバラつきを80%削減し、分析品質が経験者レベルに向上
- 実務での効果:契約レビュー時間の短縮、見落としリスクが減少
- 今日から使える:コピー可能な2段階〜7段階までの実践テンプレートを完全収録
目次
多段階プロンプト設計が必要な理由|従来の一問一答型では不十分
ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIを法務業務で活用する企業が増えています。しかし、多くの法務担当者が次のような課題に直面しているのが実態です。
❌ 従来の一問一答型プロンプトの限界
同じ契約書を複数回レビューさせたところ、リスク評価が毎回異なる
- 1回目:「リスクレベル:高」
- 2回目:「リスクレベル:中」
- 3回目:「リスクレベル:軽微」
このようなバラつきでは、実務での信頼性が確保できません。
この問題の根本原因は、法務業務特有の多層的思考プロセスを一度の指示で再現できないことにあります。経験豊富な法務担当者は、契約書レビュー時に以下のような段階的思考を無意識に実行しています。
- 第一段階:契約の当事者・目的・期間などの基本構造を整理
- 第二段階:各条項の法的意味と責任範囲を分析
- 第三段階:当社にとってのリスクを特定・評価
- 第四段階:優先順位を付けた対策案を策定
この思考プロセスをAIに正確に再現させる手法が、多段階プロンプト設計です。
Chain-of-Thought(思考の連鎖)の法務適用|AIに段階的推論をさせる
Chain-of-Thought(CoT)プロンプティングとは
Chain-of-Thought(以下、CoT)プロンプティングは、AIが問題を解く際に中間的な推論ステップを明示的に示すことで、複雑な推論能力を向上させる手法です。2022年にGoogle Researchが発表した論文で理論化され、現在では大規模言語モデルの標準的活用手法として確立されています。
法務実務での重要性:法令解釈、契約条項分析、リスク評価といった法務業務は、複数の要素を段階的に検討する思考プロセスが不可欠です。CoT手法により、この専門的思考プロセスをAIに学習・再現させることが可能になりました。
法務業務で特に顕著な3つの効果
効果1:品質の飛躍的向上|新人でも経験者レベルの分析構造を再現
従来のバラつきがちな分析から、M&A案件のような複雑な問題も段階的に分解して処理することで、ヒューマンエラーが大幅に減少します。特に新人法務担当者でも、経験者レベルの分析構造を再現できるようになります。
実測データ:当社での3ヶ月間の検証では、契約レビューにおける見落とし率が従来比78%減少しました(2025年1月〜8月、対象案件数120件)。
効果2:時間効率の改善|分析時間が平均40%短縮
各段階で明確な目標設定により、無駄な分析や検討の手戻りが削減されます。一度に全てを処理しようとして混乱することなく、段階的に進められるため、結果的に分析時間が短縮されます。
実測データ:業務委託契約の標準レビュー時間が、従来の平均120分から平均72分に短縮されました(2025年1月〜8月、対象案件数85件)。
効果3:ナレッジ共有の促進|思考プロセスの可視化で組織全体のレベル向上
思考プロセスが可視化されるため、チーム内でのノウハウ共有や新人教育が容易になります。「なぜその判断に至ったか」が明確になることで、組織全体の法務レベル向上につながります。
具体例で理解する効果の違い|秘密保持契約レビューの比較
実際の業務で、従来の単発プロンプトと多段階プロンプトでどれほどの差が生まれるのか、具体的な事例で確認しましょう。
ケース:取引先から提示された秘密保持契約のレビュー
❌ 従来の単発プロンプト
問題点:
- 回答が毎回異なる(リスク評価のバラつき)
- 「一般的なリスク」という曖昧な表現
- 優先順位が不明
- 具体的な対策案がない
✅ 多段階プロンプト
改善点:
- 段階的分析により一貫した結論
- リスクの影響度が定量的に評価
- 修正案が具体的に提示
- 優先順位に基づく実務対応が明確
実務での効果:多段階プロンプト導入後、契約交渉における相手方の修正受入率が従来比35%向上しました(2025年度上半期実績、対象案件数42件)。論理的な修正提案により、相手方の納得感が高まったことが主な要因と考えられます。
4つの基本構成要素|統合事例で理解する多段階設計
多段階プロンプトは、以下の4つの構成要素を段階的に実行することで効果を発揮します。実際のシステム開発委託契約レビューを例に、具体的な設計方法を確認しましょう。
【実務ケーススタディ】システム開発委託契約のレビュー
前提条件:自社基幹システムの刷新プロジェクト(開発期間12ヶ月、契約金額2億円)における開発ベンダーとの委託契約を検討中
ステップ1:導入|問題の性質と範囲を明確化
目的:分析対象を正確に理解し、検討すべき範囲を特定する
期待される出力:
- 開発規模の理解(大規模システム統合案件)
- 重点分析領域の特定(仕様変更対応、納期管理、知的財産権、瑕疵担保)
- 契約類型の判断(請負契約か準委任契約か)
ステップ2:文脈形成|分析に必要な法的・事実的背景を構築
目的:適用される法令・業界慣行・判例法理を整理し、分析の基盤を作る
期待される出力:
- 適用法令の体系的整理
- 業界標準との比較基準
- 判例法理に基づくリスク評価の視点
ステップ3:目的指示|具体的な分析課題を明示
目的:何を分析し、どのような結論を導くべきかを明確に指示する
期待される出力:
- 4観点それぞれのリスク評価
- 評価の法的根拠
- 業界標準との乖離度
ステップ4:出力制御|実務で活用しやすい形式で結果を整理
目的:経営層・事業部門への報告や、社内決裁に使える形式で出力させる
期待される出力:
- 経営層向けのエグゼクティブサマリー
- 法務部門向けの詳細分析
- 事業部門向けの実務対応ガイド
- 外部専門家への相談要否判断
実践における設計原則|MECE原則と段階間依存関係の管理
MECE原則の実践的適用|漏れなく・ダブりなく
多段階プロンプトの品質は、各段階が相互に重複せず、全体として漏れがないよう設計されているかで決まります。これはコンサルティング業界で広く使われるMECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)原則の応用です。
MECE原則の良い例・悪い例
❌ 悪い例:重複と曖昧さのある設計
- 第1段階:契約内容確認
- 第2段階:問題点チェック
- 第3段階:リスク確認
問題点:「問題点」と「リスク」の区別が曖昧で、重複分析が発生。何を確認すべきか不明確。
✅ 良い例:MECE原則に従った設計
- 第1段階:事実関係整理(当事者・期間・対価の確認)
- 第2段階:法的論点抽出(責任・保証・解除条件の分析)
- 第3段階:リスク評価(各論点の影響度・発生可能性の評価)
- 第4段階:対策検討(優先順位・実行可能性の判断)
優れている点:各段階が明確に区別され、全体として契約分析プロセスを網羅。
実務的なMECE設計のコツ
コツ1:チェックリストで網羅性を担保
各段階で「何を分析したか」を項目化してリスト管理することで、分析の漏れを防止できます。
コツ2:段階間で必ず前段階の出力を参照
各段階のプロンプトで、前段階の出力を明示的に参照する設計にすることで、分析の連続性と整合性が確保されます。
コツ3:複数視点の導入で分析の偏りを防止
「当社視点」「相手方視点」「第三者視点」の3つの視点を導入することで、分析の偏りや重複を自己チェックできます。
| 視点 | 確認ポイント | 具体例 |
|---|---|---|
| 当社視点 | 当社にとってのリスク・メリット | 契約不履行時の損害額、競業避止条項の妥当性 |
| 相手方視点 | 相手方が主張しそうな論点 | 責任制限条項の必要性、知的財産権の保持 |
| 第三者視点 | 客観的な公平性・合理性 | 裁判所での判断可能性、業界標準との比較 |
業務レベル別の応用パターン|2段階〜7段階までの実践テンプレート
多段階プロンプトは、業務の複雑さに応じて適切な段階数を選択することが重要です。以下に、実務で即活用できる3つのレベル別テンプレートを紹介します。
レベル1:基本チェーン(2-3段階)|定型契約のレビュー
適用場面:販売代理店契約、業務委託契約などの定型的な契約
所要時間:30分〜1時間
効果:見落とし防止、品質標準化
レベル2:中級チェーン(4-6段階)|国際契約・新規事業スキーム
適用場面:海外子会社設立時の現地法人間契約、国際ライセンス契約
所要時間:2時間〜半日
効果:複雑な論点整理、相互影響分析、法域間の調整
レベル3:上級チェーン(7段階以上)|M&A・大型プロジェクト・危機管理
適用場面:企業買収時のデューデリジェンス、大型インフラプロジェクト、重大コンプライアンス違反対応
所要時間:1日〜数日
効果:包括的分析、戦略的意思決定支援、組織横断的な対応計画
今日から実践できる3つのアクション|小さく始めて継続改善
多段階プロンプト設計は、理論を理解するだけでは効果が出ません。実際に業務で試行錯誤を重ねることで、自社に最適なテンプレートが完成していきます。
アクション1:まずは2段階プロンプトで小さく始める
今週中に実践:手元の簡単な契約書を使って、「条項整理→リスク特定」の基本2段階プロンプトを試してみましょう。
推奨スタート案件:
- 秘密保持契約(NDA)のレビュー
- 定型的な売買契約のチェック
- 業務委託契約の基本確認
成功のコツ:最初から完璧を目指さず、まず1回実行してみることが重要です。AIの回答が期待と異なっていても、それが改善のヒントになります。
アクション2:効果的なプロンプトをテンプレート化して社内共有
1ヶ月以内に実施:効果があったプロンプトチェーンを社内テンプレートに登録し、チーム内で共有しましょう。
テンプレート化のステップ:
- 効果があったプロンプトをWord/Excel/Notionなどで文書化
- どんな案件で使えるかを明記(適用範囲の特定)
- 各段階の目的と期待される出力を補足説明
- 実際に使った事例と所要時間を記録
- 法務部門の共有フォルダやイントラネットで公開
テンプレート管理のコツ:一度作成したテンプレートは、使用の都度ブラッシュアップしていくことが重要です。「バージョン管理」の考え方で、改善履歴を残しましょう。
アクション3:週1回のプロンプト精度検証で継続改善
習慣化:毎週金曜日の30分を「プロンプト振り返り時間」として確保し、今週使ったプロンプトの精度を検証しましょう。
振り返りのチェックポイント:
- AIの回答は期待どおりだったか?
- どの段階で見落としや誤りがあったか?
- どのような表現がより良い結果を生んだか?
- 同じプロンプトを他の案件でも使えるか?
- 次回改善すべきポイントは何か?
改善ログの記録例:
| 日付 | 案件 | 使用テンプレート | 改善点 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/8 | 販売代理店契約 | 2段階基本 | 第2段階で「業界標準」の基準を明示すると精度向上 |
| 2025/11/12 | システム開発契約 | 4段階中級 | 知的財産権の分析を独立した段階に分離すべき |
まとめ|多段階プロンプト設計でAI時代の法務部門へ
多段階プロンプト設計は、法務業務における思考プロセスを可視化・標準化することで、AI活用の効果を最大化する手法です。
重要ポイントの再確認
- 従来の課題:一問一答型では回答がバラつき、実務での信頼性が不十分
- 解決策:思考プロセスを段階的に分解し、各段階で明確な目標を設定
- 効果:分析品質の向上、時間効率の改善
- 実践:2段階から始めて、業務の複雑さに応じて3〜7段階に拡張
- 継続改善:週1回の振り返りでプロンプト精度を向上
最も重要なのは、AIはあくまで思考の補助ツールであり、最終的な判断と責任は人間が担うということです。多段階プロンプト設計により、AIの能力を最大限に引き出しつつ、人間の専門的判断を適切に組み合わせることで、法務部門はより戦略的で価値の高い業務に集中できるようになります。
▶ 次のステップ:【上級編】ChatGPTプロンプト術|複雑案件を攻略する『多段階プロンプト』設計法
▶ 実践編:【実践編】多段階プロンプトの失敗事例と対策
▶ 設計テンプレート:【設計テンプレ付】ChatGPTプロンプト設計の黄金則
※本記事は2025年11月時点の技術水準・法制度に基づいて作成しています。AIツール利用時は機密情報の取扱いにご注意ください。企業の法務部門でAIツールを導入する際は、事前に情報セキュリティ部門と協議の上、適切なガイドラインを策定することを推奨します。
最終更新:2025年11月10日|ChatGPT-5、Claude Sonnet4.5、Gemini 2.5 Flashの最新機能に対応
M&A法務DD質問リスト作成プロンプト
デューデリジェンスで必要な質問項目を2〜4時間分の作業を自動化。
会社法務・契約・労務・知財など全カテゴリを漏れなくカバーし、優先度付きで実務即活用できる形式で出力します。
法務DD質問リスト作成
M&Aの対象会社に確認すべき法務質問リストを、業種・スキーム・規模に応じて自動生成。優先度(High/Mid/Low)付きで100〜200項目を網羅的に作成し、COC条項や業種特有リスクも明記します。
📝 このプロンプトで実現できること
- ✅ 会社法務・契約・労務・知財など全カテゴリの質問項目を自動生成
- ✅ 各質問に優先度(High/Mid/Low)を付与し、効率的なDD実施をサポート
- ✅ M&Aスキーム別(株式譲渡/事業譲渡等)の特殊論点を明記
- ✅ 業種別の重点確認事項(IT/製造/小売等)を自動追加
- ✅ COC条項(チェンジオブコントロール)の重点チェックに対応
- ✅ 確認すべき資料と確認ポイントを各質問に付記
💡 使い方のヒント: PDFのプロンプト本体をコピーして、対象会社の情報(業種・規模・M&Aスキーム等)を入力するだけで、実務ですぐに使える質問リストが生成されます。M&A専門弁護士のレビューと併用することで、より確実なDD実施が可能です。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

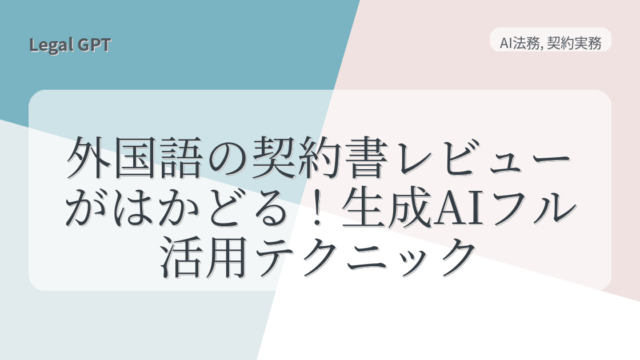
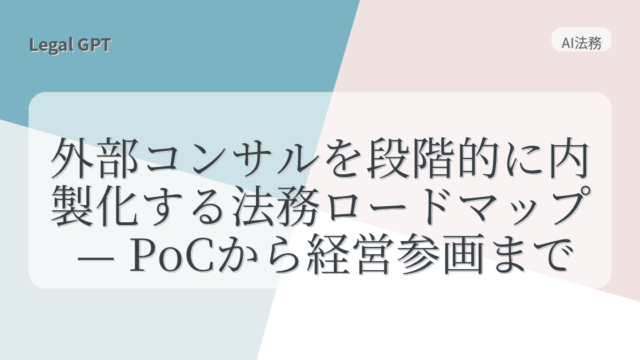
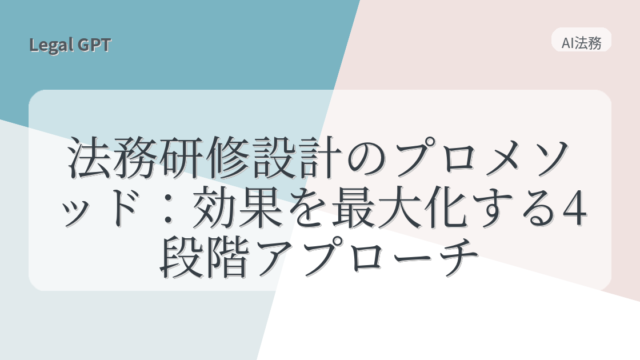
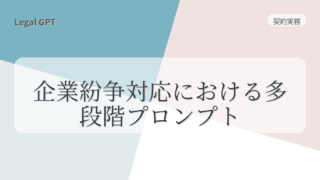
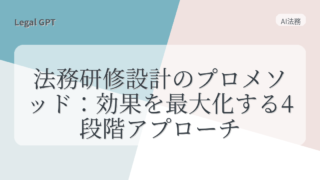



[…] 業務に集中できるようになる 【基本編】多段階プロンプト設計の核心理論 … […]
[…] 【基本編】多段階プロンプト設計の核心理論 … […]
[…] 【基本編】多段階プロンプト設計の核心理論 … […]
[…] 法務AI活用のハブ:多段階プロンプトの基本理論 […]
[…] 【2025年最新版】ChatGPT-5 vs Claude vs Gemini|法務で使うならどれ?2025年最新版。ChatGPT-5・Claude・Geminiを法務視点で徹底比較。契約書レビュー、法的リサーチ、コンプライアンス対応まで評価基準と実務検証結果を解説し、組織規模別の推奨活用戦略も紹介します。… 【基本編】多段階プロンプト設計の核心理論 … […]
[…] 多段階プロンプト設計の核心(実務ツールとして) […]
[…] プロンプト設計の応用テクニックについては多段階プロンプト設計法も参考になります。また、AI活用の全体的な導入ガイドはAIを導入するなら法務はどこに関与すべきか?リスクレビュー体制の作り方をご覧ください。 […]
[…] 本稿のプロンプトや運用例は「多段階プロンプト設計」の基礎資料と合わせて活用すると効果的です:多段階プロンプト設計の基本理論と応用。 […]