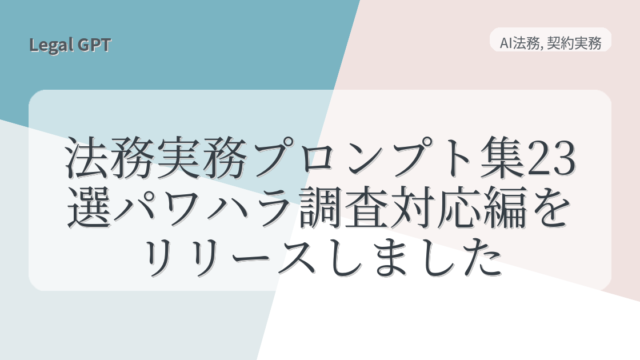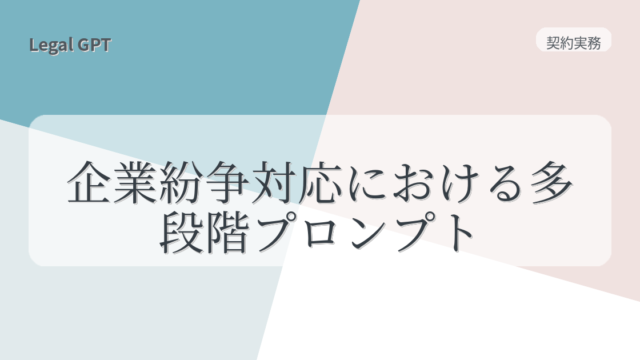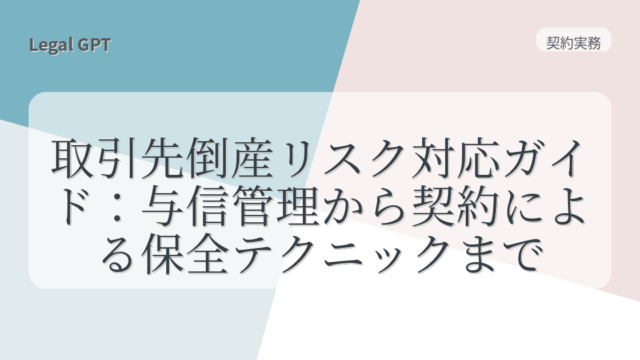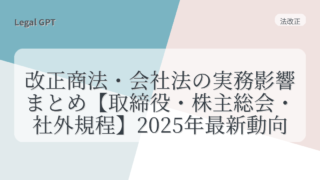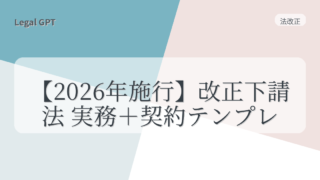NDAの目的限定と残存義務:悪例→良例の条項修正カタログ【2025年版・実務完全対応】
レビュー方針→論点抽出→修正文案→交渉論点まで、“漏れない型”で揃える
契約レビューは、経験者でも「抜け」が起きやすい作業です。STEP化して再現可能にすると、品質が安定します。
- 前提整理(当事者/取引/優先順位)
- 地雷条項の抽出(損害賠償・解除・保証・責任制限など)
- 修正文案・代替案・交渉論点(説明つき)
- レビュー結果の報告書・メール文面まで
※機密情報の入力範囲・マスキングは社内ルールに従ってください。一般的情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。
NDAの目的限定と残存義務:悪例→良例の条項修正カタログ【2025年版・実務完全対応】
最終更新日:2025年10月27日)
TL;DR(結論):NDA(秘密保持契約)で最も見落とされがちなのは「目的限定」と「残存義務(契約終了後の存続期間)」の曖昧さです。本稿は実務で頻出する悪例を示し、即時使える良例(監査・AI・再委託まで網羅)をコピペ可能な形で提供します。
重要な法令・指針(要点)
- 改正不正競争防止法(改正法)は施行日が令和6年4月1日(=2024年4月1日)であり、営業秘密の保護強化等が盛り込まれています。
- 経済産業省の「営業秘密管理指針」は令和7年3月31日に改訂され、デジタル化・生成AI時代の管理ポイントが整理されています。最新版を参照してください。
- 個人情報の扱いについては個人情報保護法(令和2年改正)の規定や個人情報保護委員会のガイドラインに従う必要があります(改正法の重要な施行日は令和4年4月1日)。
(注)本文中の条項例は一般的参考例です。特定事案での最終判断は弁護士による確認を推奨します。
本記事の構成(短縮)
- 目的限定の悪例→良例(監査・ログ対応含む)
- 残存義務(情報分類別の段階設定)
- AI(学習データ)対応の具体策
- 監査・再委託・返還・差止め等の重要条項
- コピペ可能な条項スニペット集+別紙テンプレ
1. 目的限定条項:悪例と良例(クイック比較)
| 問題点 | ❌ 悪例(短縮) | ✅ 良例(改善ポイント) |
|---|---|---|
| 目的限定が抽象的 | 「本契約に関連する業務のため」 | 別紙でプロジェクト名・期間・作業内容を特定+事前承諾手続+監査・ログ保存義務 |
| 目的変更手続 | なし | 事前書面承諾+申請項目(目的・期間・利用者・方法)+開示者の回答期限 |
| 目的の立証負担 | なし | アクセスログ保存・監査協力で立証負担を低減 |
❌ 悪例(具体)
第○条(利用目的)
受領者は、秘密情報を本契約に関連する業務のために使用することができる。問題点:
- 「本契約に関連する業務」は不明確で、受領者の恣意的解釈を許す
- 目的外利用の立証で開示者が不利になる可能性が高い
✅ 良例(監査・ログ対応版:コピー可能)
第○条(秘密情報の利用目的)
1. 受領者は、秘密情報を別紙1「利用目的一覧表」に記載された目的(以下「許諾目的」)にのみ使用し、許諾目的以外の目的で使用してはならない。
2. 受領者が許諾目的以外の目的で秘密情報を使用する必要が生じた場合、受領者は事前に開示者の書面による承諾を得なければならない。承諾の申請には以下を明記する:
(1) 利用目的の詳細
(2) 利用期間
(3) 利用者(役職・氏名)
(4) 利用方法
(5) 関連する成果物・第三者提供の有無
3. 開示者は前項の申請を受領してから14日以内に書面で承諾の可否を回答するものとする(合理的事由がある場合は延長可)。
4. 受領者は、秘密情報の取扱いに関してアクセスログを保存し、開示者からの合理的な監査要請に協力するものとする。改善ポイント:別紙でプロジェクト名・期間を明記すると目的限定が実効化します。監査・ログ義務は立証力の観点で重要です。
別紙1:利用目的一覧表(テンプレ)
| プロジェクト名 | 利用目的 | 期間 | アクセス権限者 | 禁止行為 |
|---|---|---|---|---|
| AI画像認識システム共同開発 | 技術仕様の検討、開発作業、成果物評価 | 2025/04/01〜2026/03/31 | 開発部長・技術担当3名 | 第三者提供・AI学習利用(未承諾) |
2. 残存義務(契約終了後の保護)
ポイントは情報の性質に応じた合理的期間を定めることです。技術情報と営業情報で陳腐化速度が異なるため、画一的な「終了後2年」などは避けるのが実務上適切です。営業秘密に関しては「秘密性が失われるまで」とする扱いが実務上考えられます。
❌ 悪例(画一的)
第○条(有効期間)
本契約の有効期間は契約締結日から1年間とし、秘密保持義務は契約終了後2年間存続する。✅ 良例(情報分類に応じた段階的設定:コピー可能)
第○条(有効期間及び秘密保持義務の存続)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から○年間とする。
2. 秘密保持義務は、本契約終了後も以下の各号に定める期間存続する:
(1) 技術情報(アルゴリズム、設計仕様、ソースコード等):契約終了後5年間。ただし、当該情報が不正競争防止法上の営業秘密に該当する場合は、その秘密性が失われるまで存続する。
(2) 営業情報(顧客リスト、価格体系、販売戦略等):契約終了後3年間。
(3) 個人情報(個人情報保護法に定義されるもの):法令に基づく保存義務がある場合は当該期間に従い、それ以外は本人の権利行使及び本契約の定めに従うものとする。
(4) その他の秘密情報:契約終了後2年間。
3. 前項の規定にかかわらず、当該情報が次のいずれかに該当する場合、当該秘密保持義務は消滅する:
(1) 開示者が書面により当該情報について秘密解除を行ったとき。
(2) 当該情報が受領者の責めに帰することなく公知となったとき。
(3) 受領者が独自に開発したことを合理的に証明したとき。補足:個人情報の定めは単純化を避け、個人情報保護法や保存義務(税務等)との整合性を明記してください。
3. AI(学習データ)に関する実務対応(必須)
生成AIの普及に伴い、秘密情報を学習データ化するリスクは重大です。単に「最大限努力で除去」とするだけでは実効性に乏しく、紛争時の証明も困難です。以下のように事前承諾+具体的手順+証跡提出を必須化してください。
❌ 悪例(曖昧)
第○条(AI利用)
学習済みモデルからの除去が技術的に困難である場合、受領者は当該モデルの利用を研究目的に限定し、秘密情報の除去に最大限努力する。✅ 良例(実効化)
第○条(AI学習データとしての利用)
1. 受領者は、開示者の秘密情報をAIモデルの学習データ(以下「学習データ」)として使用する場合、事前に開示者の書面による承諾を得なければならない。
2. 承諾を得た場合、受領者は以下を遵守するものとする:
(1) 学習データ化の具体的方法、保管場所、保管期間及びアクセス権限等を開示者に書面で通知すること。
(2) 学習済みモデル又は派生物(派生モデル)を第三者に提供することを禁止すること。
(3) 本契約終了時又は開示者の要求時には、受領者は学習データ及び当該秘密情報を含む派生物について削除又は無効化を行い、削除困難な場合は当該理由を文書で開示し、利用を研究目的等の限定的目的に限定する等の代替措置を講じること。
(4) 受領者は、上記措置完了後、削除証明又は措置報告書を開示者に提出すること。
3. 受領者は、削除の実行及び証跡保全に関し善良な管理者の注意を尽くすものとし、第三者に対する違反があった場合は損害賠償責任を負う。実務ノート:可能であれば別紙で「具体的な削除手順(ログ消去、モデル再学習、重みの特定手法等)」を定めると実効性が高まります。
4. 見落としがちな重要条項(監査・再委託・返還等)
監査・立会い(サンプル)
第○条(監査権限)
1. 開示者は、受領者による秘密情報の管理状況について、合理的な範囲で監査・検証を行う権利を有する。
2. 監査は、事前通知(14日前)、受領者の営業時間内、オンサイト又はオフサイト(ログ・報告書提出)により実施する。年1回を上限とする(重大疑義がある場合は例外)。
3. 受領者は監査に協力し、アクセスログ、保管場所、取扱者リスト等を提示する義務を負う。
4. 監査費用は原則開示者負担。但し重大な違反が発見された場合は受領者が負担する。再委託(フローダウン)
第○条(再委託)
1. 受領者が第三者に秘密情報の取扱いを委託する場合、事前に開示者の書面承諾を得るものとする。
2. 承諾を得た場合、受領者は委託先に本契約と同等以上の秘密保持義務を課し、委託先の違反については受領者が責任を負う(連帯責任)。
3. 受領者は委託先のリスト及び委託内容を開示者に報告する。返還・廃棄(期限・証明)
第○条(秘密情報の返還・廃棄)
1. 受領者は、契約終了後30日以内に秘密情報及び複製物を返還または復元不能な方法で廃棄する。
2. 廃棄の方法(紙:細断、電子:完全消去、クラウド:完全削除の確認等)を定め、廃棄完了後7日以内に廃棄証明書を提出する。
3. バックアップ等で自動的に保持されたデータについては、最大90日以内に削除することを原則とし、その間は本契約の義務を継続する。差止め請求・仮処分
第○条(差止請求)
1. 開示者は、受領者の違反又は違反の恐れがある場合、差止め・仮処分を請求できる。
2. 差止め請求は損害賠償請求を妨げない。5. FAQ(よくある質問)
Q1: 「事業検討」とだけ記載してもダメですか?
A: 絶対にダメとは言えませんが、実務上はリスクが高いです。最低でも「○○プロジェクトに関する協業可能性の検討」などで範囲を特定し、ログ保存・監査義務を合わせて定めることを推奨します。
Q2: 残存義務は何年が適切ですか?
A: 情報の性質に依存します。目安として技術情報3〜5年、営業情報2〜3年。営業秘密に該当する場合は「秘密性が失われるまで」とする規定が実務的に採用されることが多いです。
Q3: 無期限は必ず無効ですか?
A: いいえ。無期限条項が直ちに無効となるわけではありません。営業秘密等の性質によっては合理性を認められる場合がありますが、営業秘密以外の情報に無期限義務を課すことはリスクが高い点に注意してください。
Q4: AI学習データでどこまで規定すべきですか?
A: 最低限、(1) 事前承諾制、(2) 学習データ化の方法・保管・アクセス、(3) 派生モデルの第三者提供禁止、(4) 削除手順と証跡、(5) 削除証明・措置報告の提出を規定してください。
参考文献・法令(原典リンク)
- 不正競争防止法(改正・施行情報) — 経済産業省(概要・施行日等)。
- 営業秘密管理指針(令和7年3月31日改訂版) — 経済産業省(PDF)。
- 個人情報保護法(令和2年改正)関連 — 個人情報保護委員会(Q&A・ガイドライン)。
秘密保持契約書(NDA)作成プロンプトを無料配布
ChatGPT・Claudeにコピペするだけで、30〜60分の作業を自動化できるプロンプト集。
双方向型・片方向型の選択から、業種別カスタマイズまで、実務で即使えるテンプレートです。
秘密保持契約書(NDA)ドラフト作成プロンプト2025最新版
取引開始前の情報交換段階で必要となるNDAを、取引目的・期間・対象情報に応じて自動生成。双方向型・片方向型の選択、返還義務の有無など、実務で頻出するバリエーションに対応しています。
📋 このPDFに収録されている内容
- プロンプト本体(コピペ用) – AIに入力するだけで即使える
- 入力例・出力例 – 実際の生成結果を確認できる
- カスタマイズポイント – 自社向けに調整する方法を解説
- 業種別の注意点 – 製造業・IT・金融・小売別に対応
- よくある質問(FAQ) – 双方向型と片方向型の使い分けなど
- 関連プロンプト – 契約書リスク分析・相手方ドラフト修正など
💡 すぐに実務で使えます:PDFのプロンプトをコピーしてAIに貼り付けるだけ。業務提携検討・M&A検討・共同開発など、あらゆる場面のNDA作成に対応。GPT-5・Claude Sonnet 4.5・Gemini 2.5 Flashで動作確認済みです。

🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。