Non-FIT時代の再エネ法務──制度は自由に、現場は不自由に
Non-FIT時代の再エネ法務──制度は自由に、現場は不自由に
FIT時代の”安心感”と法務の役割
FIT制度下では、長期の固定価格による売電保証や行政認定と接続の流れが比較的定型化されていました。そのため法務は主に「制度の枠内で安全に組む」こと、定型契約の整備と運用が中心となっていました。
Non-FIT移行がもたらす複雑さ
Non-FITでは売電の出口が多様化(市場連動のFIP、相対契約、自己託送など)し、スキーム設計が高度化します。制度改正や運用指針の更新も頻繁で、法務は制度面・実務面の双方を追い続ける必要があります(改正や運用改定に関する解説記事参照)。
- FIP制度の価格補填ロジック(ベースラインや基準価格等)の理解
- PPA 等の個別交渉に伴う信用・履行リスクの見極め
- 非化石証書など環境価値取引の契約管理
- 制度変更に応じた契約見直しと社内周知
ポイント:FIT時代には想定しづらかった「スキーム設計から出口交渉まで」すべてに法務が関与する必要が生じています。
参考:法改正・契約対応の緊急ポイントに関しては、実務向けのガイドが詳しいです。例)再エネ特措法の改正と契約対応ガイド。(再エネ改正と契約対応ガイド)
Non-FIT時代における法務の”新しい役割”
単なるひな形修正にとどまらず、制度趣旨と実運用のギャップを社内に翻訳し、可変型スキームを設計する能力が求められます。また、環境価値や補助金との整合性を立体的に保つことも重要です。
- 制度趣旨と運用のギャップを翻訳して伝える
- 相対契約の交渉で信用・履行リスクを評価する
- 契約と環境価値、補助金の整合性を設計する
- 制度変更を前提にした可変型スキーム構築
事例:住民説明会・認定手続き等の運用が変わった場合、それに合わせた契約条項の導入や、住民対応フローの整備が必要になります(最新の住民説明会運用ガイド参照)。
参考:住民説明会や認定手続きの最新運用についてはこちらを参照してください。(住民説明会と認定運用ガイド)
結局、自由とは自己責任ということ
制度が柔軟になったことは事業者にとって選択肢を広げましたが、同時に「リスクを見極めて引き受ける力」が求められるようになりました。法務はその責任を事前に織り込む役割を担います。
結び(まとめ)
制度は変わっても、変わらないのは「法務が事業の防波堤であるべき」立ち位置です。今日も通知や制度改定を読み込みつつ、どこまで制度に委ね、どこから自己防衛するか──その境界線を探り続けましょう。
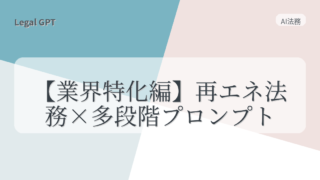
\ChatGPTをこれから使う人におすすめ!/
『はじめての生成AI ChatGPT「超」活用術』(安達恵利子 著)は、ChatGPTの基礎から実務応用までを網羅した初心者向け実践書です。
「そもそもChatGPTってどう使えばいいの?」
「どんなことができるのか、事例を交えて知りたい」
そんな方にぴったり。
・入力の基本
・正しい指示の出し方(プロンプト)
・メール・議事録・資料作成の効率化
など、仕事で今すぐ使えるノウハウが満載です。
初心者でも迷わず活用できる「3部構成」で、文系・非エンジニアでも安心!
👇Amazonで詳細をチェック

🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

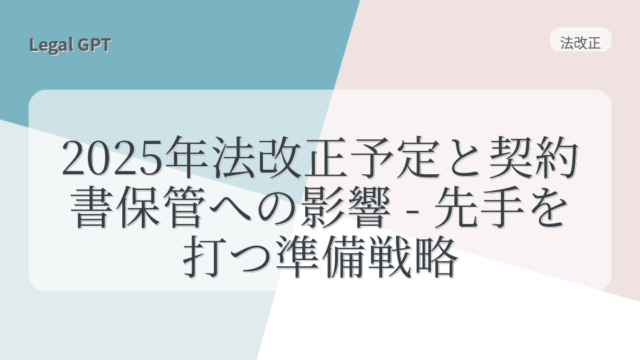
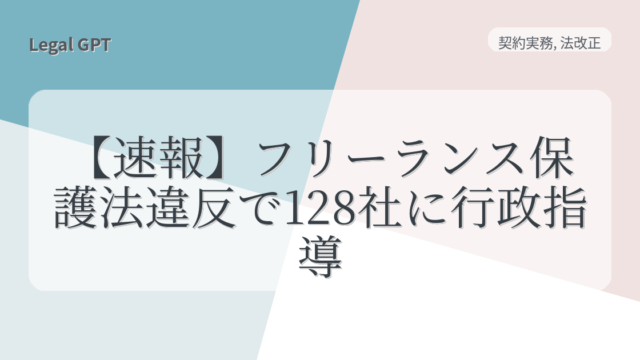
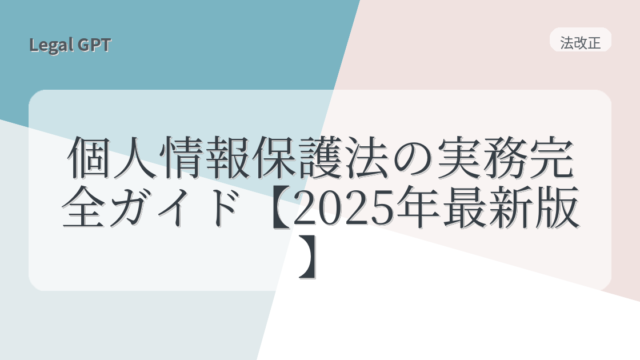
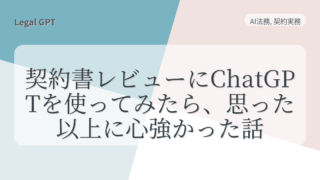
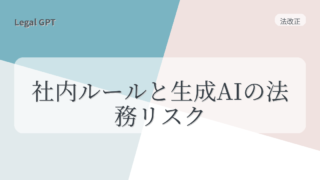



[…] Non-FIT 時代の制度変化と法務上の実務的着眼点 […]
[…] Non-FIT時代の再エネ法務:制度の自由化と現場の課題 […]