個人情報保護法改正でプライバシーポリシーの何を変える?
漏えい対応/委託・同意/社内規程/対外文面を、実務書式まで一気に作る
個情法は「条文理解」よりも、報告書・通知・規程・社内運用の文面を揃えられるかで差が出ます。
- 漏えい時:速報/確報・社内報告・顧客通知の叩き台
- 委託:契約条項・委託先管理・チェックリスト
- 同意/外部送信:説明文・同意取得・表示文面
- 規程:社内ルール整備(運用に落とす)
※機密情報の入力範囲・マスキングは社内ルールに従ってください。一般的情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。
【2025年10月最新】個人情報保護法改正対応
プライバシーポリシー変更点を表で一発比較
2024年施行済・2025年検討中の改正内容と実務対応の完全ガイド
【追記】個人情報保護委員会が2025年2月5日に公表した「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」の内容を反映しています。本文中の「2025年改正案」はいずれも検討段階の素案であり、最終的な法案・施行期日は未定です(確定ではありません)。最新情報は個人情報保護委員会の公式サイトでご確認ください。
本稿は2025年10月21日現在の公表資料・検討状況に基づき作成しています。改正法の成立・施行時期及び条文の最終内容は国会審議・政省令で変更され得ます。記事中の「見込み」「推定」「検討案」等の表現は**確定事項ではない**ことを前提にお読みください。
📌 結論要約(保存期間・適用条文・例外)
2024年4月1日施行の個人情報保護法施行規則第7条第3号改正により、ウェブスキミング対策として安全管理措置の範囲が拡大しました(施行済)。プライバシーポリシーには不正プログラム設置防止等の安全管理措置の明記が必要です。2025年の改正は現時点で検討段階の素案が示されており、同意規制の柔軟化や本人通知義務の在り方が議論されています。<注:法案成立・施行時期は未定であり、本稿内の”見込み”は過去事例に基づく推測にすぎません。最新情報は個人情報保護委員会で確認してください>。
2025年10月現在、個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに係る改正は検討段階であり、法案は未だ成立していません。本記事で取り上げる「2025年改正案」は全て検討段階の素案であり、最終的な法案では変更される可能性があります。最新情報は個人情報保護委員会の公式サイトで必ずご確認ください。
はじめに:なぜ今プライバシーポリシーの見直しが必要なのか
個人情報保護委員会は2025年1月22日に「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の今後の検討の進め方について」を公表し、2025年の改正に向けた具体的な検討が進められています。さらに、2025年2月5日には「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について(個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方)」が公表され、改正の方向性や論点整理が示されています(いずれも検討段階の資料です)。
法務担当者として押さえておくべきは、「施行日に間に合わせる」ではなく「施行前に運用開始」を目標とすることです。改正内容の確定を待つのではなく、検討案ベースでの準備を今から始める必要があります(ただし、検討案は最終案ではないため、確定後の修正を見越した運用設計を行ってください)。
改正状況の全体像(2025年10月現在)
| 区分 | 状況 | 対応優先度 | 施行予定 | 適用条文 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 2024年改正 | 施行済み | 最高 | 2024年4月1日〜 | 個人情報保護法施行規則第7条第3号 |
| 🟡 2025年改正案 | 検討中(素案) | 高 | 未定(検討段階) | 個人情報保護法第18条、第26条、第27条等(想定) |
| 🔵 課徴金制度 | 導入是非を検討中 | 中 | 未定 | 新規条文(未定) |
【確定・対応必須】2024年改正のプライバシーポリシー対応
ウェブスキミング対策関連(個人情報保護法施行規則第7条第3号改正)
改正背景:
近年、ECサイト等に不正プログラムを設置し、ユーザー入力情報を事業者のサーバを介さずに直接窃取する「ウェブスキミング」被害が深刻化。従来は「個人データ」になる前の「個人情報」段階での窃取は報告対象外でしたが、被害実態を踏まえ個人情報保護法施行規則第7条第3号が改正され、一定の個人情報段階での漏えい等も報告・通知対象に含まれるようになりました。
改正内容:
2024年4月1日施行の個人情報保護法施行規則改正により、一定の漏えい等発生時に義務づけられている個人情報保護委員会への報告(個人情報保護法第26条)と本人への通知の対象が拡大されました。
- 対象範囲の拡大:「個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱われることが予定されているもの」を含め、不正目的での取得・利用のおそれがある事案については、個人情報保護委員会への報告及び必要に応じた本人への通知の対象となります(個人情報保護法施行規則第7条第3号)
- 想定される事案:ウェブスキミング等、「不正目的をもって行われたおそれがある行為」による漏えい等が典型例
- 実務上のポイント:個人データに「なる前」の段階でも、不正アクセス等により窃取された場合は報告対象となり得る点に注意
プライバシーポリシーへの必要な追記例
📋 今月中の必須チェック項目
漏洩対応の詳細については、法改正を社内へ効率的に伝えるテンプレを活用して、社内周知を徹底してください。
【検討案ベース】2025年改正案の想定変更点
以下の記載は個人情報保護委員会が公表した検討資料(2025年1月22日、同年2月5日等)に基づく**検討段階の素案**です。最終案・法案化時には趣旨や条文が変更される可能性があるため、本文中の「検討案」「想定」等の表現は「確定事項ではない」旨を前提に参照してください。最新の確定情報は個人情報保護委員会の公表資料をご確認ください。
1. 同意規制の柔軟化(検討案)
検討内容:
個人の権利利益への直接の影響の有無という観点を考慮し、以下の場合には本人同意を要しないデータ利活用ができると整理される可能性があります(あくまで検討案です):
- 統計作成等、特定の個人との対応関係が排斥された一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とした取扱い(AI開発等を含む)
- 取得の状況からみて本人の意思に反しない取扱い(例:店舗内の防犯カメラ映像を交通量調査に利用する場合等)
適用条文(検討中):個人情報保護法第18条第1項(目的外利用の制限)、第27条第1項(第三者提供の制限)
プライバシーポリシー記載例(検討案ベース)
2. 漏洩等発生時の本人通知義務の緩和(検討案)
検討内容:
本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合においては、本人通知を要しないものと整理できるかが検討されています(検討案の一部)。
適用条文(検討中):個人情報保護法第26条第2項(本人への通知)
- 漏えい等した個人データが、数字の羅列である会員番号のみの場合
- 暗号化された状態で漏えいし、復号が技術的に困難な場合
- 漏えい範囲が限定的で、二次被害のおそれが極めて低い場合
プライバシーポリシーへの想定影響
- 漏洩時の対応手順の詳細化(本人通知を行う場合・行わない場合の基準明示)
- 通知を行わない場合の代替的な対応措置の説明(ウェブサイトでの公表等)
- 個人情報保護委員会への報告は引き続き義務(緩和の対象外)
3. 委託先事業者に対する規律強化(検討案)
検討内容:
DXの進展に伴い、委託された個人データ等の取扱いの態様や、その適正性を確保する能力など、個人データ等の適正な取扱いに係る義務の在り方を検討。特にクラウドサービス利用時の責任分界点の明確化が議論されています。
適用条文(検討中):個人情報保護法第25条(委託先の監督)
プライバシーポリシーへの想定影響
- 委託先の監督体制に関する説明の充実(選定基準、定期的な監査実施等)
- クラウドサービス利用時の責任分界点の明確化(IaaS/PaaS/SaaSの区別)
- 委託先変更時の通知方法の見直し(重要な委託先変更時の事前通知等)
- 再委託時の管理体制の明示(再委託の承認プロセス、管理責任の所在)
4. 子供の個人情報等の取扱い(検討案・新規)
検討内容:
心身の発達過程にあり、本人による関与等の規律が必ずしも期待できない子供の個人情報等の取扱いについて、保護者の関与の在り方や事業者の配慮義務等が検討されています(検討段階の論点整理)。
- 一定年齢未満の子供の個人情報取得時における保護者の同意取得義務
- 子供向けサービスにおける平易な表現でのプライバシーポリシー提示義務
- 子供の個人情報の第三者提供に対する特別な配慮義務
【表で一発比較】2025年対応の差分表
共同利用・外国第三者提供・仮名加工情報の変更点
| 項目 | 現行法(2024年10月時点) | 2025年改正案(検討中) | 適用条文 |
|---|---|---|---|
| 共同利用 |
・共同利用する者の範囲 ・利用目的 ・個人データの項目 ・管理責任者の氏名 をあらかじめ本人に通知または容易に知り得る状態に置く必要あり |
【検討中】統計作成等の目的の場合、本人同意なしでの共同利用が可能になる方向(ただし、特定の個人との対応関係が排斥された場合に限定)。最終的な要件は確定していません。 | 第27条第5項第3号 |
| 外国第三者提供 |
・本人の同意取得時に、外国の名称、個人情報保護制度、第三者が講ずる措置の情報提供が必要 ・適切性認定国への提供は例外 ・提供記録の作成・保存義務(第30条) |
【現時点で変更なしの想定】 ※ただし、クラウドサービス利用時の責任分界点の明確化が議論されており、今後ガイドライン等で詳細化される可能性があります(検討段階)。 |
第28条、第30条 |
| 仮名加工情報 |
・他の情報と照合しない限り特定個人を識別できないように加工 ・利用目的の変更制限あり ・第三者提供の禁止 ・本人への連絡等の禁止 |
【検討中】AI開発等での利活用促進のため、一定の条件下での利用範囲拡大が議論されている(具体的内容は未公表、検討段階)。 | 第41条〜第43条 |
| 安全管理措置 |
【2024年4月改正済】 ・個人データに加え、個人データとして取り扱われることが予定されている個人情報も対象 ・ウェブスキミング等の不正行為対策が明記 |
【今後の方向性(検討中)】 ・クラウドサービス利用時の責任分界点の明確化 ・委託先の監督義務の強化(選定基準、定期監査の義務化等) |
施行規則第7条第3号 第23条、第25条 |
| 漏えい等発生時の対応 |
・個人情報保護委員会への報告義務 ・本人への通知義務(報告対象事態:不正アクセス、1000人超の漏えい等) |
【検討中】 ・本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合、本人通知を不要とする方向が議論されています(ただし、個人情報保護委員会への報告義務は継続する想定)。 |
第26条 施行規則第7条 |
クッキー同意と行動ターゲティング広告の実務Q&A
電気通信事業法改正(2023年6月施行)により、クッキー等の外部送信規律が導入されました。プライバシーポリシーにおけるクッキー関連の記載は、個人情報保護法だけでなく、電気通信事業法第27条の12(外部送信規律)も考慮する必要があります。
Q1. クッキーバナー(同意取得ポップアップ)の設置は必須ですか?
個人情報保護法上、クッキー単体では原則として「個人情報」に該当しませんが、以下の場合は対応が必要です:
- 行動ターゲティング広告を実施する場合:電気通信事業法第27条の12により、利用者への情報提供または通知・公表が必要
- クッキーと他の情報を照合して個人を識別する場合:個人情報保護法第18条第1項の利用目的の通知・公表が必要
- EU居住者向けサービスを提供する場合:GDPRに基づく事前同意取得が必要
Q2. プライバシーポリシーにクッキーについて何を記載すべきですか?
Q3. 行動ターゲティング広告を実施する場合の注意点は?
- 情報提供の方法(いずれかを選択):
- ①利用者への通知+個別同意取得(オプトイン方式・推奨)
- ②プライバシーポリシー等での公表+オプトアウト機会の提供
- 記載必須事項:
- 送信される情報の内容(クッキーID、閲覧履歴、デバイス情報等)
- 送信先の第三者の名称
- 利用目的(行動ターゲティング広告配信のため等)
- オプトアウト方法(配信停止の手順)
Q4. Google Analytics(GA4)を使用する場合の対応は?
- プライバシーポリシーへの記載:Google Analytics(GA4)を使用していること、送信される情報の内容(クッキーID、ページビュー、デバイス情報等)、およびGoogleのプライバシーポリシーへのリンクを明記してください。
- IPアドレス等の取扱いの明示:GA4におけるIPアドレス等の取り扱いはGoogleの処理ポリシーおよび事業者側の設定に依存します。したがって、当社ではGoogleの処理方針および自社の設定(データ保持期間、同意管理等)に基づき、必要な匿名化・制限措置を講じています、等の趣旨を明示してください。※「自動的に全面的に匿名化される」と断定する表現は避けること。
- Googleとのデータ処理契約(DPA):必要に応じて締結・設定を確認してください。特にEU居住者向けのサービスがある場合は、データ処理に関する追加的な対応が必要となる可能性があります。
- オプトアウト機会の提供:利用者向けのオプトアウト手段(ブラウザ設定・オプトアウトツールへのリンク等)の案内を掲載してください。
- 設定の確認:GA4の管理画面でデータ保持期間・収集対象・データ削除設定等が適切に設定されているかを確認してください。
※実装・DPAの要否などは事業者の提供対象地域や設定に依存するため、自社の状況に応じて適切に対応してください。
課徴金制度の検討状況
現状:
個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会で計7回の会合を経て、2024年12月末に議論の状況を整理した報告書を取りまとめた段階です。課徴金制度の導入の是非や算定方法などは継続して検討中であり、具体的な金額水準や運用ルールは示されていません(検討段階)。
個人情報保護法違反に関しては、個人情報保護委員会の命令等に違反した場合等に刑罰が科され得ます。2022年(令和4年)改正等により罰則が強化されているため、法人に対して重い制裁が及ぶ可能性がある旨を記載する必要があります。具体的な罰則例として、重大な命令違反等に対して法人に対し1億円以下の罰金が科され得る規定が設けられている点に留意してください(法条・改正年等は法文で最終確認を)。
※罰則の適用可否・金額等は違反の態様・程度に依存します。詳細は個人情報保護委員会の解説資料およびe-Govの法文で必ずご確認ください。
課徴金制度の検討ポイント
- 導入目的:違反行為の抑止と法令遵守の実効性確保
- 対象行為:個人情報の不正取得、目的外利用、無断第三者提供等(具体的範囲は検討中)
- 算定基準:違反行為により得た利益の額を基礎とする案が有力(具体的な倍率・上限額は未定)
- 減免制度:自主報告や是正措置の実施により減免する制度の導入が検討されている
プライバシーポリシーへの想定影響(導入された場合)
- 違反時のペナルティに関する説明の追加
- 法令遵守体制に関する記載の充実(コンプライアンス・プログラムの実施等)
- 内部通報制度の整備状況の明示
実務対応チェックリスト
🟢【最優先・今月中】2024年改正完全対応
🟡【年内目標】2025年改正案準備
🔵【継続対応】基本事項の確認
チェックリスト作成の効率化には、2025年の法改正ラッシュと対応スケジュールのまとめも併せてご活用ください。
段階的対応スケジュール
Phase 1(2025年10月〜12月):基盤固め
- 2024年改正の完全対応完了(最優先)
- 2025年改正案の詳細分析(個人情報保護委員会の公表資料を継続的にウォッチ)
- 現行プライバシーポリシーの全体見直し(法定記載事項の漏れ確認)
- クッキーポリシーの整備・更新(電気通信事業法対応)
Phase 2(2026年1月〜3月予定):法案成立後の迅速対応
※時期は過去の改正例に基づく推定であり、実際の法案成立時期により変動します。現時点では検討段階のため、確定情報ではありません。
- 確定した改正内容に基づく修正案作成
- パブリックコメント対応(該当する場合)
- 社内承認プロセスの実行(取締役会承認、関係部署との調整)
- 外部法律事務所によるレビュー(必要に応じて)
Phase 3(2026年4月〜施行前予定):運用体制構築
※施行時期は法案成立後に確定します(現時点は検討段階)。
- 新プライバシーポリシーの運用開始(ウェブサイト公開、社内周知)
- 全社研修の実施(法務部門、営業部門、システム部門等)
- 委託先への対応要請(契約書変更、安全管理措置の確認等)
- 継続的なモニタリング体制の構築(定期的な法令遵守状況の確認)
よくある質問(FAQ)
2025年10月現在、個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに係る改正は検討段階にあり、法案成立時期は未定です。個人情報保護委員会が2025年2月に「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」を公表し、具体的な改正内容案が示されました。
【時期の推定(不確実性あり)】
過去の改正例(改正大綱公表→法案化→公布→施行のプロセス)を参考に運用スケジュールの検討は可能ですが、現時点では法案成立・施行は未確定です。従って、社内での準備は「検討案ベースでの準備」を行いつつ、確定情報が出た段階で速やかに最終調整する運用設計を推奨します。
2024年4月1日施行の個人情報保護法施行規則第7条第3号改正により、ウェブスキミング対策として、個人データになる前の個人情報段階での漏えい等も報告対象に拡大されました。
プライバシーポリシーには「安全管理措置」の項目に、ウェブサイトへの不正プログラム設置防止対策、入力フォームにおけるセキュリティ対策の実施(SSL/TLS暗号化、WAF導入等)、定期的なシステム脆弱性点検などを明記する必要があります。また、社内の漏洩対応マニュアルと委託先契約書の見直しも必須です。
クッキーの利用については、以下の項目を明記する必要があります:
- ①使用するクッキーの種類(必須クッキー、機能性クッキー、分析用クッキー、広告用クッキー等)
- ②各クッキーの利用目的
- ③第三者への提供の有無(Google Analytics、広告配信事業者等)
- ④ユーザーによるクッキー設定の変更方法(ブラウザ設定の案内)
- ⑤行動ターゲティング広告を実施する場合のオプトアウト方法
特に電気通信事業法改正(2023年6月施行)により、電気通信事業法第27条の12の外部送信規律が導入されたため、利用者の同意取得や情報提供の義務化に留意してください。
2025年改正案では、統計作成等の特定の個人との対応関係が排斥された一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とした取扱いを実施する場合、本人同意を要しない個人データの第三者提供が可能となる方向で検討されています。ただし、これは検討段階の内容であり、確定事項ではありません。
共同利用の場合は、現行法(個人情報保護法第27条第5項第3号)に基づき、共同利用する者の範囲、利用目的、個人データの項目、管理責任者の氏名等をあらかじめ本人に通知または本人が容易に知り得る状態に置く必要があります。
個人情報保護法第28条に基づき、外国にある第三者への個人データ提供については、以下の情報提供が必要です:
- ①本人の同意を取得する際に、当該外国の名称
- ②当該外国における個人情報保護制度
- ③当該第三者が講ずる個人情報保護措置に関する情報
また、適切性認定を受けた国・地域(EEA諸国、英国等)への提供の場合はその旨を記載します。さらに、個人情報保護法第30条に基づき、外国にある第三者への提供記録の作成・保存義務があることも明記すべきです。クラウドサービス利用時は、サーバー所在国と責任分界点も明確化してください。
まとめ:「守り」から「攻め」のプライバシー戦略へ
個人情報保護法の改正対応は、単なる法令遵守を超えて企業価値向上の機会として捉えることが重要です。検討段階の論点を踏まえつつ、事前に運用設計を行うことで、施行時の負荷を低減できます。
- 🔒 信頼性向上:最新法令準拠による顧客・取引先からの信頼獲得
- ⚡ 業務効率化:データ利活用フローの最適化による新サービス創出可能性
- 🌐 グローバル対応力:国際基準準拠による海外展開時の競争優位性
- 🛡️ リスク軽減:課徴金制度導入前の予防的対応による将来的なペナルティ回避
- 一括更新による効率化:改正対応を機に関連規程類(社内規程、委託先契約書、同意取得フォーム等)を一括見直し
- AI活用による工数削減:ただし最終判断は必ず人間が実施(法的責任の所在を明確化)
- 継続改善体制の構築:3年ごとの見直しサイクルに対応できる仕組み作り(定期的な法令情報収集、社内教育の実施)
📌 プライバシーポリシー改定の実務を効率化しませんか?
本記事で解説したプライバシーポリシー作成、安全管理措置の記載、クッキーポリシー、同意取得フォーム—— これらをAIで効率化する『個人情報保護法 AIプロンプト集(全42本)』を提供しています。
第1章・第2章でプライバシーポリシーと同意取得を完全カバー。2024年改正・2025年改正準備にも対応。
⚠️ 重要な免責事項
本記事は2025年10月21日時点の公表資料・検討状況を基に作成しています。
- 2025年改正に関する記載は全て検討案であり、確定事項ではありません
- 改正内容は国会審議や政省令策定過程で変更される場合があります
- 実務対応におきましては、必ず最新の法令、ガイドライン、Q&A等を直接ご参照いただき、必要に応じて専門家にご相談ください
📚 主要参考資料
- 個人情報保護委員会公式サイト
- 個人情報保護委員会「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しについて」
- 個人情報保護委員会「漏えい等報告・本人への通知の義務化について」
- 個人情報保護法施行規則(e-Gov法令検索)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)
- 個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について(個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方)
- 個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会報告書
- 個人情報保護委員会「現行制度と検討の方向性について(課徴金制度)」
- 総務省「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」
- Google Analytics ヘルプ「EU-focused data and privacy」
最新情報は個人情報保護委員会の公式サイトで必ずご確認ください。
プライバシーポリシーの作成プロンプト
個人情報保護法2025年改正対応。業種別カスタマイズ可能な12項目完全テンプレートで、法的要件を満たしたプライバシーポリシーを2〜4時間で作成できます。
個人情報保護法完全対応テンプレート
2025年改正動向を反映した実務即応型のプライバシーポリシー作成支援ツール。仮名加工情報、個人関連情報、漏えい報告義務など最新要件に対応し、業種別ガイドライン(金融・医療・通信・小売EC)も網羅しています。
📦 このプロンプトに収録されている内容
- 12項目完全構成テンプレート – 基本方針から改定まで、個人情報保護法が求める必須記載事項を網羅
- 業種別カスタマイズガイド – 金融・医療・通信・小売ECの4業種に対応した特記事項と注意点
- 2025年改正対応 – 仮名加工情報、個人関連情報、漏えい等報告義務への対応方法を詳細解説
- Cookie・外国移転対応 – 同意取得フロー、外国データ移転時の開示項目チェックリスト付き
- 開示請求手続き実装例 – 開示等の請求に対する具体的な対応手順と手数料設定例
- Q&A・チェックリスト – よくある質問3項目と実務確認用チェックリスト完備
💡 使い方のヒント:PDFをダウンロードしたら、プロンプトをそのままAIにコピペ。会社情報と取得する個人情報の種類を入力するだけで、法的要件を満たしたプライバシーポリシーの雛形が即座に生成されます。金融・医療など特定分野は業種別カスタマイズポイントを参照してください。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

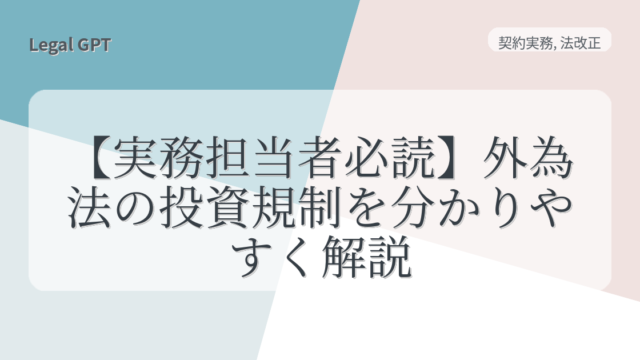
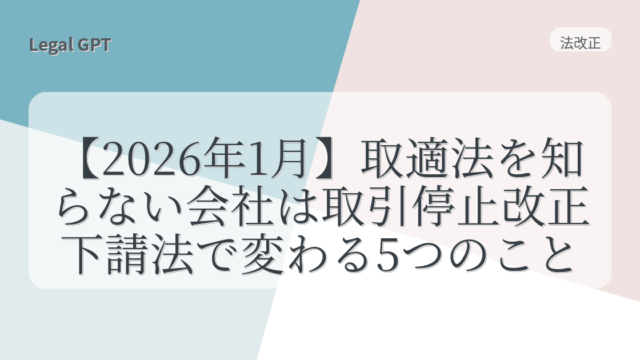
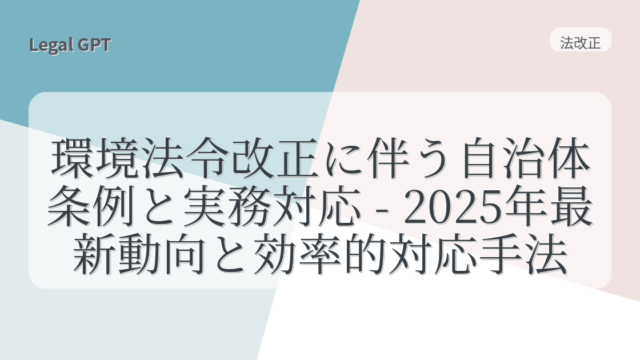
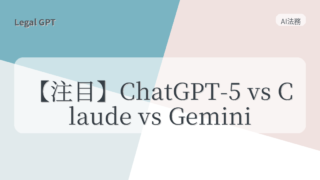
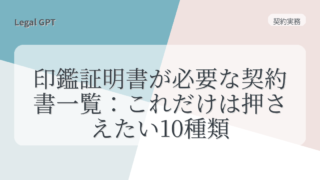



[…] 個人情報保護法改正でプライバシーポリシーの何を変える?2025年個人情報保護法改正案を踏まえ、プライバシーポリシーの見直しポイントを解説。2024年改正対応チェックリストや実務 […]
[…] 個人情報や試験データの管理に関する注意点は 個人情報保護法改正に関するガイド […]
[…] […]
[…] 個人情報保護法改正に伴うプライバシーポリシー見直しの実務ポイント(… […]
[…] 個人情報保護法改正に備えたプライバシーポリシーの実務的改定ポイント […]
[…] 個人情報保護法改正でプライバシーポリシーの何を変える? […]
whoah this blog is great i love reading your posts. Keep up the good work! You know, lots of people are hunting around for this info, you can help them greatly.
Thanks so much — I’m glad the posts are useful! I try to make the content as practical as possible for everyone searching for this info.
Thanks — I really appreciate it! Glad you find the posts useful.
[…] 個人情報保護法や通知対応の実務については、改正ポイントを整理した解説を参照してください:個人情報保護法改正と実務対応ガイド。 […]