【2025年版】NDAチェックリスト:目的限定・残存義務・不開示情報を実例で解説
レビュー方針→論点抽出→修正文案→交渉論点まで、“漏れない型”で揃える
契約レビューは、経験者でも「抜け」が起きやすい作業です。STEP化して再現可能にすると、品質が安定します。
- 前提整理(当事者/取引/優先順位)
- 地雷条項の抽出(損害賠償・解除・保証・責任制限など)
- 修正文案・代替案・交渉論点(説明つき)
- レビュー結果の報告書・メール文面まで
※機密情報の入力範囲・マスキングは社内ルールに従ってください。一般的情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。
【2025年最新】NDAチェックリスト完全版|表で一発比較
秘密情報の定義・残存義務・裁判管轄を条文直リンク付きで実例解説
個人情報保護委員会の検討会報告書(2024年12月25日公表)における検討方向(課徴金制度、委託先監督強化等)、不正競争防止法の最新運用実務(営業秘密管理指針2025年3月改訂版)を反映
結論要約(本記事のポイント)
NDA(秘密保持契約)の有効性は、不正競争防止法第2条第6項の営業秘密要件(秘密管理性・有用性・非公知性)と整合した定義、契約終了後3〜5年の残存義務条項(営業秘密に該当する限り公知となるまで保護継続)、個人情報保護法第26条の漏えい報告義務への対応が鍵となります。個人情報保護委員会の検討会報告書(2024年12月25日)では委託先監督義務の強化が検討されており、NDAでも委託先の安全管理措置の明確化が必須です。本記事では、最新法令・ガイドライン(経済産業省「AI事業者ガイドライン第1.1版」、「営業秘密管理指針2025年3月改訂版」等)に基づく10の必須チェックポイントを条文直リンク・英日対訳条項・実例付きで解説します。
序章:2025年のNDA環境変化と対応の必要性
2025年現在、企業を取り巻く秘密情報管理の環境は急速に変化しています。個人情報保護委員会が公表した「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会報告書」(2024年12月25日)では、課徴金制度の導入、委託先監督義務の強化、漏えい時の本人通知義務の見直しが検討されています(※2025年10月時点では法案化・成立は未確定)。また、生成AIへの秘密情報入力は学習データ化や再現性の観点でリスクが存在するため、従来のテンプレート型NDAでは対応できない新たな課題が生まれています。
• 個人情報保護委員会「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しについて」
• 検討会報告書(2024年12月25日)[PDF]
• 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)
• 不正競争防止法(e-Gov法令検索)
• 経済産業省「営業秘密管理指針」(2025年3月改訂版)[PDF]
• 経済産業省「AI事業者ガイドライン第1.1版」[PDF]
本記事では、これらの最新法改正検討動向と実務上の課題を踏まえ、2025年に企業法務が押さえるべきNDAの10の必須チェックポイントを、条文引用・英日対訳条項・実務事例とともに詳細に解説します。
関連記事:生成AIとNDAの具体的な改訂ポイントについては、生成AI時代のNDA改訂チェック(AI新法と実務対応)で詳しく解説しています。
【表で一発比較】NDA10項目の選択肢と適用場面
| 項目 | 選択肢A | 選択肢B | 推奨適用場面 |
|---|---|---|---|
| 1. 秘密情報の定義 | 包括型 (「本契約に関連して開示された情報」) |
特定型 (「顧客リスト、技術仕様書」等を列挙) |
包括型:初期協議、業務提携 特定型:M&A、限定的取引 |
| 2. 除外事由 | 4項目標準型 (公知、独自開発、適法取得、法令開示) |
5項目強化型 (標準4項目+既保有情報) |
標準型:一般取引 強化型:技術情報の開示 |
| 3. 開示範囲 | 役職員限定 (「自社の役職員に限る」) |
関係者含む (「役職員、アドバイザー、関連会社」) |
役職員限定:機密性高い情報 関係者含む:M&A、監査対応 |
| 4. 利用目的 | 限定型 (「●●プロジェクトの検討に限る」) |
包括型 (「取引関係の検討」) |
限定型:単発プロジェクト 包括型:継続的取引関係 |
| 5. 残存義務期間 | 3年 | 5年(営業秘密は公知まで) | 3年:一般営業情報 5年:技術情報、ノウハウ |
| 6. 返還・廃棄 | 原本のみ (「有形媒体の返還」) |
全データ (「複製物、電磁的記録含む」) |
原本のみ:物理媒体中心 全データ:デジタル取引 |
| 7. 損害賠償 | 実損害型 (「現実に生じた損害」) |
違約金型 (「金●万円」) |
実損害型:立証可能な場合 違約金型:予防的抑止 |
| 8. 個人情報対応 | 簡易型 (「個人情報保護法を遵守」) |
詳細型 (委託先監督、漏えい報告フロー明記) |
簡易型:個人データ含まない 詳細型:個人データ含む |
| 9. 準拠法・管轄 | 日本法・日本裁判所 | 相手国法・相手国裁判所 | 日本法:日本企業が開示者 相手国法:国際交渉結果 |
| 10. 反社条項 | 標準8号型 (暴力団等8類型) |
拡張型 (8類型+実質支配要件) |
標準型:一般取引 拡張型:上場企業、金融機関 |
💡 表の活用法
この比較表を参照することで、案件の性質(機密性の高さ、取引期間、国際性等)に応じて、各条項の適切な選択肢を素早く判断できます。詳細は各セクションで解説します。
1. 秘密情報の定義|不正競争防止法との整合性
不正競争防止法上の営業秘密要件
不正競争防止法第2条第6項では、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義しています。この定義には、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3要件が含まれており、NDAの秘密情報定義もこれらと整合させることが重要です。
• 不正競争防止法第2条第6項「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」
• 参考:経済産業省「営業秘密管理指針」(2025年3月改訂版)[PDF]
包括型vs特定型の戦略的選択
【悪例】曖昧な定義
❌ 問題点:「開示する情報」が何を指すのか不明確で、秘密管理性の立証が困難。
【修正例】包括型(初期協議・業務提携向け)
【修正例】特定型(M&A・限定的取引向け)
📖 英日対訳条項例
[EN] “Confidential Information” means all information disclosed by the Disclosing Party to the Receiving Party in connection with this Agreement, whether in written, oral, electronic or any other form, that is marked as “Confidential” or that should reasonably be understood to be confidential given the nature of the information and the circumstances of disclosure.
[JA] 「秘密情報」とは、開示者が受領者に対し、本契約に関連して開示する一切の情報(書面、口頭、電磁的記録その他の形式を問わない)であって、「秘密」と表示されたもの、または情報の性質および開示の状況から秘密であることが合理的に理解されるべきものをいう。
◆交渉時の着眼点
- 開示範囲が不明確な初期段階では包括型を採用し、後に情報範囲が特定できた段階で特定型に移行する段階的アプローチも有効
- 「秘密」表示の方法(マーキング、メール件名への記載等)を具体的に定める
- 口頭開示の場合の書面化期限(通常14日以内)を明記
4. 利用目的の明確化|目的外利用の悪例と修正例
利用目的の曖昧性がもたらすリスク
個人情報保護法第18条第1項では、「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない」と規定されています。NDAにおいても、秘密情報の利用目的を曖昧にすると、目的外利用のリスクが高まり、紛争時の立証が困難になります。
【悪例】曖昧な利用目的
❌ 問題点:「本契約の目的」が何を指すのか不明確で、目的外利用の判断基準がない。
【修正例】限定型(単発プロジェクト向け)
⚠️ 生成AI利用制限の実務的重要性
生成AIへの秘密情報入力は学習データ化や再現性の観点でリスクが存在するため、NDAで明示的に制限することが実務的に推奨されます。経済産業省「AI事業者ガイドライン第1.1版」でも、学習データとしての個人情報・機密情報の適切な管理が求められており、NDAにおいても明示的な制限条項の追加が必須となっています。例外として許容する場合は、プライベートモデル利用、ログ取得等の要件を明文化することが重要です。
関連記事:生成AIとNDAの詳細な改訂ポイントについては、生成AI時代のNDA改訂チェック(AI新法と実務対応)で具体的な条項例とともに解説しています。
5. 契約期間と残存義務|終了後の義務継続期間の設計
残存義務条項の法的根拠
NDAの契約期間終了後も、一定期間秘密保持義務を残存させることは、不正競争防止法上の営業秘密保護と整合的です。不正競争防止法では、営業秘密の不正取得・使用・開示行為に対する差止請求権の消滅時効は、「その行為が継続する場合において、当該行為があった事実と行為者を知った時から3年」とされています(不正競争防止法第15条第1項)。ただし、NDA上での残存期間3〜5年は実務的推奨であり、営業秘密に該当する限りは当該情報が公知となるまで保護が継続されることに留意が必要です。
• 不正競争防止法第15条第1項「差止請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 差止めの対象となる行為が継続する場合において、当該行為があったこと及び当該行為をした者を知った時から三年間行使しないとき。」
• 参考:経済産業省「営業秘密管理指針」(2025年3月改訂版)
残存期間の設定基準
| 情報の種類 | 推奨残存期間 | 理由 |
|---|---|---|
| 一般営業情報 | 3年 | 不正競争防止法の差止請求権消滅時効と整合 |
| 技術情報・ノウハウ | 5年 | 技術的優位性の維持期間を考慮 |
| 営業秘密該当情報 | 公知となるまで無期限 | 不正競争防止法上の営業秘密は公知でない限り保護継続 |
| 個人データ | 利用目的達成まで | 個人情報保護法第22条(利用目的達成後の速やかな消去) |
【条項例】残存義務条項
📖 英日対訳条項例(残存義務)
[EN] Survival of Obligations. Notwithstanding the termination or expiration of this Agreement, the obligations set forth in Articles ● (Confidentiality Obligations), ● (Return and Destruction), and ● (Damages) shall survive for a period of five (5) years from the date of termination or expiration. Provided, however, that confidentiality obligations with respect to information constituting trade secrets under the Unfair Competition Prevention Act shall survive until such information becomes publicly known.
[JA] 義務の存続。本契約の終了または満了にかかわらず、第●条(秘密保持義務)、第●条(返還および廃棄)、第●条(損害賠償)に定める義務は、終了または満了の日から5年間存続するものとする。ただし、不正競争防止法上の営業秘密に該当する情報に関する秘密保持義務は、当該情報が公知となるまで存続するものとする。
◆交渉時の着眼点
- 開示する情報の性質(技術情報、営業情報、個人データ等)に応じて残存期間を区別する
- 個人情報保護法第22条(データ内容の正確性の確保等)との整合性を確認し、個人データについては「利用目的達成後速やかに消去」とする例外規定を設ける
- 不正競争防止法上の営業秘密に該当する情報は、公知となるまで無期限で保護する旨を明記(3〜5年の期限は営業秘密以外の情報に適用)
8. 個人情報保護法対応|検討会報告書の検討動向
個人情報保護委員会の検討会報告書(2024年12月25日)
個人情報保護委員会は、2024年12月25日に「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会報告書」を公表しました。本報告書では、以下の改正事項が検討されています(※2025年10月時点では法案化・成立は未確定)。
| 検討事項 | 現行法の課題 | 検討の方向性 |
|---|---|---|
| 課徴金制度の導入 | 命令違反時の罰金は最大1億円(法人)だが、抑止力不足との指摘 | EU GDPRのように売上高の一定割合を課徴金として賦課する制度の導入を検討中 |
| 委託先監督義務の強化 | クラウドサービス等で実質的に第三者に依存するケースが拡大し、適正性確保が課題 | 委託された個人データの取扱態様に応じた監督義務の明確化を検討中 |
| 漏えい等発生時の本人通知義務の緩和 | 会員番号のみの漏えいでも1000人超なら本人通知が必須 | 本人の権利利益保護に欠けるおそれが少ない場合の通知義務免除を検討中 |
| 個人の権利利益を考慮した同意規制の見直し | 統計作成等で個人との対応関係が排斥される場合も同意が必要 | 本人の権利利益への直接影響がない場合の同意不要化を検討中 |
• 個人情報保護委員会「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しについて」
• 検討会報告書(2024年12月25日)[PDF]
• 個人情報保護法第26条「個人データの漏えい等の報告等」
• 個人情報保護法第28条「外国にある第三者への提供の制限」
現行法(2022年改正)の主要義務
1. 個人データの越境移転時の本人同意取得等(第28条)
外国にある第三者に個人データを提供する場合、原則として本人の同意が必要です。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、本人の同意なく提供可能です。
- 十分性認定を受けた国・地域への提供(EU、英国等。日本は2019年にEUから十分性認定を受けている)
- 個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している事業者への提供(標準契約条項、BCR等)
2. 漏えい等発生時の個人情報保護委員会への報告・本人通知義務(第26条)
以下の「報告対象事態」に該当する場合、個人情報保護委員会への報告および本人への通知が義務付けられています。
- 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等
- 財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等
- 不正アクセス等により個人データが漏えい等した場合
- 1,000人を超える個人データの漏えい等
NDAにおける個人情報保護条項の実装
【条項例】個人情報保護対応(詳細型)
⚠️ 検討会報告書への備え
個人情報保護委員会の検討会報告書(2024年12月25日)で委託先監督義務の強化が検討されているため、NDAにおいても以下を明記することが推奨されます(法案化・成立後は速やかにNDAテンプレートを更新)。
- 委託先(受領者)の安全管理措置の具体的内容(暗号化、アクセス制御、従業者教育等)
- 定期的な監査権(年1回の書面報告、必要に応じた実地監査)
- 再委託の禁止または事前承諾制
関連記事:個人情報保護法対応の詳細については、生成AI時代の契約書管理と運用のポイントでデータ管理フローとともに解説しています。
9. 準拠法・裁判管轄|国際取引での条項設計
準拠法・管轄条項の法的意義
国際取引におけるNDAでは、紛争発生時にどの国の法律を適用し、どの国の裁判所で解決するかを明確にすることが重要です。日本法では、民事訴訟法第11条により、当事者間で管轄裁判所を合意することができます(合意管轄)。また、「法の適用に関する通則法」第7条により、契約の準拠法を当事者間で選択することが可能です。
• 民事訴訟法第11条「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」
• 法の適用に関する通則法第7条「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」
• 参考:民事訴訟法(e-Gov法令検索)
国際取引での留意点
| 取引パターン | 推奨準拠法 | 推奨管轄 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 日本企業が開示者 | 日本法 | 日本の裁判所(東京地裁等) | 日本法での営業秘密保護を確保 |
| 日本企業が受領者(米国企業から開示) | 交渉次第 (日本法または米国州法) |
交渉次第 (日本または米国裁判所) |
米国各州法の営業秘密保護水準を確認 |
| EU企業との取引(GDPR適用) | 日本法またはEU加盟国法 | 日本またはEU裁判所 | GDPRの越境移転要件(第44条〜)を満たす必要。日本は十分性認定を受けているが、特別な種類の個人データ等は追加措置必要 |
| 中国企業との取引 | 日本法または中国法 | 日本、中国裁判所または仲裁 | 中国個人情報保護法・データ安全法の域外適用に注意 |
【条項例】準拠法・管轄(日本法・日本裁判所)
📖 英日対訳条項例(準拠法・管轄)
[EN] Governing Law and Jurisdiction. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan, without regard to its conflict of laws principles. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court as the court of first instance.
[JA] 準拠法および管轄。本契約は、抵触法の原則を除き、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。本契約に起因しまたは関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
GDPR・中国個人情報保護法への対応
1. GDPR(EU一般データ保護規則)対応
EU域内の個人データを日本に移転する場合、GDPR第44条以降の越境移転要件を満たす必要があります。日本は2019年1月にEUから十分性認定を受けているため、原則として追加の手続きなく個人データを移転できます。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 要配慮個人情報に該当しないEU域内の「特別な種類の個人データ」(人種、宗教等)は、本人同意等の追加措置が必要な場合がある
- 公的当局へのアクセス要件等、特定ケースでは追加の保護措置が求められる場合がある
- GDPRの域外適用条項(第3条)により、日本企業がEU域内の個人に商品・サービスを提供する場合、GDPR全体が適用される
2. 中国個人情報保護法・データ安全法対応
中国個人情報保護法(2021年11月施行)では、以下の場合に域外適用されます。
- 中国国内の個人に商品・サービスを提供する目的で個人情報を処理する場合
- 中国国内の個人の行動を分析・評価する場合
また、重要データの国外移転には、中国当局の安全評価が必要とされる場合があります。中国企業との取引では、中国国内でのデータ管理体制の構築や、現地法人の設置を検討する必要があります。
◆交渉時の着眼点
- 日本企業が開示者の場合、可能な限り日本法・日本裁判所を確保する
- 仲裁条項(ICC、JCAA等)を設けることで、国際的な執行可能性を高める選択肢も検討
- GDPR・中国個人情報保護法等の域外適用法令がある場合、当該法令の遵守義務を明記する
- 紛争解決前の協議条項(60日間の誠実協議等)を設けることで、訴訟コストを削減
よくある質問(FAQ)
不正競争防止法第2条第6項の営業秘密要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たすよう、開示目的に応じて包括型または特定型を選択します。包括型は「本契約に関連して開示された情報」と広く定義し除外事由で絞り込む方式、特定型は「顧客リスト、技術仕様書」など具体的に列挙する方式です。開示範囲が不明確な初期段階では包括型、M&Aなど開示対象が明確な場合は特定型が適しています。
はい、残存義務条項により契約終了後も一定期間(通常3〜5年)秘密保持義務が継続します。不正競争防止法上の営業秘密に該当する情報は、契約終了後も法的保護が継続し、当該情報が公知となるまで保護されます。ただし個人情報保護法上の個人データは、利用目的達成後は速やかに消去義務があるため、返還・廃棄条項との整合性に注意が必要です。
個人情報保護委員会の検討会報告書(2024年12月25日)では、委託先監督義務の強化や課徴金制度の導入が検討されています(法案化・成立は未確定)。現行法(2022年改正)では、個人データの越境移転時の本人同意取得(ただし十分性認定国等の例外あり)、漏えい等発生時の個人情報保護委員会への報告義務が規定されています(個人情報保護法第28条、第26条)。NDAでは、個人データの取扱目的・方法の明確化、委託先の安全管理措置の確認、漏えい時の報告フローを具体的に定めることが必須です。
日本企業が開示者の場合、日本法を準拠法とし日本の裁判所を専属的合意管轄裁判所とするのが一般的です(民事訴訟法第11条)。ただしGDPR適用国の受領者に個人データを移転する場合、GDPR第44条以降の越境移転要件(十分性認定、標準契約条項等)を満たす必要があります。日本は2019年にEUから十分性認定を受けていますが、特別な種類の個人データ等については追加措置が必要な場合があります。中国企業との取引では、中国個人情報保護法・データ安全法の域外適用条項に注意し、必要に応じて中国国内でのデータ管理体制の構築が求められます。
はい、生成AIへの秘密情報入力は学習データ化や再現性の観点でリスクが存在するため、NDAで明示的に制限することが実務的に推奨されます。条項例:「受領者は、秘密情報を生成AI(Large Language Model含む)の学習用データとして入力、アップロード、または提供してはならない。ただし、事前に開示者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない」。例外として、プライベートモデル利用やログ取得等の要件を満たす場合の利用を許容する場合は、その旨を明文化することが重要です。
結論:2025年のNDA戦略
2025年の企業法務環境において、NDAは単なる「定型契約」から「戦略的リスク管理ツール」へと進化しています。個人情報保護委員会の検討会報告書(2024年12月25日)における検討事項(課徴金制度、委託先監督強化)、生成AIへの秘密情報入力に係るリスク、国際データ規制の強化など、多面的な環境変化に対応するため、従来のテンプレート運用を脱却し、案件ごとの最適化が不可欠です。
本記事の重要ポイント
- 法令との整合性:不正競争防止法第2条第6項の営業秘密要件と整合した秘密情報定義、個人情報保護法第26条の漏えい報告義務への対応
- 残存義務の適切な設計:契約終了後3〜5年の秘密保持義務継続、営業秘密は公知となるまで保護、個人データは利用目的達成後速やかに消去
- 生成AI対応:秘密情報の生成AI入力を明示的に禁止し、例外を許容する場合はプライベートモデル・ログ取得等の要件を明文化
- 国際取引への対応:GDPR・中国個人情報保護法の域外適用条項を踏まえた準拠法・管轄設計、十分性認定の活用
- 継続的アップデート:個人情報保護法の検討動向を注視し、法案化・成立時には速やかにNDAテンプレートを更新
本記事で示したチェックポイントを活用し、最新法令・ガイドライン(経済産業省「営業秘密管理指針2025年3月改訂版」、「AI事業者ガイドライン第1.1版」等)に準拠した実効性の高いNDAを設計することで、企業は情報セキュリティリスクを最小化しつつ、事業機会の最大化を実現できます。
機密保持条項の強化案
プロンプトテンプレート【無料PDF】
既存のNDAや契約書の機密保持条項を30〜90分で徹底強化。技術情報漏洩リスク、M&A、デューデリジェンスなど、厳格な秘密保持が求められる場面で即活用できる、3段階レベル別の強化案をAIが自動生成します。
機密保持条項の強化案
秘密情報の定義の曖昧さ、技術的保護措置の欠如、違反時ペナルティの不十分さなど、現行条項の弱点を8つの観点から分析。業界標準〜高リスク取引向けまで、3段階の強化レベルで実務に即した改善案を提示します。
📝 このPDFの収録内容
- 秘密情報の定義の明確化手法 – 書面・口頭・視覚による開示の扱い、公知情報の例外規定など
- Need to Know原則の導入方法 – 知る必要のある者のみに限定する具体的条項例
- 技術的保護措置の義務付け条項 – アクセス制限・暗号化・従業員教育の規定テンプレート
- 違反時のペナルティ設定 – 損害賠償・差止請求・違約金の実務的な規定方法
- 監査権・資料返還義務の規定例 – 受領者の秘密保持状況確認、電子データを含む廃棄義務
- 3段階の強化レベル別提案 – 業界標準・推奨レベル・高リスク取引向けの段階的強化案
💡 使い方のヒント: PDFのプロンプトをコピーしてAIに貼り付けるだけ。既存の機密保持条項を入力すれば、レベル1(業界標準)〜レベル3(高リスク取引向け)まで、3段階の強化案が自動生成されます。M&A、技術情報開示、共同開発など、取引の性質に応じて最適なレベルを選択できます。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

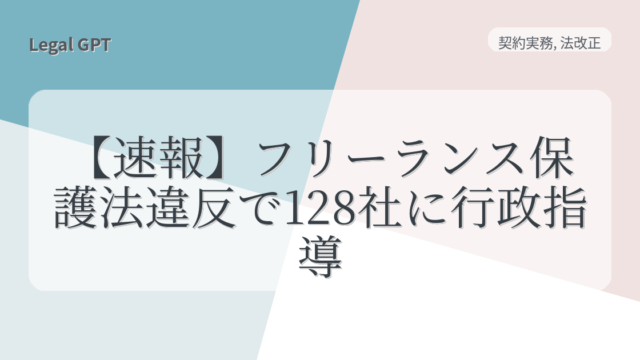
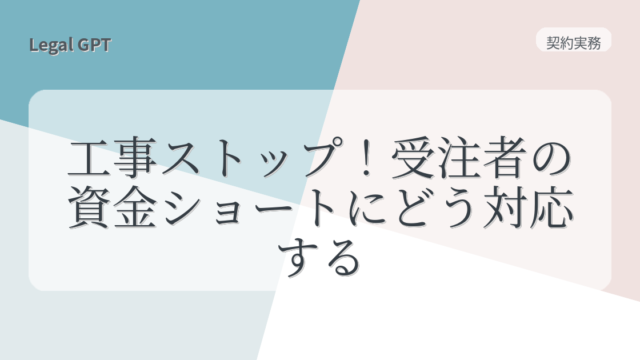
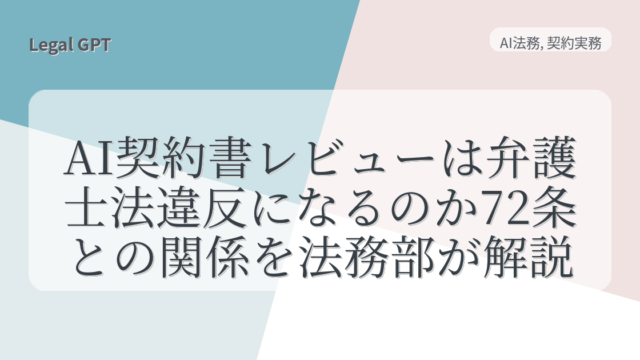
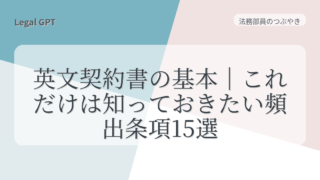
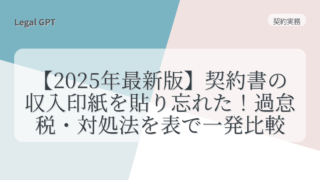



[…] NDA に盛り込むべき反社会的勢力排除条項の実務ポイント(条項テンプレあり) […]
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. But imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this website could certainly be one of the most beneficial in its field. Great blog!
Thanks so much — that’s a great suggestion! I completely agree that visuals can make posts more engaging. I’ll definitely look into adding more images and short clips in future updates.
[…] NDA(秘密保持)チェックポイント(データ・AI対応) […]
[…] NDA(秘密保持契約)の実務チェック(2025年版) — 試験データ、研究委託の証跡保全や権利関係整理の参考に。 […]
Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!
Thanks — totally agree! Maybe if more people created original content, the web would be even more interesting.
Thanks — glad you liked them! I agree, it’s always better when people create their own content.
[…] → NDA(秘密保持契約)のチェックポイント10選【2025年版】 […]
[…] NDAのチェックポイント10選(2025年版) […]
[…] NDA(秘密保持契約)のチェックポイント10選【2025年版】 — NDAの必須項目、目的限定・残存義務・除外事由・AI対応までを網羅したチェックリスト。 […]
[…] NDA(秘密保持契約)のチェックポイント10選【2025年版】 ー 業務委託と併せて締結するNDAの実務ポイント […]
[…] NDA・秘密保持契約のチェックポイント10選|2025年版 […]
[…] NDA(秘密保持契約)のチェックポイント10選【2025年版】 […]