会社法実務ガイド:取締役会・総会の落とし穴と議事録テンプレ集
会社法実務ガイド:取締役会・総会の落とし穴と議事録テンプレ集
【2025年9月版】法務実務家が陥りがちな7つの落とし穴と最新法令対応の完全解説
企業法務の現場で10年以上の経験を積んでも、取締役会と株主総会の運営で「こんなはずでは」という場面に遭遇することは少なくありません。特に最近では、オンライン会議の普及、電子署名の解釈変更、さらには2025年に向けた会社法改正の議論など、従来の実務慣行だけでは対応しきれない状況が続いています。
本記事では、法務実務家が実際に直面する「落とし穴」を7つに整理し、それぞれについて最新の法令解釈と実務対応策を提示します。また、すぐに活用できる議事録テンプレート集も併せて提供いたします。
第1部:取締役会運営の7つの落とし穴
落とし穴1:電子署名の「立会人型」解釈を誤解している
よくある誤解
2020年5月の法務省見解により、クラウド型電子署名サービス(立会人型)が取締役会議事録に使用可能になったことは広く知られています。しかし、「どの電子署名サービスでも使える」と誤解している実務家が散見されます。
正しい理解
会社法施行規則第225条は、電磁的記録に代わる「電子署名」について、(1)当該情報が当該措置を行った者の作成に係ることを示すこと、(2)当該情報について改変が行われていないか確認できること——を求めています(出典:e-Gov法令検索)。したがってクラウド型の立会人型サービスも、当該要件を満たす場合には取締役会議事録の署名代替手段として利用可能です。ただし、議事録を登記申請手続(代表取締役選定の登記等)に用いる場合やオンラインで登記申請を行う場合には、商業登記規則で定める法務大臣指定の電子証明書等の要件を満たす必要がある点に注意してください。
実務対応策
- 通常の取締役会:要件を満たすクラウド型電子署名サービスで対応可能
- 登記申請用議事録:商業登記規則で定める法務大臣指定の電子証明書等が必要となる場合
- 事前に管轄法務局に確認し、「議事録事務担当者 総務部 山田太郎」などと記名しておき、PDF署名パネル上の表示との対応を明示的に行っておく等の工夫を検討
落とし穴2:「みなし決議」の議事録作成を軽視している
よくある誤解
提案された議案につき株主全員の同意を得た場合には、可決の決議があったとみなして株主総会の開催を省略することも可能です(みなし決議。会社法319条1項)。しかし、「書面決議だから議事録は簡単でいい」と考えている実務家がいます。
正しい理解
みなし決議・みなし報告の場合にも議事録の作成が必要ですが、議事録の記載事項が通常と少し異なります。また、議事録に加え、株主の同意書またはその電磁的記録も、本店に10年間備え置かなければなりません。
実務対応策
- みなし決議でも正式な議事録作成は必須
- 同意書の保管期間も10年間であることを社内で周知徹底
- 同意書の形式(書面・電子メール等)を統一し、証拠保全の観点から電子署名付きを推奨
落とし穴3:オンライン取締役会の「同時性」要件を軽視している
よくある誤解
「Zoom等で開催すれば問題ない」と考えている実務家が多いですが、法的要件の理解が不十分なケースがあります。
正しい理解
オンラインでの出席者であっても、その場ですぐに意見を交換できる環境を確保しなければなりません。つまり、出席者の音声と画像が即座に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会している状態と同じ環境が求められます。
実務対応策
- 音声・映像の双方向リアルタイム通信の確保
- 技術的障害に備えたバックアップ手段の準備
- 議事録にオンライン参加者の参加方法(接続手段)、接続障害の発生時の扱い、バックアップ手段をあらかじめ規程化しておくことを推奨(判例実務上の争点を回避)
- 通信障害が生じた場合の株主総会決議の取り消しの訴えの特則(例えば、故意または重過失によって通信障害が発生したときに限り株主総会決議取消事由になるものとすること)が検討されている動向も注視
落とし穴4:議事録の「異議留保」記載を怠る
よくある誤解
決議に反対した取締役がいても、「議事の経過」に記載すれば十分と考えている実務家がいます。
正しい理解
取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されます(会社法369条5項、出典:e-Gov法令検索)。この推定規定は取締役の責任追及に直結する重要な規定です。
実務対応策
- 反対意見・異議がある場合は明確に「○○取締役より異議留保」と記載
- 異議の理由も簡潔に記録(後の責任追及時の証拠保全)
- 記載例:「○○取締役より『××』の理由により異議を留保する旨の発言があり、議長はこれを議事録に記録した。」
- 賛成者・反対者・棄権者を明確に区別した記載
落とし穴5:議事録保管期間の「起算日」を間違える
よくある誤解
「取締役会開催日から10年」と単純に考えている実務家がいます。
正しい理解
取締役会設置会社においては、取締役会の日から10年間、取締役会議事録を本店に備え置かなければなりません(会社法371条1項)。ここでの「取締役会の日」は開催日を指しますが、実務上は議事録完成日との関係も整理が必要です。
実務対応策
- 開催日から10年間の保管期間を厳格に管理
- 議事録完成日と保管期間起算日のずれに注意
- デジタル保管の場合も本店での備置義務は継続
落とし穴6:3か月報告義務の「実質化」対応不足
よくある誤解
業務執行取締役は、3カ月に1回以上自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、この報告については書面報告による報告の省略はできません(会社法363条2項、372条2項)ことは知っていても、形式的な報告で済ませている企業が多いです。
正しい理解
近年のコーポレートガバナンス強化の流れにより、実質的な監督機能を果たす報告内容が求められています。
実務対応策
- 定量的データを含む具体的な報告内容の標準化
- KPI達成状況、リスク管理状況等の実質的な報告
- 社外取締役でも理解可能な報告資料の作成
- 報告資料はKPIやリスク評価等の定量資料を含め、社外取締役が監督機能を果たせるレベルに整備(ガバナンス強化の潮流)
落とし穴7:過料制裁のリスクを軽視している
よくある誤解
「議事録不備で過料になることは滅多にない」と考えている実務家がいます。
正しい理解
議事録の作成義務違反、虚偽記載、備置義務違反、閲覧拒否等により、取締役等は100万円以下の過料に処せられます(会社法976条、出典:e-Gov法令検索)。
実務対応策
- 議事録作成の社内チェック体制構築
- 定期的な議事録監査の実施
- 取締役・監査役への継続的な啓発活動
第2部:2025年改正動向と実務への影響
バーチャルオンリー株主総会の法制化
現行会社法上はバーチャルオンリー株主総会の開催は認められていないが、21年産業競争力強化法改正により、一定の要件を満たした上場会社に、バーチャルオンリー株主総会の開催を認める特例が設けられた。現在の実務のニーズを踏まえ、非上場会社も含めて、会社法にバーチャル株主総会に関する規律を設けることが検討されている状況です。
実務への影響
- 非上場会社でもバーチャルオンリー総会が可能になる見込み
- 通信障害が生じた場合の株主総会決議の取り消しの訴えの特則など、新たな法的リスクへの対応準備が必要
- 社内IT環境の整備とリスク管理体制の見直しが急務
株式無償交付制度の拡大
19年改正で創設された取締役等への株式無償交付の制度について、対象を従業員等に拡大することが検討されている状況です。
実務への影響
- 従業員向けインセンティブプランの選択肢拡大
- 既存株主の利益保護手続きの複雑化
- 税務上の取扱いとの整合性確認が重要
第3部:実務で使える議事録テンプレート集
以下はそのままコピペで使える議事録テンプレート(取締役会・みなし決議・株主総会の書面決議)です。登記手続に用いる場合の注意点や電子署名の注記も付しています。
テンプレート1:取締役会議事録(通常決議)
株式会社○○○○
第○回取締役会議事録
(注)本議事録は電磁的記録により作成された。電磁的記録に記録された本議事録については、会社法施行規則第225条に基づく電子署名(方式:○○社提供クラウド型署名、タイムスタンプ有無:あり)を付し、署名に代える措置を講じた。
1. 開催日時:令和○年○月○日(○曜日)午後○時○分〜午後○時○分
2. 開催場所:当社本店○階会議室
(オンライン参加者:○○取締役[○市から参加、接続方法:Zoom])
3. 出席者:
取締役: ○名中○名出席
○○○○(議長)、○○○○、○○○○
監査役: ○名中○名出席
○○○○
4. 議事の経過及び結果:
議長より定足数の充足を確認し、適法に招集された本取締役会が成立した旨を宣言して開会した。
第1号議案 ○○○○の件
議長より、別紙資料に基づき○○について説明がなされた。
質疑応答の後、採決の結果、出席取締役の全員一致により原案どおり可決された。
【決議事項】
○○○○について、別紙のとおり承認する。
第2号議案 ○○○○の件
○○取締役より、○○について報告がなされた。
5. 議事録作成者:取締役 ○○○○
6. 議事録事務担当者:総務部 ○○○○
以上のとおり、この議事録が正確であることを証するため、出席した取締役及び監査役は次に署名(記名押印)する。
令和○年○月○日
取締役 ○○○○ ㊞
取締役 ○○○○ ㊞
監査役 ○○○○ ㊞
(備考)本議事録を商業登記手続に使用する場合、商業登記規則第102条で定める法務大臣指定の電子証明書等の要件を満たす必要がある旨を確認のこと。
テンプレート2:取締役会議事録(みなし決議)
株式会社○○○○
第○回取締役会議事録(みなし決議)
会社法第370条の規定に基づき、以下のとおり取締役会の決議があったものとみなされたので、議事録を作成する。
1. 決議事項:
第1号議案 ○○○○の件
【決議事項】
○○○○について、別紙のとおり承認する。
2. 提案者:代表取締役 ○○○○
3. 決議があったものとみなされた日:令和○年○月○日
4. 決議方法:
令和○年○月○日、代表取締役○○○○が取締役全員に対し上記議案を提案し、
令和○年○月○日までに取締役全員から書面(電磁的記録)による同意を得た。
6. 同意者:
取締役 ○○○○(同意日:令和○年○月○日、同意株式数:○○株)
取締役 ○○○○(同意日:令和○年○月○日、同意株式数:○○株)
取締役 ○○○○(同意日:令和○年○月○日、同意株式数:○○株)
(注)同意を得た日(決議があったものとみなされた日)を明記すること。保存起算日は同日から10年。
6. 議事録作成に係る職務を行った取締役:○○○○
令和○年○月○日
取締役 ○○○○ ㊞
取締役 ○○○○ ㊞
取締役 ○○○○ ㊞
テンプレート3:株主総会議事録(書面決議)
株式会社○○○○
第○期定時株主総会議事録(書面決議)
会社法第319条第1項の規定に基づき、以下のとおり株主総会の決議があったものとみなされたので、議事録を作成する。
1. 決議事項:
第1号議案 第○期計算書類承認の件
第2号議案 剰余金処分の件
第3号議案 取締役○名選任の件
2. 提案者:代表取締役 ○○○○
3. 提案日:令和○年○月○日
4. 決議があったものとみなされた日:令和○年○月○日
5. 決議方法:
株主全員(総株主の議決権の100%)から書面による同意を得た。
6. 各号議案の決議結果:
第1号議案:可決(同意株式数:○○株/総株式数:○○株)
第2号議案:可決(同意株式数:○○株/総株式数:○○株)
第3号議案:可決(同意株式数:○○株/総株式数:○○株)
(注)書面決議(みなし決議)では「同意を得た日」を明確に議事録に記載し、株式数(同意株式数/総株式数)を示すことが重要です(後日の争いを避けるため)。保存義務は「みなし決議があったものとみなされた日」から10年です。
7. 選任された取締役:
○○○○(○年○月○日生)
○○○○(○年○月○日生)
8. 議事録作成に係る職務を行った取締役:○○○○
以上のとおり決議が成立したので、この議事録を作成する。
令和○年○月○日
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ ㊞
第4部:電子化時代の議事録管理実務
電子署名導入時のチェックリスト
法的要件の確認
- [ ] 会社法施行規則225条2項の要件(本人性・非改変性)を満たす電子署名サービスの選定
- [ ] 法務省指定サービスかどうかの確認
- [ ] 代表取締役選定時の特別要件への対応方針策定
社内規程の整備
- [ ] 定款における押印規定の有無確認
- [ ] 印章管理規程の電子署名対応改訂
- [ ] 文書管理規程における電子保管規定の整備
運用体制の構築
- [ ] 議事録作成担当者の明確化と権限整理
- [ ] 書類管理者がチームで送受信した書類をすべて閲覧することができます。取締役会議事録のように秘匿性の高い書類の閲覧権限設定
- [ ] 長期保存時の危殆化リスクへの対応策検討
デジタル保管の法的留意点
10年間保管義務への対応
電子署名の信頼性は高度な暗号化技術により成り立っていますが、技術の進歩により暗号の安全性が脅かされるリスク(危殆化リスク)があり、長期署名を施しても改変されていないことを確認できるのは10年が限界という技術的制約があります。
実務対応策
- タイムスタンプの併用による完全性証明の強化
- 10年ごとの長期署名更新スケジュール策定
- 物理媒体でのバックアップ保管も併用検討
第5部:2025年法改正への準備事項
25年2月には、法務大臣から法制審議会に対し、会社法改正に係る諮問がなされた。4月以降、会社法制(株式・株主総会等関係)部会において審議が行われる状況です。
主要検討事項
- 従業員等への株式無償交付制度の拡大
- 株式交付制度の適用範囲拡大
- バーチャル株主総会の一般化
実務準備のポイント
短期的対応(2025年内)
- バーチャル総会運営規程の整備
- IT環境・セキュリティ体制の見直し
- 役員・株主への新制度説明資料の準備
中長期的対応(2026年以降)
- 従業員インセンティブ制度の再設計
- M&A戦略への株式交付制度活用検討
- 国際的な企業グループにおけるバーチャル総会の活用
第6部:実務チェックリスト
議事録作成時の必須チェック項目
電子署名関連
- [ ] 電子署名方式(サービス名・署名アルゴリズム・タイムスタンプ事業者)を議事録に注記
- [ ] 登記申請に使用する可能性がある場合の特別要件確認
- [ ] 議事録事務担当者の明記とPDF署名パネルとの対応確認
みなし決議・書面決議関連
- [ ] 株式数(分母・分子)を必ず明記
- [ ] 各株主・取締役の同意日を個別に記載
- [ ] 同意書の保管期間(10年)と形式の統一
オンライン会議関連
- [ ] オンライン参加者の発言ログ(チャット)保存
- [ ] 接続トラブルの記録と対応措置の記載
- [ ] バックアップ接続手段の準備と規程化
保管・管理関連
- [ ] 開催日からの10年間保管スケジュール確認
- [ ] デジタル保管時の表示方法・検索機能・閲覧方法の整備
- [ ] 長期保存時の危殆化リスクへの対応策(10年ごとの長期署名更新)
まとめ:法務実務家への提言
即座に実行すべき5つのアクション
- 電子署名導入の検討開始:早いときは役員全員への回覧が数日で終わるようになりましたという効率化効果は見過ごせません
- 議事録チェック体制の強化:異議留保記載の徹底、法定記載事項の遺漏防止
- 保管期間管理の厳格化:10年間の起算日管理、デジタル保管時の技術的制約への対応
- 法改正情報の継続的監視:2025年改正による実務変更への準備
- 社内教育の実施:取締役・監査役への継続的な法務研修
法務DXの本質的な意味
議事録の電子化や業務効率化は手段に過ぎません。真の目的は、法務リスクを適切に管理しながら、事業推進を支援する体制の構築にあります。
法改正や技術革新の波を受けて、法務実務家には従来の慣行にとらわれない柔軟な発想と、同時に法的根拠に基づく堅実な判断力が求められています。
本記事で紹介した落とし穴への対応と、最新法令への適切な対応により、企業法務のさらなる高度化を実現していただければ幸いです。
参考法令
- 会社法(平成17年法律第86号)
- 会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
- 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)
免責事項:本記事の内容は2025年9月1日時点の法令・解釈に基づくものです。具体的な事案については、個別に専門家にご相談ください。
社内規程新規作成の骨子案
新規に社内規程を作成する際の骨子案を自動生成。60〜120分の作業時間を短縮し、法令遵守と実務改善を両立させた規程の基本構造を迅速に構築できます。
社内規程新規作成プロンプト
テレワーク規程、情報セキュリティ規程など、あらゆる社内規程の骨子案を体系的に生成。関連法令の遵守事項から条文構成まで、実務で即利用可能な規程設計を支援します。
📦 このプロンプトでできること
- ✅ 規程の目的・適用範囲の明確化と体系的な設計
- ✅ 関連法令(労働基準法・個人情報保護法等)の遵守事項洗い出し
- ✅ 条文構成(総則→本則→附則)の骨子案を自動生成
- ✅ 各条項の趣旨・ポイント・注意点を詳細に解説
- ✅ 既存規程との整合性確認と矛盾点のチェック
- ✅ 承認プロセスから施行までの実施ステップを提示
💡 使い方のヒント:規程名と会社の業種・規模を入力するだけで、法令遵守を考慮した骨子案が生成されます。労務管理規程や情報管理規程など、あらゆる社内規程作成に活用できます。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

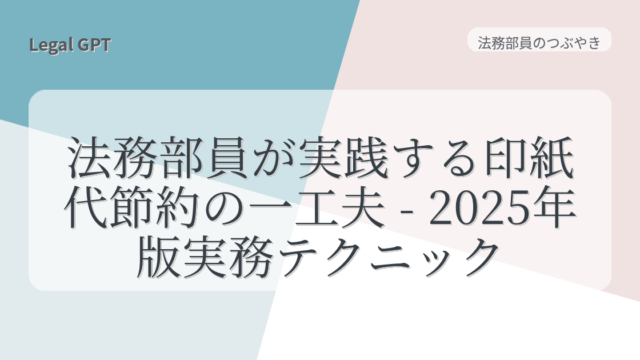
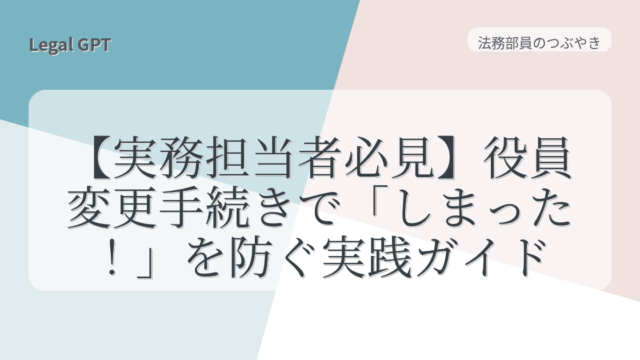
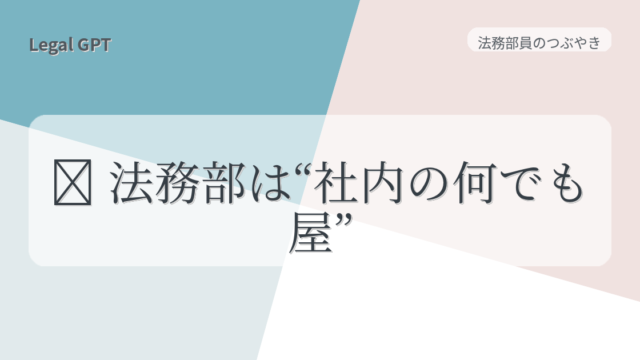
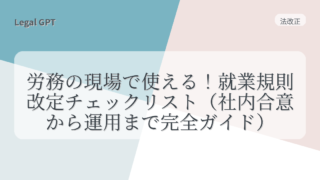
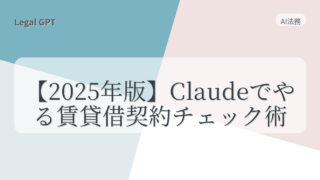



I haven¦t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂
Thanks so much — that means a lot! If you enjoy the posts, feel free to subscribe/share — I’ll keep posting quality content.