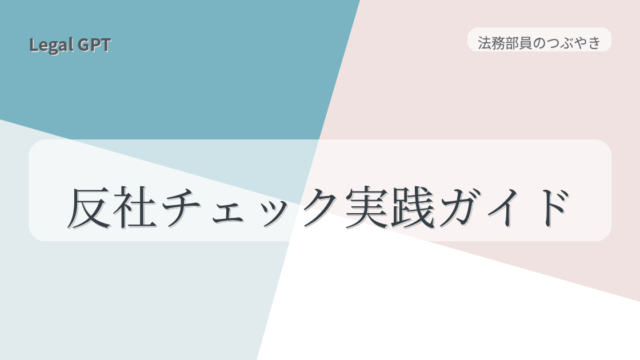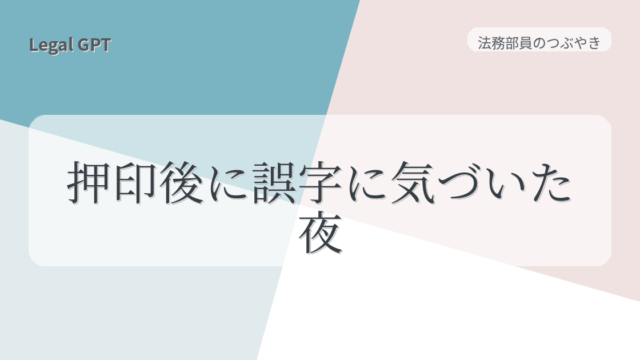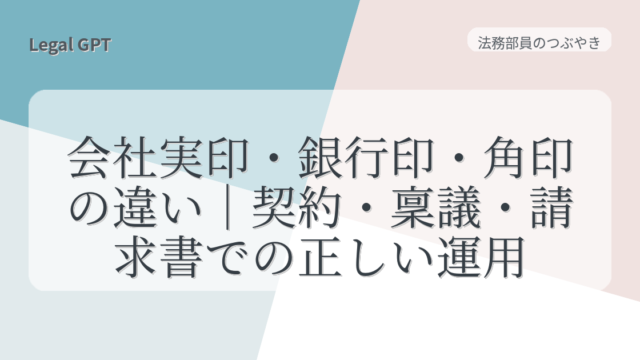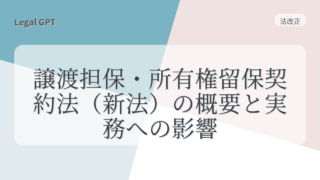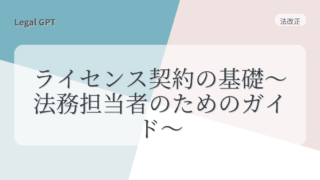社員のSNS利用によるリスクへの対応策
社員のSNS利用によるリスクへの対応策を法務部員が解説
情報漏えい発生時の対応フローや投稿監視の注意点、裁判例を紹介
【即実行すべき3つの重点対策】
法務部が今すぐ着手すべき優先事項は以下の3点です。
①初動24時間で証拠保全と削除要請 - SNS投稿による情報漏洩を発見したら、投稿のスクリーンショット取得と削除要請を24時間以内に実施してください。
②個人情報保護委員会への報告義務の確認 - 個人情報漏洩の場合、速報を発覚から概ね3〜5日以内、確報を原則30日以内(不正目的の疑いがある場合は60日以内)に提出する義務があります。報告フローを今すぐ整備してください。
③営業秘密の管理措置の点検 - 2024年改正不正競争防止法により損害賠償算定規定が拡張されました。秘密管理性の要件(アクセス制限、マル秘表示、秘密保持契約等)を直ちに点検し、不足がある場合は強化してください。
はじめに
社員によるSNS利用は、今やビジネスシーンでも当たり前の時代となりました。企業の公式アカウントだけでなく、社員個人のアカウントでも所属企業を明かして情報発信するケースが増えています。SNSは企業のブランディングや採用活動にも有効なツールである一方、営業秘密や社外秘情報、個人情報の漏洩等による情報セキュリティリスク、さらには暴言や不用意な発言による炎上リスクが深刻な経営課題となっています。
特に情報漏洩が発生した場合、多額の損害賠償責任を負うケースもあり、企業として十分な対策を講じることが不可欠です。実際、2024年には189社の上場企業及びその子会社で個人情報の漏洩事件や紛失事故が発生しており、4年連続で最多記録を更新しています。本記事では、最新の法改正や裁判例を踏まえ、法務部の実務で即活用できる対応策を解説します。
1. SNS利用で想定される3つの主要リスク
社員のSNS利用には様々なリスクが潜んでいますが、企業法務の観点から特に重要なのが、営業秘密・社外秘情報の漏洩リスク、個人情報の漏洩リスク、そして炎上リスクです。それぞれについて、最新の法令を踏まえながら詳しく見ていきましょう。
(1) 営業秘密・社外秘情報の漏洩リスク
社員が業績に関する未公表情報や新製品のデザインをSNSに投稿し、営業秘密や社外秘情報が漏洩してしまうケースは後を絶ちません。重要なのは、社員自身に悪意がなく、誤操作や誤解等に基づく過失であっても、情報漏洩に該当するという点です。「つい友人に自慢したかった」「限定公開だから大丈夫だと思った」といった軽い気持ちでの投稿が、企業に取り返しのつかない損害をもたらすことがあります。
不正競争防止法による保護と2024年4月改正のポイント
営業秘密として法的保護を受けるには、秘密管理性、有用性、非公知性という3つの要件を満たす必要があります。秘密管理性とは、アクセス制限やマル秘表示など秘密管理措置がなされていることを意味します。有用性は、有用な技術上又は営業上の情報であることで、失敗した実験データのようなネガティブ・インフォメーションにも認められ得ます。非公知性は、合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物には記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般に入手できないことを指します。
令和5年改正不正競争防止法(2024年4月施行)の実務上の要点
2024年4月に施行された改正不正競争防止法では、(i)デジタル空間における模倣行為の規制、(ii)限定提供データ・営業秘密の保護強化、(iii)損害賠償算定規定の拡張が導入されました。実務上、法務部が特に留意すべきは以下の2点です。
第一に、差止請求の要請可能性の拡大です。ビッグデータを他者に共有するサービスにおいて、データを秘密管理している場合も含め限定提供データとして保護され、侵害行為の差止め請求等を可能にする制度が整備されました。これにより、クラウド環境でデータを管理している場合でも、適切な秘密管理措置を講じていれば法的保護を受けられることが明確化されています。
第二に、損害額の算定における使用許諾料相当額の推定拡充です。改正前は、侵害者の譲渡数量を基礎として損害額を算定する際、権利者の生産能力等を超える部分については使用許諾料相当額として請求できませんでした。改正により、生産能力等を超える損害分についても使用許諾料相当額として増額請求が可能となり、営業秘密侵害に対する損害賠償の実効性が大幅に向上しています。
(2) 個人情報の漏洩リスクと2024年4月施行規則改正
顧客情報や従業員の個人情報がSNSを通じて流出するリスクも看過できません。株式会社PRIZMAが実施した調査によれば、企業の52.2%が情報漏洩の経験があると答えており、これらの多くは従業員がSNSを通じて引き起こしたものです。
報告期限の具体的な期日(法務部必携)
個人情報保護法(法第26条、個人情報保護法施行規則第8条)に基づき、個人情報漏洩に該当する場合、個人情報保護委員会への報告義務が発生します。報告は二段階で行います。
- 速報:漏洩等の事態を知った日から速やかに、概ね3〜5日以内
- 確報:原則として漏洩等の事態を知った日から30日以内(不正の目的をもって行われたおそれがある場合は60日以内)
(3) 炎上リスクと企業イメージの毀損
飲食店の社員が食品や調理器具等を使用して遊んでいる様子を動画で撮影しSNSに投稿した結果、批判が殺到する事例は後を絶ちません。このような不用意な言動がSNSに投稿・拡散されることで、企業の信用が著しく毀損され、取引停止や株価下落など深刻な経営ダメージにつながります。
2. 裁判例から学ぶSNSリスク管理の重要性
情報セキュリティ対策とSNS利用制限に関する裁判例
情報セキュリティ対策の観点からSNS利用を制限していたにもかかわらず、従業員がこれを無視したことが懲戒処分や解雇の有効性を基礎付ける事実となった裁判例が複数存在します。これらの裁判例に共通するのは、従業員の情報管理義務違反が会社に重大な損害を与えるリスクがあることを、裁判所が明確に認識しているという点です。
裁判所は、情報流出がスマートフォンの紛失・盗難によるものだけでなく、アプリのインストール、ウェブサイトやSNSの利用によるウィルス感染による情報流出の可能性も指摘しています。そして、一般的な情報漏洩対策としては、何よりも情報を持ち出さないことが肝要であるとしています。
関西電力事件最高裁判決が示す職場外行為への懲戒の可能性
最高裁は、昭和58年9月8日の判決で、次のような一般論を示しました。「企業秩序は、通常、労働者の職場内又は職務遂行に関係のある行為を規制することにより維持しうるのであるが、職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の行為であっても、企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有するものもあるのであるから、使用者は、企業秩序の維持確保のために、そのような行為をも規制の対象とし、これを理由として労働者に懲戒を課することも許される」と判示しました。
【初動対応チェックリスト(発覚〜72時間)】
発覚直後(0〜2時間以内)
- 投稿・アカウントのスクリーンショットを取得
- 当該投稿のURL、投稿ID、投稿日時を記録
- 投稿内容の拡散状況を確認
- 法務部門、情報セキュリティ部門、人事部門、広報部門に第一報
発覚後2〜24時間
- 投稿者本人に直ちに削除を要請
- SNS事業者に対して利用規約違反として削除申請
- 情報流出の範囲の仮把握
- 報告義務該当性の初期判断
発覚後24〜72時間
- デジタルフォレンジック調査業者の選定(必要な場合)
- 個人情報保護委員会への速報の準備・提出
- 被害者への通知方法の検討
- 対外発表の要否・内容・タイミングの検討
5. 効果的なSNSガイドラインの作成ポイント
就業規則への反映も忘れずに
SNSガイドラインの実効性を高めるためには、就業規則にもSNS利用に関する規定を設けることが重要です。以下に、実務で即使える就業規則の条文例を示します。
就業規則の改定手続き(労働基準法上の義務)
就業規則を新たに作成したり、既存の規則を変更したりする場合には、労働基準法第89条等に基づく法定の手続きを遵守する必要があります。
- 労働者代表の意見聴取:過半数労働組合又は労働者代表の意見を聴取し、意見書を作成・保管
- 労働基準監督署長への届出:意見書を添付して遅滞なく届出(違反すると30万円以下の罰金)
- 労働者への周知:掲示・備付け、書面交付、電子データ提供等で周知
【参考文献・参考情報(原典リンク付き・法務実務必携)】
1. 不正競争防止法関連(経済産業省)
不正競争防止法 直近の改正(令和5年)
URL: https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/kaisei_recent.html
【参照ポイント】令和6年(2024年)4月1日施行。損害賠償算定規定の拡張、国際裁判管轄の明確化等
営業秘密管理指針(令和7年(2025年)3月31日改訂版)
URL: https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
【参照ポイント】クラウド環境での管理方法、秘密保持契約(NDA)の活用方法等を実務的に解説
2. 個人情報保護法関連(個人情報保護委員会)
個人情報の漏えい等の事案が発生した場合の対応について
URL: https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/
【参照ポイント】速報(概ね3〜5日以内)、確報(原則30日以内、不正目的は60日以内)の報告書様式をダウンロード可能
個人情報保護法ガイドライン(通則編)
URL: https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
3. 裁判例(裁判所ウェブサイト)
裁判所ウェブサイト 裁判例検索
URL: https://www.courts.go.jp/
【参照ポイント】「情報管理」「SNS」「解雇」等のキーワードで検索可能
4. 労働基準法関連
労働基準法(e-Gov法令検索)
URL: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
【参照ポイント】第89条(届出義務)、第90条(意見聴取)、第120条(罰則)
【免責事項】
本記事の内容は2025年10月時点の法令・判例・指針に基づいています。法令は随時改正される可能性があり、裁判例の解釈も事案ごとに異なりますので、最新の情報については上記の原典を直接参照いただくか、労務問題・情報セキュリティに精通した弁護士等の専門家にご確認ください。
また、本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法律相談に代わるものではありません。実際の対応にあたっては、自社の状況を総合的に勘案し、必要に応じて専門家にご相談されることを強くお勧めします。
コンプライアンスマニュアル作成プロンプト
業種・規模に応じた実践的なコンプライアンスマニュアルを、2〜4時間の作業時間を短縮して作成できます。
2-06. コンプライアンスマニュアル作成
単なる法令リストではなく、現場で活用できる具体的な行動指針・判断基準・事例を含む実践的なマニュアルを設計します。
📦 収録内容
- プロンプト本体:そのままコピペして使える完全版テンプレート
- 入力例:製造業(自動車部品)の具体的な記載例
- 出力例:AIによる実際の生成結果(目次案・重点項目整理)
- カスタマイズガイド:製造業・IT・金融・小売など業種別の注意点
- よくある質問:改訂頻度・AI出力のレビュー方法・体制構築のポイント
- 関連プロンプト紹介:内部通報制度・ハラスメント防止規程との連携
💡 使い方のヒント:PDFをダウンロード後、プロンプト本体をAIにコピペし、自社情報を入力するだけ。AI出力後は必ず弁護士・法務部門によるレビューを行ってください。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。