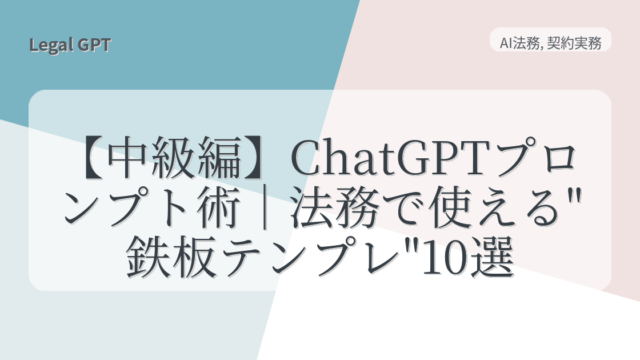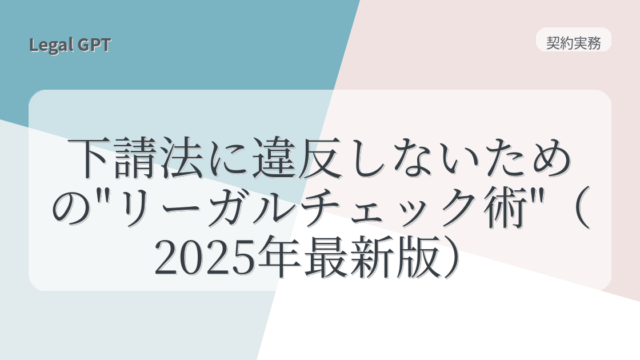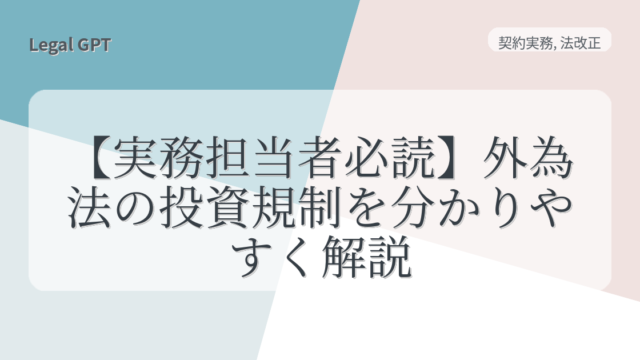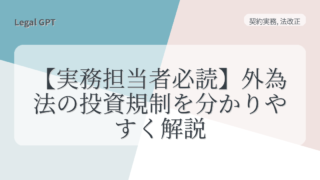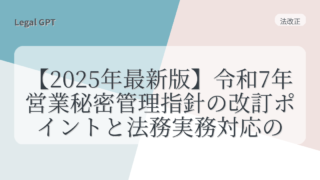契約書の保存期間 早見表【2025年最新版】税法/会社法/電帳法の交点を図解
レビュー方針→論点抽出→修正文案→交渉論点まで、“漏れない型”で揃える
契約レビューは、経験者でも「抜け」が起きやすい作業です。STEP化して再現可能にすると、品質が安定します。
- 前提整理(当事者/取引/優先順位)
- 地雷条項の抽出(損害賠償・解除・保証・責任制限など)
- 修正文案・代替案・交渉論点(説明つき)
- レビュー結果の報告書・メール文面まで
※機密情報の入力範囲・マスキングは社内ルールに従ってください。一般的情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。
契約書の保存期間 早見表【2025年最新版】
税法/会社法/電帳法の交点を図解
TL;DR(結論)
法令上の矛盾(法人税法の原則7年 vs 会社法の10年)を踏まえ、実務上は最長期間(原則として10年)で統一管理するのが安全です。法人税法上は原則7年、青色繰越欠損金がある事業年度については繰越期間に合わせて10年(平成30年4月1日以降開始事業年度が対象)となります。会社法は会計帳簿・重要資料について10年の保存を求めます。電子取引データは2024年1月1日以降、原則電子データでの保存が義務化されています(国税庁 No.5930)。
はじめに:契約書の保存期間を正しく理解していますか?
企業の法務・経理部門にとって、契約書の保存期間管理は「知っているつもり」が最も危険な業務の一つです。
- 「税務調査で契約書を破棄していたことが判明し、経費が否認された」
- 「会社法違反で過料(100万円以下)を科された」
- 「電子取引データを紙で保存していたため、電子帳簿保存法(電帳法)違反となった」
こうしたリスクを避けるためには、税法・会社法・電子帳簿保存法という3つの法律の交点を正しく理解することが不可欠です。
本記事では、2025年10月時点の最新法令に基づき、契約書の保存期間を早見表・フローチャート・条文解説の3つの角度から徹底的に整理します。
【完全保存版】契約書保存期間 早見表
まずは結論から。以下の早見表で、主要な契約書の保存期間を一目で確認できます。
| 契約書の種類 | 法人税法(※2) | 会社法(※3) | 電帳法(※4) | 実務推奨 | 起算日(※5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売買契約書 | 7年(※1) | 10年 | 7年(※1) | 10年 | 税法:申告期限翌日 会社法:事業年度末 |
| 業務委託契約書 | 7年(※1) | 10年 | 7年(※1) | 10年 | 税法:申告期限翌日 会社法:事業年度末 |
| 賃貸借契約書 | 7年(※1) | 10年 | 7年(※1) | 10年 | 税法:申告期限翌日 会社法:事業年度末 |
| 秘密保持契約(NDA) | 7年(※1) | 10年 | 7年(※1) | 10年 | 税法:申告期限翌日 会社法:事業年度末 |
| 雇用契約書 | 7年(※1) | 10年 | 7年(※1) | 10年(労基法5年) | 税法:申告期限翌日 会社法:事業年度末 |
| ライセンス契約書 | 7年(※1) | 10年 | 7年(※1) | 10年 | 税法:申告期限翌日 会社法:事業年度末 |
| 金銭消費貸借契約書 | 7年(※1) | 10年 | 7年(※1) | 10年 | 税法:申告期限翌日 会社法:事業年度末 |
| 建設工事請負契約書 | 7年(※1) | 10年 | 7年(※1) | 10年(建設業法10年) | 工事引渡し(竣工)から |
| 電子取引データ | 7年(※1) | 10年 | 7年(※1) | 10年 | 税法:申告期限翌日 |
【脚注】
(※1) 青色繰越欠損金が生じた事業年度は10年間に延長
平成30年4月1日以降に開始する事業年度が対象。それ以前は9年間。
国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間
(※2) 法人税法の根拠
法人税法第126条、法人税法施行規則第59条(青色申告法人)、第67条(普通法人等)
e-Gov 法令検索 – 法人税法
(※3) 会社法の根拠
会社法第432条第2項(会計帳簿)、第435条第4項(計算書類)、会社法施行規則第98条(事業報告)
e-Gov 法令検索 – 会社法
(※4) 電帳法の根拠
電子帳簿保存法第4条・第7条・第8条。保存期間は法人税法に準拠。
国税庁 電子帳簿保存法特設サイト
(※5) 起算日の重要注意
税法上の起算日は「確定申告書の提出期限の翌日」、会社法上の起算日は「事業年度末(帳簿閉鎖時)」と異なります。税務調査対応等では税法上の起算日を基準とすることが実務上一般的ですが、社内管理ルールは明文化してください。
(※建設業特則)
建設業における「営業に関する図書」(完成図、発注者との打合せ記録等)は工事の引渡し(竣工)から10年間保存義務があります。
建設業法施行規則第26条
※本表は一般的な目安です。契約の性質(消滅時効、特別法、建設業等の業法)により別途長期保存義務が生じる場合があります。電子取引については電帳法の区分ごとの要件確認が必須です。
⚠️ 重要ポイント
- 法人税法と会社法で期間が異なる → 長い方の「10年」で統一すれば全ての法律をクリア
- 青色繰越欠損金(赤字)がある事業年度は自動的に10年 → 最初から10年管理が効率的
- 電子取引データは原則として電磁的記録のまま保存 → 2024年1月から義務化(後述の要件参照)
- 起算日は税法と会社法で異なる → 税法「確定申告書提出期限の翌日」、会社法「事業年度末」
法的根拠を徹底解説:なぜ保存期間が定められているのか?
📋 主要3法律の条文整理
契約書の保存義務は、以下の3つの法律によって規定されています。
1. 法人税法
【適用条文】
- 法人税法第126条
- 法人税法施行規則第59条(青色申告法人)
- 法人税法施行規則第67条(普通法人等)
【保存期間】
- 原則7年間
- 青色繰越欠損金がある事業年度は10年間(平成30年4月1日以後開始事業年度。それ以前は9年)
【起算日】
確定申告書の提出期限の翌日
【対象書類】
- 帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳等)
- 書類(契約書、注文書、送り状、領収書、見積書等)
- 決算書類(貸借対照表、損益計算書等)
📖 条文参照: 国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間
2. 会社法
【適用条文】
- 会社法第432条第2項(会計帳簿)
- 会社法第435条第4項(計算書類)
- 会社法施行規則第98条(事業報告)
【保存期間】
- 10年間(全ての会計帳簿および事業に関する重要な資料)
【起算日】
- 会計帳簿:帳簿閉鎖の時(事業年度末)
- 計算書類:作成の時(事業年度末)
【対象書類】
- 会計帳簿
- 事業に関する重要な資料(契約書はここに該当)
- 計算書類および附属明細書
- 事業報告および附属明細書
📖 条文参照: e-Gov 法令検索 – 会社法第432条
✅ 契約書の位置づけ
契約書は会社法上「事業に関する重要な資料」に該当するため、10年間の保存義務があります。
3. 電子帳簿保存法(電帳法)
【適用条文】
- 電子帳簿保存法第4条(電子帳簿等保存)
- 電子帳簿保存法第7条(スキャナ保存)
- 電子帳簿保存法第8条(電子取引データ保存)
【保存期間】
- 法人税法に準拠(原則7年、青色繰越欠損金がある場合10年)
【2024年1月からの重要な変更点】
電子取引(メール・EDI・クラウドサービス等で授受した請求書・契約書等)については、2024年1月1日以降、原則として電磁的記録のまま保存することが義務化されています(宥恕措置終了)。
✅ 重要: 電子帳簿保存法は保存方法ごとに以下の3つの区分があり、それぞれ要件が異なります:
- 電子帳簿等保存(区分1): 会計ソフト等で作成した帳簿・書類を電子保存
- スキャナ保存(区分2): 紙で受領した書類をスキャンして電子保存
- 電子取引データ保存(区分3): 電子的に授受した取引情報を電子保存 ←2024年1月から義務化
【電子取引(区分3)の具体的な保存要件】
電子取引については、単に印刷して紙のみで保存し、電子データを削除する運用は原則認められません。以下の要件を満たす必要があります:
① 真実性の確保(以下のいずれか1つ)
- タイムスタンプの付与(最長でおおむね2か月と7営業日以内)
- 訂正・削除履歴が残るシステムでの保存
- 訂正・削除ができないシステムでの保存
- 事務処理規程の整備
② 可視性の確保(すべて必須)
- システム概要書の備付け
- ディスプレイ・プリンターの備付け
- 検索機能の確保(取引年月日・金額・取引先での検索)
※ タイムスタンプ付与や入力期間に関する要件は緩和され、一定要件を満たす場合は最長でおおむね2か月と7営業日以内まで認められます(国税庁)。ただし、貴社の運用設計では国税庁のガイドラインに従った要件確認が必須です。
📖 国税庁パンフレット: 電子取引データの保存方法をご確認ください(PDF)
📖 国税庁特設サイト: 電子帳簿保存法特設サイト
「7年 vs 10年」問題の実務的解決策
🤔 なぜ保存期間が異なるのか?
同一の契約書について、法律によって保存期間が異なります。
- 法人税法: 7年(税務調査の時効期間に基づく)
- 会社法: 10年(株主・債権者保護の観点から)
✅ 実務的な結論:「10年間」で統一管理
推奨アプローチ
より長い期間である「10年間」で統一して保存するのが、以下の理由から最も合理的です。
メリット
- 全ての法律をカバー: 法人税法・会社法・電帳法のいずれの要件も満たす
- 欠損金リスク対応: 赤字が出た年度を個別管理する手間が不要
- 管理の効率化: 「この書類は7年、この書類は10年」と分ける必要がない
- 将来の法改正に対応: 保存期間が延長される可能性に備えられる
デメリット
- 保管コストが若干増加(ただし電子化でカバー可能)
📊 リスク比較表
| 保存期間 | メリット | デメリット | リスク |
|---|---|---|---|
| 7年のみ | 保管コスト削減 | 会社法違反の可能性 欠損金対応漏れ |
🔴 高リスク |
| 10年統一 | 法的リスク完全回避 管理シンプル |
保管コスト増加 | 🟢 低リスク |
起算日の正確な計算方法【2025年版】
保存期間の計算で最も間違いやすいのが「起算日」です。税法と会社法で起算日が異なる点に注意が必要です。
📅 法人税法における起算日
原則: 確定申告書の提出期限の翌日
具体例
- 決算日:2024年3月31日
- 申告期限:2024年5月31日(事業年度終了から2か月)
- 保存期間満了日:
- 7年の場合 → 2031年5月31日
- 10年の場合 → 2034年5月31日
🏢 会社法における起算日
会計帳簿: 帳簿閉鎖の時(事業年度の最終日)から10年間
計算書類: 計算書類作成の時から10年間
具体例
- 決算日:2024年3月31日
- 保存期間満了日: 2034年3月31日
⚖️ 起算日の対比表(重要)
| 法律 | 起算日 | 具体例(2024年3月期) | 満了日(10年) |
|---|---|---|---|
| 法人税法 | 確定申告書提出期限の翌日 | 2024年5月31日の翌日 | 2034年5月31日 |
| 会社法 | 事業年度末(帳簿閉鎖時) | 2024年3月31日 | 2034年3月31日 |
💡 実務上のポイント
税務調査対応等では、税法上の起算日(申告期限翌日)を基準とすることが実務上分かりやすい場合が多いです。ただし、会社法上の保存義務とは起算日が異なる点(約2か月のズレ)を認識し、社内管理ルールは明文化してください。
⚠️ 申告期限延長の特例
税務署長の承認を受けて申告期限を延長した場合、起算日も延長後の申告期限の翌日となります。
例: 申告期限を1か月延長し、6月30日に提出した場合
→ 起算日は6月30日の翌日(7月1日)
→ 10年保存の場合、満了日は2034年7月1日
建設業の特殊ルール
🏗️ 建設業法による特別規定
建設業における「営業に関する図書」(完成図、発注者との打合せ記録、施工体系図等)は、工事の引渡し(竣工)から10年間保存する義務があります(建設業法施行規則第26条)。
重要な注意点:
- 起算日は「工事の引渡し」であり、契約締結日や着工日ではありません
- 契約書そのものの扱いは、契約の種類や発注形態により5年・10年の差異がある場合があるため、工事種類ごとに整理してください
保存期間違反のペナルティ
⚠️ 税務上のリスク
- 青色申告の取消し: 継続的な保存義務違反により、青色申告の承認が取り消される可能性
- 推定課税: 帳簿書類の保存不備により、税務署が推定で課税を行う可能性
- 経費否認: 保存期間内に破棄した証憑により、経費計上が認められず、追加税金を支払う可能性
- 重加算税: 意図的な隠蔽と判断された場合、重加算税(35%または40%)が課される可能性
⚖️ 会社法上のリスク
- 過料(100万円以下): 会社法第976条により、保存義務違反に対して百万円以下の過料が科される可能性があります(会社法第976条解説)。運用や事案により裁判所で金額が決まります。
- 取締役の任務懈怠責任: 適切な内部統制を構築する義務を怠ったとして、取締役が損害賠償責任を負う可能性
まとめ:今すぐ実行すべき5つのアクション
✅ 実務担当者への提言
- 保存期間の統一: 迷ったら10年で統一管理
- 起算日の明確化: 税法と会社法の起算日の違いを理解し、社内ルールを明文化
- 電子化推進: 電子帳簿保存法要件(真実性・可視性)を満たすシステム導入検討
- 定期的な見直し: 年1回の保存書類棚卸しを実施
- 部門間連携強化: 法務・経理・情報システム部門の連携体制構築
FAQ:契約書保存期間のよくある質問
Q1. 契約書の保存期間は7年と10年のどちらですか?
A. 法人税法では原則7年(青色繰越欠損金がある場合は10年)、会社法では10年間の保存が義務付けられています。実務上は、より長い10年間で統一管理することで、すべての法律要件を満たせるため推奨されます。
根拠: 国税庁 No.5930 / 会社法第432条
Q2. 電子メールで受け取った契約書を印刷して保存してもよいですか?
A. 原則不可です。2024年1月以降、電子取引データは原則として電磁的記録のまま保存する必要があります。単に印刷して紙保存のみを行い、電子データを削除することは電子帳簿保存法違反となります。ただし、真実性・可視性の要件を満たした上で電子保存し、補助的に紙でも保存することは可能です。
Q3. 保存期間の起算日はいつですか?
A. 法人税法では「確定申告書の提出期限の翌日」、会社法では「事業年度末(帳簿閉鎖時)」が起算日となり、両者は異なります(約2か月のズレ)。実務上は、税務調査対応等を考慮し、税法上の起算日(申告期限翌日)を基準とすることが一般的です。ただし、社内ルールを明確にし、どちらの起算日で管理するかを統一してください。
根拠: 国税庁 No.5930
Q4. 保存期間を過ぎた契約書は必ず破棄しなければなりませんか?
A. 保存期間を超えて保管し続けても法的問題はありません。むしろ、将来の紛争に備えて重要な契約書は保存期間を超えて保管することが推奨されます。ただし、個人情報が含まれる場合は、個人情報保護法の観点から適切な管理が必要です。
Q5. スキャナ保存を活用する際の注意点は?
A. 以下の要件を満たす必要があります:
- 解像度200dpi以上
- カラー画像での保存(原則)
- タイムスタンプの付与(最長でおおむね2か月と7営業日以内)、または訂正削除履歴が残るシステムでの保存
- 検索機能の確保(取引年月日・金額・取引先での検索)
根拠: 国税庁 電帳法特設サイト
【免責事項】
本記事は2025年10月23日時点の法令に基づいて作成しており、法的アドバイスを提供するものではありません。個別具体的な案件については、必ず弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。また、法改正により内容が変更される可能性があるため、最新の法令を必ずご確認ください。
カテゴリー: 契約実務
タグ: #契約書 #保存期間 #法人税法 #会社法 #電子帳簿保存法 #電帳法 #早見表 #実務対応
契約書保管ルールの策定プロンプト【無料PDF】
会社法・電子帳簿保存法に準拠した保管規程を60〜120分で自動生成。
契約書管理の課題を一気に解決する実践的なプロンプト集です。
契約書保管ルールの策定
法定保管期間の整理から廃棄フローまで、AIが体系的な保管規程を提案。
紙契約と電子契約の混在期にも対応した実務的なルールを即座に作成できます。
📦 収録内容
- 契約書保管規程 – 条文形式の社内規程をAIが自動生成
- 保管期間一覧表 – 契約種類別の法定期間を網羅
- 保管場所・方法の設計 – 物理保管とクラウドの両対応
- 廃棄手続きフロー – リスク判断基準と承認プロセス
- 運用チェックリスト – 締結時・終了時・棚卸し時の手順
- 段階的な実施計画 – 3フェーズで無理なく導入
💡 使い方のヒント: プロンプトをコピーして、ChatGPT・Claude・Geminiにペースト。 自社の情報(従業員数、業種、現在の課題など)を入力すると、即座にカスタマイズされた保管規程が生成されます。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。