フリーランス新法で業務委託契約が激変!必須対応事項まとめ
【2025年最新版】フリーランス新法で業務委託契約が激変!
企業が今すぐ対応すべき実務ポイント完全ガイド
本記事で分かること
- 即対応必須事項:書面(電磁的方法含む)による取引条件明示が全業務委託で必須。口約束・簡易メールのみの発注は法令違反
- 60日ルール:給付受領日から60日以内での支払期日設定が義務化。従来の「検収後翌々月末」は見直し必須
- 7つの禁止行為:1か月以上の委託で、受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき等が明文で禁止
- 違反時のリスク:行政勧告→命令→企業名公表→罰金(50万円以下)の段階的制裁措置
- 実務対応期限:新規契約は即時対応、既存契約は更新時に順次対応(2026年中の完了を推奨)
はじめに:2024年11月1日、業務委託契約の実務が変わった
2024年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号、通称:フリーランス保護新法、フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行され、業務委託契約を取り巻く法的環境が根本的に変化しました。
本法は、働き方の多様化が進展する中、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、フリーランスに業務委託を行うすべての企業に対して、新たな法的義務を課すものです。
従来の実務からの主な変更点
- 口頭発注やメッセージアプリのみでの発注が法令違反に
- 支払期日の設定基準が明文化され、「検収後翌々月末」等の慣行が見直し対象に
- 「ついでに作業依頼」「一方的な報酬減額」等が禁止行為として明文化
- 違反企業には行政勧告・企業名公表・罰金等の段階的制裁措置
2025年10月には、公正取引委員会・厚生労働省により「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(解釈指針)が改正され、2026年1月1日から施行される予定です。本記事では、この最新ガイドラインに基づいた実務対応策を詳しく解説します。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025 - 内閣官房「フリーランス・事業者間取引適正化等法」特設ページ
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html - 公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
第1章:フリーランス新法の全体像と最新動向
1-1. 法律の基本構造と目的
フリーランス新法は、「取引の適正化」と「就業環境の整備」という2つの柱で構成されています。
【柱1】取引の適正化(担当:公正取引委員会・中小企業庁)
- 書面(電磁的方法含む)による取引条件明示義務(第3条)
- 報酬支払期日の設定義務(第4条)
- 7つの禁止行為の明文化(第5条)
- 特定受託事業者からの申出制度(第6条)
【柱2】就業環境の整備(担当:厚生労働省)
- 募集情報の的確表示義務(第12条)
- 育児・介護との両立配慮義務(第13条)
- ハラスメント対策の体制整備義務(第14条)
- 中途解除時の事前予告・理由開示義務(第16条)
1-2. 適用対象の正確な理解
(1)「特定受託事業者」(フリーランス)の定義
本法における「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、以下のいずれかに該当するものをいいます(法第2条第1項)。
特定受託事業者の要件
- 個人であって、従業員を使用しないもの
- 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
⚠️ 「従業員を使用しない」の判定基準
「従業員の使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇用することをいいます(解釈指針第1部1(1))。
留意点:
- 短時間・短期間労働者(週20時間未満かつ31日未満)は「従業員」に該当しない
- 事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員の使用」に該当しない
- 法人の場合、「役員」がいないことも要件(理事、取締役、執行役、監事、監査役等)
(2)「業務委託」の範囲
本法における「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に対して行う以下の行為をいいます(法第2条第3項)。
- 物品の製造(加工を含む)を委託すること
- 情報成果物の作成を委託すること
- 役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む)
⚠️ 業務委託に該当しない取引
- 販売契約(商品の売買)
- 金銭消費貸借契約(融資)
- リース契約
- 消費者(BtoC)との取引
(3)「特定業務委託事業者」の定義
本法の規制の多くは、「特定業務委託事業者」が「特定受託事業者」に業務委託をした場合を対象としています(法第2条第6項)。
特定業務委託事業者の要件
業務委託事業者であって、以下のいずれかに該当するもの:
- 個人であって、従業員を使用するもの
- 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
⚠️ 重要な例外
第3条(書面等による取引条件の明示義務)については、発注事業者が「特定業務委託事業者」であるか否かにかかわらず、すべての業務委託事業者に適用されます。つまり、従業員を使用しない個人事業主や一人法人であっても、フリーランスに業務委託をする場合は、書面明示義務を負います。
1-3. 2025年10月ガイドライン改正のポイント
2025年10月1日、公正取引委員会・厚生労働省により「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」が改正されました。主な改正点は以下の通りです(2026年1月1日施行予定)。
主な改正ポイント
- 具体的事例の追加による解釈の明確化
- 禁止行為の判断基準のさらなる明確化
- 業界特有の取引慣行への配慮事項の追記
- 電磁的方法による明示の具体的方法の例示拡充
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html
第2章:企業が即対応すべき必須事項
【参考】期間要件別・適用義務一覧表
| 委託期間 | 適用義務 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| すべての期間 | 書面による取引条件明示 | 第3条 |
| 報酬支払期日設定・期日内支払い | 第4条 | |
| ハラスメント対策 | 第14条 | |
| 募集情報の的確表示 | 第12条 | |
| 1か月以上 | 7つの禁止行為 | 第5条 |
| 6か月以上 | 育児・介護配慮義務 | 第13条 |
| 中途解除の事前予告・理由開示 | 第16条 |
⚠️ 期間要件の判定基準
- 期間は契約期間で判定(実際の業務期間ではない)
- 契約の更新により1か月以上または6か月以上となる場合も含む
- 6か月未満の委託でも、育児・介護配慮は努力義務
2-1. 書面による取引条件明示義務(全業務委託)
法的根拠:第3条第1項
業務委託事業者は、特定受託事業者に業務委託をした場合、直ちに、以下の事項を書面又は電磁的方法により明示しなければなりません。
📋 必須明示事項(9項目)
- 給付の内容
- 具体的な業務範囲、仕様、成果物の内容等
- ❌ NG例:「システム開発業務」
- ✅ OK例:「顧客管理システムのUI設計・データベース設計・実装(Python/Django使用、詳細は別紙仕様書参照)」
- 報酬の額
- 税込/税抜の明記が必須
- ❌ NG例:「応相談」「市場価格で」
- ✅ OK例:「総額500,000円(消費税別途50,000円、合計550,000円)」
- 支払期日
- ❌ NG例:「完成後、順次支払い」
- ✅ OK例:「成果物受領日の翌月末日」
- 業務委託事業者の名称又は氏名
- 特定受託事業者の名称又は氏名
- 業務委託をした日
- 給付を受領する日又は役務の提供を受ける日・期間
- 給付を受領する場所又は役務の提供を受ける場所
- 検査をする場合:検査完了日又は検査完了日の定め方
実務上の重要な注意点
- 口頭のみの明示は無効:必ず書面又は電磁的方法による明示が必要
- 「直ちに」の意味:業務委託をした後、速やかに(実務上は当日中が望ましい)
- 電磁的方法の範囲:メール、SNSメッセージ、電子契約システム等も可(9項目が完全に含まれることが必須)
- 発注後の追加明示はNG:後から情報を追加する運用はリスクあり
- 変更時の再明示:取引条件に変更があった場合、その都度明示が必要
電磁的方法による明示の具体例
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第3条
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025 - フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A(令和6年12月18日時点)問13-17
関連Q&A
2-2. 報酬支払期日の設定(60日ルール)
法的根拠:第4条
基本ルール
- 給付を受領した日(役務提供委託の場合は役務の提供を受けた日)から起算して60日以内で、できる限り短い期間内において、支払期日を定めなければならない
- 定めた支払期日までに報酬を支払わなければならない
⚠️ 起算点の正確な理解
- 「給付受領日」= 実際に成果物を受け取った日(検収日ではない)
- 検査がある場合でも、起算点は給付受領日
- 継続的役務提供の場合:各月の役務提供完了日ごとに起算
具体例:
- 1月15日:成果物納品(給付受領日)
- 1月25日:検収完了
- 起算点:1月15日から60日以内(3月15日まで)
実務での対応例
⚠️ 再委託の特例
特定業務委託事業者が他の事業者から業務委託を受け、その業務の全部又は一部を特定受託事業者に再委託した場合、元請業務に係る給付の受領日から30日を経過する日までの範囲内で支払期日を定めることができます(第4条第3項)。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第4条
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025 - 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方 第2部第2
解釈指針(PDF)
2-3. 7つの禁止行為(1か月以上の委託)
法的根拠:第5条
⚠️ 適用対象
7つの禁止行為規定は、政令で定める期間(1か月)以上の期間行う業務委託(契約の更新により1か月以上継続することとなるものを含む)に適用されます。
① 受領拒否の禁止(第5条第1項第1号)
禁止される行為
特定受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、給付の受領を拒むこと。
具体例:
- 仕様書通りに作成された成果物を「イメージと違う」として受領拒否
- 市場環境の変化を理由に一方的に発注を取り消し
- 自社都合による計画変更を理由とした納品拒否
② 報酬の減額の禁止(第5条第1項第2号)
禁止される行為
特定受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、報酬の額を減ずること。
具体例:
- 発注後に「予算が削減された」として報酬を一方的に減額
- 振込手数料を事後的に報酬から控除
- 「消費税転嫁分を値引き」として実質的な減額
③ 返品の禁止(第5条第1項第3号)
禁止される行為
特定受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、給付を受領した後に給付の内容と同種又は類似の内容の給付に代えて給付をやり直させること。
具体例:
- 一度受領した納品物を「やっぱり別の方向性で」として返品
- 仕様変更を理由とした作り直しの要求
④ 買いたたきの禁止(第5条第1項第4号)
禁止される行為
類似の給付に対し通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること。
具体例:
- 市場相場が50万円の業務を「経験を積めるから」として10万円で発注
- 「継続発注する」ことを条件に著しく低い単価設定
⑤ 購入・利用強制の禁止(第5条第1項第5号)
禁止される行為
正当な理由がないのに、自己の指定する物を強制的に購入させ、又は役務を強制的に利用させること。
具体例:
- 業務に不要な機材の購入を強制
- 自社製品の購入を委託の条件とする
⑥ 不当な経済上の利益提供要請の禁止(第5条第1項第6号)
禁止される行為
自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
具体例:
- 委託範囲外の業務を無償で追加依頼
- 「協賛金」名目で金銭を徴収
- 自社イベントへの無償協力を強制
⑦ 不当な給付内容変更・やり直しの禁止(第5条第1項第7号)
禁止される行為
特定受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、給付の内容を変更させ、又は給付を受領した後にやり直しをさせること。
具体例:
- 当初の仕様にない機能追加を無償で要求
- 納品後に「もっと良いものにして」と大幅な修正を無償で依頼
- 発注側の指示ミスによるやり直しを受託側の負担で実施させる
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第5条
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025 - 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 第1条
施行令(内閣官房ページ) - 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方 第2部第3
解釈指針(PDF)
2-4. 就業環境整備義務
A. 募集情報の的確表示義務(第12条・全期間)
対象:すべての業務委託
特定業務委託事業者は、特定受託事業者の募集を行うときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはなりません。
具体的義務:
- 報酬額の明示(幅がある場合は範囲を明示)
- 業務内容の具体的明示
- 募集者の氏名・名称の明示
B. 育児・介護配慮義務(第13条・6か月以上)
⚠️ 対象:6か月以上の委託(未満は努力義務)
特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者の育児・介護と業務の両立に関して、申出があった場合、必要な配慮をするよう努めなければなりません(6か月以上の場合は義務)。
配慮の具体例:
- 妊婦健診のための時間確保
- 乳幼児の育児のための業務量・納期の調整
- 家族介護のためのリモート業務容認
- 短時間勤務への配慮
C. ハラスメント対策義務(第14条・全期間)
対象:すべての業務委託
特定業務委託事業者は、業務委託に関して行われる言動により特定受託業務従事者の就業環境が害されることがないよう、以下の措置を講じなければなりません。
必要な措置:
- ハラスメント相談窓口の設置
- 相談体制の整備・周知
- ハラスメント防止に関する方針の明確化
- 社内研修の実施
- 迅速かつ適切な事実確認体制
D. 中途解除の事前予告義務(第16条・6か月以上)
⚠️ 対象:6か月以上の委託
特定業務委託事業者が、やむを得ない事由なく、業務委託を中途で終了させるときは、30日前までに予告し、かつ、理由を開示しなければなりません。
重要ポイント:
- 予告:書面又は電磁的方法による
- 理由開示:具体的かつ客観的な理由の明示が必要
- 「やむを得ない事由」:天災地変等の不可抗力に限定
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第12条~第16条
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025 - 厚生労働省告示「特定業務委託事業者が講ずべき措置等に関する指針」
特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針
第3章:下請法との違いと両法同時適用時の注意点
3-1. 適用範囲の決定的な違い
| 項目 | フリーランス新法 | 下請法 |
|---|---|---|
| 発注者の要件 | 資本金制限なし(書面明示義務は全業務委託事業者、禁止行為等は特定業務委託事業者が対象) | 資本金等による親事業者の要件あり(製造委託:3億円超→3億円以下、情報成果物・役務提供委託:5,000万円超→5,000万円以下等) |
| 受注者の要件 | 従業員を使用しない個人・一人法人等(特定受託事業者) | 資本金等による下請事業者の要件あり |
| 適用取引 | 業務委託全般(物品製造、情報成果物作成、役務提供) | 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4類型 |
| 書面交付義務 | 業務委託時に直ちに(9項目明示) | 発注後直ちに(12項目記載の3条書面交付) |
| 支払期日 | 給付受領日から60日以内でできる限り短い期間 | 給付受領日から60日以内 |
| 禁止行為 | 7つの禁止行為(1か月以上の委託) | 11の禁止行為(全取引) |
| 執行機関 | 公正取引委員会・中小企業庁(取引適正化)、厚生労働省(就業環境整備) | 公正取引委員会・中小企業庁 |
3-2. 両法が同時適用される場合の実務対応
⚠️ 同時適用のケース
資本金1,000万円超の企業が、下請法の4類型に該当する業務を、従業員を使用しないフリーランスに委託する場合、両法が同時に適用されます。
(1)書面交付義務
実務対応
- 下請法の3条書面(12項目)とフリーランス新法の明示事項(9項目)の両方の要件を満たす書面を作成
- 一つの書面で両法の要件を満たすことも可能
- 記載項目は多い方(下請法の12項目)を基準に作成すれば確実
(2)支払期日
実務対応
- 両法とも「給付受領日から60日以内」を基本とする
- フリーランス新法は「できる限り短い期間」という追加要件あり
- 実務上は「できる限り短い期間」を重視した運用が安全
(3)禁止行為
実務対応
- 両法の禁止事項をすべて遵守する必要あり
- 下請法の11の禁止行為+フリーランス新法の7つの禁止行為を統合的に管理
- 重複する禁止行為も多いが、表現や要件が微妙に異なる場合があるため注意
【実務担当者向け】両法対応チェックリスト
- ☐ 取引先が「特定受託事業者」に該当するか確認
- ☐ 自社が下請法の「親事業者」に該当するか確認
- ☐ 両法が同時適用される場合、書面に両法の要件を反映
- ☐ 支払期日は「できる限り短い期間」を意識して設定
- ☐ 両法の禁止行為を統合したチェックリストを社内で整備
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方」(令和6年5月)
公正取引委員会ページ
第4章:契約書改定の実務対応
4-1. 契約書への必須追加条項
A. 取引条件明示条項
B. 禁止行為対応条項
C. 就業環境配慮条項
D. 中途解除条項(6か月以上の委託の場合)
4-2. 発注書・請求書フォーマットの改善
発注書に必ず記載すべき9項目
- 給付の内容(具体的な仕様・範囲)
- 報酬の額(税込/税抜の明記)
- 支払期日
- 委託者の氏名・名称
- 受託者の氏名・名称
- 業務委託をした日
- 給付受領日又は役務提供日・期間
- 給付受領場所又は役務提供場所
- 検査がある場合:検査完了日又はその定め方
関連記事
契約書の具体的な雛形や条文例については、以下の記事で詳しく解説しています。
第5章:違反時のリスクと執行状況
5-1. 段階的制裁措置
法的根拠:第21条(相談体制)、第22条(指導・助言)、第7条(報告・調査)、第8条(勧告)、第9条(命令)、第24条(罰則)
違反時のペナルティ(段階的)
- 相談・指導助言
- 行政機関による任意の相談対応・指導
- 改善の余地あり
- 報告要求・調査
- 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働大臣による報告要求
- 立入調査の可能性
- 勧告
- 違反行為の是正を求める行政勧告
- この段階ではまだ企業名は非公表
- 命令・企業名公表
- 勧告に従わない場合、是正を命令
- 企業名を公表(レピュテーションリスク大)
- 罰金刑
- 命令違反:50万円以下の罰金(第24条)
- 両罰規定:法人にも罰金(第26条)
- 刑事罰のため前科となる
5-2. 2025年の執行状況
2025年6月20日、中小企業庁は「フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の処理状況について」を公表しました。
主な処理状況(2024年11月1日~2025年5月31日)
- 申出・相談件数:【具体的な数値は公表資料参照】
- 指導・助言:複数件実施
- 主な違反類型:書面明示義務違反、支払遅延、報酬減額等
⚠️ 企業名公表のリスク
企業名公表は、以下の要素を総合的に考慮して行われます。
- 違反の悪質性(故意・重過失の程度)
- 違反の継続性・反復性
- 影響の程度(フリーランスへの経済的損失の大きさ)
- 改善意思の有無
- 同種違反の履歴
一度公表されると、報道・SNS等で拡散され、企業の信用に重大な影響を与えます。
5-3. 実務上のリスク事例
「うっかり違反」の典型例
- 口頭発注をメールで後追い確認
- 問題点:業務委託時の「直ちに」明示義務違反
- 対策:発注時に9項目を含むメール・書面を必ず送付
- 振込手数料の事後控除
- 問題点:報酬減額の禁止違反
- 対策:契約時に振込手数料負担を明示、または委託者負担と明記
- 「ついでに」追加作業依頼
- 問題点:経済上の利益提供要請の禁止違反
- 対策:追加業務は必ず追加報酬を設定
- 中小企業庁「フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の処理状況について」(令和7年6月20日)
中小企業庁ページ - 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第24条~第26条(罰則)
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025
第6章:実践的対応スケジュール
6-1. 即時対応事項(2025年11月~2026年2月)
⚠️ 経過措置について
フリーランス新法には経過措置は設けられていません。2024年11月1日の施行日以降、すべての新規契約・更新契約に即座に適用されます。ただし、行政は施行後に周知・相談体制やQ&Aを通じた運用上の説明・指導を行っており、既存契約については更新時に順次対応する運用実務が想定されます(詳細は各府省の周知資料を参照)
Phase 1:緊急対応(即時着手)
- ☐ 新規発注時の書面明示の徹底(メール・電子契約等で9項目を完全記載)
- ☐ 口頭発注の完全廃止
- ☐ 既存取引先の「特定受託事業者」該当性確認
- ☐ 支払期日の60日ルール適合確認
- ☐ 振込手数料等の控除慣行の即時見直し
6-2. 本格対応(2025年3月~2026年8月)
Phase 2:制度設計・契約改定
- ☐ 業務委託基本契約書の全面改定(フリーランス新法対応条項の追加)
- ☐ 発注書・請求書フォーマットの改訂
- ☐ 社内研修プログラムの実施(法務部・調達部・営業部等)
- ☐ 社内マニュアル・チェックリストの整備
- ☐ 既存契約の更新時対応(順次、新契約書への切替)
Phase 3:就業環境整備
- ☐ ハラスメント相談窓口の設置・周知
- ☐ 育児・介護配慮の申出受付体制整備
- ☐ 中途解除時の手続フロー策定(6か月以上の委託)
6-3. 定着・モニタリング(2026年9月以降)
Phase 4:継続的コンプライアンス体制
- ☐ 月次での法令遵守状況確認
- ☐ 四半期でのリスク評価
- ☐ 年次での契約書・マニュアル見直し
- ☐ 法改正・ガイドライン改正への継続的対応
【推奨】既存契約の対応期限
法的には契約更新時の対応で可能ですが、リスク管理の観点から、2026年中の完了を目標とすることを推奨します。特に以下の契約は優先的に対応してください。
- 高優先度:長期契約・高額契約・トラブル履歴のある取引先
- 中優先度:1か月以上の継続的委託
- 低優先度(ただし対応必須):短期・少額の委託
第7章:業界別対応のポイント
7-1. IT・システム開発業界
特有の注意点
- 仕様変更の頻発→「不当な変更・やり直し」リスク
- 急な納期変更→配慮義務違反リスク
- 再委託の多層構造→支払期日管理の複雑化
対応策
- 変更管理プロセスの明文化(変更時の追加報酬算定ルール)
- 追加費用の事前合意メカニズム(変更依頼→見積→承認のフロー)
- 再委託先への法令遵守指導(元請→一次下請→二次下請の支払連鎖管理)
7-2. 広告・クリエイティブ業界
特有の注意点
- 「イメージと違う」による返品→返品禁止違反
- 修正指示の曖昧さ→やり直し強制リスク
- 急なキャンペーン中止→受領拒否リスク
対応策
- 成果物の品質基準・判断基準の明文化
- 修正回数・範囲の事前設定(例:「修正は2回まで、大幅な方向性変更は追加報酬対象」)
- キャンセル時の補償ルール整備
7-3. 建設・工事業界
特有の注意点
- 現場の事情による工期変更→配慮義務関連
- 材料費高騰時の価格転嫁→買いたたき回避
- 安全装備の費用負担→購入強制回避
対応策
- 物価変動スライド条項の活用
- 安全装備費の明確な負担区分(発注者負担を明記)
- 天候等による工期変更ルールの策定
よくある質問(FAQ)
既存契約は全て作り直しが必要ですか?
法的には契約更新時の対応で可能ですが、実務上は以下の優先順位で対応することを推奨します。
- 即時対応必須:新規発注分(書面明示の徹底)
- 早期対応推奨:長期契約・高額契約(リスクの大きいもの)
- 計画的対応:その他既存契約(更新時期に合わせて順次)
ただし、施行前の契約でも、施行後に更新(自動更新含む)が行われた場合は新たな業務委託とみなされ、書面明示義務等が発生します。
メールでの発注は法的に有効ですか?
はい、「電磁的方法」として有効です。ただし以下の点に注意が必要です。
- 9項目の明示事項が完全に記載されていること
- 相手方が確実に受信できること
- 後日の証拠として保存されていること
SNSメッセージ(LINE、Slack、ChatWork等)も電磁的方法として認められますが、記録保存の観点からは、メールまたは電子契約システムの使用が望ましいとされています。
フリーランス本人が「書面不要」と言った場合は?
法的義務なので、本人の意向に関わらず書面明示が必要です。「当事者間の合意で免除」はできません。書面明示義務は、取引の透明性確保とトラブル防止のための強行規定です。
60日ルールは土日祝日を含みますか?
はい、暦日計算です。ただし、支払期日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日での支払いが実務的です(民法142条の適用)。
具体例:
- 給付受領日:1月15日(水)
- 60日後:3月15日(土)
- 実際の支払期日:3月17日(月)でも可
従業員を使用しているかどうかの確認方法は?
以下の方法で確認します。
- 確認時期:業務委託をする時点
- 確認方法:口頭でも可能だが、記録が残る方法(メール・書面)が望ましい
- 確認内容:「従業員(週20時間以上かつ31日以上雇用の労働者)を使用しているか」
業務委託後に従業員を使用するようになった場合でも、フリーランス新法の適用対象から外れません(Q&A問8)。
下請法とフリーランス新法の両方が適用される場合の注意点は?
資本金1,000万円超の企業が下請法4類型の業務をフリーランスに委託する場合、両法が同時適用されます。
対応のポイント:
- 書面交付義務:どちらか一方で両法の要求事項を満たすことも可能(実務上は下請法の12項目を満たす書面を作成すれば確実)
- 支払期日:両法とも60日以内が基本だが、フリーランス新法の「できる限り短い期間」を重視
- 禁止行為:両法の禁止事項をすべて遵守する必要あり
契約期間の要件について詳しく教えてください
フリーランス新法では期間要件により適用範囲が異なります。
- すべての期間に適用:書面明示(第3条)、支払期日設定(第4条)、ハラスメント対策(第14条)
- 1か月以上の委託に適用:7つの禁止行為(第5条)
- 6か月以上の委託に適用:育児・介護配慮義務(第13条)、中途解除の事前予告(第16条)
注意:6か月未満の委託でも、育児・介護配慮は努力義務として求められます。
まとめ:新時代の業務委託マネジメント
フリーランス新法の施行により、業務委託契約の実務は根本的に変わりました。しかし、この変化は単なるコンプライアンス負担ではなく、持続可能なパートナーシップ構築の機会でもあります。
法令遵守がもたらす3つのメリット
1. 優秀な人材の獲得・定着
- 法令遵守企業としての信頼度向上
- 「安心して働ける企業」としての評価
- 口コミによる優秀なフリーランスの紹介
2. トラブルリスクの大幅削減
- 明確な契約条件による紛争予防
- 支払期日の明確化による信頼関係構築
- ハラスメント対策による働きやすい環境
3. 業務効率化の実現
- 標準化されたプロセスによる管理コスト削減
- 明確な責任分界点による品質向上
- 継続的なパートナーシップの構築
今後の展望
フリーランス新法は、施行後3年を目途に見直しが予定されています(附則第2条第2項)。今後、以下のような発展が予想されます。
- ガイドラインの詳細化:実務指針のさらなる充実
- 業界別対応例:各業界のベストプラクティス集約
- デジタル化促進:電子契約・電子署名の標準化
最終的な行動指針
2026年2月末までの必須アクション:
- ✅ 新規発注プロセスの法令適合化完了
- ✅ 既存契約のリスク評価完了
- ✅ 社内研修プログラムの実施開始
2026年8月末までの目標:
- ✅ 既存契約の順次更新完了
- ✅ フリーランス向け相談体制の整備
- ✅ 競合他社との差別化要因として活用開始
フリーランス新法は、日本の働き方改革の大きな転換点です。法令遵守にとどまらず、新時代の業務委託マネジメントの確立により、持続可能な成長を実現しましょう。
本記事は2024年11月施行のフリーランス保護新法および2025年10月改正の解釈指針に基づいて作成しています。最新の運用指針等については、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の公式情報を必ずご確認ください。
フリーランス法への対応、まだ手作業でやりますか?
契約書チェック、発注書作成、禁止行為の判定、トラブル時の対応文書——
これらをAI×専門プロンプトで効率化。コピペで即利用可能です。
📚 収録内容(全7章)
業務委託契約書作成支援
民法・下請法対応の自動ドラフト生成
取引内容を入力するだけで、実務で即使える業務委託契約書を自動生成。弁護士監修レベルの条項設計で、契約書作成時間を45分〜120分短縮できます。
業務委託契約書作成支援プロンプト
民法・下請法を考慮した、リスクバランスの取れた契約書ドラフトを数分で作成。準委任型・請負型の区別から損害賠償条項まで、法的に適切な条文を自動提案します。
📦 このプロンプトで実現できること
- 契約書ドラフトの自動生成 – 業務内容・報酬・期間等を入力するだけで、即座に実務レベルの契約書を作成
- 民法・下請法への完全対応 – 法的要件を満たした必須条項と、リスク回避のための特約条項を自動配置
- 知的財産権・機密保持条項 – 成果物の権利帰属、秘密情報の取扱い、競業避止義務を明確に規定
- 双方向のリスク分析 – 委託者・受託者それぞれの主要リスクを箇条書きで可視化し、交渉ポイントを明示
- 業種別カスタマイズ提案 – 製造業・IT・金融・小売など、業種特有の注意点と調整ポイントを提示
- 下請法チェック機能 – 資本金・業種に応じた下請法適用判断と、必要な対応措置を自動で注意喚起
💡 使い方のヒント:PDFをダウンロードしたら、2ページ目の「プロンプト本体」をそのままコピーして、ChatGPT・Claude・Geminiに貼り付けるだけ。取引条件を入力すれば、すぐに契約書ドラフトが完成します。生成後は必ず弁護士等の専門家によるレビューを受けてください。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

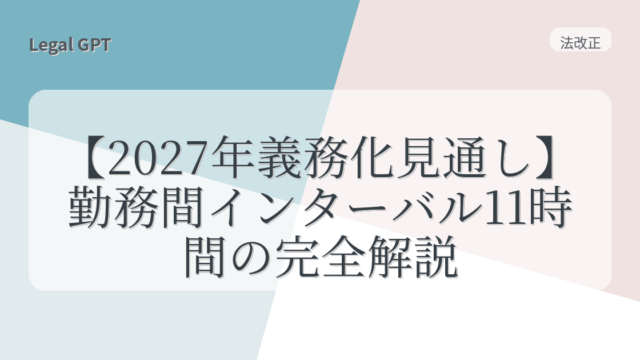
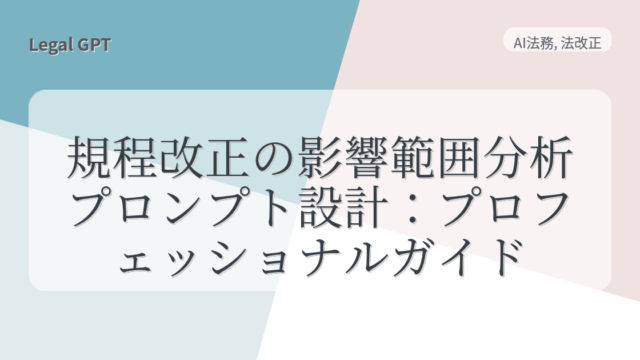
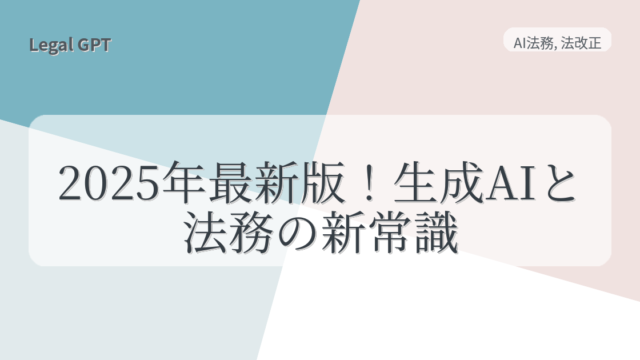
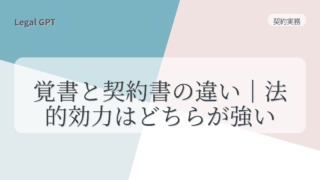
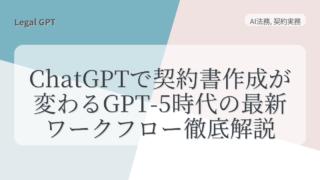



[…] […]
I like what you guys tend to be up too. Such clever work and exposure! Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.
Wow, thank you so much! We’re really excited to hear this. Adding us to your blogroll means the world to us!
Wow, thank you so much for such wonderful feedback! We’re really thrilled!
Thanks so much — honored to be part of your blogroll! Let’s keep inspiring each other through great content.
[…] フリーランス新法で業務委託契約が激変!必須対応事項まとめ 最終更新:2025-10-16(明示義務9項目・60日ルール・下請法との違い・条文例) 「支払期日は『給付受領日から60日以内でできる限り短く』の運用が必須」 […]