【2025年版】地方公務員の副業柔軟化で企業と社員が対応すべき4つのポイント|法的ガイド
2025年6月11日付の総務省通知(令和7年6月11日付・総行公第72号)を受け、地方公務員の営利企業への従事(兼業)に関する任命権者の許可運用が整理されました。通知はあくまで自治体向けの運用助言(技術的通知)であり、法改正ではなく運用の明確化・柔軟化に資するものです。本稿では、法的根拠(地方公務員法第38条等)を踏まえつつ、企業の人事・法務が直ちに取り組むべき実務対応を示します。
⚠️ 重要な法的位置づけ(実務上の留意)
本通知は行政通達的な性格の資料であり、直接に法条文を変更するものではありません。したがって具体的な許可の可否や上限設定は各自治体の運用に依存します。個別事案については所属自治体の人事担当や顧問弁護士に確認してください。
- 許可判断は任命権者の裁量だが基準は明確化(公務能率・職務公正性・品位保持)
- 全面解禁ではない:「許可制の柔軟化」であり、例外的運用が前提
- 民間側は就業規則・労務管理の見直しが必要(労働時間の通算管理など)
- 目安は参考値に留める(週8時間・月30時間等は自治体の参考値・先行事例として提示されるに留まる)
1. 総務省通知の要点(令和7年6月11日)
総務省の通知は自治体の任命権者(市長・知事等)向けに、営利企業への従事等を許可する際の留意点を整理したものです。主な変更点は以下の通りです(運用上の整理)。
① 任命権者による従業員兼業の許可が運用上明確化
任命権者は、地方公務員法第38条等に基づき個別事情を踏まえて許可の可否を判断できます。通知は「営利企業での従事が一定の要件の下で許容され得る」ことを運用上確認するもので、許可は個別判断です。
② 許可基準の提示・透明化の促進
各自治体に対し、許可判断の基準や手続を明示・公表することを促す方向が示されました。運用の透明化は職員の予見可能性や公平性確保の観点から重要です。
③ 報酬額・業務内容の個別評価
一律の金額上限よりも、業務内容・報酬の性質・職員の職務等を総合して「社会通念上相当か」を評価することが重視されます。つまり自治体ごとに個別評価が必要です。
④ 兼業時間数は「参考値」扱い
先行する自治体事例等では「週8時間・月30時間程度」という目安が示される場合がありますが、これは通知の直接的な法規定ではなくあくまで参考値です。結論的な上限は各自治体の許可基準に依存します。
通知は運用上の助言であり、最終的な法的適用は地方公務員法等の条文と各自治体の規定に基づきます。許可の可否・上限設定等は所属自治体に確認してください。
2. 法的枠組み:地方公務員法第38条・施行令第19条
基本的構造(要点)
地方公務員法第38条は、営利事業への従事を原則として制限する条文であり、例外として政令等で定める場合等があります(施行令における規定参照)。許可運用は「原則禁止→任命権者の裁量で例外許可」という構造をとるため、許可基準・手続の整備が運用上の鍵となります。
許可判断の3原則(整理)
- 公務能率の確保:兼業が本務の遂行に支障を生じさせないこと(時間・疲労・勤務時間帯の重複等を総合評価)。
- 職務の公正性の確保:兼業先との利害関係がないこと(利益相反の回避、業務上の関与と兼業の関係性等)。
- 職員及び職務の品位保持:兼業が公務員としての信用・品位を損なわないこと。
(条文参照:地方公務員法第38条、地方公務員法施行令第19条)
3. 比較表:公務員3区分と民間社員の違い(要点整理)
| 項目 | 地方公務員 | 国家公務員 | 民間企業の社員 |
|---|---|---|---|
| 法的根拠 | 地方公務員法第38条、施行令第19条(許可運用) | 国家公務員法(営利企業での兼業は原則禁止、例外は厳格) | 就業規則・労働契約(法律上の直接的な「副業禁止」規定はなし) |
| 許可主体 | 任命権者(市長・知事等)/自治体の規定に基づく | 所管大臣等(例外的取扱いが中心) | 会社(就業規則で制約) |
| 運用方向(2025年以降) | 許可制の運用明確化・透明化(自治体ごとの運用が重要) | 厳格な原則維持(変更の見込みは限定的) | 副業制度の整備・容認が進む(厚労省ガイドラインの方向) |
(参考:地方公務員法、国家公務員法、厚生労働省ガイドライン等)
4. 厚労省ガイドラインと民間企業の実務
政策的立場
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、企業における副業の取り扱いについて「原則として副業を認める方向」を示しています。ただし、企業が合理的に副業を制限できる場面(労務提供上の支障、機密漏洩、競業、名誉・信用の毀損)も明確化されています。
実務上の優先管理事項
① 労働時間の通算管理
本業・副業を合算して法定労働時間(原則週40時間)等の管理を行う必要があります。割増賃金の算定や過重労働リスクの回避の観点から、運用ルール(時間の自己申告、勤怠システム連携等)を整備してください。
② 健康管理の整備
過重労働防止のための面談や産業保健との連携、定期健康診断の活用が重要です。
③ 情報セキュリティ対策
機密情報管理の観点から、NDAや兼業先の情報管理ルールの確認・周知、必要に応じた業務制限を検討してください。
(出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」等)
5. 波及効果(企業が留意すべき点)
① 人材市場の変化
公務員を含む働き手の柔軟な働き方が進むことで、民間企業は副業を含めた雇用設計での競争が激化します。
② 企業制度の見直し圧力
就業規則、評価制度、雇用契約の見直しが必要になる場面が増えます(副業に対する許可基準や報酬処理、勤務時間の取り扱い等)。
③ 制度インフラの必要性
複数雇用に対応した勤怠システム、社会保険・税務の実務整理、プライバシー・情報管理の整備が必要です。
6. 社員向けチェックリスト(副業開始前の5項目)
✅ チェック1:就業規則の確認(必須)
- 副業の取扱い(禁止/許可制/届出制)を確認
- 許可・届出の手続、必要書類を確認
- 懲戒規程や違反時の扱いを把握
✅ チェック2:労働時間の通算
- 本業と副業の合算で週40時間等の法定時間を超えないか確認
- 残業代・割増賃金の計算方法(負担主体)を確認
✅ チェック3:競業・機密情報
- 兼業先が本業と競合しないか確認
- 本業で知った顧客情報・営業秘密を使用しない旨を徹底
✅ チェック4:社会保険・税務
- 年末調整・確定申告の要否(例:副業所得が20万円超の判定)を確認
- 被扶養者要件等への影響を確認
✅ チェック5:契約面(副業先との契約)
- 業務内容・報酬・守秘義務・損害賠償等を明文化した契約を締結
- 本業との利害調整(兼業による利害対立の回避)を明確化
7. 企業向け:2026年を見据えた対応策(優先順位付き)
対応(優先)1:就業規則の設計・改訂(法務・人事の協働)
- 許可制/届出制の運用ルールを定める(許可基準の透明化)
- 競業規定・機密保持条項・懲戒規定の整合性を確認
- 申請フォーム・審査フロー(誰が判断するか)を実務化
対応(優先)2:労務管理インフラの整備
- 勤怠システムの改修(複数勤務の時間集計・証跡確保)
- 健康管理(面談・産業保健連携)の運用化
- 残業代計算ルールの明確化(副業時間の取り扱い)
対応(優先)3:情報管理・リスク管理
- 承認時にNDAやアクセス制限等の付帯条件を設定
- 社内の推奨副業リストや禁止業種リストを作成(運用上の利便性)
実務的には、上記のうち「就業規則設計」「勤怠インフラ改修」を短期(6〜12か月)で着手することを推奨します。
8. FAQ(実務的回答)
Q1:通知は「法改正」か?
A:いいえ。通知は自治体向けの運用上の助言(行政通知)であり、直接的に法条を改めるものではありません。許可運用の判断基準を各自治体が整備することを促す趣旨です。
Q2:副業の労働時間管理は会社の責任か?
A:原則として使用者(本業の会社)が労働時間管理における主体的責任を負いますが、複数雇用の実務では副業先との協力や従業員の自己申告・証跡収集が不可欠です。
Q3:公務員の副業許可が出た場合、企業側はどう扱えばよいか?
A:許可が出ていること自体は重要なポジティブ情報ですが、企業は自社の就業規則・情報管理基準に照らして別途審査・条件付け(業務時間の制限、機密管理の追加措置等)を行うことが妥当です。
9. まとめ(実務家に向けたアクション)
総務省通知は「運用の明確化」を進めるものであり、自治体の許可運用によっては地方公務員が民間での就業機会を得る可能性が高まります。企業側は制度設計(就業規則)、労務管理(勤怠・残業代)、情報管理(NDA・アクセス制御)、健康管理という4領域を優先的に整備することが求められます。
実務的には、(1)就業規則の改訂案作成、(2)勤怠システムの要件定義、(3)兼業承認ワークフローの試行を短期的に運用してPDCAを回すことを推奨します。
改正法対応チェックリスト
法改正の対応漏れをゼロに。施行日までに確実に完了させるための体系的チェックリスト生成プロンプト
法改正対応の進捗を漏れなく確認
育児・介護休業法、個人情報保護法、会社法などの法改正に対応。影響度分析とタスクリストから自動でチェックリストを生成し、施行日までの対応状況を一元管理できます。
📦 収録内容
- ✨ コピペで使えるプロンプト本体(育児・介護休業法改正対応など実例付き)
- 📊 カテゴリー別チェックリスト構造(法的要件・社内体制・周知教育・外部対応)
- ⚠️ 対応漏れリスクが高い項目の明示と注意喚起
- 🎯 施行日までに必須の項目を優先度付きで整理
- 💡 カスタマイズのポイント(会社規模・業種に応じた調整方法)
- ❓ よくある質問(作成タイミング・更新頻度・遅延時の対処法)
Claude 4.5 Sonnet
Gemini 3
💡 使い方のヒント: プロンプトをコピーして、ChatGPT・Claude・Geminiに貼り付けるだけ。法改正名・施行日・影響部門を入力すれば、担当部門・期限・優先度付きのチェックリストが即座に完成します。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

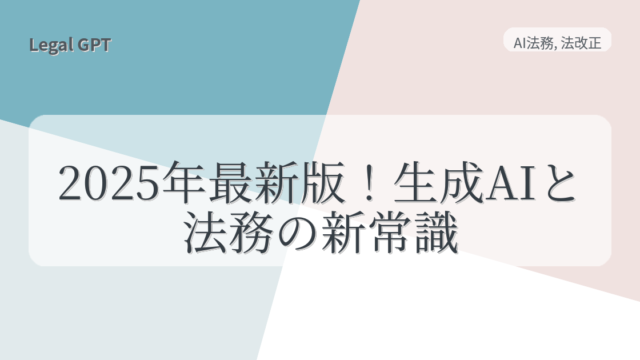
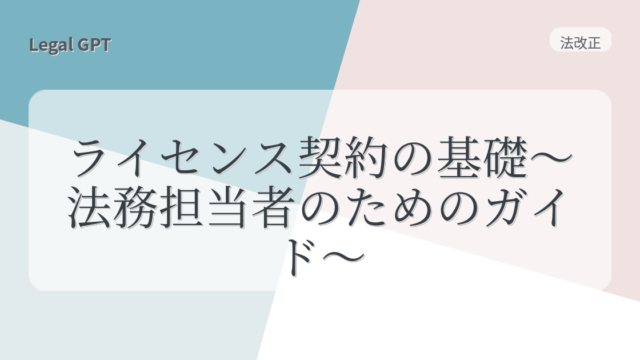
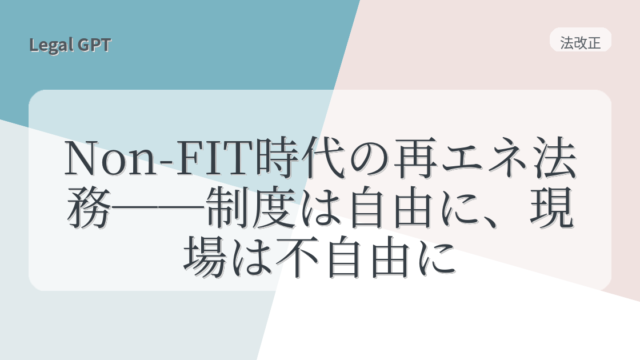
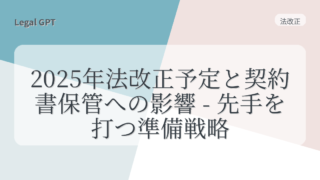
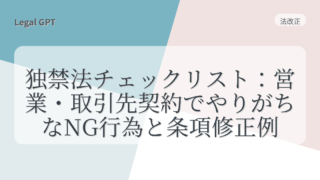


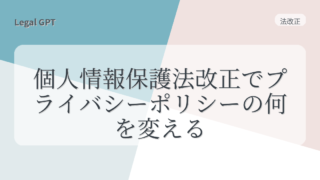
Thank you, I have just been looking for information about this topic for a while and yours is the greatest I’ve found out so far. But, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the source?
To be honest, the information in the article draws from several reliable sources. However, I do acknowledge that there are differing perspectives on this topic. I may have been clearer about citing my sources in the conclusion section.
Thank you so much! I’m glad the article was helpful. That’s a great question about the conclusion.
To be honest, I drew from several sources when writing this, but I could have been clearer about citing them in the conclusion. Sorry about that.
Thanks! I’m glad the article was helpful. You’re asking about the conclusion—that’s a good question.
To be honest, I used several sources, but I should have been more specific about them in the conclusion. My bad.