弁護士に確認するのって、いつ?
弁護士に確認するのって、いつ?
こんにちは。法務部として社内からの相談を受ける中、「これは弁護士に確認すべきか?」と判断に迷う局面は少なくありません。本稿では、実務で使える判断軸とチェック表、社内での弁護士活用のコツを整理します。
弁護士確認のタイミングは会社のDNAに左右される
経験上、弁護士への依頼タイミングは会社ごとに「色」があります。
- 慎重派の会社:契約書のドラフト段階から毎回弁護士レビューを入れる。
- 効率重視の会社:原則として法務部で完結、リスクが高い案件のみ弁護士に確認。
特に行政監督が強い業界では、まず所管省庁への照会が先に有効になることが多く、条文解釈だけでなく「運用実態」を踏まえた判断が求められます(参照:「AI時代の法務部」解説記事)。
それでも「外せない」場面は共通している
会社方針の違いがあっても、次の局面では弁護士確認を必須にしていることが多いです。
- 訴訟・紛争・仮差押え等の法的手続きが関与する場面
- 契約の解除や損害賠償請求など、重大な金銭的リスクが発生する場面
- 業法・規制法の解釈で社内判断が割れている場面
- 社外への説明責任(株主・監督官庁・取引先等)が問われる場合
- M&Aや組織再編など、企業の根幹に関わる重要事項
上場会社やガバナンスが厳格な企業では、弁護士見解そのものが「適切な手続きを踏んだ証拠」として機能します(関連記事:弁護士との付き合い方ガイド)。
判断に迷ったときの思考プロセス
現場で使える判断軸を示します。いずれかが「高」と評価されれば弁護士確認を検討してください。
- リスクの規模:金銭的損失、レピュテーション、業務継続への影響。
- 社内知見の限界:類似事例の有無、専門知識・時間の余裕。
- 説明責任の重さ:役員報告の要否、外部説明の必要性。
判断に迷ったときのチェック表
✅ 判断に迷ったときのチェック表
| 観点 | チェックポイント | 高リスクなら? |
|---|---|---|
| 金銭リスク | 損害賠償・取引停止など | 弁護士確認すべき |
| 社内知見 | 未経験・法令が複雑 | 弁護士に相談 |
| 説明責任 | 社外・役員報告の必要性 | 外部見解を取得 |
法務部として心がけていること
弁護士確認は「責任逃れ」ではなく、社内判断の妥当性を補強するエビデンスとして位置づけることが重要です。弁護士見解があると社内調整も円滑になります。
重要:弁護士に丸投げせず、社内で論点を整理してピンポイントに質問することで、より実務的で有用な回答が得られます(参照:法務チェックリストの多段階プロンプト設計ガイド)。
迷ったときの最終チェック
「半年後に役員から質問されても、きちんと根拠を説明できるか?」 — 不安があれば外部専門家の知見を借りるのが賢明です。
この問いを社内で共通の判断軸にしておくと、外部相談のタイミングがブレにくくなります。
\テレビでも話題の人気書籍!/
『頭がいい人のChatGPT & Copilotの使い方』(橋本大也 著)は、生成AIを実務にどう活かすかを“時短術”として紹介した実践的なガイドです。
ChatGPTやCopilotを活用して、
・文章作成
・資料作り
・ブレスト
・分析
など、仕事のスピードと質を一気に向上させる方法をわかりやすく解説。
「AIを使って何ができるのか」「どんな場面で活かせるのか」
初心者にもやさしく、今日から真似できる内容が満載です。
👇Amazonで詳細をチェック

📚 さらに学びたい方に:おすすめ書籍
- 『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』(幡野直人 著)
契約書レビューの流れ・コメントの書き方など、現場で役立つ基本がこの一冊に。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

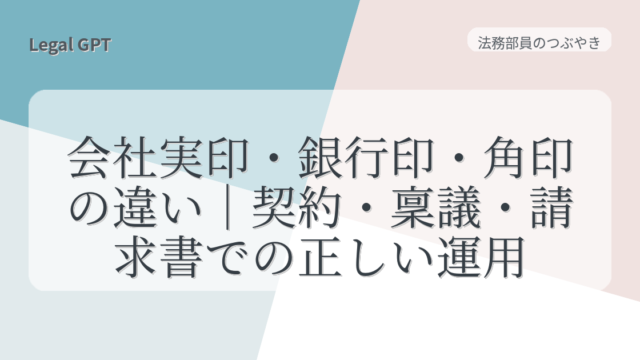
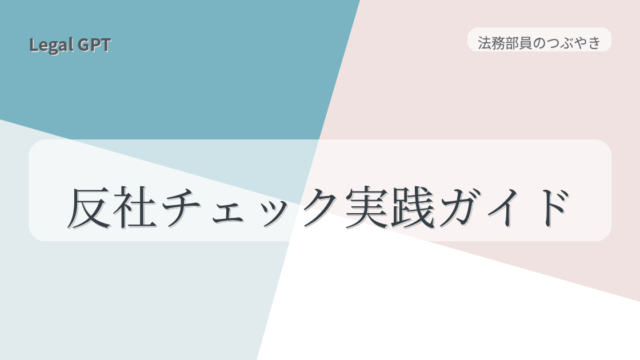
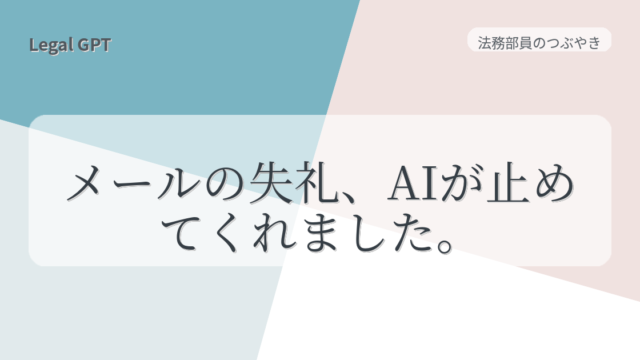
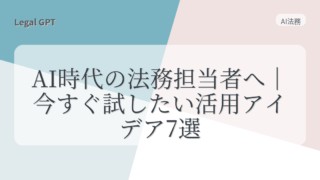
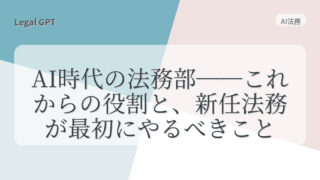



[…] 弁護士に確認するのって、いつ? … […]
[…] 弁護士に確認するのって、いつ? … 弁護士との付き合い方 〜定型業務だけじゃない“信頼関係”のつくり方〜 … […]
[…] 弁護士との付き合い方 〜定型業務だけじゃない“信頼関係”のつくり方〜 … 弁護士に確認するのって、いつ? … […]
[…] 現場判断の線引きや、いつ外部専門家にエスカレーションするかのタイミング判断が法務部の腕の見せ所です(「弁護士に確認するタイミング」についてのまとめも役立ちます:弁護士確認のタイミング解説)。 […]