【2025年最新】偽装請負チェックリスト完全版|業務委託・SES・一人常駐の適法判断基準と実務対策
【2025年最新】偽装請負チェックリスト完全版|業務委託・SES・一人常駐の適法判断基準と実務対策
労働基準監督署の最新チェックポイントと労働契約申込みみなし制度を徹底解説。最終更新:2025年10月28日
📌 結論|3つの核心ポイント(1分で読める)
- 労働者派遣法第40条の6に基づく「労働契約の申込みのみなし制度」が適用され得ます。具体的には、偽装請負と認定されかつみなし発生日から1年以内に労働者が承諾した場合に、発注者と労働者との間で労働契約が成立する可能性があります。発注者が当該状態を知らなかった(善意無過失)場合は適用が排除され得ますが、長期・組織的な継続が認められる場合は「免れる目的」が推認され、発注者の立証負担が事実上重くなる点に留意してください。
- 判断基準は37号告示と運用実態の総合評価:37号告示は請負/派遣の判断における重要な行政基準であり、「指揮命令」「労務管理」「服務管理」の各要素が実効的に受託者側で行われていることが求められます。実際の判断は契約書の文言だけでなく、運用実態を総合的に評価する点に注意してください。
- 一人常駐とSESは特にハイリスク:受託者の管理責任者が形骸化していないことを「記録」で証明できることが必須。特に電子証拠(チャットログ・勤怠ログ等)の保全が実務上の鍵となっています。
適用条文:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(派遣法)第40条の6、昭和61年労働省告示第37号
1. 偽装請負とは|法的定義と最新実務動向
1.1 偽装請負の基本定義
偽装請負とは、契約形態は「業務委託(請負・委任)」であるにもかかわらず、発注者が受託者の労働者に直接指揮命令を行うなど、実態が労働者派遣に該当する状態をいいます。
- 契約書は「システム開発業務委託契約」だが、発注者の社員が受託者の技術者に毎日の作業内容を直接指示している
- 「客先常駐」のSES契約で、受託者の管理者が形骸化し、発注者が出退勤・休暇管理を実質的に行っている
- 一人常駐の業務委託で、受託者の管理責任者が存在しない、または名目だけで機能していない
1.2 2025年の実務動向
【重要】2025年の執行強化ポイント
- フリーランス保護法(2024年11月施行)との連携強化:業務委託でも実態が「雇用類似」と判断されれば同法の適用対象となり、書面交付義務等が発生
- デジタル監視の強化:チャットログ、勤怠システムのアクセスログ等の電子証拠の重視
- 内部通報の増加:働き方改革による労働者の権利意識向上で、労働局への申告が増加傾向
2. 法的根拠と判断基準|37号告示と派遣法40条の6
2.1 適用法令の体系
| 法令 | 内容 | 実務への影響 |
|---|---|---|
| 労働者派遣法 | 派遣事業の許可制、派遣先の義務等を規定 | 偽装請負=無許可派遣として違法 |
| 37号告示 (昭和61年労働省告示第37号) |
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 | 実務上の判断基準として最重要 |
| 派遣法40条の6 | 労働契約申込みみなし制度 | 偽装請負認定時に直接雇用義務が発生 |
| 職業安定法44条 | 労働者供給事業の禁止 | 悪質な偽装請負は労働者供給として刑事罰の対象 |
2.2 37号告示による判断基準
37号告示は請負/派遣の判断における重要な行政基準であり、通常は以下の各要素が実効的に受託者側で行われていることが求められます。ただし、実際の判断は契約書の文言だけでなく、運用実態を総合的に評価する点に注意してください(単一要素の欠如が直ちに派遣該当を意味するわけではありませんが、実務上は3要素すべてが機能していることが重要です)。
- 業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行う(指揮命令の独立性)
- 受託者が作業者に対して具体的な作業手順・方法を指示
- 作業進捗の管理を受託者が行う
- 労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行う(労務管理の独立性)
- 始業・終業時刻、休憩、休日の管理を受託者が行う
- 時間外労働の指示を受託者が行う
- 企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行う(服務管理の独立性)
- 遅刻・欠勤への対応を受託者が行う
- 服務規律違反への懲戒を受託者が行う
2.3 労働契約申込みみなし制度(派遣法40条の6)
⚠️ 最重要リスク:労働契約申込みのみなしと承諾による契約成立
偽装請負が認定され、かつ「派遣法の適用を免れる目的」があると判断された場合、発注者は違法派遣開始時に遡って労働者に対し労働契約の申込みをしたものとみなされます(派遣法第40条の6第1項第4号)。
重要:みなし申込みがなされた場合、労働者がみなし発生日から1年以内に当該申込みを承諾すれば、発注者と労働者との間で労働契約が成立します(承諾がなければ労働契約は成立しません)。
善意無過失の抗弁:発注者が偽装請負であることを「知らず、かつ知らなかったことに過失がない」(善意無過失)場合は適用が排除されます。ただし、長期・組織的な継続が認められる場合、発注者側が善意無過失を立証する責任が事実上重くなる点に注意が必要です(後述の東リ事件参照)。
【東リ事件の教訓】
大阪高裁令和3年11月4日判決では、約18年間にわたる偽装請負に対し、発注者へのみなし申込み適用を認めました。継続性・組織的態様が認められると「免れる目的」が推認されるという重要な判断基準が示されています。
3. 【2025年版】労働局が重点チェックする5項目
3.1 指揮命令の実態(最重要)
- 発注者が受託者の労働者に対して日常的に作業内容を直接指示
- 具体的な作業手順・工程・順序を発注者が決定
- 発注者の朝礼への参加を義務付け
- 発注者の社内チャットで直接業務指示
- 単発的・補助的な技術説明(例:新設備の操作方法を1回説明)
- 成果物の仕様確認・検収時の指摘
- 安全管理上必要な注意喚起(労働安全衛生法に基づく措置)
判断基準:頻度・継続性・具体性が重要。「助言」レベルを超えて「指示」になっていないか
3.2 労働時間管理の実態
| 項目 | ❌ 違法パターン | ✅ 適法パターン |
|---|---|---|
| 出退勤 | 発注者が出退勤時刻を指定・管理 | 受託者が管理。発注者は施設利用時間帯を「提供」するのみ |
| 休暇 | 発注者が休暇取得を承認 | 受託者の管理者が承認し、発注者には事後報告 |
| 残業 | 発注者が残業を直接指示 | 受託者が業務状況を判断して指示 |
| 欠勤対応 | 発注者が欠勤者への対応を決定 | 受託者が代替要員を手配 |
3.3 一人常駐における管理体制
⚠️ 一人常駐は最もリスクが高い形態
労働局は一人常駐案件に対して特に厳格な審査を行います。受託者の管理責任者が「実在し、実際に機能している」ことを証拠で示せなければ、偽装請負と判断される可能性が高まります。
3.4 SES契約特有のチェックポイント
- スキルシート審査→面接による人選:発注者が「この人でお願いします」と実質的に選考
- 常駐後の指揮命令:「顔合わせ」だけのはずが、実態は日常的な直接指示
- 勤怠管理システムの共有:発注者のシステムで勤怠を直接管理
3.5 デジタル証拠の重視
2025年の新傾向:電子証拠の徹底調査
労働局は以下の電子証拠を重点的にチェックします:
- Slack・Teams等のチャットログ(誰が誰に指示しているか)
- メールの送受信記録(CC・To関係の分析)
- 勤怠管理システムのアクセスログ
- 入退室記録・セキュリティカードの利用履歴
対策:「発注者が直接指示していない」ことを示すログ保全が重要
4. 東リ事件判決から学ぶ実務教訓
4.1 事案の概要
大阪高裁令和3年11月4日判決(東リ事件)は、約18年間にわたる偽装請負に対して労働契約申込みみなし制度の適用を認めた重要判例です。
- 発注者(東リ)の工場内で、複数の請負会社から派遣された労働者が長期間就労
- 実態として発注者の従業員と同様の指揮命令下で作業
- 請負契約の形式だが、37号告示の要件を満たさない状態が継続
4.2 判決の重要ポイント
【重要判断】「免れる目的」の推認と立証責任
裁判所は、継続性・組織的態様から「派遣法の適用を免れる目的」を推認できると判断しました。つまり、長期間にわたる偽装請負は「知らなかった」という抗弁が認められにくくなります。
控訴審(大阪高裁)の重要な指摘:偽装請負の状態が「日常的かつ継続的」に続いていると認められる場合には、発注者側に「法の適用を免れる目的」があったことを推認できると述べ、発注者側が「免れる目的がなかった」ことを立証する必要性を示唆しています。そのため、長期にわたる常駐案件では運用記録・是正履歴等の保全が極めて重要です。
4.3 実務への影響
- 善意無過失の立証責任の重さ:形式的な契約書だけでは不十分。定期的な実態確認と是正措置の記録が重要。継続的な案件では「知らなかった」が通りにくい
- 長期継続のリスク:数年〜十数年にわたる同一形態の継続は、組織的・意図的と判断されやすい。東リ事件では約18年間の継続が「免れる目的」推認の根拠とされた
- 予防措置の記録化:37号告示遵守のための社内チェック体制と記録が善意無過失の証明に不可欠。定期的な実態調査と是正記録の保管が推奨される
5. 適法な業務委託契約の設計ポイント
5.1 契約書に必須の条項
第●条(業務の遂行) 1. 乙(受託者)は、自己の責任において本業務を遂行するものとし、 業務の遂行方法、作業手順、進捗管理等は乙が決定する。 2. 甲(発注者)は、乙の業務遂行に関し、乙の労働者に対して 直接の指揮命令を行わないものとする。 3. 甲が業務に関する連絡・確認を行う場合は、乙が指定する 管理責任者を通じて行うものとする。【管理責任者の明記】
第●条(管理責任者) 1. 乙は、本業務の遂行にあたり、管理責任者を選任し、 その氏名・連絡先を甲に通知する。 2. 管理責任者は、以下の業務を行う。 (1) 乙の労働者に対する業務指示 (2) 労働時間の管理 (3) 甲との連絡窓口 (4) 業務の進捗管理・品質管理【成果物・検収の明確化】
第●条(成果物及び検収) 1. 本業務の成果物は、別紙仕様書に定めるとおりとする。 2. 乙は、成果物完成後、甲に納品する。 3. 甲は、納品日から●営業日以内に検収を行い、 合格・不合格を書面で通知する。
5.2 避けるべきNGワード
| ❌ NGワード | 理由 | ✅ 代替表現 |
|---|---|---|
| 「甲の指揮命令下で」 | 派遣関係を示唆 | 「乙の責任において」 |
| 「甲の就業規則に従う」 | 労働者性を示唆 | 「乙が定める業務遂行規則に従う」 |
| 「甲が勤怠を管理する」 | 労務管理の実態を示唆 | 「乙が労働時間を管理し、甲に報告する」 |
| 「常駐」「出向」 | 派遣を連想 | 「甲の施設において業務を行う」 |
6. 一人常駐の適法運用|管理責任者の実在証明
6.1 一人常駐が違法とされる理由
一人常駐そのものが違法なわけではありません。しかし、受託者の管理責任者が現場にいないため、37号告示の要件である「自ら指揮命令を行う」が形骸化しやすいのです。
6.2 適法運用のための5つの必須要件
6.3 実在証明のための記録管理
- 日報・週報:作業者→管理責任者への報告メール(CC等で証跡保全)
- 指示記録:管理責任者→作業者への業務指示(チャット・メール)
- 面談記録:月次の1on1ミーティングの議事録
- 評価シート:四半期または半期ごとの業績評価
- 教育訓練:社内研修参加記録、資格取得支援
7. SES契約特有のリスクと対策
7.1 SES契約とは
SES(System Engineering Service)契約は、IT技術者を発注者の指定する場所で業務に従事させる準委任契約の一形態です。「技術者派遣」と呼ばれることもありますが、法的には派遣契約ではなく業務委託契約です。
7.2 SES特有の3大リスク
リスク①:スキルシート審査と面接
❌ 違法パターン
- 発注者が複数のスキルシートから「この人で」と人選を決定
- 発注者が技術者と直接面接し、合否判定を行う
- 発注者の要求する特定のスキル・経験年数を満たす者のみを受け入れる
✅ 適法な運用
- 受託者が業務に適した技術者を選定・派遣
- 発注者との「顔合わせ」は業務説明のみに限定(選考ではない)
- 契約は「技術支援サービス」であり、特定個人の提供ではないことを明記
リスク②:常駐後の指揮命令
| 行為 | リスク度 | 判断ポイント |
|---|---|---|
| 発注者の朝礼への参加 | ⚠️ 中 | 「出席義務」なら×。「任意参加可」なら〇 |
| 発注者のチャットツール使用 | ⚠️ 中 | 連絡手段なら〇。業務指示手段なら× |
| 発注者の社員と同じデスク配置 | △ 低 | 配置自体は問題ないが、指示系統が明確であること |
| 発注者による日報チェック | 🔴 高 | 「受領・確認」なら〇。「承認・指示」なら× |
リスク③:勤怠管理の混在
適法な勤怠管理の原則
- 勤怠管理システムは受託者のシステムを使用
- 発注者は「施設利用可能時間」を提供するのみ
- 時間外労働は受託者の管理責任者が判断・指示
- 休暇承認は受託者が行い、発注者へは事後報告
8. 実務チェックリスト|自社診断30項目
8.1 契約段階(10項目)
8.2 運用段階(15項目)
8.3 記録・証拠(5項目)
⚠️ 緊急度判定
- 20項目未満:🔴 高リスク(即座の改善が必要)
- 20-25項目:⚠️ 中リスク(早急な検討が必要)
- 26項目以上:✅ リスク管理できているが、継続的な確認が必要
9. 労働局調査の実態と対応フロー
9.1 調査のトリガー
- 労働者からの申告(最多):「実態は派遣なのに業務委託契約にされている」との通報
- 定期監督:業種・規模等に基づく計画的調査
- 労働災害発生時:事故調査の過程で実態が発覚
- 他機関からの情報提供:税務署、労働基準監督署等との連携
9.2 調査の流れ
- 立入調査(原則、事前通告なし)
- 都道府県労働局の需給調整部門の職員が来訪
- 調査対象:発注者・受託者の両方
- 帳簿・書類の確認
- 契約書、SOW、作業報告書、勤怠記録
- メール・チャットログ
- 入退室記録、勤怠システムのログ
- 関係者ヒアリング
- 発注者の担当者
- 受託者の管理責任者
- 実際に業務に従事している労働者
- 総合判断
- 37号告示の要件充足性を判定
- 契約書と実態の乖離を確認
- 行政指導または処分
- 軽微な場合:是正指導
- 重大な場合:改善命令、企業名公表
- 悪質な場合:刑事告発(職業安定法違反等)
9.3 調査時に提示すべき証拠と保全のポイント
【実務上の重要ポイント】電子証拠の保全とメタデータ
労働局調査では電子証拠が重視されます。特に以下の点に注意してください:
- 管理責任者の指示メール:To/CCが「管理責任者→作業者」となっていることが重要。発注者が直接作業者に送信していないことの証明
- チャットログのメタデータ:送信者・送信時刻・受信者の記録。「誰が誰に何を指示したか」が客観的に証明される
- 勤怠承認ログ:受託者の管理責任者による承認記録。システムログでタイムスタンプと承認者IDが記録されていることが望ましい
- 発注者からの連絡記録:万が一発注者から直接連絡があった場合、それが「助言」か「指示」かを区別する注記を残す
| カテゴリ | 具体的資料 | 目的 |
|---|---|---|
| 契約関係 | 業務委託契約書、SOW、注文書、請求書 | 契約形態の確認 |
| 管理体制 | 管理責任者の選任通知、組織図、職掌規程 | 管理責任者の実在性証明 |
| 指揮命令 | 管理責任者→作業者への指示メール(メタデータ含む)、業務報告書 | 指揮命令の独立性証明 |
| 労務管理 | 勤怠記録(受託者システム)、休暇承認記録、管理責任者の承認ログ | 労務管理の独立性証明 |
| 評価・教育 | 業績評価シート、研修参加記録、面談記録 | 労働者性の否定 |
| 成果物 | 検収書、納品書、受領書 | 請負性の証明(請負契約の場合) |
| 電子ログ | チャット・メールのメタデータ、入退室ログ、システムアクセスログ | 運用実態の客観的証明 |
9.4 是正勧告を受けた場合の対応
- 即座の是正:指摘事項の内容確認と緊急対応(直接指示の中止等)
- 改善計画の策定:是正措置と再発防止策を文書化
- 弁護士への相談:法的リスク評価と今後の対応方針決定
- 労働局への報告:改善計画書の提出と実施状況報告
- 社内体制の見直し:同様の案件がないか全件チェック
10. FAQ|よくある質問と回答
A. いいえ。一人常駐そのものは違法ではありません。ただし、受託者の管理責任者が実際に機能していることを証明できる体制と記録が必須です。管理責任者が形骸化していると判断されれば違法となります。
A. 単発的・補助的な技術説明(例:新設備の操作方法を1回説明)は適法です。しかし、日常的・継続的な作業手順の指示は違法と判断されます。判断基準は「頻度」「継続性」「具体性」です。
A. 事前の「顔合わせ」(業務説明のみ)は許容されます。しかし、発注者が複数候補から選考・合否判定を行う場合は違法性が高まります。「業務説明」と「人選」の線引きが重要です。
A. 連絡手段として使用するのは問題ありませんが、業務指示の手段として使用すると違法性が高まります。チャットログが証拠となるため、「誰が誰に何を指示したか」が明確に記録されます。
A. 即座の是正が必要です。以下の対応を推奨します:
- 弁護士への相談(法的リスク評価)
- 直接指示の即時中止
- 受託者の管理責任者との連絡体制の確立
- 契約内容と運用実態の整合性確認
- 必要に応じて労働者派遣契約への切り替え検討
注意:自主的に労働局に相談・届出することで、悪質性の評価が下がる可能性があります。
A. 発注者が「偽装請負であることを知らず、かつ知らなかったことに過失がない」ことを立証する必要があります。以下の記録が重要です:
- 37号告示遵守のための社内チェックリスト・マニュアルの整備と実施記録
- 定期的なコンプライアンス研修の実施記録(参加者名簿・配布資料)
- 契約時の実態確認記録(管理責任者へのヒアリング、現場視察記録等)
- 問題発覚時の迅速な是正措置の記録(指摘事項・改善計画・実施状況)
重要:ただし、長期間(数年以上)継続している場合は、「免れる目的」が推認され、発注者の立証責任が重くなります(東リ事件参照)。形式的な記録だけでなく、実効性のある管理体制の証明が求められます。
なお、みなし申込みが成立した場合でも、労働者がみなし発生日から1年以内に承諾しなければ労働契約は成立しません。
参考資料・一次情報
- 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)及び疑義応答集(Q&A)— 厚生労働省
- 労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド(PDF)— 厚生労働省
- 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(派遣法)— e-Gov法令検索
- 職業安定法 — e-Gov法令検索
- 東リ事件(大阪高裁 令和3年11月4日判決)— 労働契約申込みみなし制度の適用を認めた重要判例。「免れる目的」の推認と立証責任に関する実務上の指針
- 労働者派遣制度の概要 — 厚生労働省
業務委託契約書作成支援プロンプト【無料配布中】
取引内容を入力するだけで、民法・下請法を考慮した実務レベルの契約書ドラフトを45分〜120分で自動生成。企業法務担当者・弁護士の知見を凝縮したプロンプトを、今すぐ実務に活用できます。
業務委託契約書作成支援
GPT-5 / Claude 4.5 Sonnet / Gemini 2.5 Flash対応。委任と請負の区別、知的財産権の帰属、下請法チェックまで、リスクバランスの取れた条項を提案します。
📚 収録内容
- ✅ コピペで使えるプロンプト本体(そのままAIに貼り付け可能)
- ✅ 実務での入力例(システム開発・製造業など業種別サンプル)
- ✅ AI生成結果のサンプル(条文ドラフト・リスク分析付き)
- ✅ 業種別カスタマイズポイント(IT・製造・金融・小売など)
- ✅ よくある質問(委任と請負の違い、下請法の判断基準など)
- ✅ 関連プロンプトの紹介(NDA作成・契約書リスク分析など)
💡 使い方のヒント:PDFのプロンプトをコピーして、ChatGPT・Claude・Geminiに貼り付けるだけ。取引内容を入力すれば、法的リスクを考慮した契約書ドラフトが自動生成されます。生成後は必ず専門家のレビューを受けてください。
優越的地位濫用リスクの初期診断プロンプト
独禁法・下請法のリスクを初期段階で診断し、公正取引委員会からの警告・課徴金リスクを事前回避。2026年1月施行の改正法にも完全対応。
優越的地位濫用リスクの初期診断
取引条件・取引慣行の独禁法リスクを体系的に診断。下請法適用判定、優越的地位の3要件分析、具体的な改善アクションプランまで包括的にカバー。
このプロンプトで診断できること
- 下請法(中小受託取引適正化法)の適用有無を資本金・従業員数から自動判定
- 優越的地位の濫用該当性を3要件(地位の優越性・利用・不当性)で体系的に分析
- 具体的な濫用類型(買いたたき・協賛金要請・受領拒否等)への該当性を個別検討
- 各リスク項目のリスクレベル(高・中・低)と法的根拠を明示
- 改善が必要な事項と具体的な対応策を優先順位付きで提案
- 2026年1月施行の改正法(手形払い禁止・協議義務等)への対応準備
💡 使い方のヒント: ダウンロードしたPDFのプロンプトをコピーして、GPT-5.1、Claude 4.5 Sonnet、またはGemini 3に貼り付け。取引条件の情報を入力するだけで、独禁法・下請法リスクの包括的な診断レポートが生成されます。専門家レビューを必須としつつ、初期診断の工数を大幅削減できます。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

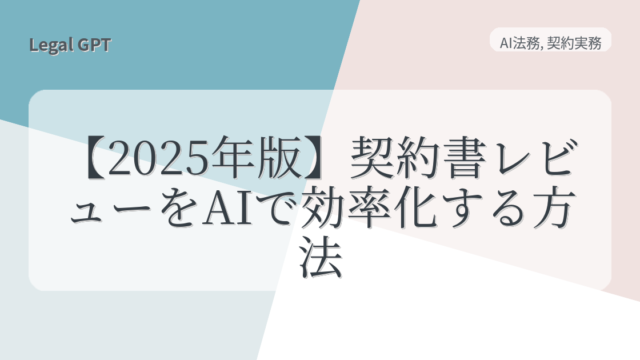
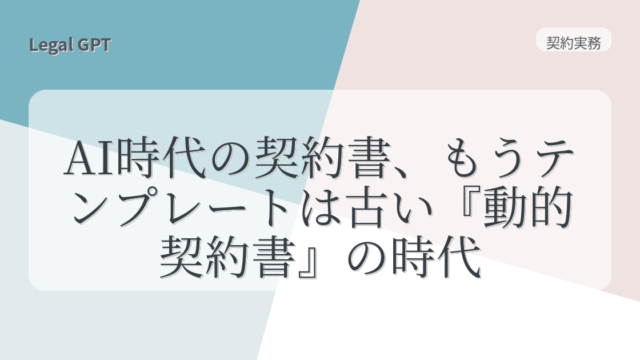
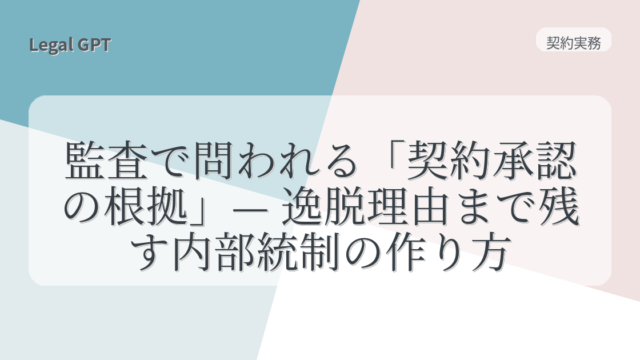
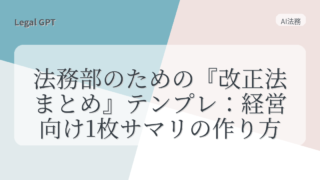
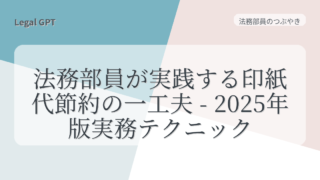



Loving the info on this web site, you have done great job on the blog posts.
Thanks so much — that means a lot! I put a lot of effort into each post, so I’m really happy to hear you’re enjoying them.