労務の現場で使える!就業規則改定チェックリスト(社内合意から運用まで完全ガイド)
2025年10月施行分の育児介護休業法改正内容を追記しました。高年齢者雇用安定法の経過措置終了(2025年4月1日)に関する最新情報を反映しています。
【2025年最新版】就業規則改定チェックリスト完全ガイド|法改正対応から運用まで5段階で徹底解説
2025年は育児・介護休業法の大幅改正(育児介護休業法第16条の2、第17条等)と高年齢者雇用安定法の経過措置終了により、多くの企業で就業規則の緊急対応が求められています。育児介護休業法は4月と10月の段階施行、高年齢者雇用安定法は4月1日の経過措置終了と、複数の重要な変更が連続して実施されました。法令への対応だけでは不十分で、改正内容を正確に理解し、社内合意を得て、適切に運用まで持っていくことが真の成功です。
📌 関連記事:2025年の法改正全体像や施行スケジュール、社内展開の実務ポイントは以下の記事で詳しく解説しています。
→ 2025年法改正対応ロードマップ|下半期の施行スケジュールと優先対応事項
🎯 就業規則改定の5つのフェーズ全体像
就業規則の改定は、以下の5つのフェーズで構成されます。各フェーズでの漏れが、後々のトラブルや法令違反につながるため、段階的なアプローチが重要です。
- Phase 1:改正内容の把握・影響分析
法改正の全体像把握、自社への影響度評価、優先度判定 - Phase 2:改定案の作成・法的妥当性確認
条文案作成、法的妥当性確認、不利益変更の検討 - Phase 3:社内合意形成・意見聴取
労働者代表からの意見聴取、全社員への事前周知 - Phase 4:労働基準監督署への届出
届出書類準備、届出先・方法確認、法的リスク回避 - Phase 5:運用開始・定着化
従業員への周知、関連システム整備、運用品質向上
💡 ポイント:各フェーズは順番に進めるのが基本ですが、Phase 1と2は並行作業も可能です。ただし、Phase 3(社内合意)の前に必ずPhase 2(法的妥当性確認)を完了させることが重要です。
Phase 1:改正内容の把握・影響分析
📋 改正内容把握チェックリスト
☑ 法改正の全体像把握
- 施行日の確認(複数回に分かれる場合は各段階を整理)
- 対象企業規模の確認(従業員数、業種等の条件)
- 義務規定・努力義務規定の区別
- 罰則の有無・内容の確認
- 経過措置の適用範囲と終了時期
☑ 自社への影響度評価
- 現行就業規則との差分分析(条文の新設・変更・削除箇所の特定)
- 関連する社内制度(人事制度、評価制度、福利厚生等)への波及効果
- 必要な予算・リソースの概算(システム改修費用、外部専門家費用等)
- 対応期限の設定(施行日から逆算した社内スケジュール)
☑ 優先度判定の3軸評価
- 法的リスク:高(罰則あり・義務)/ 中(行政指導対象)/ 低(努力義務)
- 実務への影響度:大(全社員対象)/ 中(特定部門・職種)/ 小(一部のみ)
- 対応緊急度:即座(施行済み)/ 1ヶ月以内(施行間近)/ 3ヶ月以内(準備期間あり)
🔍 2025年重点改正事項の確認ポイント
📌 育児・介護休業法(4月・10月段階施行)
【2025年4月1日施行】主な変更内容:
- 子の看護等休暇の拡充:対象が「小学校第3学年修了時(満9歳到達後最初の3月31日)まで」に拡大(育児介護休業法第16条の2)
- 取得理由の追加:「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が取得事由に追加
- 労使協定の除外規定廃止:「勤続6か月未満の除外」が廃止され、原則全員が対象に
- 所定外労働の制限拡大:請求に基づく残業免除の対象が「3歳未満」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大(同法第17条)
- 育児休業取得状況の公表義務拡大:従業員数300人超1,000人以下の企業にも公表義務が拡大
【2025年10月1日施行予定】主な変更内容:
- 柔軟な働き方措置の義務化:3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、複数の選択肢(始業時刻変更、テレワーク、短時間勤務、養育休暇付与等)から選択できる措置を提示し、個別意向確認を実施
- 個別意向聴取・配慮の義務化:妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮が事業主に義務付け
⚠️ 注意:10月施行分の詳細は厚生労働省令・告示で定められます。最新情報は必ず厚生労働省公式サイトでご確認ください。
📌 高年齢者雇用安定法(2025年4月1日・経過措置終了)
- 65歳までの雇用確保が完全義務化:継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる経過措置が2025年3月31日で終了
- 希望者全員を対象:2025年4月1日以降は、65歳までの継続雇用を希望する全従業員を対象とする制度が必要(高年齢者雇用安定法第9条)
- 3つの選択肢:①65歳までの定年引上げ、②希望者全員の65歳までの継続雇用制度導入、③定年制の廃止のいずれかを選択
📌 関連記事:規程改正の影響範囲分析や段階的導入手法については以下で詳しく解説しています。
→ 規程改正の影響範囲分析プロンプト設計ガイド|ChatGPT活用で漏れを防ぐ
Phase 2:改定案の作成・法的妥当性確認
📝 改定案作成チェックリスト
☑ 条文案の作成
- 法令の条文を就業規則の表現に適切に変換(法律用語を社内用語に置換)
- 社内用語・役職名との統一性確認(「従業員」「社員」「労働者」の使い分け等)
- 既存条文との整合性確認(矛盾・重複の排除、条文番号の整理)
- 関連規程(賃金規程、育児介護休業規程、定年再雇用規程等)との連携確認
☑ 法的妥当性の確認
- 労働基準法など労働関連法令より従業員に不利な内容でないことの確認
- 労働協約との矛盾がないことの確認(労働協約 > 就業規則 > 個別労働契約の優先順位)
- 最低賃金法、男女雇用機会均等法等の関連法令への適合性確認
- 顧問弁護士・社会保険労務士による内容確認(推奨)
☑ 不利益変更の検討(労働契約法第10条)
- 従業員にとって不利益に変更される内容がないか全条文チェック
- 不利益変更がある場合の合理性要件の検討:
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件変更の必要性(法改正対応、経営上の必要性等)
- 変更後の内容の相当性
- 労働組合等との交渉状況
- 激変緩和措置・経過措置の検討
🔍 実務で揉めやすいポイントと対策
⚠️ 子の看護等休暇の運用注意点
- 年次付与日数:改正で年間付与日数は変わりません(現行:年5日/子2人以上で10日)。ただし、事業主独自に付与日数を増やすことは可能
- 申請様式の整備:取得理由の追加に対応した申請書フォーマットの改訂、勤怠システムでの取得理由選択肢の追加
- 勤続6か月未満の労働者への対応:採用直後の短期契約者、試用期間中の者も原則対象となるため、就業規則・雇用契約書の見直しが必要
⚠️ 個別周知・意向確認での法的留意点(10月施行分)
- 誘導禁止:利用を控えさせるような誘導や、特定の選択肢への誘導は行政監督の対象。客観的・中立的な情報提供を徹底
- 面談記録の保存:面談日時、参加者、提示した選択肢、労働者の回答内容、事業主の配慮事項を記録し保存
- 面談記録様式の準備:標準フォーマットを作成し、記録漏れを防止
⚠️ 段階的施行への対応戦略
育児・介護休業法のように4月施行と10月施行の2回分が必要な場合、就業規則の変更も原則2回必要です。ただし、10月施行分を4月に前倒しして一括対応することも可能です(より従業員に有利な条件となるため法的問題なし)。
| 対応パターン | メリット | デメリット | 推奨ケース |
|---|---|---|---|
| 2回分割対応 (4月+10月) |
・段階的な準備が可能 ・各施行日に合わせた対応 |
・2回の届出・周知が必要 ・事務負担増 |
大企業、複雑な制度設計が必要な場合 |
| 一括前倒し対応 (4月に全部) |
・1回の届出・周知で完了 ・従業員へのアピール効果大 |
・初期準備負担大 ・システム改修が複雑化 |
中小企業、理事会承認が必要な組織 |
💡 推奨:理事会等の承認が必要な保育園・こども園等では、事務負担軽減のため一括前倒し対応を検討することをお勧めします。
Phase 3:社内合意形成・意見聴取
🤝 労働者代表からの意見聴取(法定手続)
☑ 労働者代表の選定
- 第1優先:労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合
- 第2優先:労働組合がない場合は「労働者の過半数を代表する者」を民主的に選出
- 過半数代表者は管理監督者を除く者から選出
- 選出方法:挙手、投票、話し合い等の民主的な方法で選出
- 目的の明確化:「就業規則について意見を聴くため」と明示して選出
💡 選出手順の具体例:①全従業員への告知(選出目的・日程・方法)、②立候補受付または推薦、③投票または挙手による選出、④選出結果の公表と議事録作成・保存。選出手続が不適切な場合、後日の労働紛争で手続瑕疵として問題になるため、選出過程の記録保存を強く推奨します。
☑ 意見聴取の実施
- 改定案の十分な説明時間の確保(最低でも1週間前には改定案を提供)
- 質疑応答・意見交換の機会設定(対面またはオンライン面談)
- 重要:意見が反対であっても就業規則の効力自体は原則として失われないことを説明。ただし、選出手続や意見聴取が形式的・不適切な場合は手続瑕疵として問題になる可能性があるため、適正な手続と記録保存が重要
- 意見書への労働者代表の記名(氏名明示)を取得
☑ 意見書の作成
- 労働者代表の氏名・所属部署・選出方法の記載
- 意見内容の正確な記録(賛成・反対・条件付き賛成等)
- 労働者代表の記名(氏名明示)が必要。近年の行政手続見直しにより、従来の押印・自筆署名は必須ではなくなっていますが、誰が作成したかが明確になるよう記載してください
- 作成日付の明記(受理時の形式不備防止)
📢 全社員への事前周知
- 改正の背景・目的の説明:なぜ今回の改定が必要なのか、法改正の趣旨を平易に説明
- 従業員への具体的影響の明示:「誰が」「いつから」「何ができるようになるのか」を具体例で説明
- 施行日・経過措置の周知:段階施行の場合は各段階の内容を明確に区別
- 質問受付窓口の設定:人事部門の担当者・連絡先を明示
📌 関連記事:社内周知文書やFAQの作成方法については以下で詳しく解説しています。
→ 法改正を社内に伝えるパターン別テンプレート集|ChatGPTで効率化
Phase 4:労働基準監督署への届出
📋 届出書類準備チェックリスト
☑ 必要書類の準備(各2部)
- 就業規則(変更)届:所轄労働基準監督署に備え付けの様式、または厚生労働省サイトからダウンロード
- 変更後の就業規則:改定後の全文(製本またはホチキス留め)
- 労働者代表の意見書:署名または記名押印済みのもの
- 新旧対照表(任意だが強く推奨):変更箇所が一目で分かる対照表
☑ 届出先・方法の確認
- 届出先:事業場を管轄する労働基準監督署(会社本社所在地ではなく、各事業場の所在地)
- 複数事業場がある場合:それぞれの事業場の管轄監督署に個別届出が必要
- 届出方法:①窓口持参、②郵送、③電子申請(e-Gov)から選択可能
- 電子申請について:2025年1月から労働安全衛生法関係の一部手続(労働保険関係成立届等、常時100人超の事業場対象)で電子申請が原則義務化されましたが、就業規則の届出は現時点で電子申請義務化の対象外です。ただし今後の行政デジタル化の動向に注意が必要です
☑ 届出タイミング
- 基本原則:就業規則の施行日までに遅滞なく届出
- 施行日前であっても完成していれば届出可能(むしろ余裕を持った届出を推奨)
- 定期的な改定を行う企業では、年1回または半年1回などの運用ルール策定を検討
⚖️ 法的リスクの回避
☑ 届出義務の確認
- 対象事業場:常時10人以上の労働者を使用する事業場(労働基準法第89条)
- 「常時」の判断:繁閑の差があっても通常時の人数で判断。パート・アルバイト含む
- 規模拡大により常時10人以上となった場合は、遅滞なく就業規則を作成・届出
☑ 罰則規定の理解
- 作成・届出義務違反:30万円以下の罰金(労働基準法第120条)
- 行政指導・是正勧告のリスク(労働基準監督署の定期監督で指摘される可能性)
- 労働紛争時に「就業規則の届出義務違反」が不利な事情として扱われるリスク
💡 実務Tips:届出時は必ず受領印のある控えを受け取りましょう(窓口の場合)。郵送の場合は返信用封筒を同封し、押印済み控えの返送を依頼します。電子申請の場合は受理通知を保存します。
Phase 5:運用開始・定着化
📢 従業員への周知義務(労働基準法第106条)
就業規則は従業員に周知して初めて効力を持ちます。以下のいずれかの方法で周知が必要です:
- ①常時各作業場の見やすい場所へ掲示:休憩室、事務所等に掲示
- ②書面で交付:全従業員に就業規則の写しを配付
- ③電磁的記録:社内イントラネット、共有フォルダ等で常時閲覧可能な状態にする
📢 実効性のある周知策
- 管理職向け説明会の実施:管理職が部下からの質問に答えられるよう、詳細な説明会を開催
- 一般従業員向け説明会・勉強会:改正の趣旨、具体的な利用方法、申請手続を分かりやすく説明
- 社内報・イントラネットでの継続的な情報発信:施行後3ヶ月程度は定期的に情報発信
- FAQ作成・質問対応体制の整備:想定される質問をまとめたFAQを事前作成
🔄 運用定着化の取り組み
- 運用開始後1ヶ月での初期課題の洗い出し:申請件数、問合せ内容、システム不具合等をモニタリング
- 3ヶ月後の運用状況レビュー:制度利用状況、従業員満足度、業務への影響を評価
- 年1回の制度見直し・改善検討:PDCAサイクルを回し、継続的改善
- 労働基準監督署の調査対応準備:就業規則、意見書、届出控えを整理し、いつでも提示できる状態に
☑ 関連システム・手続きの整備
- 人事システムの設定変更:休暇区分の追加、対象者範囲の変更等
- 申請書類・様式の更新:子の看護休暇申請書、柔軟な働き方措置の意向確認書等
- 給与計算システムの設定変更:休暇控除・手当支給の計算ロジック変更
- 勤怠管理システムの設定変更:休暇コード追加、集計ロジック変更
💼 運用品質向上のポイント
- 継続的な法改正キャッチアップ体制:
- 法改正情報の定期収集(厚生労働省、労働局、業界団体の情報)
- 顧問弁護士・社会保険労務士との定期相談体制(月次または四半期)
- 人事労務系セミナー・研修への参加
- 属人化防止・ナレッジ共有:
- 就業規則改定手順書・マニュアルの整備
- 過去の改定履歴・判断根拠の記録保存(なぜこの条文にしたのか等)
- 複数名での改定業務体制の構築(主担当・副担当制)
📊 2025年重要改正の一覧比較表
2025年の主要な法改正を一覧で比較できます。自社への影響度を判断する際の参考にしてください。
| 法律名 | 施行日 | 主な変更内容 | 対象企業 | 罰則 |
|---|---|---|---|---|
| 育児介護休業法 | 2025年4月1日 2025年10月1日 |
・子の看護休暇拡充 ・残業免除範囲拡大 ・柔軟な働き方措置義務化 ・個別意向聴取義務化 |
全企業 (公表義務は300人超) |
育児介護休業法自体に直接的な刑罰(罰金刑等)は定められていません。ただし、制度を適正に運用しない場合には行政指導・是正勧告、必要に応じた企業名公表等の行政措置が採られる可能性があり、関連法令違反が確認されれば別途行政処分や民事紛争のリスクが生じます。詳細は厚生労働省の解説資料等を参照してください。 |
| 高年齢者雇用安定法 | 2025年4月1日 (経過措置終了) |
・65歳までの雇用確保完全義務化 ・希望者全員対象 |
全企業 | 刑事罰は定められていないが、行政指導や勧告の対象となり得る(詳細は法令・通達を確認) |
| 労働基準法 | 常時適用 | ・就業規則作成・届出義務 (常時10人以上) |
常時10人以上の事業場 | 就業規則の作成・届出義務違反には30万円以下の罰金(労働基準法第120条) |
⚠️ 重要:上記は主要な改正のみを記載しています。詳細は各法令の条文および厚生労働省の通達・ガイドラインを必ずご確認ください。
📅 対応スケジュール例(2025年10月施行対応)
10月施行分の育児介護休業法改正に対応する場合の標準的なスケジュール例です。
| 時期 | フェーズ | 主な作業内容 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 7月上旬 | Phase 1 | ・改正内容の詳細確認 ・現行規則との差分分析 ・プロジェクトチーム設置 |
人事部・法務部 |
| 7月中旬〜下旬 | Phase 2 | ・改定案の作成 ・顧問社労士への確認 ・関連規程の整合性確認 |
人事部(主) 法務部(支援) |
| 8月上旬〜中旬 | Phase 3 | ・労働者代表の選出 ・意見聴取 ・全社員への事前周知 |
人事部・総務部 |
| 8月下旬 | Phase 4 | ・労働基準監督署へ届出 ・受理確認 |
人事部・総務部 |
| 9月 | Phase 5準備 | ・管理職向け説明会 ・申請様式の準備 ・システム改修テスト |
人事部・IT部 |
| 10月1日〜 | Phase 5運用 | ・新制度運用開始 ・問合せ対応 ・運用状況モニタリング |
人事部(全社) |
💡 ポイント:上記は標準的なスケジュールです。企業規模や組織体制により調整してください。特に理事会承認が必要な組織では、理事会開催時期を考慮したスケジュール設定が重要です。
❓ よくある質問(FAQ)
Q1. 就業規則の改定は必ず労働基準監督署に届出が必要ですか?
A1. 常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則の作成・変更時に所轄労働基準監督署への届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。届出を怠ると30万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第120条)。
Q2. 2025年の育児介護休業法改正で最も重要な変更点は何ですか?
A2. 2025年4月施行では①子の看護休暇の対象が小学校3年生修了まで拡大、②残業免除の対象が小学校就学前まで拡大されました。10月施行では③3歳以上小学校就学前の子を持つ労働者への柔軟な働き方措置の提示と個別意向確認が義務化されます。特に10月施行分は制度設計と運用体制の構築に時間を要するため、早めの準備が重要です。
Q3. 就業規則の意見聴取で労働者代表が反対意見を述べた場合、効力はどうなりますか?
A3. 労働者代表の意見が反対でも原則として就業規則の効力自体は失われません(法令上の効力は存続)。ただし、労働者代表の選出手続や意見聴取が適正に行われていない場合(例:使用者が代表者を指名した、形式的な意見聴取のみで実質的な協議がなかった等)は、手続上の瑕疵を理由に行政指導や労働審判等で問題になる可能性があります。意見書には労働者代表の記名(氏名明示)が必要で、届出時に添付することが法律で定められています。反対意見があった場合は、その理由を記録し、可能な範囲で改善を検討することが望ましいです。
Q4. 高年齢者雇用安定法の経過措置終了で何が変わりますか?
A4. 2025年4月1日以降、65歳までの雇用確保措置が完全義務化されました。経過措置が終了したため、継続雇用制度の対象者を限定していた企業は、希望者全員を65歳まで雇用する制度に変更する必要があります。①65歳までの定年引上げ、②希望者全員の65歳までの継続雇用制度導入、③定年制の廃止のいずれかを選択してください。
Q5. 就業規則改定の一連の作業にはどのくらいの期間が必要ですか?
A5. 一般的に2〜3ヶ月程度が目安です。改正内容の把握と影響分析に2〜3週間、改定案作成と法的妥当性確認に2〜3週間、社内合意形成に3〜4週間、届出準備と運用開始準備に1〜2週間程度を見込むと良いでしょう。ただし、組織規模や内部手続の複雑さにより変動します。
Q6. 10月施行分を待たずに4月に前倒し対応するメリットは何ですか?
A6. ①届出・周知が1回で済み事務負担が軽減、②従業員満足度向上とアピール効果、③理事会等の承認手続が1回で済むなどのメリットがあります。特に保育園・こども園等の理事会承認が必要な組織や、中小企業では一括前倒し対応が効率的です。
Q7. ChatGPT等のAIツールを就業規則改定に活用する際の注意点は?
A7. AIツールは情報収集・影響範囲分析・修正文案のドラフト作成に非常に有用ですが、最終的な法的判断は必ず人間(弁護士・社労士)が行う必要があります。また、機密情報(社外秘の人事制度等)はAIに入力しないよう注意してください。規程改正へのAI活用方法も参考にしてください。
Q8. 柔軟な働き方措置の意向聴取(10月施行)の記録は何を残すべきですか?
A8. 意向聴取の面談記録には以下の項目を含めることを推奨します:①面談実施日時、②参加者(労働者・人事担当者等)、③提示した選択肢の内容(始業時刻変更、テレワーク、短時間勤務等)、④労働者の回答・希望内容、⑤事業主が講じる配慮事項、⑥記録作成者・作成日、⑦記録の保存場所・保存期間。この記録は行政調査時の確認資料となるため、最低3年間の保存を推奨します。
📚 参考資料・一次情報リンク集
🏛 厚生労働省 公式資料
- 育児・介護休業法改正ポイントのご案内(PDF)【2025年4月・10月施行】
- 育児・介護休業法に関するパンフレット・リーフレット
- 高年齢者雇用安定法の改正~継続雇用制度の経過措置終了~
- 就業規則作成・届出の手引き
- 労働基準法関係主要様式(就業規則届様式含む)
- 行政手続における押印の見直しについて【意見書の押印要件廃止関連】
📖 Legal GPT 関連記事
- 2025年法改正対応ロードマップ|下半期の施行スケジュールと優先対応事項
- 規程改正の影響範囲分析プロンプト設計ガイド|ChatGPT活用で漏れを防ぐ
- 法改正を社内に伝えるパターン別テンプレート集|ChatGPTで効率化
- 社内規程の改訂、こんな課題ありませんか?|ChatGPT活用で効率化する方法
📌 免責事項:本記事は2025年10月28日時点の法令・通達に基づいて作成されています。最新の法改正情報、施行令・施行規則の詳細については、必ず厚生労働省や管轄労働局の公式情報をご確認ください。また、個別の事案については顧問弁護士や社会保険労務士にご相談することをお勧めします。
就業規則の改定案作成プロンプト
法改正対応から実務改善まで、労働関係法令に精通したAIが適法かつ効果的な就業規則改定案を自動生成。2025年施行の育児・介護休業法改正にも完全対応し、2〜4時間の作業時間を大幅削減できます。
就業規則改定の完全サポート
労働基準法・労働契約法・育児介護休業法等の最新法令に基づき、条文形式の改定案から新旧対照表、不利益変更リスク評価、手続きチェックリストまで一括作成。法務担当者・社労士の実務負担を大幅に軽減します。
📦 このプロンプトに収録されている内容
- ✅ プロンプト本体(労働関係法令に基づく改定案作成用)
- ✅ 入力例(育児・介護休業法改正対応の具体例)
- ✅ 出力例(条文形式の改定案・新旧対照表)
- ✅ カスタマイズのポイント(企業規模・業種別の調整方法)
- ✅ 業種別の注意点(製造業・IT・金融・小売等)
- ✅ よくある質問(法改正対応のタイミング・不利益変更への対応)
Claude 4.5
Gemini 3
💡 使い方のヒント: プロンプトをAIにコピペして、現行規則の条文と改定目的を入力するだけで、条文形式の改定案・新旧対照表・リスク評価が即座に生成されます。法務担当者・社労士による最終確認は必須ですが、初稿作成の時間を大幅に短縮できます。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

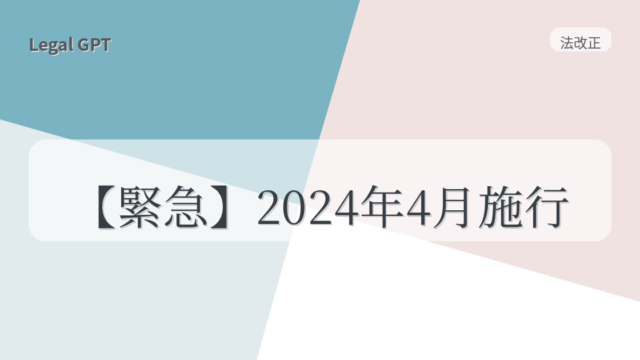
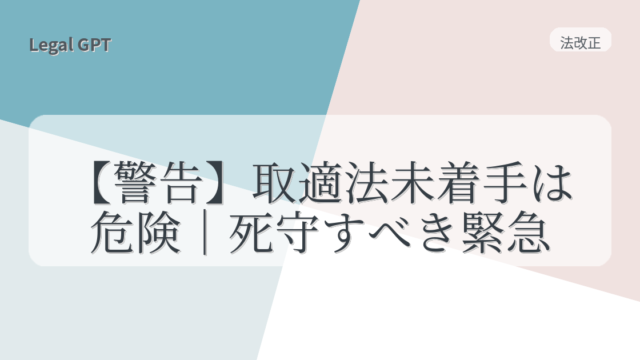
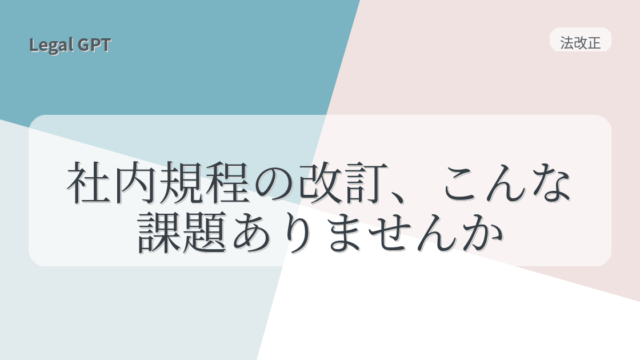
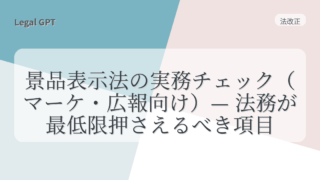
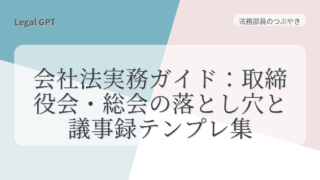



[…] SNSポリシーを就業規則に反映するための改定チェックリスト(手続き〜周… […]
Very interesting topic, thankyou for putting up. “I do not pretend to know where many ignorant men are sure-that is all that agnosticism means.” by Clarence Darrow.
I truly appreciate you bringing this thoughtful perspective to the discussion. I hope we can continue to have such meaningful conversations here.
Thank you so much! I really appreciate you sharing this great quote.
I really appreciate when readers share insights like this. Thanks again!
[…] […]