【法務部奮闘記】競業避止義務誓約書、完成まで3ヶ月の試行錯誤
【法務部奮闘記】競業避止義務誓約書、完成まで3ヶ月の試行錯誤
~専門家の厳しいダメ出しを受けながら、ようやく実用レベルに到達した記録~
プロローグ:突然の”宿題”
「うちも競業避止義務の誓約書、作らないと」
202〇年5月のある日、役員会議でこの話が出ました。きっかけは、開発部門の中核社員が競合他社に転職し、重要な開発プロジェクトの情報が流出したのではないかという疑念でした。
法務部の私に白羽の矢が立ちました。
「とりあえず、弁護士さんと相談しながら進めて」
簡単に言われましたが、競業避止義務なんて大学でちらっと習った程度。実務で作るのは初めてです。
第1週:「ググってコピペ」で大失敗
まずは「競業避止義務 誓約書 ひな形」でGoogle検索。いくつかサンプルを見つけて、それらしく組み合わせてドラフトを作成しました。
第○条(退職後の競業避止義務)
従業員は、退職後3年間、同業他社への就職を禁止する。
代償:なし
違反時:違約金1000万円
上司の反応:「…これ、本当に有効なの?」
そうです。代償もなし、3年間という長期間、違約金も根拠不明。完全にコピペの継ぎ接ぎでした。
【失敗ポイント1】
- 基本的な法的要件を理解していない
- 判例研究をしていない
- 「なんとなく」で条項を作成
第2週:判例を読んで愕然
慌てて判例データベースにアクセスしました。競業避止義務に関する古典的事例としてはフォセコ・ジャパン事件(奈良地判 昭和45年10月23日)があり、本件では競業避止特約の有効性は事案依存で判断されること、特に営業秘密の存在およびその管理態様が重視される点が示されています1。最新の実務動向としては、技術分野の陳腐化の速さや顧客関係の帰属(個人帰属性)などを理由に、制限期間を短めに評価する裁判例も見られます(後述の東京地裁令和5年3月判決等)。判例検討から得た主要な教訓は次のとおりです:憲法22条に基づく職業選択の自由との調整、代償措置の重要性、期間・地域・職務の最小限化、及び営業秘密の明確化です。
【参考判例メモ】
- フォセコ・ジャパン事件(奈良地判 昭和45年10月23日):競業避止特約の有効性判断は事案依存であり、営業秘密の存在と管理措置が重要とされた。1
- ダイオーズ事件:1年間の制限で有効性認定。
- 中部日本広告社事件:管理職なら3年も合理的とされた例。
- 東京地裁 令和5年3月23日判決:AI開発エンジニアの技術陳腐化が早い分野では6ヶ月の制限期間が妥当と認定。2
「これは簡単じゃない…」と実感した瞬間でした。
第3週:弁護士との初回相談で現実を知る
顧問弁護士の先生との初回打ち合わせ。私の修正版ドラフトを見せると…
弁護士:「うーん、いくつか問題がありますね」
【指摘事項】
-
営業秘密の定義が曖昧
- 不正競争防止法の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たすか?
- どの情報が保護対象なのか明確でない
- 管理措置(アクセス制御、ログ管理、NDA等)の現状確認が必要
-
代償措置の水準が不適切
- 代償の有無は裁判所が重視する要素であり、代償が全くない場合は実務上「有効性が否定されるリスクが高い」と評価されることが多い。ただし、それだけで一律に「無効」となるとまでは断言できないため、本文では断定表現を避け、「高リスク」または「必要性が極めて高い」と記述します。3
- 代償の設計では(i)金額水準、(ii)支払方法・開始時期・停止条件、(iii)税務処理の扱い、の3点を明確に定める必要があります。
-
違約金が過度に刑罰的
- 損害の合理的見積り(計算根拠)に基づいていない
- 裁判所で減額される可能性が高い
弁護士:「まず、どんな営業秘密を持っているか整理しましょう」
第4週:営業秘密の洗い出し作業
技術部門、営業部門と連携して、保護すべき営業秘密をリストアップしました。
| 分類 | 内容 | 秘密管理措置 | 有用性 | 非公知性 | 陳腐化期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技術情報 | 独自アルゴリズム | アクセス制限・ログ管理 | ○ | ○ | 2-3年 |
| 顧客情報 | 契約条件・購買履歴 | NDA・ラベリング | ○ | ○ | 1-2年 |
| 営業情報 | 価格体系・販売戦略 | 限定共有・定期見直し | ○ | ○ | 6ヶ月-1年 |
| 管理情報 | 人事評価・給与体系 | 役職者限定アクセス | △ | ○ | 1年 |
重要な発見:意外と「秘密管理性」を満たしていない情報が多い!
別紙「営業秘密定義」には、各情報について「秘密管理措置の現状」「予想される陳腐化期間」「業務上の有用性」を具体的に記載することが誓約書の前提条件となります。
アクセス権限の設定、NDAsの徹底、ログ管理などの体制整備から始めることになりました。
第5週:業界別事例の研究
弁護士のアドバイスで、同業他社の事例を調査しました。
【IT業界の動向】
- 制限期間:6ヶ月〜1年が主流
- 地域制限:首都圏内が一般的
- 代償措置:月収の6〜12ヶ月分
【製造業との比較】
- 制限期間:1〜2年(技術の陳腐化が遅いため)
- 地域制限:全国または海外も含む場合あり
- 代償措置:退職金への上乗せ方式も多い
この調査で、自社の業界特性に応じた制限設計の重要性を理解しました。
第6週:条項設計のブレイクスルー
弁護士と共に、条項の詳細設計に着手。ここで大きなブレイクスルーがありました。
第○条(定義)
1. 「営業秘密」とは、別紙1に定めるとおり、不正競争防止法第2条第6項に照らし、
(i) 秘密として管理されていること、(ii) 事業活動に有用であること、
(iii) 公知でないことを満たす情報をいう。
第●条(退職後の競業避止義務)
1. 乙は、退職日から起算して12ヶ月間、別紙1に定める営業秘密に係る業務に
直接従事する法人への就職を行ってはならない。
ただし、次の行為は除外する:
(1) 公知の情報のみを利用する行為
(2) 乙の一般的技能・経験に基づく業務(別紙2に定義)
2. 地域的制限は関東1都6県に限定する。
第▲条(代償)
1. 甲は、乙が前条義務を履行することの対価として、退職日の属する月の
翌月分から起算して毎月20万円を支払う。支払は甲の普通銀行口座振込により、
毎月末日に行う。
2. 支払は乙が前条義務を遵守することを条件とする。乙が当該義務に違反した場合、
甲は支払を停止し、既払金の返還を請求できる。
第■条(違反時の救済)
1. 乙が本契約に違反したとき、甲は差止請求、合理的に算定した損害賠償及び
違約金(別紙3の計算式による)を請求できる。ただし当該違約金が過度に
刑罰的であると判断される場合は裁判所により調整され得る。
設計のポイント
- 営業秘密を別途定義し、一般的技能は明確に除外
- 代償措置の実効性確保(具体的支払方法を明記)
- 過度に刑罰的でない違約金設定
第7週:税務上の落とし穴発見
条項はほぼ完成したと思っていた矢先、税理士から重要な指摘が。
税務上の注意(必読):
定期的給付(制限期間中に毎月支払う方式)は、国税庁の取扱い上、原則として「給与等」に該当し、源泉徴収が必要となる可能性が高いです4。一方で、支払を退職一時金として設計する場合は退職所得として扱われ得ますが、支払の趣旨・形式次第で税務上の扱いが変わります。したがって、代償設計を行う際は税理士と事前に協議し、支払スキーム(給与課税か退職所得か)を明確に文書化しておくことが不可欠です。国税庁のガイダンス事例を本文に引用しておくと説得力が増します。
【解決策】
- 支払方式を「退職時一時金(退職金上乗せ)」に変更検討
- 対価関係を明確にするため契約書に明記
- 税務上の取扱いを事前に税理士と確認
- 源泉徴収の要否について国税庁の見解を確認(No.2739/No.2732参照)4
第8週:社内調整という新たな試練
法的には問題ない条項ができたものの、今度は社内調整で難航しました。
【人事部門の懸念】
- 「優秀な人材の採用に悪影響では?」
- 「既存社員の反発が心配」
【経営陣の懸念】
- 「代償措置のコストが予想以上に高い」
- 「本当に効果があるのか?」
【労働組合の反発】
- 「労働者の権利侵害だ」
- 「まず労働条件の改善が先では?」
【解決への道筋】
- 段階的導入(まず管理職のみから開始)
- 対象者の限定(営業秘密に接触する者のみ)
- 代償措置の具体的説明(生活保障の観点)
- 運用実績の定期的レビュー
第9週:最終チェックで判例検証
弁護士による最終チェックで、最新判例との適合性を確認しました。
【大阪地裁 令和6年1月16日判決のポイント】
- 顧客との人的関係は原則として個人に帰属
- 企業固有の営業秘密と個人の専門知識を明確に区別
- 代償措置の水準は制限の程度と比例すべき
- 判決番号:令和4年(ワ)第11394号(不正競争防止法違反事件)5
この判例を踏まえ、顧客リストの取扱いを慎重に再検討しました。単なる顧客の連絡先ではなく、「契約条件・購買履歴・商談経緯」等の企業固有情報に限定して営業秘密として管理することとしました。
第10週:実務運用体制の構築
条項の完成と並行して、実務運用体制を整備しました。
新規採用・昇格 → 営業秘密アクセスレベル付与
↓
営業秘密管理台帳と突合
↓
必要に応じて誓約書締結
↓
退職面談時に再確認
↓
代償措置の支払実行
↓
転職先モニタリング
↓
違反疑い発生時は弁護士相談
【チェックリスト完成版】
- □ 営業秘密の3要件確認済み
- □ 対象者の職務範囲明確化済み
- □ 制限期間の合理性確認済み
- □ 代償措置の水準・支払方法確定済み
- □ 税務処理方法確認済み
- □ 違約金の合理的根拠算出済み
- □ 社内説明・承認完了
- □ 運用体制構築済み
まとめ:完璧より実用、そして継続改善
3ヶ月の試行錯誤を通じて学んだ最大の教訓は、「完璧な契約書」より「実用的で継続改善できる契約書」の重要性でした。
法務部の仕事は条項を作ることではなく、事業リスクを適切に管理しながら、ビジネスを支援すること。そのためには:
- 最新の法的知識の継続的習得
- 他部門との密接な連携
- 専門家との適切な協働
- 実務運用を見据えた制度設計
競業避止義務誓約書の作成は、これらすべてを学ぶ絶好の機会でした。
雇用契約書の作成プロンプト【2024年4月改正対応】
正社員・契約社員・パートなど全雇用形態に対応。就業場所・業務変更範囲の明示、無期転換ルール対応など、最新の労働基準法に準拠した契約書を30分〜90分で自動生成できます。
雇用契約書の作成
2024年4月施行の改正労働基準法に完全対応。就業場所・業務の変更範囲明示、無期転換ルール、パート・有期雇用労働法の追加明示事項など、法的要件を網羅した実務即応の雇用契約書を生成します。
📦 このプロンプトに収録されている内容
- 01 2024年4月改正対応の雇用契約書自動生成プロンプト
- 02 正社員・契約社員・パートなど全雇用形態対応
- 03 就業場所・業務変更範囲の明示方法(法定事項)
- 04 無期転換ルール対応の契約書作成手順
- 05 入力例3種(正社員・契約社員・パート)と出力例
- 06 業種別カスタマイズポイントと重要注意事項
Claude 4.5
Gemini 3
💡 使い方のヒント:ダウンロードしたPDFからプロンプトをコピーして、ChatGPT・Claude・Geminiに貼り付けるだけ。雇用形態・職種・勤務地などの情報を入力すれば、法的要件を満たした雇用契約書が自動生成されます。人事労務担当者による最終確認は必須です。
🔍 関連ガイドへ進む
この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。

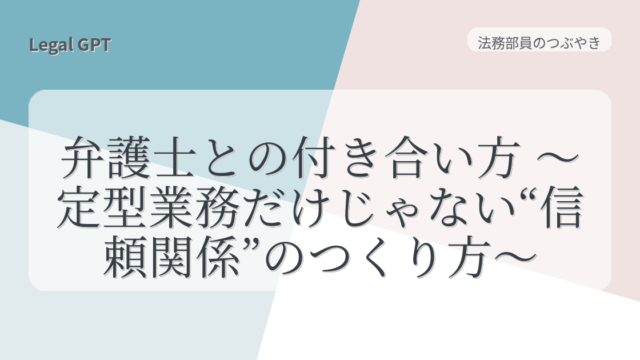
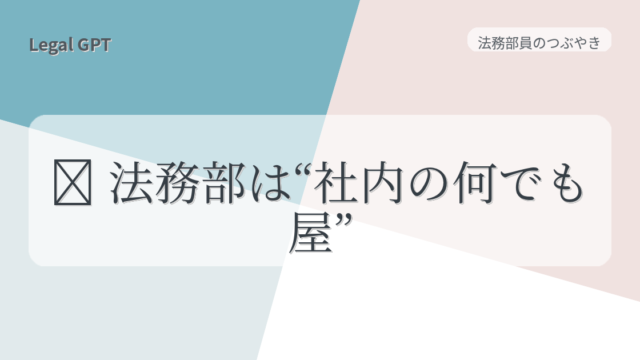
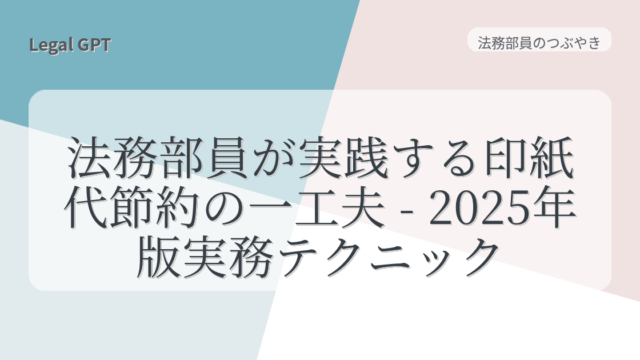
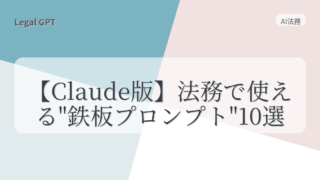
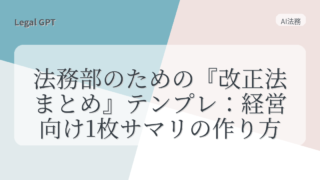



[…] 【法務部奮闘記】競業避止義務誓約書、完成まで3ヶ月の試行錯誤 […]